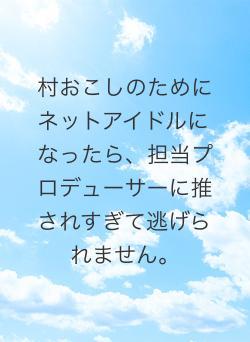その相談が僕のもとへ届いたのは文化祭2日目が開幕する1時間前のことだった。
映画研究同好会の部室で今日の準備をしていた僕はぴりりとスマホが鳴ったのに目をやった。初めて西園寺さんから電話がかかってきてびっくりしながらも通話ボタンをおそるおそるぽちりと押した。
「ねえ。今どこにいる?」
「今は映画研究同好会の部室だけど……どうかしたの?」
「ええとね。ちょっと守須くんに相談があって……。教室まで来てくれない?」
「うん。わかった。今から向かうね」
一体何の相談だろうと僕は不安になりながらも西園寺さんに頼られている気がして少し嬉しい気持ちが不安より勝った。
「お願い! この通り!」
ぱん、と両手を合わせて僕に頭を下げる西園寺さんに合わせてAチームの他のキャストもみんな頭を下げる。玲乃は寝坊して遅れているらしく教室にはいなかった。
「あの、その、僕でいいの?」
潤んだ瞳の西園寺さんに念の為確認してみる。
「守須くんしかいないの! あの馬鹿の代わりをお願いできるのは」
Aチームのキャスト全員が力強く頷いている。
「昨日の文化祭でかき氷食べすぎて体調不良で休んだAチームの高見くんの代わりに女装して欲しいの……!」
高見くんというのはAチームにて女装を担当する予定の男子生徒だ。小さい頃から「馬鹿」が付くほどのサッカー少年で、日焼けした褐色の肌や少し茶色がかった髪の毛が平成男子感満載の爽やかなスポーツ男子だ。
僕は昨日、玲乃と保健室から教室に帰ってきたときに高見くんとすれ違った。高見くんの担当時間は終わったらしく、いつものようにワイシャツの下に黄色いクラスTシャツを着込んで連れの男子生徒と何やら話していたのを覚えている。
その時、高見くんは確かに玲乃にこう言った。
『玲乃。俺は今日、漢になるぞ。かき氷何杯食べられるか隣のクラスの望月と勝負だ!』
その後の経緯については西園寺さんが先程説明した通りだ。
結果、高見くんは10杯のかき氷を食べ切り勝負には勝ったものの、文化祭2日目には体調不良のため登校できなかった。
僕は笑っちゃいけないとわかっているものの、学校を休んだ理由が小学生の勝負みたいに可愛く思えてつい和やかに受け止めてしまいそうだった。
「で、どうなの? 守須くん。高見くんの代わりに今日1日コンカフェ嬢として女装してくれる?」
あまりにも真剣な瞳で聞いてくる西園寺さんやAチームのみんなの圧に負けて、僕はゆっくりと頷いた。
「えと、僕でよければ高見くんの代わりに女装するよ」
「よっしゃー!!」
と西園寺さんが雄叫びを上げたのを見て、Aチームのみんなが拳を突き上げて「おーっ!」と気合いを入れた。僕はその勢いに言葉を失ったが、気を取り直して西園寺さんに1つだけ質問をする。
「でも僕、女装なんてしたことないけど大丈夫なのかな?」
素朴な疑問を伝えると西園寺さんは得意げにグッドポーズをした。
「女装のメイクは任せて! わたしが魔法をかけてあげる。衣装も高見くんのがあるからそれを着れば大丈夫。高見くんより守須くんのほうが細いから上手く衣装の大きさ調整するね。安心して」
文化祭2日目がスタートするまであと1時間。
教室内でクラスのみんながチームに別れて最終日の準備を始めた。僕も覚悟を決めて西園寺さんにぺこりと頭を下げる。
「……わかった。僕ができることならなんでもやってみるよ。メイクと衣装お願いします……!」
「ありがとう! さあ、みんな守須くんの準備に入るわよ。メイクと衣装用意して」
Aチームのみんなは既にメイクや衣装が完了していた。裏方に集まり大きな姿見の前に置いてある椅子に座らされる。
「ここからは集中したいから、みんなは他のチームの準備を手伝ってて」
西園寺さんから指示を受けるとAチームのみんなが散り散りに裏方から出ていった。普段あまり話したことのない西園寺さんと二人きり。どうやって話しかけたらいいのかわからずにおろおろしていた。
そしてこの時、僕はまだこのあと自分の身に何が起きるのかを知らなかった。
「ごめん。寝坊したー」
文化祭2日目スタートの15分前に玲乃が教室に入ってきた。九重くんがピエロのように貼り付けた笑顔のまま、玲乃の腕を縛り裏方へ連行する。
「九重。手ぇ痛いー」
「スタート15分前だぞ。まじでハラハラさせんなよ。西園寺ー! 玲乃連れてきた」
西園寺さんが般若の如く顔を歪めて玲乃の腕を引っ張る。
「あんたねえ舐めてんの?」
「ごめんね。でもそんなに顔顰めてたらメイクよれるよ」
遅刻したことを謝るものの、まったく悪びれない様子で口をきく玲乃に西園寺さんがバシンとクッションファンデを頬に叩きつけた。
「ねえメイクするから黙って?」
「……はい」
その時の西園寺さんの圧に玲乃は初めて女は怖いと思ったのだという。
「ふうー。やっぱイレギュラーあると、この私でも焦る」
「ごめんね。メイクも衣装もありがとう」
玲乃がきゅるると目を潤ませて言えば、西園寺さんは仕方ないなあとばかりに溜息をついた。
「まあ。元が整ってるからそんなにメイクに時間はかからなかったのがムカつく」
ぶつぶつ呟くご立腹な様子の西園寺さんを恐れて玲乃は裏方から抜け出し教室へと顔をのぞかせた。
「んん?」
玲乃は教室の入口でお客さんを待つキャストのうちのひとりに違和感を覚える。
白エプロンの黒色のメイド服を着た人物の背格好がよく知る人物に似ていて目を疑った。しかし、自分の見間違えだと思ったのにその人物のおしりには丸いふわふわの黒いファーがついていて、黒い耳もつけている。その長くて黒い耳がひょこんとこちらを振り向いた。
「おはよう。玲乃」
「……」
目を見開き無言のままの玲乃を安心させるために、僕はちょっとずつ玲乃に近づきながら再び声をかける。固まってしまっている玲乃を見るのは珍しかったので、まじまじと観察してしまう。
玲乃も西園寺さんから女装メイクを施されており、白いエプロンを着用している。近くで見れば見るほど女の子みたいにかわいい。けど、ずっと玲乃のことを見過ぎていたら他のクラスメイトから変に思われるかも。
そう考えて僕は普段通り振舞おうと心に決めた。
「玲乃? 寝坊したってほんと?」
「睦……?」
僕が目の前で喋ったことでようやく何が起きているのか理解したらしい。
「え。なんで。なにやってんの? キャストやるの?」
慌てる玲乃の様子を見れることが珍しくて僕は内心むふふと笑いながら事の経緯を説明しようとすると、西園寺さんがひょこっと横から出てきた。待ってましたと言わんばかりの登場だ。
「高見くんの代わりにね。コンカフェのキャストとして女装してもらうことにしたの。高見くんのやつ、昨日かき氷食べすぎて体調不良で急遽休みになったの」
呆れたように話す西園寺さんに玲乃も「うそでしょ」と呟く。
玲乃は真顔で手を口もとにあてた。
まるで『考える人』のポーズのような横顔に僕は綺麗だなと見入っていた。
その時の玲乃の胸の内が、嵐みたいに荒れているなんて、僕は知る由もなかった。
(──かわいいかわいいかわいいかわいい)
もちろんそんな玲乃の心の声が聞こえない僕はスカートの裾を下に引っ張ってなるべく肌の露出を避けようとする。なんか、足元がすーすーする。変な感じ。
「守須くんって髪の毛で顔が隠れてることが多いからこんなに美形だったなんて知れてびっくり。高見くんなんかよりずっと素直でかわいい。今日は一緒にお仕事頑張ろうね」
にぎにぎと西園寺さんに手を握られて僕はこくんと頷いた。僕にとっての西園寺さんは、優しくてノリが良いお姉ちゃんみたいな存在になっていた。人見知りの僕にもこまめに声をかけてくれて面倒見がいい。
「こんなに西園寺さんが綺麗にしてくれたから、一生懸命頑張ってみる」
「へへ。そう言ってもらえると嬉しいな。頑張ろうね!」
西園寺さんは僕のうさ耳をつんつんとして形を整えてから教室の入口へと向かった。僕も胸元の白いリボンの形を整える。僕の心の奥からやる気の塊がめらめらと火を噴いていた。
「玲乃も行こ。もうお客さん来ちゃうよ」
後ろを振り返り手を差し伸べると、玲乃は無言でその手を掴んだ。その力強さに少し目を見張る。痛いほどではないけど、離さないと言われているようなそんな強さ。それが素直に嬉しいと思ってしまう。
「あんまり……無理はしないで。何かあったら声かけて。その時は助けるから」
力強い瞳で伝えてくれる玲乃のことが頼もしい。
今日も一日、文化祭を楽しもうと思って少し不安げな玲乃を安心させるために笑顔を浮かべた。
「……そんなにかわいくしてちゃダメ」
「何で?」
「鼻血出る人出そうだから……」
そう言って玲乃は自身の鼻を押さえて、そそくさと裏方へ向かって歩き出してしまう。
なんだかよくわからないけど、お客さんを笑顔にするために頑張ろうと心に決めた。
映画研究同好会の部室で今日の準備をしていた僕はぴりりとスマホが鳴ったのに目をやった。初めて西園寺さんから電話がかかってきてびっくりしながらも通話ボタンをおそるおそるぽちりと押した。
「ねえ。今どこにいる?」
「今は映画研究同好会の部室だけど……どうかしたの?」
「ええとね。ちょっと守須くんに相談があって……。教室まで来てくれない?」
「うん。わかった。今から向かうね」
一体何の相談だろうと僕は不安になりながらも西園寺さんに頼られている気がして少し嬉しい気持ちが不安より勝った。
「お願い! この通り!」
ぱん、と両手を合わせて僕に頭を下げる西園寺さんに合わせてAチームの他のキャストもみんな頭を下げる。玲乃は寝坊して遅れているらしく教室にはいなかった。
「あの、その、僕でいいの?」
潤んだ瞳の西園寺さんに念の為確認してみる。
「守須くんしかいないの! あの馬鹿の代わりをお願いできるのは」
Aチームのキャスト全員が力強く頷いている。
「昨日の文化祭でかき氷食べすぎて体調不良で休んだAチームの高見くんの代わりに女装して欲しいの……!」
高見くんというのはAチームにて女装を担当する予定の男子生徒だ。小さい頃から「馬鹿」が付くほどのサッカー少年で、日焼けした褐色の肌や少し茶色がかった髪の毛が平成男子感満載の爽やかなスポーツ男子だ。
僕は昨日、玲乃と保健室から教室に帰ってきたときに高見くんとすれ違った。高見くんの担当時間は終わったらしく、いつものようにワイシャツの下に黄色いクラスTシャツを着込んで連れの男子生徒と何やら話していたのを覚えている。
その時、高見くんは確かに玲乃にこう言った。
『玲乃。俺は今日、漢になるぞ。かき氷何杯食べられるか隣のクラスの望月と勝負だ!』
その後の経緯については西園寺さんが先程説明した通りだ。
結果、高見くんは10杯のかき氷を食べ切り勝負には勝ったものの、文化祭2日目には体調不良のため登校できなかった。
僕は笑っちゃいけないとわかっているものの、学校を休んだ理由が小学生の勝負みたいに可愛く思えてつい和やかに受け止めてしまいそうだった。
「で、どうなの? 守須くん。高見くんの代わりに今日1日コンカフェ嬢として女装してくれる?」
あまりにも真剣な瞳で聞いてくる西園寺さんやAチームのみんなの圧に負けて、僕はゆっくりと頷いた。
「えと、僕でよければ高見くんの代わりに女装するよ」
「よっしゃー!!」
と西園寺さんが雄叫びを上げたのを見て、Aチームのみんなが拳を突き上げて「おーっ!」と気合いを入れた。僕はその勢いに言葉を失ったが、気を取り直して西園寺さんに1つだけ質問をする。
「でも僕、女装なんてしたことないけど大丈夫なのかな?」
素朴な疑問を伝えると西園寺さんは得意げにグッドポーズをした。
「女装のメイクは任せて! わたしが魔法をかけてあげる。衣装も高見くんのがあるからそれを着れば大丈夫。高見くんより守須くんのほうが細いから上手く衣装の大きさ調整するね。安心して」
文化祭2日目がスタートするまであと1時間。
教室内でクラスのみんながチームに別れて最終日の準備を始めた。僕も覚悟を決めて西園寺さんにぺこりと頭を下げる。
「……わかった。僕ができることならなんでもやってみるよ。メイクと衣装お願いします……!」
「ありがとう! さあ、みんな守須くんの準備に入るわよ。メイクと衣装用意して」
Aチームのみんなは既にメイクや衣装が完了していた。裏方に集まり大きな姿見の前に置いてある椅子に座らされる。
「ここからは集中したいから、みんなは他のチームの準備を手伝ってて」
西園寺さんから指示を受けるとAチームのみんなが散り散りに裏方から出ていった。普段あまり話したことのない西園寺さんと二人きり。どうやって話しかけたらいいのかわからずにおろおろしていた。
そしてこの時、僕はまだこのあと自分の身に何が起きるのかを知らなかった。
「ごめん。寝坊したー」
文化祭2日目スタートの15分前に玲乃が教室に入ってきた。九重くんがピエロのように貼り付けた笑顔のまま、玲乃の腕を縛り裏方へ連行する。
「九重。手ぇ痛いー」
「スタート15分前だぞ。まじでハラハラさせんなよ。西園寺ー! 玲乃連れてきた」
西園寺さんが般若の如く顔を歪めて玲乃の腕を引っ張る。
「あんたねえ舐めてんの?」
「ごめんね。でもそんなに顔顰めてたらメイクよれるよ」
遅刻したことを謝るものの、まったく悪びれない様子で口をきく玲乃に西園寺さんがバシンとクッションファンデを頬に叩きつけた。
「ねえメイクするから黙って?」
「……はい」
その時の西園寺さんの圧に玲乃は初めて女は怖いと思ったのだという。
「ふうー。やっぱイレギュラーあると、この私でも焦る」
「ごめんね。メイクも衣装もありがとう」
玲乃がきゅるると目を潤ませて言えば、西園寺さんは仕方ないなあとばかりに溜息をついた。
「まあ。元が整ってるからそんなにメイクに時間はかからなかったのがムカつく」
ぶつぶつ呟くご立腹な様子の西園寺さんを恐れて玲乃は裏方から抜け出し教室へと顔をのぞかせた。
「んん?」
玲乃は教室の入口でお客さんを待つキャストのうちのひとりに違和感を覚える。
白エプロンの黒色のメイド服を着た人物の背格好がよく知る人物に似ていて目を疑った。しかし、自分の見間違えだと思ったのにその人物のおしりには丸いふわふわの黒いファーがついていて、黒い耳もつけている。その長くて黒い耳がひょこんとこちらを振り向いた。
「おはよう。玲乃」
「……」
目を見開き無言のままの玲乃を安心させるために、僕はちょっとずつ玲乃に近づきながら再び声をかける。固まってしまっている玲乃を見るのは珍しかったので、まじまじと観察してしまう。
玲乃も西園寺さんから女装メイクを施されており、白いエプロンを着用している。近くで見れば見るほど女の子みたいにかわいい。けど、ずっと玲乃のことを見過ぎていたら他のクラスメイトから変に思われるかも。
そう考えて僕は普段通り振舞おうと心に決めた。
「玲乃? 寝坊したってほんと?」
「睦……?」
僕が目の前で喋ったことでようやく何が起きているのか理解したらしい。
「え。なんで。なにやってんの? キャストやるの?」
慌てる玲乃の様子を見れることが珍しくて僕は内心むふふと笑いながら事の経緯を説明しようとすると、西園寺さんがひょこっと横から出てきた。待ってましたと言わんばかりの登場だ。
「高見くんの代わりにね。コンカフェのキャストとして女装してもらうことにしたの。高見くんのやつ、昨日かき氷食べすぎて体調不良で急遽休みになったの」
呆れたように話す西園寺さんに玲乃も「うそでしょ」と呟く。
玲乃は真顔で手を口もとにあてた。
まるで『考える人』のポーズのような横顔に僕は綺麗だなと見入っていた。
その時の玲乃の胸の内が、嵐みたいに荒れているなんて、僕は知る由もなかった。
(──かわいいかわいいかわいいかわいい)
もちろんそんな玲乃の心の声が聞こえない僕はスカートの裾を下に引っ張ってなるべく肌の露出を避けようとする。なんか、足元がすーすーする。変な感じ。
「守須くんって髪の毛で顔が隠れてることが多いからこんなに美形だったなんて知れてびっくり。高見くんなんかよりずっと素直でかわいい。今日は一緒にお仕事頑張ろうね」
にぎにぎと西園寺さんに手を握られて僕はこくんと頷いた。僕にとっての西園寺さんは、優しくてノリが良いお姉ちゃんみたいな存在になっていた。人見知りの僕にもこまめに声をかけてくれて面倒見がいい。
「こんなに西園寺さんが綺麗にしてくれたから、一生懸命頑張ってみる」
「へへ。そう言ってもらえると嬉しいな。頑張ろうね!」
西園寺さんは僕のうさ耳をつんつんとして形を整えてから教室の入口へと向かった。僕も胸元の白いリボンの形を整える。僕の心の奥からやる気の塊がめらめらと火を噴いていた。
「玲乃も行こ。もうお客さん来ちゃうよ」
後ろを振り返り手を差し伸べると、玲乃は無言でその手を掴んだ。その力強さに少し目を見張る。痛いほどではないけど、離さないと言われているようなそんな強さ。それが素直に嬉しいと思ってしまう。
「あんまり……無理はしないで。何かあったら声かけて。その時は助けるから」
力強い瞳で伝えてくれる玲乃のことが頼もしい。
今日も一日、文化祭を楽しもうと思って少し不安げな玲乃を安心させるために笑顔を浮かべた。
「……そんなにかわいくしてちゃダメ」
「何で?」
「鼻血出る人出そうだから……」
そう言って玲乃は自身の鼻を押さえて、そそくさと裏方へ向かって歩き出してしまう。
なんだかよくわからないけど、お客さんを笑顔にするために頑張ろうと心に決めた。