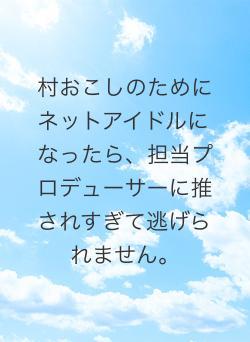「歩くの辛いよね。前かがみになってる。俺が睦のことおんぶする」
「えっ、でもそんな申し訳ないよ。それに、他の人に見られたら……」
玲乃に変な噂がくっつくのは嫌だ。でも、甘えたいのが本心だった。
「ほら。乗って」
「……うん。ありがとう」
僕はそのまましゃがみこんだ玲乃の広い背中に身体を預けることにした。ぎゅっと両腕を玲乃の肩に回してくっつく。重くないかな、と不安になってしまう。けれど玲乃は軽々と僕を背負うとすたすたと歩き出した。
力持ちだなあ……。
「なんか昔のこと思い出した」
僕は玲乃の歩く振動を心地よく感じながら瞼を閉じる。瞼の裏にはいつかの二人の様子が浮かび上がった。
あれは確か近所に住んでいるおじいさんの番犬に玲乃が吠えられて泣いちゃったときだった。「びぇー」と鼻水ぐちゃぐちゃ、大きな瞳には涙の粒が止めどなく溢れていたっけ。
恐怖に立ちすくみ震えて動けなくなっている玲乃を僕がおんぶして家に帰った。グズグズ泣いてた玲乃はもういない。今はその面影すらない。あの頃は玲乃のことを睦がおんぶしていたのに、今はまるで逆。高校二年生にもなって玲乃におんぶされる自分のことが、ひどく幼く感じた。
「ん。ついたよ」
無事に自宅の部屋の前までおんぶされて降ろされた。玲乃はいつも通り振る舞いながら僕の髪を撫でる。
「一緒に帰ってくれてありがとう」
本心だった。小さい頃から両親に感謝することの大切さを叩き込まれている。玲乃は満足そうに頷く。
至れり尽くせりだなと僕は深々とお辞儀する。
玲乃は「任せて」と返事をすると耳元でそっと囁いた。
「睦がして欲しかったらお風呂も手伝ってあげるし、着替えも手伝うよ。明日の朝、そのまま一緒に学校行こ」
僕があんぐりと口を開けているのを気にせずに玲乃は自分の部屋に入っていく。自分のだらしない顔が玲乃に丸見えだったのに気づいた僕は慌ててドアノブを引いて部屋へ入った。
「ただいま」
返ってくる声はないけど、いつもの習慣でそうしてしまう。
僕の両親は共働きで夜中にならないと帰宅しない。両親は朝早く家から出てしまうし、休みも不定期なので一緒に過ごす時間は少ない。けれどそれに対して文句を言ったりはしない。
両親はひとりっ子の僕のために生活費や大学への進学費を用意しようと奔走してくれている。
僕はいつもそんな両親が誇れるような息子になりたいと考えていた。
だから今日も夜遅くまでテスト勉強をする。明日からの中間テストでは自己ベスト更新を目標にしている。勉強に集中していると背中の痛みを感じなくてすんだ。
「えっ、でもそんな申し訳ないよ。それに、他の人に見られたら……」
玲乃に変な噂がくっつくのは嫌だ。でも、甘えたいのが本心だった。
「ほら。乗って」
「……うん。ありがとう」
僕はそのまましゃがみこんだ玲乃の広い背中に身体を預けることにした。ぎゅっと両腕を玲乃の肩に回してくっつく。重くないかな、と不安になってしまう。けれど玲乃は軽々と僕を背負うとすたすたと歩き出した。
力持ちだなあ……。
「なんか昔のこと思い出した」
僕は玲乃の歩く振動を心地よく感じながら瞼を閉じる。瞼の裏にはいつかの二人の様子が浮かび上がった。
あれは確か近所に住んでいるおじいさんの番犬に玲乃が吠えられて泣いちゃったときだった。「びぇー」と鼻水ぐちゃぐちゃ、大きな瞳には涙の粒が止めどなく溢れていたっけ。
恐怖に立ちすくみ震えて動けなくなっている玲乃を僕がおんぶして家に帰った。グズグズ泣いてた玲乃はもういない。今はその面影すらない。あの頃は玲乃のことを睦がおんぶしていたのに、今はまるで逆。高校二年生にもなって玲乃におんぶされる自分のことが、ひどく幼く感じた。
「ん。ついたよ」
無事に自宅の部屋の前までおんぶされて降ろされた。玲乃はいつも通り振る舞いながら僕の髪を撫でる。
「一緒に帰ってくれてありがとう」
本心だった。小さい頃から両親に感謝することの大切さを叩き込まれている。玲乃は満足そうに頷く。
至れり尽くせりだなと僕は深々とお辞儀する。
玲乃は「任せて」と返事をすると耳元でそっと囁いた。
「睦がして欲しかったらお風呂も手伝ってあげるし、着替えも手伝うよ。明日の朝、そのまま一緒に学校行こ」
僕があんぐりと口を開けているのを気にせずに玲乃は自分の部屋に入っていく。自分のだらしない顔が玲乃に丸見えだったのに気づいた僕は慌ててドアノブを引いて部屋へ入った。
「ただいま」
返ってくる声はないけど、いつもの習慣でそうしてしまう。
僕の両親は共働きで夜中にならないと帰宅しない。両親は朝早く家から出てしまうし、休みも不定期なので一緒に過ごす時間は少ない。けれどそれに対して文句を言ったりはしない。
両親はひとりっ子の僕のために生活費や大学への進学費を用意しようと奔走してくれている。
僕はいつもそんな両親が誇れるような息子になりたいと考えていた。
だから今日も夜遅くまでテスト勉強をする。明日からの中間テストでは自己ベスト更新を目標にしている。勉強に集中していると背中の痛みを感じなくてすんだ。