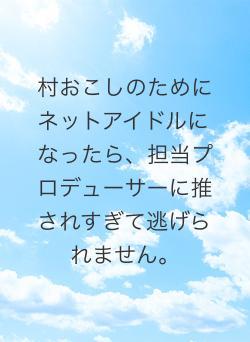「どこか痛いところない?」
気遣わしげな玲乃の声にほっと肩の力が抜ける。そのまま膝から地面に崩れ落ちそうになるのを、玲乃が抱きとめてくれた。
「だい、じょうぶ……」
「全然大丈夫じゃなさそう」
「……ごめ、ん。安心したら力抜けちゃって……っ」
背中の鈍い痛みに声を洩らすとすぐさま身体を抱き起こして顔を覗かれる。玲乃の顔、近くて少し怒ってる。眉を寄せて、何か言いたげ。
「どこが痛い?」
「……背中。さっき、突き飛ばされて壁にぶつかっちゃったから」
「……そうか。保健室行くよ」
「えっ。待って……そんな大事じゃないよ」
「だめ。俺が心配だから」
有無を言わさない瞳。僕はこくんと頷くことにした。
玲乃に支えられながら歩く校舎の廊下は、やけに長く感じた。
こんなに距離近くて、心臓持たないよ……。
足を運ぶたびに、背中の奥がじん、と鈍く痛む。それと同時に胸がきゅっと甘く疼いた。
「ゆっくりでいいよ」
耳元で囁くように言われて、反射的にうなずく。
誰かにそう言われたのは、久しぶりだった。
保健室のドアを開けると、ひんやりした空気が頬に触れた。
白いカーテンと消毒液の匂い。少しだけ、安心する。
保健の先生に事情を簡単に説明すると、僕はベッドに座らされた。
「上、脱げる?」
「……はい」
ワイシャツを肩からずらすと、背中に空気が触れて、思わず息を吸い込む。
「ちょっと青くなってるね」
先生の声が近い。先生の指が痛む場所を静かにさする。
触れられた場所がじん、と熱を持つ。
「湿布貼るよ。少し冷たいから」
背中に触れた瞬間、ひやっとした感触が広がった。
「……っ」
小さく声が漏れてしまう。
「痛い?」
先生が手を止める。
「だ、大丈夫です……ちょっとだけ」
「無理しない。しばらくは体育は禁止」
先生はそう言って、湿布を丁寧に押さえた。
処置が終わると、カーテンが静かに閉められる。
先生は「少し休んでから帰れ」と言い残して、奥へ下がっていった。
ベッドの横に立っていた玲乃が、そっと近づいてくる。
「……思ったより、痛そう」
低い声。
責めるでもなく、ただ心配している響きだった。
「うん……ちょっとだけ」
正直に言うと、玲乃は小さく息を吐いた。
「我慢しすぎ」
「……ごめん」
「謝らなくていいよ」
即座に返される。
「睦は悪いこと、ひとつもしてない」
その言葉が、胸の奥に静かに落ちた。
ベッドに座ったまま、僕は湿布の貼られた背中の違和感を感じていた。
少し冷たくて、少し痛い。
でも、不思議とさっきまでの震えは治まっていた。
隣にいる玲乃の気配が、はっきりと伝わってくる。
「睦」
玲乃が、少し間を置いて言う。
「怖かったよね」
その一言で、喉の奥が詰まる。
「……うん」
短く答えると、視界が滲んだ。
「でも、もう一人にしないから」
玲乃はそう言って、僕の肩にそっと手を置いた。
強くもなく、逃げ道を塞ぐわけでもない、ただそこにある手。
背中はまだ少し痛い。
痣だって、たぶんしばらく消えない。
それでも。
この痛みは、
誰かに助けられた証みたいに思えてしまった。
僕は俯いたまま、小さく息を整える。
──大丈夫。
今は、そう思えた。
玲乃に背を向けるようにして、ワイシャツに袖を通す。
背中に湿布が貼られているせいで、腕を上げるたびにじわりとした違和感が走った。
「……痛む?」
すぐ後ろから声がする。
「ううん。大丈夫」
大丈夫、という言葉が口癖みたいになっている自分に、少しだけ苦笑した。
着替え終わって振り返ると、玲乃はベッドの横に立ったまま、少し困った顔をしていた。
「……さっきの、ちゃんと聞いてほしい」
低く、真剣な声。
「謝ったこと」
僕は首を傾げる。
「なんで玲乃が謝るの」
「俺がもっと早く気づいてたら、あんな目に遭わせなかった」
まっすぐな視線。
逃げ場がない。
「睦が傷つくの、見たくなかった」
胸の奥が、きゅっと縮んだ。
「……でも」
言葉を選びながら、続ける。
「助けてくれたのは玲乃だよ。あのままだったら、どうなってたかわからない」
そう言うと、玲乃は一瞬目を伏せた。
「それでも」
小さく、でもはっきり。
「俺は睦のこと守れなかった。怖かったよね」
さっき抱きしめられたときの感触が、ふっと蘇る。
強くもなく、乱暴でもなかった。ただ必死だった。
「……怖くなかった、って言ったら嘘になる」
正直に言う。
「でも、玲乃が来てくれたから……ちゃんと戻ってこられた」
何から、と言葉にできないまま。
玲乃は少し驚いた顔をして、それから、困ったように笑った。
「……そっか」
それ以上は何も言わなかったけれど、その表情は少しだけ軽くなった気がした。
保健室を出ると、外はすっかり夕暮れだった。
校舎の影が長く伸びて、昼間とは別の顔をしている。
「一緒に帰ろ」
玲乃は当然みたいに言う。
「ううん。僕、歩くの遅いから一人で──」
「だめ」
即答だった。
「今日くらい、俺に甘えて」
その言葉に、反論できなくなる。
並んで歩く帰り道。
足並みを揃えてくれているのが、はっきりわかる。
沈黙が続いても、気まずくはなかった。
「……睦」
少し歩いたところで、玲乃が名前を呼ぶ。
「これからは、何かあったら言って」
横顔を見ると、真剣な目をしていた。
「一人で抱えないで」
その言葉が、胸に残る。
「……うん」
小さく返事をすると、玲乃はそれでいい、と言うみたいに前を向いた。
背中の湿布は、まだ少し冷たい。
歩くたび、鈍い痛みもある。
それでも。
夕焼けの中を、誰かと一緒に帰るこの時間は、
不思議なくらい、あたたかかった。
今日のことは、きっと簡単には忘れられない。
でも──。
この帰り道のことも、
同じくらい、心に残る気がしていた。