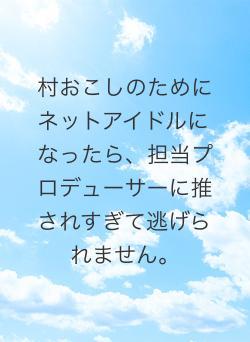「なあ。もやしくん。ちょっと面貸せよ」
翌日の放課後、下駄箱で靴を取り出していた僕は、背後からかけられた低い声に肩を強張らせた。
振り返らなくても、誰だかはすぐにわかった。
村野と三上。
同じクラスで、いつも玲乃の近くにいる二人だ。
僕は視線を落としたまま、小さくうなずく。逆らう選択肢なんて、最初からなかった。
体育館裏は、人の気配がほとんどなかった。
コンクリートの壁に背中を預ける形で立たされ、村野が一歩、距離を詰めてくる。
「お前さ、マジで目障りなんだよ」
低い声。怒鳴っているわけでもないのに、胸の奥がぎゅっと縮む。
「いつも下向いて、ボソボソ喋って。陰気くせえんだよ」
何か言わなきゃ、と思うのに、言葉が喉に引っかかって出てこない。
代わりに出たのは、情けないくらい小さな声だった。
「……ごめんなさい」
「ほら、それ」
三上が肩をすくめて笑う。
「すぐ謝るとこ。そういうとこが余計ムカつくんだって」
村野が、僕の胸元を指で軽く突いた。
突き飛ばすほど強くはない。それなのに、足元がぐらついて、背中が壁にぶつかる。
ごん、という鈍い音。壁にぶつかった背中がじいんと痛む。
心臓が早鐘みたいに鳴り出す。
逃げたいのに、身体が言うことをきかない。
「別にさ、殴りたいわけじゃねえんだよ」
村野はそう言いながら、僕の前に立ちはだかる。
「ただ、お前が調子に乗らなきゃいいだけ」
調子に乗る、って何だろう。
息をして、学校に来て、同じ教室にいることだろうか。
三上が僕のカバンを足で引き寄せ、軽く蹴る。
「この前、お前に教室の掃除させた後、玲乃から叱られてさあ。シンプルに不愉快。次、玲乃にチクったらわかるよな?」
玲乃にチクる。
その言葉だけで、頭の中が真っ白になる。僕と玲乃の関係に気づかれたら終わりだ。そう思ったら涙が溢れてきて、視界が滲んでいく。
「は? こいつこんなんで泣いてんの? よっわ」
村野と三上の嘲笑うような声にさらに涙が溢れてくる。自分の弱さを思い知った気がした。
──もう、だめだ。
そう思った瞬間だった。
「お前ら、ダサいことしてんな」
低くて、落ち着いた声。
聞き慣れたその声が、背中越しに届いた。
息を詰めたまま、ゆっくり顔を上げる。
視界に入ったのは、黒く光るローファー。
次いで、制服のズボン、真っ直ぐ伸びた背中。
玲乃だった。
僕と村野、三上を一段高い位置から見下ろすように立っている。
表情は、驚くほど冷静だった。
「は? なんだよ。玲乃かよ」
村野が舌打ちする。
「お前には関係ねえだろ」
「関係ある」
玲乃は即答した。
「その子、クラスメイトだから」
それだけ言って、一歩、前に出る。
ただそれだけなのに、空気が変わったのがわかった。
村野は一瞬、言葉に詰まったあと、強がるように胸ぐらを掴もうと手を伸ばす。
けれど。
「触んな」
玲乃はその手首を掴み、力を込めるでもなく、ただ下に押し下げた。
「……っ」
村野が顔を歪める。
殴ったわけじゃない。ただ、動きを止められただけだ。
「今すぐ離れろ」
声は静かだったけれど、有無を言わせない強さがあった。
三上が後ろから口を挟む。
「二対一だぞ?」
玲乃は振り返りもしない。
「だから?」
短い一言。
「続けたいなら、先生呼ぶけど」
その言葉に、二人の動きが止まった。
体育館裏は、思っている以上に声が響く。
誰かが来ても、おかしくない時間帯だ。
「……ちっ」
最初に視線を逸らしたのは、三上だった。
「行くぞ、村野」
「はぁ!? まだ──」
「いいから!」
三上に腕を引かれ、村野は悔しそうに僕を睨みつける。
「覚えとけよ」
吐き捨てるように言って、二人は足早に去っていった。
その背中が角を曲がって見えなくなるまで、玲乃は動かなかった。
完全に人の気配が消えてから、ようやく僕の方を振り返る。
「……大丈夫か」
その一言で、張り詰めていたものが一気にほどけた。
「れ、の……」
名前を呼んだ途端、声が震える。
玲乃は少し驚いた顔をしてから、すぐに視線を柔らげた。
「無理すんな。立てる?」
差し出された手を見つめる。
その手は、さっきまで村野を制していたとは思えないほど、落ち着いていた。
僕は小さくうなずいて、震える指でその手を掴んだ。
引き上げられると、視界が一気に高くなる。
──助かった。
その事実が、胸の奥にじんわり染みていく。
痛みよりも、怖さよりも。
今はただ、玲乃がここに来てくれたことが嬉しかった。
翌日の放課後、下駄箱で靴を取り出していた僕は、背後からかけられた低い声に肩を強張らせた。
振り返らなくても、誰だかはすぐにわかった。
村野と三上。
同じクラスで、いつも玲乃の近くにいる二人だ。
僕は視線を落としたまま、小さくうなずく。逆らう選択肢なんて、最初からなかった。
体育館裏は、人の気配がほとんどなかった。
コンクリートの壁に背中を預ける形で立たされ、村野が一歩、距離を詰めてくる。
「お前さ、マジで目障りなんだよ」
低い声。怒鳴っているわけでもないのに、胸の奥がぎゅっと縮む。
「いつも下向いて、ボソボソ喋って。陰気くせえんだよ」
何か言わなきゃ、と思うのに、言葉が喉に引っかかって出てこない。
代わりに出たのは、情けないくらい小さな声だった。
「……ごめんなさい」
「ほら、それ」
三上が肩をすくめて笑う。
「すぐ謝るとこ。そういうとこが余計ムカつくんだって」
村野が、僕の胸元を指で軽く突いた。
突き飛ばすほど強くはない。それなのに、足元がぐらついて、背中が壁にぶつかる。
ごん、という鈍い音。壁にぶつかった背中がじいんと痛む。
心臓が早鐘みたいに鳴り出す。
逃げたいのに、身体が言うことをきかない。
「別にさ、殴りたいわけじゃねえんだよ」
村野はそう言いながら、僕の前に立ちはだかる。
「ただ、お前が調子に乗らなきゃいいだけ」
調子に乗る、って何だろう。
息をして、学校に来て、同じ教室にいることだろうか。
三上が僕のカバンを足で引き寄せ、軽く蹴る。
「この前、お前に教室の掃除させた後、玲乃から叱られてさあ。シンプルに不愉快。次、玲乃にチクったらわかるよな?」
玲乃にチクる。
その言葉だけで、頭の中が真っ白になる。僕と玲乃の関係に気づかれたら終わりだ。そう思ったら涙が溢れてきて、視界が滲んでいく。
「は? こいつこんなんで泣いてんの? よっわ」
村野と三上の嘲笑うような声にさらに涙が溢れてくる。自分の弱さを思い知った気がした。
──もう、だめだ。
そう思った瞬間だった。
「お前ら、ダサいことしてんな」
低くて、落ち着いた声。
聞き慣れたその声が、背中越しに届いた。
息を詰めたまま、ゆっくり顔を上げる。
視界に入ったのは、黒く光るローファー。
次いで、制服のズボン、真っ直ぐ伸びた背中。
玲乃だった。
僕と村野、三上を一段高い位置から見下ろすように立っている。
表情は、驚くほど冷静だった。
「は? なんだよ。玲乃かよ」
村野が舌打ちする。
「お前には関係ねえだろ」
「関係ある」
玲乃は即答した。
「その子、クラスメイトだから」
それだけ言って、一歩、前に出る。
ただそれだけなのに、空気が変わったのがわかった。
村野は一瞬、言葉に詰まったあと、強がるように胸ぐらを掴もうと手を伸ばす。
けれど。
「触んな」
玲乃はその手首を掴み、力を込めるでもなく、ただ下に押し下げた。
「……っ」
村野が顔を歪める。
殴ったわけじゃない。ただ、動きを止められただけだ。
「今すぐ離れろ」
声は静かだったけれど、有無を言わせない強さがあった。
三上が後ろから口を挟む。
「二対一だぞ?」
玲乃は振り返りもしない。
「だから?」
短い一言。
「続けたいなら、先生呼ぶけど」
その言葉に、二人の動きが止まった。
体育館裏は、思っている以上に声が響く。
誰かが来ても、おかしくない時間帯だ。
「……ちっ」
最初に視線を逸らしたのは、三上だった。
「行くぞ、村野」
「はぁ!? まだ──」
「いいから!」
三上に腕を引かれ、村野は悔しそうに僕を睨みつける。
「覚えとけよ」
吐き捨てるように言って、二人は足早に去っていった。
その背中が角を曲がって見えなくなるまで、玲乃は動かなかった。
完全に人の気配が消えてから、ようやく僕の方を振り返る。
「……大丈夫か」
その一言で、張り詰めていたものが一気にほどけた。
「れ、の……」
名前を呼んだ途端、声が震える。
玲乃は少し驚いた顔をしてから、すぐに視線を柔らげた。
「無理すんな。立てる?」
差し出された手を見つめる。
その手は、さっきまで村野を制していたとは思えないほど、落ち着いていた。
僕は小さくうなずいて、震える指でその手を掴んだ。
引き上げられると、視界が一気に高くなる。
──助かった。
その事実が、胸の奥にじんわり染みていく。
痛みよりも、怖さよりも。
今はただ、玲乃がここに来てくれたことが嬉しかった。