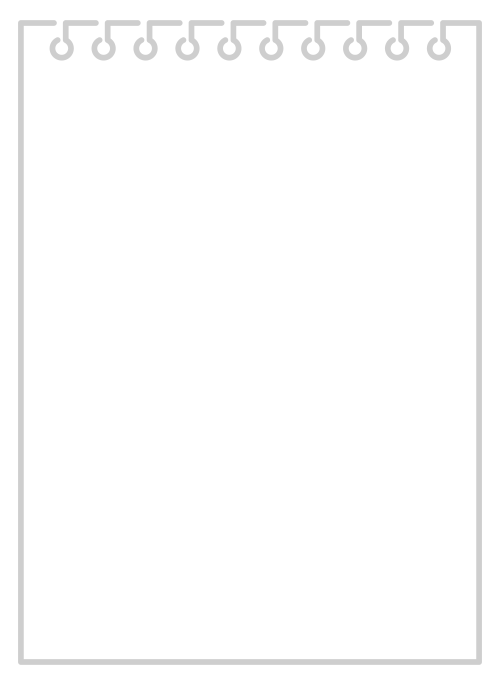しばらく人力車に乗せられ、降りた先に目に映ったのは伊澄家と同じくらいの大きさの屋敷であった。
その圧倒されるような雰囲気に私はごくりと唾を呑む。伊澄家当主の嫁として挨拶をするというのは思えば今日が初めてである。
私の緊張が伝わったのか私の手を握った緋瑠人さん。横を見れば、緋瑠人さんは穏やかな顔で笑っている。
「和香さんも緊張するんだね」
「…それは、だって、嫁いだ身としては伊澄の家に恥じないようにしないとと思ってますから」
「大丈夫、俺『臆病者の当主』って恥晒しの異名があるからもう今の伊澄家に恥も外聞もない」
「それ堂々と言う事じゃないですよ」
「確かにそうだね」
へらりと笑った緋瑠人さん。なんだか不思議と肩の力が抜けた。手を引かれて歩き出したが、次は繋がれた手のぬくもりがやや顔を熱くさせる。
この人は、いつも何の気なしに触れてくるけれど、そういうところは臆病者を発揮しない。
本当に、不思議な人だと思う、不思議な魅力がある人、なんてそんなこと本人には言えないけれど。
照れ臭さのようなものが湧き上がってきて私は誤魔化すように繋がれていた手を離した。
「和香さん?」
幾分か先を歩いていた緋瑠人さんが離れた手を気にして足を止めてこちらを振り返る。
私は手を持ってきていた小さな鞄の中に入れてあるものを取り出した。
「これ」
差し出したそれを緋瑠人さんがゆっくりと受け取る。
「これは?」
「お守りです」
「お守り…」
「使わなくなった鬼怪刀の刃を削って、中に入れております。私がいなくても魔除け代わりにはなると思いますが効力はどこまであるか…」
体を引き寄せられていつのまにか緋瑠人さんの体の中に収まっていた。背中にまわった緋瑠人さんの腕が逃がさないようにか少し強まる。
「ひ、緋瑠人さんあの、ここ外…」
「ありがとう」
耳元で聞こえたそんな真っ直ぐな声に私は照れくささを隠すための行動が逆効果だったことを悟ってぐっと体に力を入れる。感情が持っていかれそうだったからだ。
「ただのお守りですよ」
そう言うと、緋瑠人さんは手の中にあるお守りを私の背中あたりで揺らした。お守りについている小さな鈴がチリンと音を立てる。
「俺のために作ってくれたのが嬉しいんだ。大好き、和香さん」
なんで、会って間もないのにこんなに真っ直ぐに気持ちを伝えてくれるのだろう。
ゆっくりと彼の背中に手をまわそうとしたその時であった。
「あの」
近くで聞こえた控えめな声。
咄嗟に緋瑠人さんの体を押し除ける。人様の家の前でなんてことをしていたのだろうかと我に返り、声の方に頭を下げた。
「すみません、なんというか、そういうのではなくて」
「もしかして、伊澄家の方ですか」
私のしどろもどろな言い訳に冷静な声を返され、私はおずおずと頭を上げる。立っていたのは私とあまり歳の変わらない女性であった。
抱き合っているところみられたにも関わらず何事もなかったかのように隣の緋瑠人さんが「はい」とにこやかに返事をする。
「あなたは鎌苅家の末っ子の、志乃子さんですね」
緋瑠人さんの言葉に少し驚いたような顔をして小さく頷いた女性が前に手を組んだままゆっくりと私たちに近づいてくる。
「中で姉たちが待っております、行きましょう」
私たちのそばで足を止めてそう言った志乃子さんは顔を合わせないまま少し先を歩き始める。
隣を見れば緋瑠人さんの笑みが消えていた。少し虚な瞳で先をいく志乃子さんを見つめている。
「緋瑠人さん?」
名を呼べば我に返ったようにいつもの笑みに戻り、「行こうか」と再び私の手を握った。
前を歩く志乃子さんに聞こえないように私は緋瑠人さんに顔を寄せた。
「なぜあの方が末っ子の志乃子さんだと分かったんですか?」
「小さい頃会ったことがあるんだ、末っ子同士というか、省かれもの同士仲良くしてた、彼女は俺より幼かったから覚えてないんだと思う」
「省かれもの同士…」
引っかかる言葉であったが、志乃子さんが大きな扉の前で足を止めたため、口をつぐんだ。
門から鎌苅家の敷地内に入って結構歩いたように思う。
それに、あたりを見渡せば離れがたくさんあり、扉もいくつか見つけたため、志乃子さんが来なければ正直ここまで辿り着けたかどうかも分からない。
志乃子さんが扉を開け、「どうぞ」と私たちを中に促した。
「緋瑠人さん」
「なに」
「さすがに中では手を離してください」
「なんで?」
ちらりと私たちの側で凛と佇んでいる志乃子さんを視界に入れる。私の視線に気づいた志乃子さんは着物の袖で口元を隠した。
「私のことはお気になさらず、もう行きます」
気を悪くさせてしまったかもしれないと、来て早々嫁の立場として印象が悪くなってはこれからの不安材料になるのは確かだと緋瑠人さんとの繋がれている手を荒々しく外し、私は離れて行こうとする志乃子さんに手を伸ばした。
「…心配しなくても、私は家のことには関わりないので」
伸ばした手は弾かれ、冷たく感情が感じられない言葉が投げられる。
「右奥のお部屋にお姉様とお兄様がいます。そこに向かってください、私はこれで」
「君も鎌苅家の人間だろう、相続の件に関しては一緒に話をするべきでしょう」
緋瑠人さんの言葉に志乃子さんがこちらに背中を向けたまま足を止めた。
そして怪訝な横顔をこちらに向け、袖口を口元に当てる。
「いいえ、私はここにはおりたくありません」
そう言って私たちが向かおうとしている方とは逆の方へ早足で去っていく。
緋瑠人さんの方をみると、苦い顔でこちらを見ていた。そして人差し指を自らの方へと向ける。
「俺が臭かったのかな、あからさまに嫌な顔してたけど」
「違うと思いますけど」
どうか、厄介ごとには巻き込まれませんようにと願う時にかぎってそれは嫌な予感の上に成り立つ感情なのだということを私は知っている。
いなくなった志乃子さんのあとを目で追って深いため息をついた。