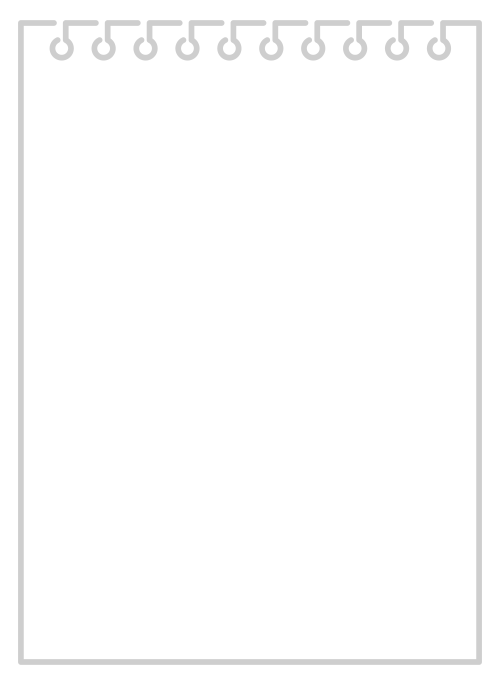ーーーーーーー
控えめな戸を叩く音で私は筆を動かす手を止めた。
「はい」と返事をすると戸がゆっくりと開く。
「和香さん」
顔を覗かせたのは申し訳なさそうな表情の緋瑠人さんである。身をくるりと返して緋瑠人さんの方に向く。
「どうしましたか」
「ああ、いや、中々寝つけなくて」
それを言いたいのは私の方だ。自分の家だろうに、とため息をつきたいのを堪えて私は「どうぞ中へ」と彼を促す。緋瑠人さんが部屋に入ってきて戸が閉まった瞬間、なんだか妙に緊張した。
控えめに私たちを照らしている部屋の光が一瞬乱れた。
私の正面に座った緋瑠人さんがにこりと笑う。
「ここでの暮らしはどう?」
「…なんというか、坂戸の家にはないものばかりで新鮮な気持ちです」
「へえ、例えば?」
私はおずおずと人差し指を上に向ける。
「部屋の作りが全体的に洋風ですし、電気なども通っております」
「坂戸の家でも電気は通ってたでしょう」
「基本夜は蝋燭の光の元で書き物をしておりましたので」
「ふうん」
そう言って緋瑠人さんが身を滑らせるように私に近づいて、すぐそばにある小さな棚を積み重ねた机を覗き込んだ。
「何書いているの?」
「父に近況報告を」
「へえ、マメだね」
私のすぐそばでそう言って途中まで書いていたそれを覗き込んでいる緋瑠人さん。机に肘を置いて、「綺麗な字」と言葉をこぼす。静かな空間、薄暗く、小さな電球だけが私たちを照らしている。
「机と椅子を今度買ってこよう、こんなところで書き物をすると足が痛むでしょう」
「いえ結構です、慣れてますので」
ふわりと緋瑠人さんの香りが鼻を掠める。
逃げようしていた体が緋瑠人さんの方に向けられ、そのまま気づけば抱きしめられていた。
先ほどまで普通の会話をしていたのに、なぜこんな状況に。と、身動きが出来ずにいた私に緋瑠人さんは小さな声で私の名を数回呼んだ。
「あ、あの、緋瑠人さん、これは…」
「夜目を瞑ると怖くなるんだ、いつか俺も父や兄たちのようになるんじゃないかって。毎日夢をみる、あの日のこと」
「緋瑠人さん」
そっと背中に手を添えると、緋瑠人さんの腕が強まる。
「和香さん、お願いだから一生俺のこと守ってね」
言葉は、執着は、時に相手を深く縛り付けるものだと思う。それは、あやかしが人間と契約をする時に似ているのだろう。彼の言う「一生」とはそういうことだ。これも一種の契約で、だから、私をここに嫁がせた。
この大きな家の中でこの男は『臆病者』という枷を抱えながら必死に生きているのだ。
「はい」
気づけば返事をしていた。ゆっくりと体が離れていく、安堵するまもなく何故かそのまま床に体が倒れた。視界に入った男が、先ほどとはうってかわっていつしか見せた笑みとは少し違ったような顔を見せた。
「でもさ、たぶん和香さん、本当に自分がただの用心棒だと思ってるみたいだけど」
気づけば上に緋瑠人さんがいる。そして、不敵に笑みをこぼした彼は私に顔を近づけた。
「君は俺の妻ってこと、忘れないでね」
頭から頬をなぞるようにその手が降りていく。
「お、臆病者が、こんなことできるわけ」
「なに、臆病者のひ弱な三男坊は恋もしちゃいけないし、好きな人に触れてもいけないの?」
「っ、まっ」
「またない」
首のあたりを噛まれ、声を出さないようにと唇を噛み締める。やはり、部屋に入れるべきじゃなかった。
夫婦になったとはいえど、所詮はあやかしから守るための存在だとこの男を侮っていた。
心の準備など、できているはずもない。父に向けた手紙に書き加えることがある「どうか私を坂戸の家に戻してください」と。
「…好きだよ、和香さん」
到底、逃げられるわけもないのだけど。
近づくその顔に私を覚悟を決め、目を瞑る。
ーーーが、すぐさま開いた。
緋瑠人さんの鳩尾に膝をめり込ませて、そのまま身を反転させて立ち上がる。
緋瑠人さんは苦しそうにその場にうずくまった。
「わ、和香さん、今、わりといい雰囲気だった…」
「言ってる場合ですかっ」
「え?」
「あやかしです!」
そう言った瞬間、閉まっていた戸が開き、気を抜けば身が後ろに倒れ込んでしまうほどの風が私たちを包む。
そばに置いていた鬼怪刀をなんとか手に取り、構えた。
風が止んだと思った矢先、開いた戸の暗闇からゆっくりと何かがこちらに近づいてくる。
緋瑠人さんよりも幾分か大きいそれは、初日にみた小さなあやかしとは比べものにならないほどの強さであることは明白だった。
「わ、和香さん、あれ…」
「今から結界の張ってる離れに逃げれますか」
「無理!1人で行けない!一緒に行こう!」
「子供か!」と声を荒げそうになったが、それを覆いつくすような唸り声があやかしから発せられる。
開いた大きな口から白い牙が光った。
刀を抜いて構えるとあやかしは私の持っている刀が鬼怪刀であることに気付いたのか少しの動揺を見せた。
その小さな隙をつくように私はあやかしに向かい走り出す。
「和香さん!」
緋瑠人さんの心配を帯びた声が部屋に響いた。
私はやはり、彼を守るためにここにきた。浮ついた気持ちが芽生えたら守るものも守れない。
自分の体を覆うほどの腕が上から振り落とされる。
「っ!」
刀を一度床に突き刺し、柄に片手を置きそれを軸にして体を浮かせたあと振り落とされたあやかしの腕に飛び乗った。
そのまま上から斬り殺そうとしたが、反対の腕で体ごと振り払われる。
衝撃を逃すために地面肩叩きつけられる前に体を捩り、地面に足をめり込ませた。
すぐ後ろには緋瑠人さんがいる。
あやかしは、大きな口が目立つ獣になっているが存在は黒いモヤに覆われており、その瞳がどこに向いているかは分からない。
しかし、私の後ろにいる緋瑠人さんを狙っていることは明確だった。
「…緋瑠人さん、1人で逃げられますか」
「腰が抜けて無理かも」
弱々しい声が背後から聞こえる。失神されるよりは、まだ会話ができるだけ幾分かましだ。
あやかしは思い通りにならないことが納得いかないのか大きな唸り声を上げた。
「あなた、もしかして元は人間?」
その問いにあやかしは答えない。大きな口からは唾液が滴れており、言葉になっていない声をあげ続けている。どんな契約を結んだのか、なぜ、あやかしになってしまったのか問いただすこともできない。こうなってしまえばもう、
「答えないなら、さっさと狩ってしまうまで」
あやかしに向かい走り出した瞬間、また手が叩き潰すように振り落とされるが飛んで腕に刀を突き刺した。
苦しそうな声を響かせたが同情の余地などない。
あやかし自身の欲望が大きければ大きいほど、一発で仕留めるのは難しい。
人間でいう心臓、核なる部分を斬らないとその存在は消えない。
身を翻し、勢いのまま刀をあやかしの首から胸あたりにかけて一気に上から下に切り裂いた。
赤黒い飛沫をあげて存在が消えていく。
何度か荒い呼吸を繰り返して、わたしはあやかしが残した黒いしみと地面に入ったヒビを視界に入れゆっくりと息を吐く。
そして今だに尻をついて唖然としている緋瑠人さんをみる。
「大丈夫ですか、緋瑠人さん」
「こっちの台詞だよ」
ゆっくりと立ち上がった緋瑠人さんが歩いてきた。
そして自分の着物の袖を持ち上げて私の頬にあてる。
「返り血がついてる」
「あやかしの残骸は、返り血というのでしょうか」
「残骸って言い方の方がぞっとするからやめて」
そう言って苦笑いで返り血を拭った後、深く息を吐いて私を抱きしめる。
「ありがとう、和香さん」
「いえ」
こんな調子であやかしを寄せつける旦那様のそばにいて私がゆっくり眠られる日がくるのかいささか不安である。