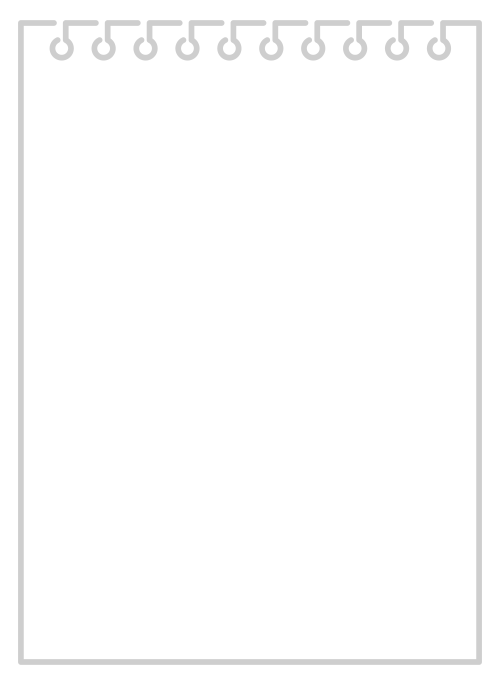2人きりの空間、正面には名家伊澄の若き当主、緋瑠人さんが座っている。
先ほどからにこにこと笑みをこぼしながら私を見つめている緋瑠人さん。何なのだ、この時間は。
「あ、あの」
「なんだい、和香さん」
「今回、嫁いだのは、緋瑠人さんをあやかしから守るためだと父から伺っております」
緋瑠人さんは少し悩むように顎に手を添えたあと、小さく口を開いた。
「それもある」
「それしかないですよね」
「確かに和香さんはあやかしのことに関して、申し分ない腕をもってる。だから側におきたいってのもあるけど」
少し離れた距離を縮めるように、緋瑠人さんは腕を前についてそのまま身を滑らせるように私に近づく。端正な顔がいきなり至近距離にきて、思わず身を後ろにしようとしたが緋瑠人さんは私の片手をつかまえてそのまま手前にひいた。
「っ」
「聞いてない?俺が君に惚れてるってこと」
その瞳が先ほどの軽やかな笑みとは異なる弧を描いた。握られている手に力が入った。
「わ、私は、緋瑠人さんと以前にお話したことがありましたでしょうか」
戸惑いを隠しきれないままそう問うと、緋瑠人さんは「ううん」と首を横に振った。
では、なぜ惚れているだなんて。まさかあやかしから自分を守ってくれる存在がほしくて適当なことを言っているんじゃないだろうか。むしろそっちの方がいい。
しかし、無情にも緋瑠人さんの口から「でも」と続きの言葉が紡がれる。
「以前君のところの神社で舞をみたことがあって、そこで和香さんを見たんだ」
「舞…」
「そう、まるで蝶みたいに舞っていて目が離せなくてとんでもなく綺麗で、一目惚れだったんだ」
真っ直ぐとしたその言葉と瞳、容易く動揺した。顔に熱が溜まっていく。
1年に1度行われる神社の祭りで行った舞のことを言っているのだろう。伊澄家からは多額の寄付をもらっているためこちらももてなさない訳にはいかない。
でも、
「お父様や長男の昌史さんとはお会いしましたが、あの時緋瑠人さんとは…」
「俺は所詮、臆病者の三男だからね。一家が絡む行事ごとでは父や昌史兄さんとは一緒にいなかったんだ、恥をかかせるだけだし」
でも今や伊澄家の当主になっている。いや、ならざるを得ない。何せ全員亡くなっているのだから。
私は手をするりと外して、自らの膝の上に避難させたあと、緋瑠人さんから距離をとるように少し身を後ろにずらした。
「やっぱり、こんなあやかし寄せつけ体質で、怖がりの臆病者の男に嫁ぎたくなんてなかったよね」
拗ねたような口ぶりでそう言って手を反対側の着物の袖の中に入れて小さく唸った緋瑠人さん。
歳は私より3つ上の22歳だときいているが、どこか幼くみえる。顔つきは大人びており、端正だが、言動がそうさせているのだろう。
私は、「いえ」と言葉を発したあと、畳に手をつき頭を下げた。
「失礼も承知で1つお伺いしてもよろしいでしょうか」
「なに?」
「伊澄の血を引くものは、全員殺されたと話を伺っております」
「…うん」
緋瑠人さんの声が幾分か低くなった。触れられたくない話だろうが私もここに住まう以上、聞きたいことがたくさんある。
両手をついたまま顔を上げた。
「あの事件はあやかし、もしくは、あやかしと契約を結んだ人間の所業の可能性はございますか」
緋瑠人さんは驚いたように瞳を開いたあと、瞳を落として小さく息をはいた。
「ああ、なるほどね」と、そう動いたあと口角が少し上がる。
「俺がこの体質を利用して、俺を虫螻のように扱ってきた父や兄たちに復讐した、とかそういうことを疑ってる?」
「いえ、そういうわけでは」
「まあそういう噂が流れてもしようがないよね、現に伊澄家の当主になっちゃってるし」
「困った困った」と後頭部に手を添えてへらりと笑った緋瑠人さん。
「あの時、俺は田沼と出かけていて、帰った時にはこの家は血の海だった。本当はこんな家なんだか怖いし、早く売り払いたいところだけど父や兄たちが残した仕事がたくさんあってね」
「そうですか」
「本当は当主なんて大それた立場は務まらないんだ」
だから、自分はこの事件とは全く関係ないと。まあ確かに臆病者で当主などという肩書きに興味がない緋瑠人さんが家族を殺すとは到底思えない。
あやかしをみて失神する男だ。人殺しなんて絶対に無理。
ひとまず1番に疑っていたことは自分の心の中で払えたようには思える。だからと言って、完全に信用したわけではないけれど。
そもそも一目惚れだなんて、そんなものも信じていない。
「父たちの事件に関しては、俺もよく分からないんだ。誰が殺したのかも」
「…探したいとは思わないんですか」
緋瑠人さんは小さく唸った。
「変に探って、俺も殺されちゃったら怖いし」
肩を上げて両腕に手を添えた緋瑠人さん。とことん臆病者である。
私は小さく息をはいた。
「分かりました、私も事件に関しては少し気になりはしますが、ひとまず緋瑠人さんをお支えできるよう精進いたします」
緋瑠人さんの瞳に光が宿る。そしてなぜか縮こめていた両腕を広げた。
「なんですか?」
「めでたく夫婦になるんだ、愛の抱擁を」
「結構です」