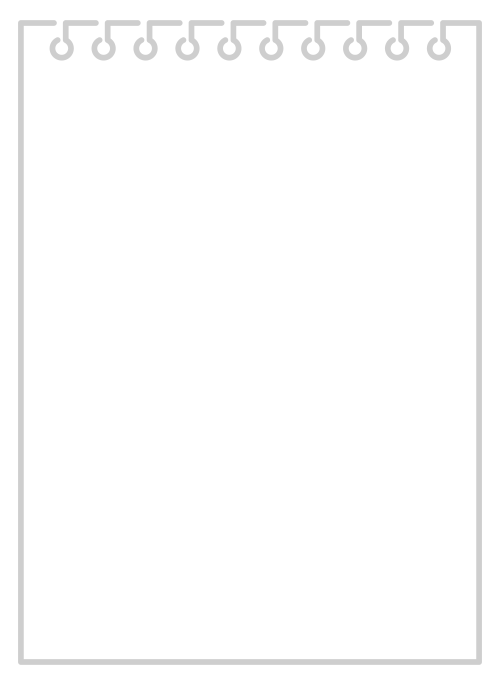ーーーーーー
「和香、伊澄家に嫁いでくれ」
秋晴れの朝、外では鳥たちが呑気に鳴いている。
目の前に置かれた朝食を今日も綺麗に食べ切ったそんな穏やかな日に父の口から吐き出された物騒な言葉。
飲んでいたお茶を喉に詰まらせて咳き込んだ。
口元を手で押さえて、少し前のめりで苦しんでいる私の横で、妹の香織が不服そうに腰を浮かす。
私の代わりに【伊澄家に嫁ぐことがどんなに危ないことか】を力説してくれるのかと思ったが、妹の口からこぼれたのは存外違うものであった。
「ええ、お姉様だけ嫁に行くなんてずるい」
「不服な部分確実にそこじゃないでしょ」
軽く喉を鳴らして自身を落ち着かせたあと、至って冷静に私は子供のように頬を膨らませている香織の肩を軽く叩く。大袈裟に「もう、お姉様野蛮」などと舌を出していた。なるほど、これは嫁ぐには時間かかるかもしれない。
「お父様、聞き間違いではなければ先ほど『伊澄家』とおっしゃいましたか?」
「ああ」
「ああ」って。ずぞぞぞぞっと味噌汁を盛大に音を立てて飲んでいる父を睨みつける。香織がこそりと私の耳元に顔を寄せた。
「みてお姉様、お父様も確実にお姉様に怒られると思って茶碗で顔を隠してるわ、冷静さを保ててないのね」
「冷静さを保ててないのはお互い様よ、あのじじい自分がどんな発言したか分かってんのかしら」
「お父様をじじい呼びなんて、殺されますよお姉様」
「返り討ちですわよ」
「聞こえているんだが」
父が冷静さを保てていない手つきで茶碗をお盆の上に置いた。冷静さを保ててないが故に底がぶつかる音がやけに響く。
私は一度咳払いをして、姿勢を正した。
「お父様、伊澄家ってどういうことですか?なぜわざわざあんな物騒な名家に」
「伊澄家は、昔からうちの神社に多額の寄付をしてくれているのはお前も知ってるだろう」
「ですが」
「物騒だというのはごもっともだ、あそこは三男の緋瑠人さん以外、全員…」
「殺されてますよね」
その私の言葉で空気が張り詰めた。今まで、お父様の意向に背いたことはほとんどない。それは私自身も納得して修行や学問に励んできたから。
しかし、こればかりは容認しかねる。
「伊澄家の惨殺事件、まだ解決していませんよね、あの人たちは解決する気があるのかも分かりません。そもそも、あの事件は人間の所業とは思えませんし、もしかしたらあやかしが」
「和香」
続きを制するように父が私の名を呼んだ。押し黙った私に父は1つため息をついて口を開く。
「惨殺事件があやかしと関係しているかどうかは分からないが、1つ気掛かりなことがあってな」
「気掛かり?」
「生き残った息子、緋瑠人さんはどうやら」
「超美男子なんでしょ!?」
父の声に被せるように香織が両手を合わせてそう言う。
「いや、まあ、そうなんだが」
「いいなあお姉様、私が代わりに嫁ぎたい」
「それは無理だ」
父は香織の言葉に首を横に振った。香織が再び頬に空気をためる。その姿を横目に私は「それはなぜですか」と父に問う。代わってくれるものなら代わってほしい。私が誰かに嫁ぐなど無理に決まっている。ましてや昔からの名家であり何かと物騒な『伊澄家』だなんて。
「緋瑠人さんは、どうやらあやかしを寄せ付けやすい体質らしくてな、しかも、とんでもない臆病者らしい」
「お姉様、しっかり励んできてください」
「切り替え早くない?」
香織はすでに話を聞く気がなくなったのか、「さて片付け片付け」と立ち上がりその場を逃れようとしている。そんな姿を呆れ顔で見送っていると、父は再び真剣な顔で私を見つめた。
ああ、なんとなく、意図が理解できた気がする。
「要は、用心棒が必要なんですね」
「そんな言い方をするな、名家の嫁に行けるんだ」
「しかし、私たちの家は代々あやかし狩りの一族ではあるものの、今の世は他にもあやかしを狩れるものは大勢います。なぜ、私なのですか?
それに嫁など面倒くさいことをしていないで、誰か雇えばいいのでは」
「それがな」
父が苦い顔をしていた。そして言いにくそうに視線を落とす。嫌な、予感がした。
「惚れてるらしい」
「誰が」
「緋瑠人さんが」
「誰に」
「お前に」
「なぜですか。私は緋瑠人さんの顔も知らなければ話したこともございません」
惚れている、など到底私に向けられた言葉だと思えない。人違いではないのだろうか。
用心棒として働けと言われた方が単純で、幾分かマシであったのに。
「私もよく分からないんだ。しかし、今後の寄付…両家の関係を考えて、あちら様の要望をのむしかできないだろう」
父はバツの悪そうにそう言って私の前にそれを差し出した。
「これ…」
「新しい鬼怪刀だ、お前のために打った」
「鬼怪刀ならお父様から譲り受けたものがあります」
「新品をつかえ、これから使うことが多くなる」
「結局嫁は名目で、用心棒じゃないですか」
「まあそう言うな。いいか、あやかしは」
ーーー「鬼怪刀でしか狩れない」
私は父の言葉に頷いた。そして刀を受け取る。
昔から口酸っぱく言われてきた言葉だった。あやかしは普通の刀では祓えない。
鬼怪刀といわれる刀で、能力をもったもの達だけが奴らを祓うことができる。
「和香、お前はここ数十年の代の中で1番あやかし狩りの素質がある。絶対に緋瑠人さんを危ない目に合わせるなよ」
「はい。伊澄家からの寄付を途絶えさせないためにも」
「それ以上言ってくれるな、責められてる気分になる」
「責めてるんです、お父様」
ニコリと笑ってそういえば父は口をへの字に曲げて「すまない」と蚊の鳴くような小さな小さな声を放った。
こうして私は、謎が多い名家の「伊澄家」ひいては生き残りの1人息子に嫁入りすることになってしまったのである。