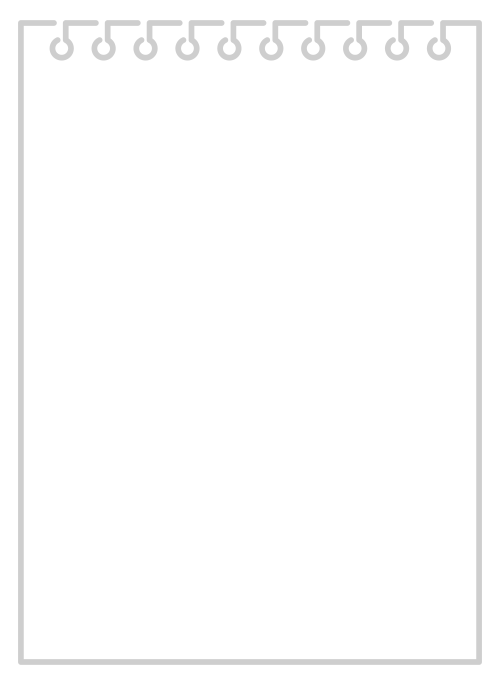ーーーーーー
「…緋瑠人さん?」
タオルで髪の毛を拭きながら部屋に戻る途中私は廊下の先にいる姿を視界に入れて足を止めた。
緋瑠人さんはこちらに気づいておらず、緋瑠人さんの正面には志乃子さんがいた。
どこか苦しそうな様子の志乃子さんの前で、緋瑠人さんはそっと手を差し伸べている。
なんだか、少し心がもやりと霧がかかったような感覚になった。その気持ちの答えを巡らせることから逃げるように私は視線を逸らし、部屋の中に入る。
「っ」
気を遣ってもらったのか、部屋には布団が敷かれており2つ綺麗に合わさり並んでいた。
咄嗟にその距離を離す。
別に走ったわけでもないのに変に息が切れ、私はゆっくりと息を吸った。こんなに取り乱すなんてバカみたいだ。所詮私は緋瑠人さんを守るための嫁。それ以上の感情を抱いてしまうことは「あやかしから彼を守る」という信念から外れてしまう。
うつつを抜かしていては、守れない。
両手を腰に当て、短く息を吐いた。
と、その瞬間に部屋の戸があく。
「なんで部屋の真ん中に仁王立ちしているの、和香さん」
「あ、えっと」
「ああ、布団敷いてくれたんだね」
「いえ、これはおそらく使用人の方が…」
「そっか」
先ほどの志乃子さんとの光景が脳裏をよぎり緋瑠人さんを直視できない。
私がわたわたと行き場のない焦りを身にまとっていると緋瑠人さんは小さく笑いながら布団の上に座った。
「お風呂大きくて、温泉みたいで気持ちが良かったね」
「そ、うですね」
立ち上がったままそう返事をする。
嫁いでまだ間もない私にとって緋瑠人さんと2人きりで過ごす時間というのはいまだに慣れていない。
そして勝手に気まずさを抱えている私にとってこの状況は正直逃げたい。
もはや小さなあやかしでも出てほしいくらい。
「和香さん」
「はい」
「座って」
緋瑠人さんが自分の正面をぽんぽんと軽く叩く。
おそるおそるといった形で正座で座れば手に持っているタオルが抜き取られ、頭に被せられた。
「わっ…」
「まだ髪の毛濡れてるよ」
「じ、自分で拭きます」
「いいからいいから」
優しい圧で私の髪の毛を拭いていく緋瑠人さん。
見え隠れする緋瑠人さんの顔が少し嬉しそうだった。
「緋瑠人さん」
「ん?」
「…先ほど、志乃子さんと何を話されていたんでしょうか」
自分の口から放たれたそれ。思わず手で口元をおさえる。こんな聞き方、ダメだ。
なんだか責めているみたいな言い方になってしまった。
緋瑠人さんの手の動きが止まる。不安になり、落としていた視線をあげた。
それと同時に緋瑠人さんの顔が近づく。
「嫉妬、してくれたの?」
「なっ」
黒い靄の正体をいとも容易く「嫉妬」の言葉で片付けられたのが解せない。違う、と思いたい。
首を横に振ると、緋瑠人さんの手のひらが頬に触れた。
「和香さん」
「はい」
「他に何か不安なことはない?」
「不安なこと?」
「今日みたいに何も知らない人間から好き勝手言われて、和香さんが傷ついてたら、俺から離れたら嫌だなって」
何も知らない人間、というのは鎌苅家の満さんたちのことを言っているのだろう。
あの時は何も知らない人間がどう言おうと気にしませんと真っ直ぐな瞳で言っていたのに、私に向けられた今の瞳は不安を帯びていた。
これが、緋瑠人さんの本音なのだろうか。
私はゆっくりと再度首を横に振る。
「嫁いできたのに、そんな簡単に逃げ出しませんよ」
そう言えば、緋瑠人さんの手が頬から降りていき私の手を絡めとる。
「守ってくれるのはとても嬉しいけど、やっぱりそれ以外の感情も感じたいな、和香さん」
「っ、」
ぎゅっと握られた手。端に溢れた「臆病者だし」という言葉。握られた手の上からもう一方の手を重ねた。
「意外と、緋瑠人さんは臆病者じゃないと思います」
「え?」
「ちゃんと自分の意見をもっていて、芯があって、素敵な人です」
間違えないように言葉を選んだわけではなく、自然と放った言葉。ああ、これが自分の本心なのだと気づいた時には顔に熱が溜まる。
「え、じゃあ俺のこと好きってこと?いや、大好きってこと?キスしていい?」
「ダメです」
手を無理やり押し退けて私は恥ずかしさのあまり布団の中に潜り込んだ。
真っ暗になった視界の外で「素直じゃないなあ、和香さん」とどこか嬉しそうな緋瑠人さんの声が聞こえた。