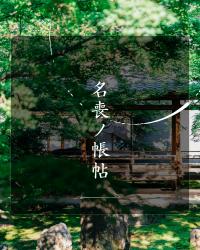打ち上げ当日となってしまった。
つい先日まで、テストの存在に打ちひしがれていたはずのクラスメイトたちも、今はそんなことをすっかり忘れてしまったかのように、体育祭の余韻に浸って笑顔を交わしていた。
気づけば、打ち上げメンバーが集まるグループチャットに僕もいつの間にか加わっていた。
参加するために名前を紙に書いたんだ。
誰が僕をそのグループに招待してくれたのかなんて、考えるまでもなくわかってしまった。
いつも僕を気にかけてくれて、そっと手を差し伸べてくれるりくと。
彼の優しさに胸の奥がじんわりと温かくなった。
参加者はなんと47名。
その人数の多さに思わず目を見張った。
ブロックの半数以上の人が参加する規模数。
急な呼びかけだったはずなのに、これだけの人数が集まるなんて。
僕にとっては信じられないことで、みんなのノリの良さと団結力に驚かされた。
本当に、あっという間に予定が決まり、準備が進んでいったことにも驚きだった。
会場候補や持ち物などの話題が次々と飛び交う。
僕はその流れに圧倒されるだけだった。
その流れの速さに臆することもなく、幹事役として全体をまとめてくれている廿楽君のリーダーシップに感謝していた。
打ち上げの会場に選ばれたのは、駅からすぐの場所にある、持ち込み可能なカラオケ複合型施設。
アクセスも良くて、みんなが集まりやすい立地。
誰もが納得の選択だったように思う。
事前に少し調べてみると、その施設は想像以上に大きかった。
公式サイトにはカラフルな写真が並べられていて、複数のフロアに分かれているようだった。
カラオケだけでなく、ボウリングやダーツ、ビリヤードなどが揃っていて、さらに複数の飲食店が入っている充実ぶりだった。
ファストフード店からカフェまで。
ジャンルも豊富で、食事の選択にも困らなさそうだった。
遊びも食事もその施設内で楽しめる、まるでテーマパークのような場所のように思えた。
僕のようにあまり外出しない人間にとっては、少しだけ敷居が高く感じられる場所。
しかも、高校生割引と平日割引を併用できるらしい。
僕たちのような学生にとってはとてもありがたいサービスだった。
通常料金よりもかなり安くなるようで、予算を気にしていた僕にはまさに朗報だった。
僕以外にも予算について気にしていた人はいるみたいで、良心的な価格設定で楽しめる施設を見つけ出してくれたりくとには、あらためて感謝の気持ちでいっぱいだ。
お金の心配をせずに楽しめるというだけで、気持ちが随分と軽くなった。
「学生証忘れないように。」
そう連絡があったことを思い出して、僕は鞄の中から学生証を取り出した。
受付の店員さんにそっと差し出す。
手が少しだけ震えていたのは、初めてのことに少しばかり緊張していたせいだった。
できるだけ丁寧に、失礼のないようにと心がけた。
店員は慣れた手つきで学生証を確認していく。
「学生証の提示にご協力いただきまして、ありがとうございます。ドリンクバーの機械は受け付け横にございます。通路の突き当たりはお手洗いになっておりまして、左手に進んでいただきますとカラオケルームやエンタメコーナーがございます。注意していただきたいのは、飲食物はカラオケルームのみ持ち込み可能となっている点です。2階には飲食店やコンビニもございます。お代金は代表の廿楽様よりいただいておりますので、ごゆっくりとお楽しみくださいませ。」
「はい。」を何度使ったかわからない。
施設内の説明をしてくださった店員に会釈をし、好きなドリンクを入れてカラオケルームを目指す。
ドアを開ける前に念のため軽くノックして入ると、もう既にほとんど全員集まっていそうだった。
みんな思い思いに楽しんでいる。
写真で見るより広いカラオケルームに驚いて、立ちすくんでいると、僕に気づいたりくとが席を立ち、傍に寄って説明をしてくれた。
「澪かー!店員かと思って焦った。真ん中においてあるザルん中に各自持ちよったものを入れてる!ココにいない人たちはエンタメコーナーや食事に行ってるから、澪も好きなときに曲いれたりダーツに行ったりごはん食べたりしてくれよな!」
歌っている人の邪魔にならないようにという配慮だろう。
僕は声を潜めながらりくとに問いかけた。
「あの、お金はいつ渡せばいい?りくとがみんなの代金を立て替えてくれたって店員に聞いて。」
「あとでチャットで知らせるつもりだったんだけど、先に伝えとこうか。」
歌い終わった頃を見計らって、マイクをとった彼。
「あー、あー。ちょっと注目!あとで連絡はするけど一応伝えておきまーす。今日の代金は現金でも電子でもどっちでもいいので、夏休み前までに返してもらえたら助かるかなー!」
部屋の空気を壊さないように明るく柔らかいトーンで話す。
「わかった」「了解」「承知」
各々がりくとに返事をする。
「澪も適当に座って、打ち上げ楽しんで。」
「うん。ありがとう。」
彼はマイクを持ったまま、みんなの前まで行き、曲を歌い始める。
僕は鞄から出した大袋のお菓子を開封し、ザルに乗せていく。
すでにザルの中には個包装のお菓子たちが敷き詰められている。
僕は空になった袋を小さくしばると空いている席に腰を下ろした。
鞄からお菓子袋と入れ換えに出したのは勉強ノート。
この大勢の中、僕にはマイクの順が回ってくることはないだろう。
回ってきたとしても歌える曲がそもそもない。
音楽に疎い僕は、最近流行している話題の曲など知らないからだ。
みんなが盛り上がる定番ソングも分からない。
ノートを確認しながら、時々ザルに視線を移す。
僕の持ってきていたお菓子に手を伸ばしている人や、食べてくれている人を見て、安堵の息を漏らした。
どうやらこのお菓子の選択で間違っていなかったようだ。
歌が歌えるわけでもなく、盛り上げ上手なはずもない僕は、それ以降勉強に集中していた。
「みーおー!澪ー!」
りくとの声がカラオケルームに響いて、僕は思わず顔を上げた。
周りには誰の姿もなく、カラオケルームには僕と彼の2人だけだった。
「り、くと……。」
「みんな、そろそろお昼で2階の飲食店に行くってさ。」
りくとはスマホの画面を見せながら言った。
気づけばもう12時を過ぎていて、時間の流れがあっという間だったことに驚いた。
「みんな、鞄とか置いて食べに行ってるみたいだから、僕はここに残ってるよ。」
「貸し切りとはいえ、荷物を置きっぱなしってのはちょっと不用心だしな。それなら、俺もここに残ろっと。」
そう言って、りくとは僕の隣に座り直した。
「みんな今いないし、澪も何か歌ってみなよ。」
「多分、陸と知らないと思うけど。」
「いーよ、いーよ。歌える曲歌って楽しむのがなんぼでしょ。みんなもいないし、ほら。」
りくとか手渡されたマイクを取り、1曲だけ歌うことにした。
音程が外れてしまう僕の歌に、りくとは合いの手を入れてくれる。
マラカスやタンバリンまで持ち出して、僕の歌を盛り上げてくれた。
食事から戻ってきたみんなと入れ替りで僕たちは2人、カラオケルームを出る。
食事後はダーツやビリヤード、ボウリングなどのエンタメコーナーへ。
僕の不得手なことでも一緒に笑って楽しんでくれる。
そんな時間を設けてくれたりくとには感謝してもしきれない。
りくとは僕に気を使ってくれているのか、カラオケルームに戻ろうとは言なかった。
周囲に誰もいないことを確認して、僕は意を決して言葉を口にした。
「あの……りくとさえ良ければ、今度どこかへ遊びに行きませんか!」
「おっ、それってデートのお誘い?いいよ、行こう。いつにする?」
「学期末テストが終わった後の夏休み期間中......文化祭の準備に重ならなければ......とか?」
自分から言い出したことなのに、言葉尻が小さくなっていく。
「それならさ、休み明けテストの勉強見てほしい!期末テストは今さら間に合わないから捨ててるんだけど、勉強デートとかどう?俺得にしかならないけど、澪先生。」
「う、うん。それで僕も構わないよ。他者に学んだ内容を教えることは、最も効果的な想起学習の手法のひとつだって言われてるから。」
よっしゃ。とガッツポーズをしているりくと。
よほど勉強に自信がないのだろうか。
「俺、自分の部屋だと集中できないタイプでさ。図書館だと声出せないし、ファミレスだと長居しすぎると迷惑になっちゃうし……。」
「それなら、僕の家とかってどうかな?」
マジで?!ありがてぇと言っている彼。
文化祭の準備が終わったあとや、準備がない日に学校でという案はもあった。
なのに口に出してしまったのは自分の家。
部屋を綺麗にしておかないとなと頭の隅で考える。
「学期末テストも頑張らないと。わからないところがあったら聞いてくれていいから。」
そう伝えると、期末テストまでの連絡は全てわからないことを聞く質問のための手段と化していた。
途中からはりくとから電話がかかってくるようになり、通話をつなげたまま勉強を行った。
その甲斐あってかりくとはなんとか赤点を回避することができたようだった。
夏休みの午前中は全員対象の特別授業、午後から文化祭の準備を行うこととなっている。
文化祭仕様になりつつある教室で授業を受けるのはなんだか変な感じだ。
僕は段ボールや角材を物置から運び出し、図案に沿って小道具を作る作業を黙々とこなしていた。
体育祭でりくとと一緒にゴールしたことがきっかけだったのか、準備中に話しかけてくれる人がちらほら現れた。
僕はその変化に戸惑いながらも、どこか嬉しかった。
「廿楽と仲良いって聞いたからさ。」
話しかけてくる人の第一声には必ずりくとの名前が含まれていて、そのたびに僕の胸はくすぐったくなるような、でも誇らしい気持ちで満たされていた。
誰かと自然に話せるようになったことが、こんなにも嬉しいなんて、去年の僕には想像もできなかっただろう。
何もかもりくとのお陰だ。
「5組の甘楽 澪です。えーっと、よろしく。」
「こちらこそよろしく。でも名前は知ってたよ。」
名前までは覚えてもらえてないだろうと名乗ると、同じクラスなのに覚えてないわけないと、意図せず笑いをとってしまった。
文化祭の準備が重ならなかった日。
そして、僕の家にりくとが来て、一緒に勉強をする日。
「ありがとう。」
僕はりくとにお礼を伝えた。
「なにがー?」
「クラスの人と話せるようになった。去年はりくとが隣の席になった1月に初めてクラスメイトと話したのに。きっかけが全部りくとだから。」
「えー?俺なにもしてなくない?」
「してくれてる。いつもいっぱいもらってるよ。りくとは、僕の憧れで……道しるべみたいな存在なんだ。」
「それを言うなら、澪の方だって。誰も気づかないようなことに気づける優しさって、すごいと思う。りくとは、誰かの支えになってるのに、それを誇らない。そういうところ、僕は本当に……すごく好きだなって思ってる。」
好きっていうの恥ずいな。勉強しようぜ、勉強!と苦手な勉強に向き合う姿、横顔を盗み見ると、少し赤くなっている。
僕もつられてしまいそうになって、慌ててペンをとり、ノートに問題を解いてゆく。
僕は左利き、彼は右利き。
お互いの小指があたり、肩が跳ねる。
すぐに謝り、引くこともできだが僕たちはそれをしなかった。
僕たちはどちらともなく手を重ねて、そっと繋いだ。
正直、手を繋いだまま勉強しづらい。
でも、そんな不便さなんてどうでもよくなるくらい、今の僕は心の底から幸せだった。
手を繋いだまま2人で黙々と勉強を続け、りくとが詰まって手を止めたときには僕が教える。
こうして、勉強会──いや、僕たちの初めての家デートは静かに幕を下ろした。
りくとが帰った後、静かになった部屋の中で、さっきまでそこにりくとがいたんだと改めて実感する。
ページをめくる音や笑い声を思い出しながら、彼の匂いが僕の部屋まだ残ってるような気がしてくる。
狭いはずの僕の部屋が、彼と過ごしていたからか、1人になった今は広く思えた。
つい先日まで、テストの存在に打ちひしがれていたはずのクラスメイトたちも、今はそんなことをすっかり忘れてしまったかのように、体育祭の余韻に浸って笑顔を交わしていた。
気づけば、打ち上げメンバーが集まるグループチャットに僕もいつの間にか加わっていた。
参加するために名前を紙に書いたんだ。
誰が僕をそのグループに招待してくれたのかなんて、考えるまでもなくわかってしまった。
いつも僕を気にかけてくれて、そっと手を差し伸べてくれるりくと。
彼の優しさに胸の奥がじんわりと温かくなった。
参加者はなんと47名。
その人数の多さに思わず目を見張った。
ブロックの半数以上の人が参加する規模数。
急な呼びかけだったはずなのに、これだけの人数が集まるなんて。
僕にとっては信じられないことで、みんなのノリの良さと団結力に驚かされた。
本当に、あっという間に予定が決まり、準備が進んでいったことにも驚きだった。
会場候補や持ち物などの話題が次々と飛び交う。
僕はその流れに圧倒されるだけだった。
その流れの速さに臆することもなく、幹事役として全体をまとめてくれている廿楽君のリーダーシップに感謝していた。
打ち上げの会場に選ばれたのは、駅からすぐの場所にある、持ち込み可能なカラオケ複合型施設。
アクセスも良くて、みんなが集まりやすい立地。
誰もが納得の選択だったように思う。
事前に少し調べてみると、その施設は想像以上に大きかった。
公式サイトにはカラフルな写真が並べられていて、複数のフロアに分かれているようだった。
カラオケだけでなく、ボウリングやダーツ、ビリヤードなどが揃っていて、さらに複数の飲食店が入っている充実ぶりだった。
ファストフード店からカフェまで。
ジャンルも豊富で、食事の選択にも困らなさそうだった。
遊びも食事もその施設内で楽しめる、まるでテーマパークのような場所のように思えた。
僕のようにあまり外出しない人間にとっては、少しだけ敷居が高く感じられる場所。
しかも、高校生割引と平日割引を併用できるらしい。
僕たちのような学生にとってはとてもありがたいサービスだった。
通常料金よりもかなり安くなるようで、予算を気にしていた僕にはまさに朗報だった。
僕以外にも予算について気にしていた人はいるみたいで、良心的な価格設定で楽しめる施設を見つけ出してくれたりくとには、あらためて感謝の気持ちでいっぱいだ。
お金の心配をせずに楽しめるというだけで、気持ちが随分と軽くなった。
「学生証忘れないように。」
そう連絡があったことを思い出して、僕は鞄の中から学生証を取り出した。
受付の店員さんにそっと差し出す。
手が少しだけ震えていたのは、初めてのことに少しばかり緊張していたせいだった。
できるだけ丁寧に、失礼のないようにと心がけた。
店員は慣れた手つきで学生証を確認していく。
「学生証の提示にご協力いただきまして、ありがとうございます。ドリンクバーの機械は受け付け横にございます。通路の突き当たりはお手洗いになっておりまして、左手に進んでいただきますとカラオケルームやエンタメコーナーがございます。注意していただきたいのは、飲食物はカラオケルームのみ持ち込み可能となっている点です。2階には飲食店やコンビニもございます。お代金は代表の廿楽様よりいただいておりますので、ごゆっくりとお楽しみくださいませ。」
「はい。」を何度使ったかわからない。
施設内の説明をしてくださった店員に会釈をし、好きなドリンクを入れてカラオケルームを目指す。
ドアを開ける前に念のため軽くノックして入ると、もう既にほとんど全員集まっていそうだった。
みんな思い思いに楽しんでいる。
写真で見るより広いカラオケルームに驚いて、立ちすくんでいると、僕に気づいたりくとが席を立ち、傍に寄って説明をしてくれた。
「澪かー!店員かと思って焦った。真ん中においてあるザルん中に各自持ちよったものを入れてる!ココにいない人たちはエンタメコーナーや食事に行ってるから、澪も好きなときに曲いれたりダーツに行ったりごはん食べたりしてくれよな!」
歌っている人の邪魔にならないようにという配慮だろう。
僕は声を潜めながらりくとに問いかけた。
「あの、お金はいつ渡せばいい?りくとがみんなの代金を立て替えてくれたって店員に聞いて。」
「あとでチャットで知らせるつもりだったんだけど、先に伝えとこうか。」
歌い終わった頃を見計らって、マイクをとった彼。
「あー、あー。ちょっと注目!あとで連絡はするけど一応伝えておきまーす。今日の代金は現金でも電子でもどっちでもいいので、夏休み前までに返してもらえたら助かるかなー!」
部屋の空気を壊さないように明るく柔らかいトーンで話す。
「わかった」「了解」「承知」
各々がりくとに返事をする。
「澪も適当に座って、打ち上げ楽しんで。」
「うん。ありがとう。」
彼はマイクを持ったまま、みんなの前まで行き、曲を歌い始める。
僕は鞄から出した大袋のお菓子を開封し、ザルに乗せていく。
すでにザルの中には個包装のお菓子たちが敷き詰められている。
僕は空になった袋を小さくしばると空いている席に腰を下ろした。
鞄からお菓子袋と入れ換えに出したのは勉強ノート。
この大勢の中、僕にはマイクの順が回ってくることはないだろう。
回ってきたとしても歌える曲がそもそもない。
音楽に疎い僕は、最近流行している話題の曲など知らないからだ。
みんなが盛り上がる定番ソングも分からない。
ノートを確認しながら、時々ザルに視線を移す。
僕の持ってきていたお菓子に手を伸ばしている人や、食べてくれている人を見て、安堵の息を漏らした。
どうやらこのお菓子の選択で間違っていなかったようだ。
歌が歌えるわけでもなく、盛り上げ上手なはずもない僕は、それ以降勉強に集中していた。
「みーおー!澪ー!」
りくとの声がカラオケルームに響いて、僕は思わず顔を上げた。
周りには誰の姿もなく、カラオケルームには僕と彼の2人だけだった。
「り、くと……。」
「みんな、そろそろお昼で2階の飲食店に行くってさ。」
りくとはスマホの画面を見せながら言った。
気づけばもう12時を過ぎていて、時間の流れがあっという間だったことに驚いた。
「みんな、鞄とか置いて食べに行ってるみたいだから、僕はここに残ってるよ。」
「貸し切りとはいえ、荷物を置きっぱなしってのはちょっと不用心だしな。それなら、俺もここに残ろっと。」
そう言って、りくとは僕の隣に座り直した。
「みんな今いないし、澪も何か歌ってみなよ。」
「多分、陸と知らないと思うけど。」
「いーよ、いーよ。歌える曲歌って楽しむのがなんぼでしょ。みんなもいないし、ほら。」
りくとか手渡されたマイクを取り、1曲だけ歌うことにした。
音程が外れてしまう僕の歌に、りくとは合いの手を入れてくれる。
マラカスやタンバリンまで持ち出して、僕の歌を盛り上げてくれた。
食事から戻ってきたみんなと入れ替りで僕たちは2人、カラオケルームを出る。
食事後はダーツやビリヤード、ボウリングなどのエンタメコーナーへ。
僕の不得手なことでも一緒に笑って楽しんでくれる。
そんな時間を設けてくれたりくとには感謝してもしきれない。
りくとは僕に気を使ってくれているのか、カラオケルームに戻ろうとは言なかった。
周囲に誰もいないことを確認して、僕は意を決して言葉を口にした。
「あの……りくとさえ良ければ、今度どこかへ遊びに行きませんか!」
「おっ、それってデートのお誘い?いいよ、行こう。いつにする?」
「学期末テストが終わった後の夏休み期間中......文化祭の準備に重ならなければ......とか?」
自分から言い出したことなのに、言葉尻が小さくなっていく。
「それならさ、休み明けテストの勉強見てほしい!期末テストは今さら間に合わないから捨ててるんだけど、勉強デートとかどう?俺得にしかならないけど、澪先生。」
「う、うん。それで僕も構わないよ。他者に学んだ内容を教えることは、最も効果的な想起学習の手法のひとつだって言われてるから。」
よっしゃ。とガッツポーズをしているりくと。
よほど勉強に自信がないのだろうか。
「俺、自分の部屋だと集中できないタイプでさ。図書館だと声出せないし、ファミレスだと長居しすぎると迷惑になっちゃうし……。」
「それなら、僕の家とかってどうかな?」
マジで?!ありがてぇと言っている彼。
文化祭の準備が終わったあとや、準備がない日に学校でという案はもあった。
なのに口に出してしまったのは自分の家。
部屋を綺麗にしておかないとなと頭の隅で考える。
「学期末テストも頑張らないと。わからないところがあったら聞いてくれていいから。」
そう伝えると、期末テストまでの連絡は全てわからないことを聞く質問のための手段と化していた。
途中からはりくとから電話がかかってくるようになり、通話をつなげたまま勉強を行った。
その甲斐あってかりくとはなんとか赤点を回避することができたようだった。
夏休みの午前中は全員対象の特別授業、午後から文化祭の準備を行うこととなっている。
文化祭仕様になりつつある教室で授業を受けるのはなんだか変な感じだ。
僕は段ボールや角材を物置から運び出し、図案に沿って小道具を作る作業を黙々とこなしていた。
体育祭でりくとと一緒にゴールしたことがきっかけだったのか、準備中に話しかけてくれる人がちらほら現れた。
僕はその変化に戸惑いながらも、どこか嬉しかった。
「廿楽と仲良いって聞いたからさ。」
話しかけてくる人の第一声には必ずりくとの名前が含まれていて、そのたびに僕の胸はくすぐったくなるような、でも誇らしい気持ちで満たされていた。
誰かと自然に話せるようになったことが、こんなにも嬉しいなんて、去年の僕には想像もできなかっただろう。
何もかもりくとのお陰だ。
「5組の甘楽 澪です。えーっと、よろしく。」
「こちらこそよろしく。でも名前は知ってたよ。」
名前までは覚えてもらえてないだろうと名乗ると、同じクラスなのに覚えてないわけないと、意図せず笑いをとってしまった。
文化祭の準備が重ならなかった日。
そして、僕の家にりくとが来て、一緒に勉強をする日。
「ありがとう。」
僕はりくとにお礼を伝えた。
「なにがー?」
「クラスの人と話せるようになった。去年はりくとが隣の席になった1月に初めてクラスメイトと話したのに。きっかけが全部りくとだから。」
「えー?俺なにもしてなくない?」
「してくれてる。いつもいっぱいもらってるよ。りくとは、僕の憧れで……道しるべみたいな存在なんだ。」
「それを言うなら、澪の方だって。誰も気づかないようなことに気づける優しさって、すごいと思う。りくとは、誰かの支えになってるのに、それを誇らない。そういうところ、僕は本当に……すごく好きだなって思ってる。」
好きっていうの恥ずいな。勉強しようぜ、勉強!と苦手な勉強に向き合う姿、横顔を盗み見ると、少し赤くなっている。
僕もつられてしまいそうになって、慌ててペンをとり、ノートに問題を解いてゆく。
僕は左利き、彼は右利き。
お互いの小指があたり、肩が跳ねる。
すぐに謝り、引くこともできだが僕たちはそれをしなかった。
僕たちはどちらともなく手を重ねて、そっと繋いだ。
正直、手を繋いだまま勉強しづらい。
でも、そんな不便さなんてどうでもよくなるくらい、今の僕は心の底から幸せだった。
手を繋いだまま2人で黙々と勉強を続け、りくとが詰まって手を止めたときには僕が教える。
こうして、勉強会──いや、僕たちの初めての家デートは静かに幕を下ろした。
りくとが帰った後、静かになった部屋の中で、さっきまでそこにりくとがいたんだと改めて実感する。
ページをめくる音や笑い声を思い出しながら、彼の匂いが僕の部屋まだ残ってるような気がしてくる。
狭いはずの僕の部屋が、彼と過ごしていたからか、1人になった今は広く思えた。