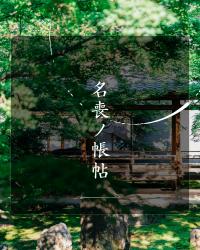ついに体育祭当日がやってきた。
空は晴れていて、体育祭日和と言っていいだろう。
しかし僕は体育祭よりも大事なことがある。
僕は、あの日の雨の中で廿楽君を置き去りにしてしまった場所に立っていた。
あのときの後悔と、廿楽君の答えを受け止めて、今日こそはちゃんと向き合いたい。
「ごめん、待たせて。」
少し息を弾ませながら廿楽君が現れる。
「ううん。僕も今来たばかりだよ。」
返した言葉は、少しだけ嘘だったけれど、彼を待つ時間さえも僕にとっては心地よいものだったから、何も問題ではなかった。
「行こっか。」
「うん、そうだね。」
廿楽君が優しく促してくれて、僕らは並んで歩き始めた。
体育祭とはいえ、まだ生徒たちが登校するには早すぎる時間帯。
まだ誰もいない校舎へ向かうその道は、まるでふたりだけの世界のようだった。
「澪さ、改めてありがとう。あの日のこと、俺は驚いたっていうより、すごく嬉しかったんだ。ずっと考えて、何が自分の答えなのか悩んだんだけど、はっきりした言葉にはできなくて……でも、出た答えは『澪のことをもっと知りたい』ってことだった。俺、異性とも同性とも、誰かと付き合った経験なんてなくてさ。だから、ふたりで手探りで進んでいけたらいいなって思ったんだ。……今も、澪の気持ちは俺に向いてる?」
「もちろん、好きなままだよ。むしろ、毎日少しずつその気持ちが大きくなってる気がする。今も、久しぶりに廿楽君と会って話せて嬉しいんだ。僕が距離を置こうっていったのに、真剣に考えてくれて歩み寄ろうとしてくれて、本当にありがとう。」
「ありがとう、澪。俺のことを好きでいてくれて、本当に嬉しい。だからさ……俺たち、恋人になろう。友達っていう枠を越えて、もっと関係を深めていこう。」
そのときの廿楽君の表情は、冗談や照れ笑いなんて一切浮かべていない。
まっすぐ僕の目を見ていた。
からかっている様子なんて微塵もなくて、彼が本気で僕との関係を大切にしようとしてくれていることが、痛いほど伝わってきた。
廿楽君は、僕の気持ちを否定することもなく、偏見を持つこともなく、ただ僕という存在をそのまま受け止めてくれた。
そんな優しさや誠実さは、ずっと前から知っていたはずなのに。
改めて気づかされて、胸がじんわりと熱くなった。
「僕も、廿楽君と一緒に、ひとつひとつ丁寧に積み重ねていきたいです。これから、恋人としてよろしくお願いします。」
あの雨の日、僕の中でずっと温めていた気持ちのすべてで、彼に伝えることができて本当に良かったと思った。
こうして、僕たちは晴れて恋人同士になった。
まだぎこちない部分もあるけれど、互いに向き合って、少しずつ歩いていける関係が始まったことに、胸がいっぱいになった。
「じゃあさ、早速だけど……手とか、繋いでみる?」
廿楽君は何気なく、でも僕にとってはかなり難易度の高いことをさらりと口にしてきて、僕は思わず固まってしまった。
「む、むりむり……いや、無理ってわけじゃないけど、ちょっとだけ早いかも……ペース的に。」
僕は慌てて言葉を繋ぎながら、顔が熱くなるのを止められなかった。
廿楽君は、普段から人と話すときの距離が近くて、誰に対しても自然に接することができる人。
だからこそ、こういうこともさらりと言えるのかもしれない。
「そっかぁ。じゃあ、どうしようか。」
廿楽君は僕の反応を受け止めながら、考えてくれている。
そして、彼が思いついたこと。
僕も何とかできそうだと思ったので、了承したはいいものの、やはりすぐにすぐはできそうにない。
「ほら、もうすぐ学校着くぞ。頑張れ、澪。」
廿楽君の口から僕の名前が自然に紡がれるだけで、心がどうにかなりそうなくらい嬉しい。
なのに、今度は僕が彼の名前を呼ばなきゃいけないなんて。
想像していたより高いハードルさに、僕は内心で軽くパニックになっていた。
しかも、まさかの制限時間つき。
学校に着くまでに呼ばなきゃいけないというプレッシャーが、僕の心臓をさらに追い詰めてきた。
「……り、く、と」
意を決して、僕は彼の名前を口にした。
声が震えていたかもしれないけれど、僕なりの精一杯。
「ははっ、それカタコトすぎるだろ」
廿楽君は肩を揺らして笑う。
僕が勇気を振り絞って真剣に名前を呼んだのに。
廿楽君はそれがツボに入ったらしく、肩を振るわせて笑い続けている。
よく見ると、廿楽君の目元にはうっすら涙まで滲んでいた。
僕は恥ずかしさと愛しさでどうにかなりそうだった。
「ごめんごめん。」
そう言いながら、全然反省していない廿楽君の軽い謝罪にすら、僕は愛しさが込み上げてきてしまう。
自分がどれだけ彼に夢中なのかを改めて思い知らされた。
これはもう、重症かもしれない。
「あの、りくと。」
「どしたー?」
「お昼とかは今まで通り別で食べよう。友達との時間を大切にしてほしいし、僕といてもたつ噂なんて存在しないと思うけど、念のために。」
恋人と同じ学校と言えば、一緒に登下校とお昼ごはんだと思ってたのになーと呟いている。
僕に勇気がないばかりに不満そうな顔を見ると申し訳なくなる。
心の準備がまだかかりそうだと伝えると、ゆっくり進んでいけば良いよと伝えてくれた。
学校へつくと、指定の更衣室で学年とクラスのゼッケン付きブロックTシャツに着替える。
僕ら、2年2組と5組はFブロック。
これまで体育祭なんて、ただの苦行だと思っていた僕が、少しずつ楽しみに感じている。
それはきっと、りくとマジックとしか言いようがない。
順位なんて気にしたことはなかった。
しかし、チームが盛り上がっている中で、自分が足を引っ張らないようにしないとと思う。
僕は長縄跳びに出場するため、最初の種目であるスウェーデンリレーを見ることはできなかった。
けれど、応援席から聞こえてくる歓声や拍手の熱量から、きっと良い順位だったんだろうと感じた。
その後、結果のアナウンスが流れて、僕たちFブロックは第1種目で3位に入ったことがわかり、チームの士気がさらに高まっていくのを感じた。
僕も綱引きで頑張ろうと意気込んでいたけれど、実際の結果は惨敗。
引っ張れど、綱はずるずる相手チームの方へ動いていく。
そのたびにチームの空気が少しずつ沈んでいくのがわかって、手の痛さも尋常じゃない。
得点表によると、今のところFブロックは合計7点で、全体の6位。
7チーム中下から数えた方が早い。
まだ始まったばかりだから、これから巻き返そうとみんな燃えている。
僕が出場する種目はもう済んだ。
これから出場する仲間たちがきっと巻き返してくれると信じて、僕はただ祈るような気持ちで応援席に座っていた。
次の競技は障害&借りものリレー。
障害物リレーと借りもの競争を混ぜたようなもの。
設置されている様々な障害物ゾーンを抜けた先のお題箱に書かれている物や者と共にゴールして、次の走者にたすきを渡していくもの。
一番初めにお題箱にたどり着いた人が引いたのは、『本日誕生日の人』
誰かいないか呼び掛けているけれど、誰もいないのか、ブロックメンバーに次のお題にいけと再度お題箱に手を突っ込んで引いた紙に書いてあったのは『ハズレ』
「ハズレを引いたようなので、90秒間待機になります。次は当たりのお題を引けると良いですね。」
お題箱の近くにいる係員がマイクを通して伝える。
ハズレを引いてしまった人に、ブロックテントから「次こそ頑張れよ」「まだ大丈夫」と励ます声が飛んでいた。
「澪!来て!一緒に走るぞ!」
突然りくとの声が響いて、僕は思わず反応してしまった。
障害&借りものリレーにりくとは出場するのはしっていたけど、なぜまた僕を呼ぶのか分からず、頭が真っ白になった。
「え?え、なに?どういうこと?」
僕は混乱しながらも足を動かし、りくとの元へ向かった。
周囲の視線が集まっているのがわかって、一体どんなお題で僕が呼ばれたのか、まったく分からないまま走った。
「えっと、今回のお題は『好い人』です。このお題は恋愛に関する項目として設定していて、好きな人や恋人などを遠回しに示す内容でした。では、この方とゴールされた理由をお聞かせいただけますか?」と、係の生徒がマイクを通して説明する。
背中にじわじわと熱が広がっていく。
マイクを受け取ったりくとは話し始めた。
「俺たちは去年、同じクラスでした。最初の印象は、名前が似てるなっていうくらいだったんですけど、話してみるとすごく面白くて、優しくて、良い奴なんですよ。あ、ちなみに……恋人はいます。恋愛のお題だって気づかずに、彼とゴールしちゃったんですけど。」
「確かに『好い人』って、いろんな意味がありますもんね。人それぞれの解釈があることを考慮していなかったのは、こちらの落ち度です!では最後に、お二人のお名前を教えていただけますか?名前が似ているっておっしゃっていたので。」
係の生徒は少し笑いながら、場を和ませるように言ってくれた。
「廿楽と「甘楽です」」
僕たちは順番に名前を答えた。
「二十と甘い、ですね!確かに似てますね!ありがとうございます!このお題はクリアになりますので、Fブロックの次の走者はスタートしてください。」
係の生徒は笑顔で返してくれ、場をスムーズに進行させた。
マイクを返すと共にお題の紙も回収らしい。
「体育祭の思い出として持って帰ってもいいですか?」
「あ、はいわかりました。どうぞお持ち帰りください!」
以外にもあっさり許可を得ることができたりくとは、嬉しそうに大事にお題の紙を折り畳みポケットにいれていた。
ゴールした人たちは終了エリアにて待機せねばならないらしい。
お題に書かれているものが見つからない人、お題のハズレを引いてしまう人、お題に沿っておらずペナルティになる人。
次の競技の騎馬戦より盛り上がっていた。
「以上で午前の部は終了します。昼食後に午後の部を再開しますので時間厳守でお集まりください。最後に先生方からのお知らせは......ないようですので、解散してください。」
僕は、今は4位かと考えながら歩く。
友達と楽しそうに話す姿を見て良いなと羨ましく思ってしまう。
なるべく平然を装って、あくまでも自然な距離感を保ちつつ耳を傾ける。
「つづらぁー、恋人できたなんか聞いてねーぞ。」
「女子たちが騒いでたぞー。」
「いつ別れるんだーって虎視眈々とお前を狙ってる女子で溢れているからな。」
「質問責めにされる前に弁当食っておけよ。」
「あはは。まっさかー、ないない。あと別れるわけないからさ。言葉に気をつけろよ、このー!」
『恋人はいます』と『別れるわけない』を何度も頭のなかで反芻してはにやけそうになってしまう顔を必死に押さえた。
午後の競技が始まると、運動神経抜群の陽キャたちが次々と活躍してくれて、Fブロックはどの種目でも安定して上位に食い込んでいた。
ただ、惜しかったのは応援合戦だった。
途中で音響トラブルが起きて、曲が途切れてしまったこと。
さらに加えて、退場時に転んでしまった女子がいた。
時間内に退場できなかった場合、いかなる理由があろうとも減点対象。
転んでしまった女子が涙をこぼしているのを見て、りくとがみんなに聞こえる程度の小さな声をかけていた。
「大丈夫だよな。俺らで巻き返そうぜ!」
入退場門で騒ぐとそれもやはり減点となる。
その言葉に、みんなが静かに頷いていて、彼の存在がどれだけチームにとって大きいかを改めて感じた。
なぜ僕がこの状況を知り得ているのかというと、7競技目の終わったあと。
多人多脚走を負えて退場したメンバーの1人がブロック対抗リレーにも連続出場するはずだった。
しかし、騎馬戦で負傷した足をお昼に冷やしてテーピングしただけで多人多脚走に出ていたようで悪化してしまったらしい。
代走者としてりくとに声をかけられて、ふたつ返事で了承してしまったけれど、今になってその決断を少しだけ後悔していた。
僕の走順は、アンカーであるりくとの直前。
つまり、彼にバトンを渡すという重大な役目を担うことになっている。
バトンを渡してくれたメンバーが「自分のペースで」と優しく声をかけてくれて、その言葉に少しだけ肩の力が抜けた。
僕は小さく「ありがとう」と呟いて、全力で走り出した。
のは3年各ブロックと僕たちFブロック。
新体力テストの50m走の結果が平均よりも遅い僕が抜擢された意味がわからない。
けれど、懸命に腕を振って足を前に出してゆく。
僕がバトンを渡すと、りくとは力強く「任せろ」と言って走り出した。
その背中は頼もしくて、僕が作ってしまった差を埋めるように、彼はぐんぐんと前へ進んでいった。
実況の声が高まり、「最終コーナーを曲がった先、リレーを制するのは……Fブロックだぁぁぁあ!」と叫ばれた瞬間、応援席が歓声で揺れた。
「体育祭の部、結果発表です。第1位は、合計69点で3年Aブロック。続いて第2位は、66点で2年Fブロック!」
その瞬間、応援席から歓声が上がった。
惜しくも優勝は逃したけれど、僕たちFブロックが2位に食い込んだことは、十分に誇れる結果だった。
「以上で体育祭を終わります。学期末テストや休み明けテストもありますので、気持ちを切り替えて勉強に励んでください!」
その途端、体育祭の熱気に包まれていた空気が一気に現実へと引き戻されて、あちこちからため息が漏れていた。
体育祭も終わり、ブロックTシャツから着替えた後。
HRも終わり担任が教室から出て行ったのと入れ替わりでりくとが入ってきた。
「明後日の振替休日って空いてる人いる?打ち上げしようって話になってるんだけど。」
自然な流れでみんなに声をかけ、教室の空気が一気に明るくなった。
りくとの提案に、教室のあちこちから「行きたい!」「楽しそう!」という声が上がり、あっという間に賛成の輪が広がっていった。
彼の言葉には、自然と人を動かす力がある。彼が何かを言えば、みんなが自然とそれに従って動き出す。そんな彼の存在が、改めてすごいなと思った。
「あとで紙の回収に来るから、ちゃんと書いておいてくれよな。」
りくとは僕の目をまっすぐ見ながら、クラス全体に声をかけた。
打ち上げに参加するかどうかはまだ決めきれていなかったけれど、りくとの言葉が背中を押してくれた気がした。
僕は名前を書いて、次の人に紙を回した。
打ち上げと言っても具体的に何をするものなのか全く想像がつかない。
楽しそうな雰囲気に参加させてもらえるという初めての経験に心が躍る。
もし、居づらかった時の場合にも備えて、テスト勉強の道具を持っていっていようと決めた。
空は晴れていて、体育祭日和と言っていいだろう。
しかし僕は体育祭よりも大事なことがある。
僕は、あの日の雨の中で廿楽君を置き去りにしてしまった場所に立っていた。
あのときの後悔と、廿楽君の答えを受け止めて、今日こそはちゃんと向き合いたい。
「ごめん、待たせて。」
少し息を弾ませながら廿楽君が現れる。
「ううん。僕も今来たばかりだよ。」
返した言葉は、少しだけ嘘だったけれど、彼を待つ時間さえも僕にとっては心地よいものだったから、何も問題ではなかった。
「行こっか。」
「うん、そうだね。」
廿楽君が優しく促してくれて、僕らは並んで歩き始めた。
体育祭とはいえ、まだ生徒たちが登校するには早すぎる時間帯。
まだ誰もいない校舎へ向かうその道は、まるでふたりだけの世界のようだった。
「澪さ、改めてありがとう。あの日のこと、俺は驚いたっていうより、すごく嬉しかったんだ。ずっと考えて、何が自分の答えなのか悩んだんだけど、はっきりした言葉にはできなくて……でも、出た答えは『澪のことをもっと知りたい』ってことだった。俺、異性とも同性とも、誰かと付き合った経験なんてなくてさ。だから、ふたりで手探りで進んでいけたらいいなって思ったんだ。……今も、澪の気持ちは俺に向いてる?」
「もちろん、好きなままだよ。むしろ、毎日少しずつその気持ちが大きくなってる気がする。今も、久しぶりに廿楽君と会って話せて嬉しいんだ。僕が距離を置こうっていったのに、真剣に考えてくれて歩み寄ろうとしてくれて、本当にありがとう。」
「ありがとう、澪。俺のことを好きでいてくれて、本当に嬉しい。だからさ……俺たち、恋人になろう。友達っていう枠を越えて、もっと関係を深めていこう。」
そのときの廿楽君の表情は、冗談や照れ笑いなんて一切浮かべていない。
まっすぐ僕の目を見ていた。
からかっている様子なんて微塵もなくて、彼が本気で僕との関係を大切にしようとしてくれていることが、痛いほど伝わってきた。
廿楽君は、僕の気持ちを否定することもなく、偏見を持つこともなく、ただ僕という存在をそのまま受け止めてくれた。
そんな優しさや誠実さは、ずっと前から知っていたはずなのに。
改めて気づかされて、胸がじんわりと熱くなった。
「僕も、廿楽君と一緒に、ひとつひとつ丁寧に積み重ねていきたいです。これから、恋人としてよろしくお願いします。」
あの雨の日、僕の中でずっと温めていた気持ちのすべてで、彼に伝えることができて本当に良かったと思った。
こうして、僕たちは晴れて恋人同士になった。
まだぎこちない部分もあるけれど、互いに向き合って、少しずつ歩いていける関係が始まったことに、胸がいっぱいになった。
「じゃあさ、早速だけど……手とか、繋いでみる?」
廿楽君は何気なく、でも僕にとってはかなり難易度の高いことをさらりと口にしてきて、僕は思わず固まってしまった。
「む、むりむり……いや、無理ってわけじゃないけど、ちょっとだけ早いかも……ペース的に。」
僕は慌てて言葉を繋ぎながら、顔が熱くなるのを止められなかった。
廿楽君は、普段から人と話すときの距離が近くて、誰に対しても自然に接することができる人。
だからこそ、こういうこともさらりと言えるのかもしれない。
「そっかぁ。じゃあ、どうしようか。」
廿楽君は僕の反応を受け止めながら、考えてくれている。
そして、彼が思いついたこと。
僕も何とかできそうだと思ったので、了承したはいいものの、やはりすぐにすぐはできそうにない。
「ほら、もうすぐ学校着くぞ。頑張れ、澪。」
廿楽君の口から僕の名前が自然に紡がれるだけで、心がどうにかなりそうなくらい嬉しい。
なのに、今度は僕が彼の名前を呼ばなきゃいけないなんて。
想像していたより高いハードルさに、僕は内心で軽くパニックになっていた。
しかも、まさかの制限時間つき。
学校に着くまでに呼ばなきゃいけないというプレッシャーが、僕の心臓をさらに追い詰めてきた。
「……り、く、と」
意を決して、僕は彼の名前を口にした。
声が震えていたかもしれないけれど、僕なりの精一杯。
「ははっ、それカタコトすぎるだろ」
廿楽君は肩を揺らして笑う。
僕が勇気を振り絞って真剣に名前を呼んだのに。
廿楽君はそれがツボに入ったらしく、肩を振るわせて笑い続けている。
よく見ると、廿楽君の目元にはうっすら涙まで滲んでいた。
僕は恥ずかしさと愛しさでどうにかなりそうだった。
「ごめんごめん。」
そう言いながら、全然反省していない廿楽君の軽い謝罪にすら、僕は愛しさが込み上げてきてしまう。
自分がどれだけ彼に夢中なのかを改めて思い知らされた。
これはもう、重症かもしれない。
「あの、りくと。」
「どしたー?」
「お昼とかは今まで通り別で食べよう。友達との時間を大切にしてほしいし、僕といてもたつ噂なんて存在しないと思うけど、念のために。」
恋人と同じ学校と言えば、一緒に登下校とお昼ごはんだと思ってたのになーと呟いている。
僕に勇気がないばかりに不満そうな顔を見ると申し訳なくなる。
心の準備がまだかかりそうだと伝えると、ゆっくり進んでいけば良いよと伝えてくれた。
学校へつくと、指定の更衣室で学年とクラスのゼッケン付きブロックTシャツに着替える。
僕ら、2年2組と5組はFブロック。
これまで体育祭なんて、ただの苦行だと思っていた僕が、少しずつ楽しみに感じている。
それはきっと、りくとマジックとしか言いようがない。
順位なんて気にしたことはなかった。
しかし、チームが盛り上がっている中で、自分が足を引っ張らないようにしないとと思う。
僕は長縄跳びに出場するため、最初の種目であるスウェーデンリレーを見ることはできなかった。
けれど、応援席から聞こえてくる歓声や拍手の熱量から、きっと良い順位だったんだろうと感じた。
その後、結果のアナウンスが流れて、僕たちFブロックは第1種目で3位に入ったことがわかり、チームの士気がさらに高まっていくのを感じた。
僕も綱引きで頑張ろうと意気込んでいたけれど、実際の結果は惨敗。
引っ張れど、綱はずるずる相手チームの方へ動いていく。
そのたびにチームの空気が少しずつ沈んでいくのがわかって、手の痛さも尋常じゃない。
得点表によると、今のところFブロックは合計7点で、全体の6位。
7チーム中下から数えた方が早い。
まだ始まったばかりだから、これから巻き返そうとみんな燃えている。
僕が出場する種目はもう済んだ。
これから出場する仲間たちがきっと巻き返してくれると信じて、僕はただ祈るような気持ちで応援席に座っていた。
次の競技は障害&借りものリレー。
障害物リレーと借りもの競争を混ぜたようなもの。
設置されている様々な障害物ゾーンを抜けた先のお題箱に書かれている物や者と共にゴールして、次の走者にたすきを渡していくもの。
一番初めにお題箱にたどり着いた人が引いたのは、『本日誕生日の人』
誰かいないか呼び掛けているけれど、誰もいないのか、ブロックメンバーに次のお題にいけと再度お題箱に手を突っ込んで引いた紙に書いてあったのは『ハズレ』
「ハズレを引いたようなので、90秒間待機になります。次は当たりのお題を引けると良いですね。」
お題箱の近くにいる係員がマイクを通して伝える。
ハズレを引いてしまった人に、ブロックテントから「次こそ頑張れよ」「まだ大丈夫」と励ます声が飛んでいた。
「澪!来て!一緒に走るぞ!」
突然りくとの声が響いて、僕は思わず反応してしまった。
障害&借りものリレーにりくとは出場するのはしっていたけど、なぜまた僕を呼ぶのか分からず、頭が真っ白になった。
「え?え、なに?どういうこと?」
僕は混乱しながらも足を動かし、りくとの元へ向かった。
周囲の視線が集まっているのがわかって、一体どんなお題で僕が呼ばれたのか、まったく分からないまま走った。
「えっと、今回のお題は『好い人』です。このお題は恋愛に関する項目として設定していて、好きな人や恋人などを遠回しに示す内容でした。では、この方とゴールされた理由をお聞かせいただけますか?」と、係の生徒がマイクを通して説明する。
背中にじわじわと熱が広がっていく。
マイクを受け取ったりくとは話し始めた。
「俺たちは去年、同じクラスでした。最初の印象は、名前が似てるなっていうくらいだったんですけど、話してみるとすごく面白くて、優しくて、良い奴なんですよ。あ、ちなみに……恋人はいます。恋愛のお題だって気づかずに、彼とゴールしちゃったんですけど。」
「確かに『好い人』って、いろんな意味がありますもんね。人それぞれの解釈があることを考慮していなかったのは、こちらの落ち度です!では最後に、お二人のお名前を教えていただけますか?名前が似ているっておっしゃっていたので。」
係の生徒は少し笑いながら、場を和ませるように言ってくれた。
「廿楽と「甘楽です」」
僕たちは順番に名前を答えた。
「二十と甘い、ですね!確かに似てますね!ありがとうございます!このお題はクリアになりますので、Fブロックの次の走者はスタートしてください。」
係の生徒は笑顔で返してくれ、場をスムーズに進行させた。
マイクを返すと共にお題の紙も回収らしい。
「体育祭の思い出として持って帰ってもいいですか?」
「あ、はいわかりました。どうぞお持ち帰りください!」
以外にもあっさり許可を得ることができたりくとは、嬉しそうに大事にお題の紙を折り畳みポケットにいれていた。
ゴールした人たちは終了エリアにて待機せねばならないらしい。
お題に書かれているものが見つからない人、お題のハズレを引いてしまう人、お題に沿っておらずペナルティになる人。
次の競技の騎馬戦より盛り上がっていた。
「以上で午前の部は終了します。昼食後に午後の部を再開しますので時間厳守でお集まりください。最後に先生方からのお知らせは......ないようですので、解散してください。」
僕は、今は4位かと考えながら歩く。
友達と楽しそうに話す姿を見て良いなと羨ましく思ってしまう。
なるべく平然を装って、あくまでも自然な距離感を保ちつつ耳を傾ける。
「つづらぁー、恋人できたなんか聞いてねーぞ。」
「女子たちが騒いでたぞー。」
「いつ別れるんだーって虎視眈々とお前を狙ってる女子で溢れているからな。」
「質問責めにされる前に弁当食っておけよ。」
「あはは。まっさかー、ないない。あと別れるわけないからさ。言葉に気をつけろよ、このー!」
『恋人はいます』と『別れるわけない』を何度も頭のなかで反芻してはにやけそうになってしまう顔を必死に押さえた。
午後の競技が始まると、運動神経抜群の陽キャたちが次々と活躍してくれて、Fブロックはどの種目でも安定して上位に食い込んでいた。
ただ、惜しかったのは応援合戦だった。
途中で音響トラブルが起きて、曲が途切れてしまったこと。
さらに加えて、退場時に転んでしまった女子がいた。
時間内に退場できなかった場合、いかなる理由があろうとも減点対象。
転んでしまった女子が涙をこぼしているのを見て、りくとがみんなに聞こえる程度の小さな声をかけていた。
「大丈夫だよな。俺らで巻き返そうぜ!」
入退場門で騒ぐとそれもやはり減点となる。
その言葉に、みんなが静かに頷いていて、彼の存在がどれだけチームにとって大きいかを改めて感じた。
なぜ僕がこの状況を知り得ているのかというと、7競技目の終わったあと。
多人多脚走を負えて退場したメンバーの1人がブロック対抗リレーにも連続出場するはずだった。
しかし、騎馬戦で負傷した足をお昼に冷やしてテーピングしただけで多人多脚走に出ていたようで悪化してしまったらしい。
代走者としてりくとに声をかけられて、ふたつ返事で了承してしまったけれど、今になってその決断を少しだけ後悔していた。
僕の走順は、アンカーであるりくとの直前。
つまり、彼にバトンを渡すという重大な役目を担うことになっている。
バトンを渡してくれたメンバーが「自分のペースで」と優しく声をかけてくれて、その言葉に少しだけ肩の力が抜けた。
僕は小さく「ありがとう」と呟いて、全力で走り出した。
のは3年各ブロックと僕たちFブロック。
新体力テストの50m走の結果が平均よりも遅い僕が抜擢された意味がわからない。
けれど、懸命に腕を振って足を前に出してゆく。
僕がバトンを渡すと、りくとは力強く「任せろ」と言って走り出した。
その背中は頼もしくて、僕が作ってしまった差を埋めるように、彼はぐんぐんと前へ進んでいった。
実況の声が高まり、「最終コーナーを曲がった先、リレーを制するのは……Fブロックだぁぁぁあ!」と叫ばれた瞬間、応援席が歓声で揺れた。
「体育祭の部、結果発表です。第1位は、合計69点で3年Aブロック。続いて第2位は、66点で2年Fブロック!」
その瞬間、応援席から歓声が上がった。
惜しくも優勝は逃したけれど、僕たちFブロックが2位に食い込んだことは、十分に誇れる結果だった。
「以上で体育祭を終わります。学期末テストや休み明けテストもありますので、気持ちを切り替えて勉強に励んでください!」
その途端、体育祭の熱気に包まれていた空気が一気に現実へと引き戻されて、あちこちからため息が漏れていた。
体育祭も終わり、ブロックTシャツから着替えた後。
HRも終わり担任が教室から出て行ったのと入れ替わりでりくとが入ってきた。
「明後日の振替休日って空いてる人いる?打ち上げしようって話になってるんだけど。」
自然な流れでみんなに声をかけ、教室の空気が一気に明るくなった。
りくとの提案に、教室のあちこちから「行きたい!」「楽しそう!」という声が上がり、あっという間に賛成の輪が広がっていった。
彼の言葉には、自然と人を動かす力がある。彼が何かを言えば、みんなが自然とそれに従って動き出す。そんな彼の存在が、改めてすごいなと思った。
「あとで紙の回収に来るから、ちゃんと書いておいてくれよな。」
りくとは僕の目をまっすぐ見ながら、クラス全体に声をかけた。
打ち上げに参加するかどうかはまだ決めきれていなかったけれど、りくとの言葉が背中を押してくれた気がした。
僕は名前を書いて、次の人に紙を回した。
打ち上げと言っても具体的に何をするものなのか全く想像がつかない。
楽しそうな雰囲気に参加させてもらえるという初めての経験に心が躍る。
もし、居づらかった時の場合にも備えて、テスト勉強の道具を持っていっていようと決めた。