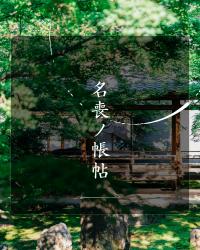体育祭までのカウントダウンが始まり、残り1ヶ月を切った頃。
廊下や教室のあちこちで準備や練習の話題が飛び交っていた。
その日の放課後、空は灰色に染まっている。
雨がようやく小降りになったのを見計らって、僕は昇降口でそっと傘を開き、帰路につこうとしていた。
「おっ、澪!ちょうどいいところにいた!」と、後ろから聞き慣れた声が響いてきて、僕は驚いて振り返ると、そこには息を弾ませながら駆け寄ってくる廿楽君の姿があった。
廿楽君は、雨に濡れた髪を軽く払いつつ、「傘、入れてくれない?」と笑顔で言ってくる。
さっきまで、練習していたんだろうか。
雨で校庭が使えない日は、廊下や体育館で練習していることを思い出す。
廿楽君の自然な距離感に僕の心臓が少しだけ跳ねた。
僕の傘はすでに開いていて、彼が入るスペースは十分にあった。
けれど、突然の展開に頭が追いつかない。
しばしフリーズして、手元の傘を見つめることしかできなかった。
今日の天気は朝から雨だったから、廿楽君は傘を忘れたのかもしれないという考えはなかった。
彼が僕の傘に入ってきたのは、きっと偶然ではなく、何かしらの意図があったのかもしれない。
僕は「どうぞ」と小さく言って傘を差し出し、廿楽君がその中に入ってきた。
背の高い僕たち2人が並んで歩く姿は、性別が違えばからかわれるのではないかというくらい肩の距離が近かった。
傘の上では、パラパラと雨粒が軽やかに跳ねていて、その音が少しずつ心を落ち着かせてくれているような気がした。
足元では、アスファルトに溜まった水たまりが、歩くたびに小さく跳ねて、靴の先に冷たいしぶきを飛ばしてくる。
「あのさ、最近さ……俺たち、あんまり話してないなって気づいてさ。」
廿楽君は傘の下で言葉を探しながら続けた。
「連絡しようか迷ったんだけど、やっぱりこういうのは、ちゃんと顔を見て話したくて。」
その言葉には、僕との関係を大切に思ってくれている気持ちが滲んでいるようで、胸の奥がじんわりと熱くなった。
「もしさ、俺のことがウザいとか、キモいとか思ってるなら、ちゃんと言ってほしいんだ。」
「もし、もう俺のこと嫌いになったとかでも、それでもいいからさ。」
彼は、僕の気持ちを受け止める覚悟を持っているようで、その言葉の重さに僕は思わず息を呑んだ。
廿楽君の声は真剣で、冗談めかした雰囲気は一切なくて、僕の気持ちを尊重しようとしてくれているのが痛いほど伝わってきた。
「できれば、これからも澪とは仲良くしていたいって思ってる。」
「もし俺に至らないところがあるなら、ちゃんと直すから。」
その言葉は、僕の心にまっすぐ届く。
そんなふうに、優しく、でも真剣に言葉を紡ぐ廿楽君の姿から、僕のことを気にかけてくれていることが伝わってくる。
彼の言葉のひとつひとつから、僕のことを思ってくれている気遣いがひしひしと伝わってくる。
その優しさに触れるたびに、僕の胸の奥がじんわりと温かくなっていった。
ウザいとかキモいなんて言葉は、どう考えても廿楽君よりも僕の方がずっと似合っている。
現に廿楽君によこしまな想いを抱いている僕だ。
そんなふうに自分を卑下してしまう。
廿楽君のことを嫌いになるなんて、僕には絶対にありえない。
むしろ、嫌われるのは僕だろう。
体育祭の練習で話す機会が少なくなっていたとしても。
たとえどんなに距離ができても、僕の中で廿楽君はずっと特別な存在だから。
廿楽君と2人きりで、同じ傘の下を並んで歩いて帰る。
僕にとっては夢の中でも描いたことのないような出来事で、現実とは思えない。
雨の日なんてただ憂鬱で、傘を差しても濡れるし、靴も汚れる。
いいことなんて何ひとつもないと思っていた。
「……好きだなぁ。」
僕は思わず口にしてしまった。
「俺も雨、けっこう好きなんだ。」
僕がポツリと呟いたその言葉は、雨音に紛れてかき消されることなく、廿楽君に届いてしまった。
「あの……違くて……。いや、違うくなくて……。」
僕は言葉をうまく繋げられずに、混乱したまま口を動かしてしまった。
廿楽君は雨の話にすり替えてくれた。
なのに僕はその優しいフォローすらうまく拾えず、むしろ自分の気持ちを露呈させてしまう結果になってしまった。
彼の顔は傘の影で半分しか見えなかったけれど、その横顔の輪郭から戸惑っているのがはっきりと伝わる。
僕は自分の言葉が彼を困らせてしまったことに気づいた。
言葉にしなくても、表情に出さなくても、廿楽君が今どう感じているのかが、なぜか僕には手に取るようにわかってしまった。
こんなふうに気持ちを口にするつもりなんて、最初はまったくなかった。
なのに、雨の音と彼の優しさに包まれて、僕の心の奥にしまっていた言葉が、勝手にこぼれ落ちてしまった。
今さら「言わなければよかった」と後悔しても、もう戻らない。
廿楽君に届いてしまった以上、僕はこの気持ちと向き合うしかなかった。
もう、なるようになれ。
そう心の中で覚悟を決めて、僕は自分の気持ちを隠すことなく、すべてを彼に伝えることにした。
「もし僕のこの気持ちが歪んだ恋心だって思われても、嗤ってくれて構わない。そっち側からしたら、きっと理解しづらいことだと思う。でも、それでも僕は、廿楽 陸翔のことが好きなんだ。ずっと、ずっと前から。本当は、こんなふうに伝えるつもりなんてなかった。君と話せるだけで、それだけで十分だったんだ。好きになった人がたまたま廿楽君で、そしてその人が同性だった。それだけのこと。でも、そんな話、信じられないよね。気持ち悪いって思われても仕方ない。不快な話を聞かせてしまって、本当にごめん。だから、少しだけ距離を置かせてほしい。僕の勝手な都合で申し訳ないけど、今はそれしか思いつかない。」
僕は、心の奥に溜め込んでいた言葉を一気に吐き出す。
途切れることなく捲し立ててしまったのは、彼の反応を聞くのが怖くて、言葉の隙間を作らないようにするためだった。
廿楽君が僕の腕をそっと掴んで引き留めようとしたその瞬間、僕はその手を振り払って、雨の中を全力で走り出した。
彼の表情を見るのが怖くて、傘を廿楽君に押し付けるように渡して、僕は何も持たずに雨の中へ飛び出したのだ。
服も髪も靴も、すぐにびしょ濡れになって、それでも僕は止まらずにただただ走り続けた。
廿楽君が、僕が押し付けた傘を開いたまま逆さにして、雨に打たれながらその場に立ち尽くしていたことを知らなかった。
ずぶ濡れになっていたのは僕だけじゃなかった。
廿楽君もまた、僕と同じように雨に打たれていたことを、僕は後になって知ることになる。
あの日の雨の告白以来、廿楽君からは一度も連絡が来ることはなかった。
廿楽君から話しかけてもらえる前までの去年の僕の日常戻っていった。
自分から距離を置いたはずなのに、廿楽君以外と話す相手がいない僕にとって、学校はただ通うだけの場所。
以前感じていたささやかな楽しささえも、すっかり色褪せてしまった。
廿楽君がいないだけで、味気ないように感じてしまう。
何度もスマホを開いては、通知がないことを確認して、落胆してしまう。
自分に呆れながら、それでもどこかで廿楽君からの連絡を期待してしまう自分がいた。
思い返せば、いつも会話のきっかけを作ってくれていたのは廿楽君からで。
僕から話しかけたことなんてほとんどなくて、彼の優しさに甘えていたことに今さら気づいた。
どう考えても僕が全面的に悪かった。
突然気持ちをぶつけて、何の余地も与えずに逃げるように走り去った僕の行動は、彼にとってどれほど困惑させるものだっただろう。
謝るべきなのか。
そう思いながらも、今さら「ごめん」と言うことで、あのときの僕の言葉が消えるわけでもない。
すべてをなかったことにできるわけでもない。
かえって彼を混乱させるだけなのではないかという不安が押し寄せる。
指がなかなか動かなかった。
自分の弱さに呆れながら、苦笑いを浮かべる。
現実から目を背けるように、画面の光を遮断した。
けれど、電源を落とした直後、スマホが突然震え始めた。
タイミングを見計らったかのような着信。
画面に灯った光。
表示された名前を見た瞬間、僕は思わず目を見開いて、息を呑んだ。
『廿楽 陸翔』
僕の指先は震えながらも、画面から目を離すことができなかった。
何度も目を擦って、見間違いじゃないかと確認する。
それでも、そこには確かに廿楽君の名前があって、現実だと認めるしかなかった。
迷いに迷って、ようやく電話に出ようとボタンを押しかけたその瞬間、着信は切れた。
画面には「不在着信」の文字だけが残される。
「留守番メッセージが1件あります」と表示されていて、再生ボタンを押す。
「俺のこと、もしかしてブロックしてたりする?」
留守電の中の廿楽君の声は、少しだけ不安そうだった。
「もしブロックしてないなら、気づいたときでいいから。俺は、いつでも澪からの連絡を待ってる。」
その言葉は、涙が出そうになるほど温かかった。
僕は震える指で廿楽君の名前をタップして、折り返しの電話をかけた。
心臓の鼓動が早くなって、呼び出し音の一つ一つが永遠のように長く感じられた。
呼び出し音が数回鳴ったあと、すぐに電話口から廿楽君の声が聞こえてきた。
「澪にブロックされたんじゃないかって、ちょっと焦ったよ。」
廿楽君は冗談めかして言ったけれど、その声の奥には本当に心配していた気持ちがあり、僕は胸がきゅっと締めつけられた。
「そんなこと、するわけないよ。」
僕はすぐに答えた。
彼の連絡先を消すなんて、僕には絶対にできないことだったから。
だって、それは僕が好きな人の連絡先だから。
そこまで言葉にする勇気はなかったけれど、きっと声の調子で伝わってしまったかもしれない。
そう思うと、今更ながら恥ずかしくなってきてしまった。
互いに何を言えばいいのか分からずに、しばらく無言の時間が続いてしまう。
「俺、ずっと考えてたんだ。人を好きになるってさ、理屈じゃどうにもならないことだよな。誰を好きになるかなんて、自然に心が動くものだと思う。だから、澪の気持ちを聞いても、俺は不快になんてならなかった。ましてや嗤うなんて、そんなこと思えるはずがない。澪が『本当は伝えるつもりなんてなかった』って言ってたから、もしかしてこのまま無かったことにしたいのかなって思ったりもした。でも、それって澪の気持ちを踏みにじることになるって気づいたんだ。澪が勇気を出して伝えてくれたその想いを、歪だなんて思わないし、曖昧にして終わらせるなんて、俺にはできない。」
僕は静かに廿楽君の声に耳を傾ける。
「正直に言うと、俺はこれまで誰かとちゃんと付き合ったことなんてなくて、全部片思いで終わってきた。好きになっても、伝える勇気がなくて、どうせ無理だって思って、自分でその気持ちを萎ませてきたんだ。だから、澪があんなふうにまっすぐ気持ちを伝えてくれたことが、すごく眩しく見えた。」
僕は、廿楽君が全部忘れて、僕のことなんて最初から知らなかったフリをしてくれたら、それでよかったのにと思っていた。
でも、彼はそうしなかった。
僕の気持ちに向き合ってくれた。
廿楽君の言葉があまりにも真っ直ぐで、優しくて、僕は何も言えなくなってしまった。
胸がいっぱいで、ただ「うん」と小さく相槌を打つことしかできなかった。
「だからこそ、澪が思いがけず口にしてしまった言葉だったとしても、俺はそれがすごいことだと思った。勇気がいることだし、簡単にできることじゃない。だからこそ、俺もちゃんと向き合って、真剣に答えを出さなきゃいけないって思ってる。」
「……ありがとう、廿楽君。」
僕は、彼の言葉に胸がいっぱいになりながら、感謝の気持ちを込めてそう伝えた。
それだけで、僕の気持ちは救われた気がするよ。
「俺の方こそ、ありがとう。澪が気持ちを伝えてくれたこと、本当に嬉しかった。俺、体育祭までにはちゃんと答えを出したいと思ってる。だから、それまで少しだけ待っててほしい。」
廿楽君の誠実さがひしひしと伝わってくる。
「それじゃあ、またね。」
お互いに短く挨拶を交わして、通話は静かに切れた。
スマホの画面が暗くなったあとも、僕は画面を見つめた。
本当に、廿楽君はずるい。
あんなふうに優しくて、真剣で、僕の気持ちをちゃんと受け止めてくれる。
好きにならずにいられるはずがない。
でも、体育祭の日に、もしかしたら「ごめん」と断られる可能性だってある。
あまり期待しないでおくことにした。
「期待しない。期待しない……。」
僕は自分に言い聞かせるように何度も呟いた。
期待してしまえば、傷つくかもしれないから。
廊下や教室のあちこちで準備や練習の話題が飛び交っていた。
その日の放課後、空は灰色に染まっている。
雨がようやく小降りになったのを見計らって、僕は昇降口でそっと傘を開き、帰路につこうとしていた。
「おっ、澪!ちょうどいいところにいた!」と、後ろから聞き慣れた声が響いてきて、僕は驚いて振り返ると、そこには息を弾ませながら駆け寄ってくる廿楽君の姿があった。
廿楽君は、雨に濡れた髪を軽く払いつつ、「傘、入れてくれない?」と笑顔で言ってくる。
さっきまで、練習していたんだろうか。
雨で校庭が使えない日は、廊下や体育館で練習していることを思い出す。
廿楽君の自然な距離感に僕の心臓が少しだけ跳ねた。
僕の傘はすでに開いていて、彼が入るスペースは十分にあった。
けれど、突然の展開に頭が追いつかない。
しばしフリーズして、手元の傘を見つめることしかできなかった。
今日の天気は朝から雨だったから、廿楽君は傘を忘れたのかもしれないという考えはなかった。
彼が僕の傘に入ってきたのは、きっと偶然ではなく、何かしらの意図があったのかもしれない。
僕は「どうぞ」と小さく言って傘を差し出し、廿楽君がその中に入ってきた。
背の高い僕たち2人が並んで歩く姿は、性別が違えばからかわれるのではないかというくらい肩の距離が近かった。
傘の上では、パラパラと雨粒が軽やかに跳ねていて、その音が少しずつ心を落ち着かせてくれているような気がした。
足元では、アスファルトに溜まった水たまりが、歩くたびに小さく跳ねて、靴の先に冷たいしぶきを飛ばしてくる。
「あのさ、最近さ……俺たち、あんまり話してないなって気づいてさ。」
廿楽君は傘の下で言葉を探しながら続けた。
「連絡しようか迷ったんだけど、やっぱりこういうのは、ちゃんと顔を見て話したくて。」
その言葉には、僕との関係を大切に思ってくれている気持ちが滲んでいるようで、胸の奥がじんわりと熱くなった。
「もしさ、俺のことがウザいとか、キモいとか思ってるなら、ちゃんと言ってほしいんだ。」
「もし、もう俺のこと嫌いになったとかでも、それでもいいからさ。」
彼は、僕の気持ちを受け止める覚悟を持っているようで、その言葉の重さに僕は思わず息を呑んだ。
廿楽君の声は真剣で、冗談めかした雰囲気は一切なくて、僕の気持ちを尊重しようとしてくれているのが痛いほど伝わってきた。
「できれば、これからも澪とは仲良くしていたいって思ってる。」
「もし俺に至らないところがあるなら、ちゃんと直すから。」
その言葉は、僕の心にまっすぐ届く。
そんなふうに、優しく、でも真剣に言葉を紡ぐ廿楽君の姿から、僕のことを気にかけてくれていることが伝わってくる。
彼の言葉のひとつひとつから、僕のことを思ってくれている気遣いがひしひしと伝わってくる。
その優しさに触れるたびに、僕の胸の奥がじんわりと温かくなっていった。
ウザいとかキモいなんて言葉は、どう考えても廿楽君よりも僕の方がずっと似合っている。
現に廿楽君によこしまな想いを抱いている僕だ。
そんなふうに自分を卑下してしまう。
廿楽君のことを嫌いになるなんて、僕には絶対にありえない。
むしろ、嫌われるのは僕だろう。
体育祭の練習で話す機会が少なくなっていたとしても。
たとえどんなに距離ができても、僕の中で廿楽君はずっと特別な存在だから。
廿楽君と2人きりで、同じ傘の下を並んで歩いて帰る。
僕にとっては夢の中でも描いたことのないような出来事で、現実とは思えない。
雨の日なんてただ憂鬱で、傘を差しても濡れるし、靴も汚れる。
いいことなんて何ひとつもないと思っていた。
「……好きだなぁ。」
僕は思わず口にしてしまった。
「俺も雨、けっこう好きなんだ。」
僕がポツリと呟いたその言葉は、雨音に紛れてかき消されることなく、廿楽君に届いてしまった。
「あの……違くて……。いや、違うくなくて……。」
僕は言葉をうまく繋げられずに、混乱したまま口を動かしてしまった。
廿楽君は雨の話にすり替えてくれた。
なのに僕はその優しいフォローすらうまく拾えず、むしろ自分の気持ちを露呈させてしまう結果になってしまった。
彼の顔は傘の影で半分しか見えなかったけれど、その横顔の輪郭から戸惑っているのがはっきりと伝わる。
僕は自分の言葉が彼を困らせてしまったことに気づいた。
言葉にしなくても、表情に出さなくても、廿楽君が今どう感じているのかが、なぜか僕には手に取るようにわかってしまった。
こんなふうに気持ちを口にするつもりなんて、最初はまったくなかった。
なのに、雨の音と彼の優しさに包まれて、僕の心の奥にしまっていた言葉が、勝手にこぼれ落ちてしまった。
今さら「言わなければよかった」と後悔しても、もう戻らない。
廿楽君に届いてしまった以上、僕はこの気持ちと向き合うしかなかった。
もう、なるようになれ。
そう心の中で覚悟を決めて、僕は自分の気持ちを隠すことなく、すべてを彼に伝えることにした。
「もし僕のこの気持ちが歪んだ恋心だって思われても、嗤ってくれて構わない。そっち側からしたら、きっと理解しづらいことだと思う。でも、それでも僕は、廿楽 陸翔のことが好きなんだ。ずっと、ずっと前から。本当は、こんなふうに伝えるつもりなんてなかった。君と話せるだけで、それだけで十分だったんだ。好きになった人がたまたま廿楽君で、そしてその人が同性だった。それだけのこと。でも、そんな話、信じられないよね。気持ち悪いって思われても仕方ない。不快な話を聞かせてしまって、本当にごめん。だから、少しだけ距離を置かせてほしい。僕の勝手な都合で申し訳ないけど、今はそれしか思いつかない。」
僕は、心の奥に溜め込んでいた言葉を一気に吐き出す。
途切れることなく捲し立ててしまったのは、彼の反応を聞くのが怖くて、言葉の隙間を作らないようにするためだった。
廿楽君が僕の腕をそっと掴んで引き留めようとしたその瞬間、僕はその手を振り払って、雨の中を全力で走り出した。
彼の表情を見るのが怖くて、傘を廿楽君に押し付けるように渡して、僕は何も持たずに雨の中へ飛び出したのだ。
服も髪も靴も、すぐにびしょ濡れになって、それでも僕は止まらずにただただ走り続けた。
廿楽君が、僕が押し付けた傘を開いたまま逆さにして、雨に打たれながらその場に立ち尽くしていたことを知らなかった。
ずぶ濡れになっていたのは僕だけじゃなかった。
廿楽君もまた、僕と同じように雨に打たれていたことを、僕は後になって知ることになる。
あの日の雨の告白以来、廿楽君からは一度も連絡が来ることはなかった。
廿楽君から話しかけてもらえる前までの去年の僕の日常戻っていった。
自分から距離を置いたはずなのに、廿楽君以外と話す相手がいない僕にとって、学校はただ通うだけの場所。
以前感じていたささやかな楽しささえも、すっかり色褪せてしまった。
廿楽君がいないだけで、味気ないように感じてしまう。
何度もスマホを開いては、通知がないことを確認して、落胆してしまう。
自分に呆れながら、それでもどこかで廿楽君からの連絡を期待してしまう自分がいた。
思い返せば、いつも会話のきっかけを作ってくれていたのは廿楽君からで。
僕から話しかけたことなんてほとんどなくて、彼の優しさに甘えていたことに今さら気づいた。
どう考えても僕が全面的に悪かった。
突然気持ちをぶつけて、何の余地も与えずに逃げるように走り去った僕の行動は、彼にとってどれほど困惑させるものだっただろう。
謝るべきなのか。
そう思いながらも、今さら「ごめん」と言うことで、あのときの僕の言葉が消えるわけでもない。
すべてをなかったことにできるわけでもない。
かえって彼を混乱させるだけなのではないかという不安が押し寄せる。
指がなかなか動かなかった。
自分の弱さに呆れながら、苦笑いを浮かべる。
現実から目を背けるように、画面の光を遮断した。
けれど、電源を落とした直後、スマホが突然震え始めた。
タイミングを見計らったかのような着信。
画面に灯った光。
表示された名前を見た瞬間、僕は思わず目を見開いて、息を呑んだ。
『廿楽 陸翔』
僕の指先は震えながらも、画面から目を離すことができなかった。
何度も目を擦って、見間違いじゃないかと確認する。
それでも、そこには確かに廿楽君の名前があって、現実だと認めるしかなかった。
迷いに迷って、ようやく電話に出ようとボタンを押しかけたその瞬間、着信は切れた。
画面には「不在着信」の文字だけが残される。
「留守番メッセージが1件あります」と表示されていて、再生ボタンを押す。
「俺のこと、もしかしてブロックしてたりする?」
留守電の中の廿楽君の声は、少しだけ不安そうだった。
「もしブロックしてないなら、気づいたときでいいから。俺は、いつでも澪からの連絡を待ってる。」
その言葉は、涙が出そうになるほど温かかった。
僕は震える指で廿楽君の名前をタップして、折り返しの電話をかけた。
心臓の鼓動が早くなって、呼び出し音の一つ一つが永遠のように長く感じられた。
呼び出し音が数回鳴ったあと、すぐに電話口から廿楽君の声が聞こえてきた。
「澪にブロックされたんじゃないかって、ちょっと焦ったよ。」
廿楽君は冗談めかして言ったけれど、その声の奥には本当に心配していた気持ちがあり、僕は胸がきゅっと締めつけられた。
「そんなこと、するわけないよ。」
僕はすぐに答えた。
彼の連絡先を消すなんて、僕には絶対にできないことだったから。
だって、それは僕が好きな人の連絡先だから。
そこまで言葉にする勇気はなかったけれど、きっと声の調子で伝わってしまったかもしれない。
そう思うと、今更ながら恥ずかしくなってきてしまった。
互いに何を言えばいいのか分からずに、しばらく無言の時間が続いてしまう。
「俺、ずっと考えてたんだ。人を好きになるってさ、理屈じゃどうにもならないことだよな。誰を好きになるかなんて、自然に心が動くものだと思う。だから、澪の気持ちを聞いても、俺は不快になんてならなかった。ましてや嗤うなんて、そんなこと思えるはずがない。澪が『本当は伝えるつもりなんてなかった』って言ってたから、もしかしてこのまま無かったことにしたいのかなって思ったりもした。でも、それって澪の気持ちを踏みにじることになるって気づいたんだ。澪が勇気を出して伝えてくれたその想いを、歪だなんて思わないし、曖昧にして終わらせるなんて、俺にはできない。」
僕は静かに廿楽君の声に耳を傾ける。
「正直に言うと、俺はこれまで誰かとちゃんと付き合ったことなんてなくて、全部片思いで終わってきた。好きになっても、伝える勇気がなくて、どうせ無理だって思って、自分でその気持ちを萎ませてきたんだ。だから、澪があんなふうにまっすぐ気持ちを伝えてくれたことが、すごく眩しく見えた。」
僕は、廿楽君が全部忘れて、僕のことなんて最初から知らなかったフリをしてくれたら、それでよかったのにと思っていた。
でも、彼はそうしなかった。
僕の気持ちに向き合ってくれた。
廿楽君の言葉があまりにも真っ直ぐで、優しくて、僕は何も言えなくなってしまった。
胸がいっぱいで、ただ「うん」と小さく相槌を打つことしかできなかった。
「だからこそ、澪が思いがけず口にしてしまった言葉だったとしても、俺はそれがすごいことだと思った。勇気がいることだし、簡単にできることじゃない。だからこそ、俺もちゃんと向き合って、真剣に答えを出さなきゃいけないって思ってる。」
「……ありがとう、廿楽君。」
僕は、彼の言葉に胸がいっぱいになりながら、感謝の気持ちを込めてそう伝えた。
それだけで、僕の気持ちは救われた気がするよ。
「俺の方こそ、ありがとう。澪が気持ちを伝えてくれたこと、本当に嬉しかった。俺、体育祭までにはちゃんと答えを出したいと思ってる。だから、それまで少しだけ待っててほしい。」
廿楽君の誠実さがひしひしと伝わってくる。
「それじゃあ、またね。」
お互いに短く挨拶を交わして、通話は静かに切れた。
スマホの画面が暗くなったあとも、僕は画面を見つめた。
本当に、廿楽君はずるい。
あんなふうに優しくて、真剣で、僕の気持ちをちゃんと受け止めてくれる。
好きにならずにいられるはずがない。
でも、体育祭の日に、もしかしたら「ごめん」と断られる可能性だってある。
あまり期待しないでおくことにした。
「期待しない。期待しない……。」
僕は自分に言い聞かせるように何度も呟いた。
期待してしまえば、傷つくかもしれないから。