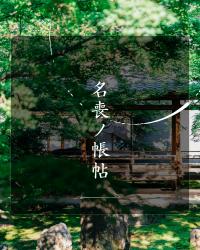新しいクラスでの生活が始まってしばらく経ち、授業の流れにも少しずつ慣れてきた頃。
……とはいえ、僕自身の過ごし方は変わっていない。
教室の中で誰かと積極的に話すこともない。
昼休みには自分の席に座ったまま、静かにお弁当を広げるだけ。
周囲の会話に耳を傾けてはいるものの、自分からその輪に入って話そうとはしない。
相変わらず誰とも深く関わることなく、ひとりで過ごす時間を選び続けている。
周囲の賑やかさとは無縁の、静かな日々を淡々と送っていた。
そんな中、学校では体育祭に向けた準備が本格的に始まり、校内全体の空気が少しずつ活気づいていくのを感じていた。
先生たちもチームを組んで生徒たちに混ざり、競技に参加するそうだ。
そのためか、先生たちの声にも熱が入っている。
学校の年間行事として、6月には体育祭が予定されていて、その後の9月には文化祭が控えている。
どちらも生徒たちが一丸となって取り組んでいかないといけない行事。
生徒たちはそれぞれのイベントに向けて準備を進めていくことになる。
そのため、4月と5月の2ヶ月間は体育祭に向けた準備期間とされていて、授業の合間や放課後には、競技の練習や役割分担などが少しずつ始まっていた。
中には早朝練習というものもあるようだ。
体育祭が終わると、6月の後半から夏休みにかけては文化祭の準備期間となり、今度は教室の雰囲気が文化祭仕様に切り替わっていくことになる。
体育祭では、全員が最低でも1種目には参加しなければならないというルールがあり、僕はその中で比較的人との関わりが少なくて済みそうな綱引きに出場することが決まった。
大勢で力を合わせなければならない競技ではあるが、個別に話す必要が少なく、指示に従ってただただ綱を引っ張っていくのみ。
僕にとっては唯一の選択肢だった。
体育祭で行われる競技は全部で9種目あり、それぞれが異なる形式やルールで構成されていて、生徒たちは自分の得意なものや希望に応じて参加していた。
体育祭の午前中には、スウェーデンリレー、綱引き、障害物&借りものリレー、そして騎馬戦という4つの競技が予定されていて、それぞれがチームワークや瞬発力を求められる種目ばかりだった。
午後には、ウーバーボール、長縄跳び、多人数で足を結んで走る多人多脚、クラスごとの応援合戦、そして最後にチーム対抗リレーという5つの競技が行われる予定で、どれも協力と団結が求められる内容だった。
こうした競技に参加するには、当然ながら誰かと協力しなければならない。
ただ自分ひとりで頑張るだけではどうにもならない。
そのためにはコミュニケーションが不可欠。
僕のように人と話すことが苦手な人間には、こうした協力型の行事はなかなかにハードルが高く感じられる。
協力したくても、言葉にして連携を取っていきたくても、自自分だけがその輪の外にいるような感じになってしまうであろうことは想像に難くない。
今年の体育祭の競技を企画した人たちは、どうやら協力プレイを重視して種目を選んだようで、個人で完結するような競技はほとんどなく、どれも誰かと関わることが前提になっていた。
きっと、みんなで盛り上がれるようにという意図があるのだろう。
けれど僕にとってはそのみんなという言葉にどうしても圧力を感じてしまう。
本音を言えば、玉入れのような無難で個人でも参加しやすい競技があればよかったのにとひねくれた考えをしてしまう。
けれど、そんなことを口に出して文句を言える立場でもなく、僕はただ静かに受け入れるしかなかった。
不満を口にしたところで今更競技の変更がされることはないだろう。
変なことを口走り、輪を乱して、士気を下げることだけはしたくない。
僕が出場することになった綱引きは、放課後に特別な練習があるわけではなく、体育の授業の中でのみ練習が行われるため、他の競技に比べて準備の負担は少なかった。
並び順を決めて、一番後ろの掛け声に合わせて綱を引く練習のみ。
シンプルでわかりやすい。
体育祭の準備期間に入ってからは、体育の授業でもそれぞれの競技ごとに分かれて練習することが多くなったからだろう。
以前はよく見かけていた廿楽君の姿を、最近はほとんど見かけなくなってしまった。
廿楽君は体育祭のすべてのリレー種目に出場する予定だと言っていて、練習がかなり大変だと話していたことを思い出す。
以前よりも顔を会わせる機会が減ったことを、ひとりで彼の姿が見えない理由に納得していた。
喩え合同授業だとしても、同じクラスでもないとこんなに顔を合わせなくなってしまうんだと少し寂しくなる。
彼は「大変だよ」と口では言っていたけれど、その表情はむしろ楽しそうだった。
仲間と一緒に過ごす時間を心から楽しんでいるように見えた。
みかけた彼の笑顔には、疲れなんかよりも充実感が溢れているように見えた。
僕は、休み時間にクラスの友達と楽しそうに話している廿楽君のそばを、何も言わずにただ通り過ぎるだけ。
彼の輪の中に入ることも、声をかけることなど到底できるはずもない。
彼の周りのいつも社交的そうで明るい人たちの中に飛び込むには、あまりにも勇気が足らなすぎた。
うつむき加減で視線を地面に落としながら、少し早足でその場を静かに通り過ぎることしかできなかった。
それでも、廿楽君のそばを通り過ぎるときだけは、ほんの少しだけ歩く速度を落としていた。
彼の声が聞こえる距離にいる時間を、少しでも長く引き伸ばしたい。
そんな思いで、僕は自然と足取りをゆっくりにしていた。
僕のことなんてきっと見ていないであろう廿楽君や、彼の周りにいる同級生たちは、僕が少しでも長くその場にいたいと願っていることなんて、当然知らないし、気づくこともないだろう。
彼らにとって僕は、届通り過ぎていくだけの同級生。
いちいち今通ったのがだれかなんて気にも留めないはずである。
ほんの少しでも長く廿楽君の近くにいたくて、彼の声を聞いておきたくて。
そんな気持ちを表に出してしまえば、周囲の人たちに気持ち悪がられたり、ウザがられたりするかもしれないという不安が常に頭の中にあった僕。
欲を言えば、そこに立ち止まっていたい。
輪に入ることはなくとも、そこにいることが許される人間でありたかった。
僕が立ち止まっていれば、舌打ちをされ、邪魔だと肩にぶつかられてしまうだろう。
だから今日も、いつものように耳をそばだてて、廿楽君の声を拾おうとしながらその場を通り過ぎようとした。
彼がどのような話をしながら笑っているのか。
そんなことを知れるだけで、僕の味気ない一日が、少しだけ特別なものになる気がするから。
通り過ぎるだけの、ものの数秒間。
たかだか数秒だろうと思われるのは心外だが、されど数秒なのだ。
この数秒間に、彼の存在を感じられることが、僕にとってはささやかな幸せだと声を大にして言いたい。
そのとき、彼が楽しそうに話している輪の中、にいつもは見かけない女の子の姿が混ざっているのを見かけた。
彼の隣で笑っているその女の子は、明るく楽しそうに彼に話しかけていた。
それもなんと、ボディータッチまでしていた。
今まで見たことのない組み合わせに、思わず足が止まってしまいそうになった。
僕の心はざわついた。
彼がだれと話しているかなんて、普段なら気にしないようにしていたのに。
普段は男子ばかりと話している廿楽君が、今日は女の子と笑い合っている。
園女の子の存在が、泉の中に小石を落として広がっていく波紋のように、僕の心の中に波を作った。
体育祭の準備を通して仲良くなったのかもしれない。
今のはただの作戦会議か何かだろうと考えようとしても、僕の胸の奥の痛みが消えることはなかった。
やっぱり、廿楽君も普通に女子が好きなんだろうか。
そんな考えが頭をよぎった瞬間、僕の心の中に言葉ではうまく説明できない感情がじわじわと広がっていくことを自覚する。
嫉妬とも寂しさとも違う。
胸の奥がきゅっと締め付けられるような感覚がする。
……あれ?と、自分の思考に違和感を覚えた。
今、僕は一体何を考えた?
頭の中で繰り返されるその問いに、すぐには答えが出なかった。
思考が絡まり、複雑だ。
だけれど、なにか大切なものを見落としている気がして落ち着かない。
廿楽君の好きな人が女子かもしれない。
そんなありふれた可能性を頭の中で想像しただけで、僕の胸の奥がズキリと痛んだ。
綱引きの練習でロープを強く握り続けたせいで、手のひらにはまだヒリヒリと痛みが残っている。
そんな手のひらよりも、今感じている胸の痛みの方が比べ物にならないほどずっと鋭くて、深くて、僕はその違いに戸惑っていた。
どうしてこんなにも苦しくなってしまうのか。
身体の痛みよりも、心の痛みのほうが重たいのはなぜか。
まったく理解できずにいた。
この胸の痛みは、ただの憧れや友情ではなくて、もしかしたら恋愛的な意味で廿楽君のことを好きなのかもしれない。
そんな考えが頭をよぎった瞬間、今まで曖昧だった感情の輪郭がはっきりと見えてきた気がした。
ずっと心の奥にあった感情が、ようやく名前を持ったような感覚。
僕の中で感情の正体が恋だと知って、腑に落ちた。
今まで曖昧だったもやもやとした感情に名前がついたことで、僕の気持ちはスッと軽くなった。
「でも、この気持ちは誰にも知られてはいけない。」
そう心の中で静かに呟いた僕は、今の関係を壊さないために、この感情をそっと胸の奥にしまっておくことを決めた。
廿楽君が同性に対して恋愛感情を抱くことがあるかどうかなんて、僕には分からない。
そもそもそんな可能性があるかどうかすら確信が持てない。
世間一般的の価値観で言えば、同性同士の恋愛が受け入れられない可能性の方が高いのではなかろうか。
僕のこの気持ちも、きっと理解されることなく否定されてしまうかもしれない。
そんな不安がよぎり、余計にこの気持ちを口に出すことが怖かった。
今の僕にとって、唯一まともに会話ができる相手が廿楽君だけという状況。
これが、この気持ちを余計に強くしてしまっているだけなのかもしれないのではなかろうか。
もしかしたら、廿楽君との間にある友情──いや、彼が僕のことを本当に友達だと思ってくれているかどうかも分からないけれど。
この関係を、僕が勝手に勘違いしているだけなのだと、自分に言い聞かせた。
だから僕は、この気持ちはただの勘違いだと、自分自身に強く思い込ませることにして、心の中でその感情に蓋をするように閉じ込めた。
そうしなければ、今の廿楽君との関係──唯一話せる相手である彼との繋がりを失くさないために。
……とはいえ、僕自身の過ごし方は変わっていない。
教室の中で誰かと積極的に話すこともない。
昼休みには自分の席に座ったまま、静かにお弁当を広げるだけ。
周囲の会話に耳を傾けてはいるものの、自分からその輪に入って話そうとはしない。
相変わらず誰とも深く関わることなく、ひとりで過ごす時間を選び続けている。
周囲の賑やかさとは無縁の、静かな日々を淡々と送っていた。
そんな中、学校では体育祭に向けた準備が本格的に始まり、校内全体の空気が少しずつ活気づいていくのを感じていた。
先生たちもチームを組んで生徒たちに混ざり、競技に参加するそうだ。
そのためか、先生たちの声にも熱が入っている。
学校の年間行事として、6月には体育祭が予定されていて、その後の9月には文化祭が控えている。
どちらも生徒たちが一丸となって取り組んでいかないといけない行事。
生徒たちはそれぞれのイベントに向けて準備を進めていくことになる。
そのため、4月と5月の2ヶ月間は体育祭に向けた準備期間とされていて、授業の合間や放課後には、競技の練習や役割分担などが少しずつ始まっていた。
中には早朝練習というものもあるようだ。
体育祭が終わると、6月の後半から夏休みにかけては文化祭の準備期間となり、今度は教室の雰囲気が文化祭仕様に切り替わっていくことになる。
体育祭では、全員が最低でも1種目には参加しなければならないというルールがあり、僕はその中で比較的人との関わりが少なくて済みそうな綱引きに出場することが決まった。
大勢で力を合わせなければならない競技ではあるが、個別に話す必要が少なく、指示に従ってただただ綱を引っ張っていくのみ。
僕にとっては唯一の選択肢だった。
体育祭で行われる競技は全部で9種目あり、それぞれが異なる形式やルールで構成されていて、生徒たちは自分の得意なものや希望に応じて参加していた。
体育祭の午前中には、スウェーデンリレー、綱引き、障害物&借りものリレー、そして騎馬戦という4つの競技が予定されていて、それぞれがチームワークや瞬発力を求められる種目ばかりだった。
午後には、ウーバーボール、長縄跳び、多人数で足を結んで走る多人多脚、クラスごとの応援合戦、そして最後にチーム対抗リレーという5つの競技が行われる予定で、どれも協力と団結が求められる内容だった。
こうした競技に参加するには、当然ながら誰かと協力しなければならない。
ただ自分ひとりで頑張るだけではどうにもならない。
そのためにはコミュニケーションが不可欠。
僕のように人と話すことが苦手な人間には、こうした協力型の行事はなかなかにハードルが高く感じられる。
協力したくても、言葉にして連携を取っていきたくても、自自分だけがその輪の外にいるような感じになってしまうであろうことは想像に難くない。
今年の体育祭の競技を企画した人たちは、どうやら協力プレイを重視して種目を選んだようで、個人で完結するような競技はほとんどなく、どれも誰かと関わることが前提になっていた。
きっと、みんなで盛り上がれるようにという意図があるのだろう。
けれど僕にとってはそのみんなという言葉にどうしても圧力を感じてしまう。
本音を言えば、玉入れのような無難で個人でも参加しやすい競技があればよかったのにとひねくれた考えをしてしまう。
けれど、そんなことを口に出して文句を言える立場でもなく、僕はただ静かに受け入れるしかなかった。
不満を口にしたところで今更競技の変更がされることはないだろう。
変なことを口走り、輪を乱して、士気を下げることだけはしたくない。
僕が出場することになった綱引きは、放課後に特別な練習があるわけではなく、体育の授業の中でのみ練習が行われるため、他の競技に比べて準備の負担は少なかった。
並び順を決めて、一番後ろの掛け声に合わせて綱を引く練習のみ。
シンプルでわかりやすい。
体育祭の準備期間に入ってからは、体育の授業でもそれぞれの競技ごとに分かれて練習することが多くなったからだろう。
以前はよく見かけていた廿楽君の姿を、最近はほとんど見かけなくなってしまった。
廿楽君は体育祭のすべてのリレー種目に出場する予定だと言っていて、練習がかなり大変だと話していたことを思い出す。
以前よりも顔を会わせる機会が減ったことを、ひとりで彼の姿が見えない理由に納得していた。
喩え合同授業だとしても、同じクラスでもないとこんなに顔を合わせなくなってしまうんだと少し寂しくなる。
彼は「大変だよ」と口では言っていたけれど、その表情はむしろ楽しそうだった。
仲間と一緒に過ごす時間を心から楽しんでいるように見えた。
みかけた彼の笑顔には、疲れなんかよりも充実感が溢れているように見えた。
僕は、休み時間にクラスの友達と楽しそうに話している廿楽君のそばを、何も言わずにただ通り過ぎるだけ。
彼の輪の中に入ることも、声をかけることなど到底できるはずもない。
彼の周りのいつも社交的そうで明るい人たちの中に飛び込むには、あまりにも勇気が足らなすぎた。
うつむき加減で視線を地面に落としながら、少し早足でその場を静かに通り過ぎることしかできなかった。
それでも、廿楽君のそばを通り過ぎるときだけは、ほんの少しだけ歩く速度を落としていた。
彼の声が聞こえる距離にいる時間を、少しでも長く引き伸ばしたい。
そんな思いで、僕は自然と足取りをゆっくりにしていた。
僕のことなんてきっと見ていないであろう廿楽君や、彼の周りにいる同級生たちは、僕が少しでも長くその場にいたいと願っていることなんて、当然知らないし、気づくこともないだろう。
彼らにとって僕は、届通り過ぎていくだけの同級生。
いちいち今通ったのがだれかなんて気にも留めないはずである。
ほんの少しでも長く廿楽君の近くにいたくて、彼の声を聞いておきたくて。
そんな気持ちを表に出してしまえば、周囲の人たちに気持ち悪がられたり、ウザがられたりするかもしれないという不安が常に頭の中にあった僕。
欲を言えば、そこに立ち止まっていたい。
輪に入ることはなくとも、そこにいることが許される人間でありたかった。
僕が立ち止まっていれば、舌打ちをされ、邪魔だと肩にぶつかられてしまうだろう。
だから今日も、いつものように耳をそばだてて、廿楽君の声を拾おうとしながらその場を通り過ぎようとした。
彼がどのような話をしながら笑っているのか。
そんなことを知れるだけで、僕の味気ない一日が、少しだけ特別なものになる気がするから。
通り過ぎるだけの、ものの数秒間。
たかだか数秒だろうと思われるのは心外だが、されど数秒なのだ。
この数秒間に、彼の存在を感じられることが、僕にとってはささやかな幸せだと声を大にして言いたい。
そのとき、彼が楽しそうに話している輪の中、にいつもは見かけない女の子の姿が混ざっているのを見かけた。
彼の隣で笑っているその女の子は、明るく楽しそうに彼に話しかけていた。
それもなんと、ボディータッチまでしていた。
今まで見たことのない組み合わせに、思わず足が止まってしまいそうになった。
僕の心はざわついた。
彼がだれと話しているかなんて、普段なら気にしないようにしていたのに。
普段は男子ばかりと話している廿楽君が、今日は女の子と笑い合っている。
園女の子の存在が、泉の中に小石を落として広がっていく波紋のように、僕の心の中に波を作った。
体育祭の準備を通して仲良くなったのかもしれない。
今のはただの作戦会議か何かだろうと考えようとしても、僕の胸の奥の痛みが消えることはなかった。
やっぱり、廿楽君も普通に女子が好きなんだろうか。
そんな考えが頭をよぎった瞬間、僕の心の中に言葉ではうまく説明できない感情がじわじわと広がっていくことを自覚する。
嫉妬とも寂しさとも違う。
胸の奥がきゅっと締め付けられるような感覚がする。
……あれ?と、自分の思考に違和感を覚えた。
今、僕は一体何を考えた?
頭の中で繰り返されるその問いに、すぐには答えが出なかった。
思考が絡まり、複雑だ。
だけれど、なにか大切なものを見落としている気がして落ち着かない。
廿楽君の好きな人が女子かもしれない。
そんなありふれた可能性を頭の中で想像しただけで、僕の胸の奥がズキリと痛んだ。
綱引きの練習でロープを強く握り続けたせいで、手のひらにはまだヒリヒリと痛みが残っている。
そんな手のひらよりも、今感じている胸の痛みの方が比べ物にならないほどずっと鋭くて、深くて、僕はその違いに戸惑っていた。
どうしてこんなにも苦しくなってしまうのか。
身体の痛みよりも、心の痛みのほうが重たいのはなぜか。
まったく理解できずにいた。
この胸の痛みは、ただの憧れや友情ではなくて、もしかしたら恋愛的な意味で廿楽君のことを好きなのかもしれない。
そんな考えが頭をよぎった瞬間、今まで曖昧だった感情の輪郭がはっきりと見えてきた気がした。
ずっと心の奥にあった感情が、ようやく名前を持ったような感覚。
僕の中で感情の正体が恋だと知って、腑に落ちた。
今まで曖昧だったもやもやとした感情に名前がついたことで、僕の気持ちはスッと軽くなった。
「でも、この気持ちは誰にも知られてはいけない。」
そう心の中で静かに呟いた僕は、今の関係を壊さないために、この感情をそっと胸の奥にしまっておくことを決めた。
廿楽君が同性に対して恋愛感情を抱くことがあるかどうかなんて、僕には分からない。
そもそもそんな可能性があるかどうかすら確信が持てない。
世間一般的の価値観で言えば、同性同士の恋愛が受け入れられない可能性の方が高いのではなかろうか。
僕のこの気持ちも、きっと理解されることなく否定されてしまうかもしれない。
そんな不安がよぎり、余計にこの気持ちを口に出すことが怖かった。
今の僕にとって、唯一まともに会話ができる相手が廿楽君だけという状況。
これが、この気持ちを余計に強くしてしまっているだけなのかもしれないのではなかろうか。
もしかしたら、廿楽君との間にある友情──いや、彼が僕のことを本当に友達だと思ってくれているかどうかも分からないけれど。
この関係を、僕が勝手に勘違いしているだけなのだと、自分に言い聞かせた。
だから僕は、この気持ちはただの勘違いだと、自分自身に強く思い込ませることにして、心の中でその感情に蓋をするように閉じ込めた。
そうしなければ、今の廿楽君との関係──唯一話せる相手である彼との繋がりを失くさないために。