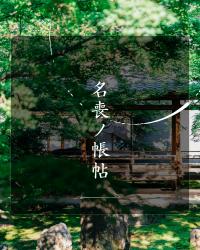金曜の5限。
昼食を食べ終えたばかりの胃がずっしりと重たく感じられて、そのせいで身体を動かすことへの憂鬱な気持ちと、午後特有の眠気がじわじわと押し寄せてきて、頭の中がぼんやりと霞んでいく。
このタイミングで体育の授業があるなんて、正直言って僕にとっては最悪で、身体を動かす気力などないに等しい。
体育なんて、正直いちばんやりたくない時間帯だ。
けれど、今日の体育の時間は、いつもとは少しだけ違っている。
心の奥底では、僕は密かに期待していた。
今日の体育は2組との合同授業だといいなという僕個人の淡い希望を抱いていたから。
そわそわと落ち着かない気持ちをなだめ、体操服に着替えて体育館へと足を運んだ。
そこには本当に廿楽君の姿があって、僕の心臓は驚きと嬉しさで一気に跳ね上がった。
廿楽君は、新しいクラスでできたばかりの友達と思われる人たちに囲まれていた。
中心にいる彼は、自然と周囲の視線を集めてしまうような存在感だった。
そんな中に僕が入っていく勇気があるはずもない。
僕は、初日の自己紹介でなんとか覚えたクラスメイトたちの出席番号と名前を頼りに、自分が座るべき場所を探した。
どうやらクラスメイトたちはそれぞれ自由に好きな場所に座っているようで、僕は体育館の隅の目立たない場所にそっと腰を下ろした。
僕を注視する人なんていないと思うが、できるだけ人の視線を避けるようにして静かに座っているほうが落ち着くからだ。
「よし、そろそろチャイムが鳴る時間だな。みんな、クラスごとに男女に分かれて、背の順に並び替えてくれ!」
体育の先生が声を張り上げて指示を出し、みんなが一斉に動き始めた。
やっぱり、自由に座っていられるはずもないよなと納得する。
背の順ならばと、自分の背の高さを考えて後ろの方へと移動した。
周囲では、クラスメイトたちが楽しそうに背比べをしながら、誰が前で誰が後ろかを決めていた。
僕はそんな光景を眺めるだけで、静かに立っていた。
平均的で微妙な身長だと、前後の位置を決めるためにはどうしても周囲との比較が必要になって、自然と会話が生まれる場面が必然的に多くなる。
人との会話が苦手な僕のようなタイプにとっては、背が極端に高いか低いかであれば、何も言わずとも自然に並ぶ位置が決まるから楽ではあった。
平均的な身長だとどうしても他人とのやり取りが必要になってしまうのが考えるだけでも辛く、背の高さに感謝をする日が来るなんて思ってもみなかった。
クラスメイトたちが楽しそうに背比べをしたり、笑い声を交わしたりしているその賑やかな空気の中で、チャイムの音はまるで背景音のようにかき消されていた。
ようやく全員が背の順に並び終えたタイミングで、体育の先生が大きく手を叩いて、体育館に響くその音が、ざわついていた空気を一瞬で静めた。
全員の視線が自然と先生の方へと向けられる。
「背の順に並んでくれてありがとう。新任式で僕の紹介はあったと思うけど、たぶん覚えてない人がほとんどだよね。これから授業を通して、少しずつ覚えてくれたら嬉しいです。さて、今日みんなに背の順で並んでもらったのは、新体力テストを行うためです。ペアは、並んでいる順番で前後の人と組んでもらいます!」
そう先生が明るく説明した。
「背の順でペアを組む」という言葉が耳に入った瞬間、僕の頭の中は真っ白になってしまい、思考が止まった。
心臓の鼓動だけがやけに大きく感じられる。
僕のクラスの男子の人数は奇数だ。
背の順でペアを組むとなると、どうしてもひとり余ってしまう状況は避けられない。
そして、その余りに当てはまるのは僕だった。
このままでは、先生とペアを組まされるか、あるいは前に並んでいる背の近い人たちと無理やり3人組にされるかのどちらかだろう。
どちらにしても居心地の悪さがつきまとう未来が頭の中に浮かんでいた。
そんな可能性を考えただけで、胃のあたりがキリキリと痛み始めて、さっき食べた昼食がせりあがってくる感覚に襲われた。
もし先生とペアになってしまったら、授業の見本として前に出される可能性もあるだろう。
みんなの前で注目を浴びるなんて、僕には到底務まるはずがない。
もし3人組になったら、他の2人に気を使わせてしまうだろう。
居たたまれない気まずさを感じてしまうことが目に見えている。
しかも、今年から赴任してきたばかりの新任の先生は僕のことを何も知らないから、どんな指示をされるのかも予測がつかず、その未知の恐怖がさらに僕の不安を煽っていた。
実際に、僕のすぐ前に並んでいる2番目と3番目に背が高い男子からの視線が、まるで針のように僕に突き刺さる。
「どうするんだよ」
そんな風に言いたげな空気が痛いほど伝わってきた。
先生とペアになっても、3人組になっても、どちらにしても最悪でしかない。
そう思っていたそのとき、思いがけない声が体育館に響いた。
「先生!2組の廿楽です。うちのクラスの男子も奇数なんですけど、5組の人とペアを組んでもいいですか?」
先生は少し驚いたような顔をしながらも、「いいぞ。そこの2人はクラスは違うけど……それでも構わないよな?」と僕の方を見て確認しているようだった。
先生の視線が僕に向けられた瞬間、僕は言葉を発する余裕はなかった。
その代わりとにかく何度も大きく頷いて、廿楽君の申し出に全力で賛同していることを必死に伝えた。
僕のすぐ前に並んでいる2番目と3番目に背が高い男子も、安堵したように「良かったな」とでも言いあっているのか互いに目くばせしていた。
「よろしくな」
「う、うん。こちらこそ、よろしく。先生に申し出てくれてありがとう。」
廿楽君は自然な口調でそう言ってくれて、その優しさが僕の心にじんわりと染み込む。
ペア決めが済んだところで、女子たちが別の体育館に移動していく。
周囲の男子の中には、女子と同じ体育館で新体力テストを受けたかったと不満げにぼやいている人たちもいた。
男子は今集合している第二体育館で行うそうだ。
全部で8種目。
握力、長座体前屈、反復横跳びに立ち幅跳び。
ここまではよかった。
問題はこの今目の前にあるマット、上体起こしだ。
30秒間ペアの相手が両足を抑えて固定の補助をしなくてはならない。
そう。彼の手が僕の身体に触れるし、逆もしかり。
距離の近さと、身体的接触という事実に、心臓が早鐘のように鳴り始めていた。
この状況を乗り越えるためには、心を落ち着けて集中するしかない。
僕は頭の中で「大丈夫」と何度も唱えながら、精神を整えることに必死だった。
息を吐いて、またゆっくり吸い込んで、呼吸のリズムを整えることで、少しでも心のざわつきを抑えようとした。
何度か繰り返しても、落ち着くことはなかった。
早くしないと全体に迷惑がかかる。
覚悟を決めれないまま僕は、マットの上にそっと身体を倒して、上体起こしの体勢に入った。
ストップウォッチの音が鳴り響いた瞬間、周囲の男子たちは一斉に上体起こしを始める。
マットの上で身体を起こす音と息遣いが重なっていた。
僕は視線を体育館の天井や他の生徒たちの方へと目を向けることにした。
運動部に所属していると思われる男子たちは、驚くほどのスピードで上体を起こしていた。
その動きの速さに圧倒されながら、僕は自分のペースで上体起こしをすることに必死だった。
周囲を見る余力すらなくなり、僕は目をぎゅっと閉じることにした。
視覚からの情報を遮断しながら、ただ自分のリズムだけを頼りに上体起こしに専念した。
「澪、肘がちゃんと太ももについてないぞ」
疲れてきたところで廿楽君の声が耳に届いてきて目を開けた。
「え、あ……」
思わず声が漏れてしまい、自分の肘と太ももの位置を確認するために視線を落とした。
そのあと、何気なく廿楽君の方を見ると、目が合ってしまった。
その瞬間、僕の顔が熱を帯びていくのがはっきりとわかった。
頬がじんわりと熱くなっていくのを感じながら、僕は視線をそらすようにして身体を倒した。
背中をマットにぴたりとつけて、残りの時間が早く過ぎてくれることだけを願っていた。
そのまま動かずにじっとしていると、やがて30秒が経過したようで、体育館にストップウォッチの音が再び鳴り響く。
やっと終わったという安堵を感じる間もなく、すぐに僕が廿楽君の足を支える番になってしまった。
「さっき、声かけちゃってごめんな。」
「いや、大丈夫。疲れてたし、あれ以上はもう無理だったと思うから、気にしないで。」
廿楽君が少し申し訳なさそうに言ってくれて、その気遣いに僕は慌てて言葉を返した。
わざわざ声をかけてくれたのに、それに対して謝らせてしまったことが申し訳なくて、むしろ僕の方こそ謝りたいくらいだ。
僕は廿楽君の両肘がしっかりと両太ももに触れる回数だけに集中することにした。
数を数えながら支えていたら、思っていたよりもずっと早く30秒が過ぎていた。
限られた授業時間の中では、すべての新体力テストの項目を終えることは到底できず、結局いくつかの種目は次回に持ち越されることになった。
次回の体育は火曜日の2限に行われる予定で、そのときに残っていた20メートルシャトルランと50メートル走、そしてハンドボール投げの3種目をまとめて実施することになるそうだ。
授業の前半では、まず瞬発力や腕の力が試される種目の50メートル走とハンドボール投げを。
そして授業の後半には、最も体力を消耗する20メートルシャトルランを行うそうだ。
50メートルを全力で走った直後に、さらに20メートルの距離を何度も往復しなければならないという流れは、体力的にも精神的にもかなりハード。
僕は体力も気力もない僕は、すでに気持ちが萎えてしまっていた。
空腹状態の4限でも、満福状態の5限でもないことが唯一の救いかもしれない。
無情にもやって来た、火曜の2限。
「澪、今回の記録どうだった?」
そう廿楽君が僕の方に歩み寄ってきて、気さくな声でそう尋ねてくれる。
「えっと……こんな感じだった。」
僕は記録の書かれた用紙をそっと彼に差し出した。
心の中がざわつくのを感じながらも、なるべく普通にいつもと同じように話すように専念した。
「おぉ、澪すごいじゃん!平均を超えてる項目もあるし、なんなら俺より良い記録のところもある。」
廿楽君が驚いたように声を上げて、なんともない僕の記録を褒めてくれた。
「身体だけは昔からなぜか柔らかくてさ。小さい頃から男のくせにってよく笑われてたんだ」
過去の記憶がふと蘇ってきた。
僕が上手に笑顔を作ることができず、引きつった苦笑いだったせいだろう。
廿楽君が申し訳なさそうに眉を下げるものだから、彼に余計な気を遣わせたくないという思いで僕は話題をそらした。
「廿楽君はどうだった?」
尋ねてみると、僕に自身の記録表を見せてくれた廿楽君。
すべての項目で平均を上回る記録を出していて、評価はもちろんAクラス。
彼の運動能力の高さに僕は改めて感心した。
昼食を食べ終えたばかりの胃がずっしりと重たく感じられて、そのせいで身体を動かすことへの憂鬱な気持ちと、午後特有の眠気がじわじわと押し寄せてきて、頭の中がぼんやりと霞んでいく。
このタイミングで体育の授業があるなんて、正直言って僕にとっては最悪で、身体を動かす気力などないに等しい。
体育なんて、正直いちばんやりたくない時間帯だ。
けれど、今日の体育の時間は、いつもとは少しだけ違っている。
心の奥底では、僕は密かに期待していた。
今日の体育は2組との合同授業だといいなという僕個人の淡い希望を抱いていたから。
そわそわと落ち着かない気持ちをなだめ、体操服に着替えて体育館へと足を運んだ。
そこには本当に廿楽君の姿があって、僕の心臓は驚きと嬉しさで一気に跳ね上がった。
廿楽君は、新しいクラスでできたばかりの友達と思われる人たちに囲まれていた。
中心にいる彼は、自然と周囲の視線を集めてしまうような存在感だった。
そんな中に僕が入っていく勇気があるはずもない。
僕は、初日の自己紹介でなんとか覚えたクラスメイトたちの出席番号と名前を頼りに、自分が座るべき場所を探した。
どうやらクラスメイトたちはそれぞれ自由に好きな場所に座っているようで、僕は体育館の隅の目立たない場所にそっと腰を下ろした。
僕を注視する人なんていないと思うが、できるだけ人の視線を避けるようにして静かに座っているほうが落ち着くからだ。
「よし、そろそろチャイムが鳴る時間だな。みんな、クラスごとに男女に分かれて、背の順に並び替えてくれ!」
体育の先生が声を張り上げて指示を出し、みんなが一斉に動き始めた。
やっぱり、自由に座っていられるはずもないよなと納得する。
背の順ならばと、自分の背の高さを考えて後ろの方へと移動した。
周囲では、クラスメイトたちが楽しそうに背比べをしながら、誰が前で誰が後ろかを決めていた。
僕はそんな光景を眺めるだけで、静かに立っていた。
平均的で微妙な身長だと、前後の位置を決めるためにはどうしても周囲との比較が必要になって、自然と会話が生まれる場面が必然的に多くなる。
人との会話が苦手な僕のようなタイプにとっては、背が極端に高いか低いかであれば、何も言わずとも自然に並ぶ位置が決まるから楽ではあった。
平均的な身長だとどうしても他人とのやり取りが必要になってしまうのが考えるだけでも辛く、背の高さに感謝をする日が来るなんて思ってもみなかった。
クラスメイトたちが楽しそうに背比べをしたり、笑い声を交わしたりしているその賑やかな空気の中で、チャイムの音はまるで背景音のようにかき消されていた。
ようやく全員が背の順に並び終えたタイミングで、体育の先生が大きく手を叩いて、体育館に響くその音が、ざわついていた空気を一瞬で静めた。
全員の視線が自然と先生の方へと向けられる。
「背の順に並んでくれてありがとう。新任式で僕の紹介はあったと思うけど、たぶん覚えてない人がほとんどだよね。これから授業を通して、少しずつ覚えてくれたら嬉しいです。さて、今日みんなに背の順で並んでもらったのは、新体力テストを行うためです。ペアは、並んでいる順番で前後の人と組んでもらいます!」
そう先生が明るく説明した。
「背の順でペアを組む」という言葉が耳に入った瞬間、僕の頭の中は真っ白になってしまい、思考が止まった。
心臓の鼓動だけがやけに大きく感じられる。
僕のクラスの男子の人数は奇数だ。
背の順でペアを組むとなると、どうしてもひとり余ってしまう状況は避けられない。
そして、その余りに当てはまるのは僕だった。
このままでは、先生とペアを組まされるか、あるいは前に並んでいる背の近い人たちと無理やり3人組にされるかのどちらかだろう。
どちらにしても居心地の悪さがつきまとう未来が頭の中に浮かんでいた。
そんな可能性を考えただけで、胃のあたりがキリキリと痛み始めて、さっき食べた昼食がせりあがってくる感覚に襲われた。
もし先生とペアになってしまったら、授業の見本として前に出される可能性もあるだろう。
みんなの前で注目を浴びるなんて、僕には到底務まるはずがない。
もし3人組になったら、他の2人に気を使わせてしまうだろう。
居たたまれない気まずさを感じてしまうことが目に見えている。
しかも、今年から赴任してきたばかりの新任の先生は僕のことを何も知らないから、どんな指示をされるのかも予測がつかず、その未知の恐怖がさらに僕の不安を煽っていた。
実際に、僕のすぐ前に並んでいる2番目と3番目に背が高い男子からの視線が、まるで針のように僕に突き刺さる。
「どうするんだよ」
そんな風に言いたげな空気が痛いほど伝わってきた。
先生とペアになっても、3人組になっても、どちらにしても最悪でしかない。
そう思っていたそのとき、思いがけない声が体育館に響いた。
「先生!2組の廿楽です。うちのクラスの男子も奇数なんですけど、5組の人とペアを組んでもいいですか?」
先生は少し驚いたような顔をしながらも、「いいぞ。そこの2人はクラスは違うけど……それでも構わないよな?」と僕の方を見て確認しているようだった。
先生の視線が僕に向けられた瞬間、僕は言葉を発する余裕はなかった。
その代わりとにかく何度も大きく頷いて、廿楽君の申し出に全力で賛同していることを必死に伝えた。
僕のすぐ前に並んでいる2番目と3番目に背が高い男子も、安堵したように「良かったな」とでも言いあっているのか互いに目くばせしていた。
「よろしくな」
「う、うん。こちらこそ、よろしく。先生に申し出てくれてありがとう。」
廿楽君は自然な口調でそう言ってくれて、その優しさが僕の心にじんわりと染み込む。
ペア決めが済んだところで、女子たちが別の体育館に移動していく。
周囲の男子の中には、女子と同じ体育館で新体力テストを受けたかったと不満げにぼやいている人たちもいた。
男子は今集合している第二体育館で行うそうだ。
全部で8種目。
握力、長座体前屈、反復横跳びに立ち幅跳び。
ここまではよかった。
問題はこの今目の前にあるマット、上体起こしだ。
30秒間ペアの相手が両足を抑えて固定の補助をしなくてはならない。
そう。彼の手が僕の身体に触れるし、逆もしかり。
距離の近さと、身体的接触という事実に、心臓が早鐘のように鳴り始めていた。
この状況を乗り越えるためには、心を落ち着けて集中するしかない。
僕は頭の中で「大丈夫」と何度も唱えながら、精神を整えることに必死だった。
息を吐いて、またゆっくり吸い込んで、呼吸のリズムを整えることで、少しでも心のざわつきを抑えようとした。
何度か繰り返しても、落ち着くことはなかった。
早くしないと全体に迷惑がかかる。
覚悟を決めれないまま僕は、マットの上にそっと身体を倒して、上体起こしの体勢に入った。
ストップウォッチの音が鳴り響いた瞬間、周囲の男子たちは一斉に上体起こしを始める。
マットの上で身体を起こす音と息遣いが重なっていた。
僕は視線を体育館の天井や他の生徒たちの方へと目を向けることにした。
運動部に所属していると思われる男子たちは、驚くほどのスピードで上体を起こしていた。
その動きの速さに圧倒されながら、僕は自分のペースで上体起こしをすることに必死だった。
周囲を見る余力すらなくなり、僕は目をぎゅっと閉じることにした。
視覚からの情報を遮断しながら、ただ自分のリズムだけを頼りに上体起こしに専念した。
「澪、肘がちゃんと太ももについてないぞ」
疲れてきたところで廿楽君の声が耳に届いてきて目を開けた。
「え、あ……」
思わず声が漏れてしまい、自分の肘と太ももの位置を確認するために視線を落とした。
そのあと、何気なく廿楽君の方を見ると、目が合ってしまった。
その瞬間、僕の顔が熱を帯びていくのがはっきりとわかった。
頬がじんわりと熱くなっていくのを感じながら、僕は視線をそらすようにして身体を倒した。
背中をマットにぴたりとつけて、残りの時間が早く過ぎてくれることだけを願っていた。
そのまま動かずにじっとしていると、やがて30秒が経過したようで、体育館にストップウォッチの音が再び鳴り響く。
やっと終わったという安堵を感じる間もなく、すぐに僕が廿楽君の足を支える番になってしまった。
「さっき、声かけちゃってごめんな。」
「いや、大丈夫。疲れてたし、あれ以上はもう無理だったと思うから、気にしないで。」
廿楽君が少し申し訳なさそうに言ってくれて、その気遣いに僕は慌てて言葉を返した。
わざわざ声をかけてくれたのに、それに対して謝らせてしまったことが申し訳なくて、むしろ僕の方こそ謝りたいくらいだ。
僕は廿楽君の両肘がしっかりと両太ももに触れる回数だけに集中することにした。
数を数えながら支えていたら、思っていたよりもずっと早く30秒が過ぎていた。
限られた授業時間の中では、すべての新体力テストの項目を終えることは到底できず、結局いくつかの種目は次回に持ち越されることになった。
次回の体育は火曜日の2限に行われる予定で、そのときに残っていた20メートルシャトルランと50メートル走、そしてハンドボール投げの3種目をまとめて実施することになるそうだ。
授業の前半では、まず瞬発力や腕の力が試される種目の50メートル走とハンドボール投げを。
そして授業の後半には、最も体力を消耗する20メートルシャトルランを行うそうだ。
50メートルを全力で走った直後に、さらに20メートルの距離を何度も往復しなければならないという流れは、体力的にも精神的にもかなりハード。
僕は体力も気力もない僕は、すでに気持ちが萎えてしまっていた。
空腹状態の4限でも、満福状態の5限でもないことが唯一の救いかもしれない。
無情にもやって来た、火曜の2限。
「澪、今回の記録どうだった?」
そう廿楽君が僕の方に歩み寄ってきて、気さくな声でそう尋ねてくれる。
「えっと……こんな感じだった。」
僕は記録の書かれた用紙をそっと彼に差し出した。
心の中がざわつくのを感じながらも、なるべく普通にいつもと同じように話すように専念した。
「おぉ、澪すごいじゃん!平均を超えてる項目もあるし、なんなら俺より良い記録のところもある。」
廿楽君が驚いたように声を上げて、なんともない僕の記録を褒めてくれた。
「身体だけは昔からなぜか柔らかくてさ。小さい頃から男のくせにってよく笑われてたんだ」
過去の記憶がふと蘇ってきた。
僕が上手に笑顔を作ることができず、引きつった苦笑いだったせいだろう。
廿楽君が申し訳なさそうに眉を下げるものだから、彼に余計な気を遣わせたくないという思いで僕は話題をそらした。
「廿楽君はどうだった?」
尋ねてみると、僕に自身の記録表を見せてくれた廿楽君。
すべての項目で平均を上回る記録を出していて、評価はもちろんAクラス。
彼の運動能力の高さに僕は改めて感心した。