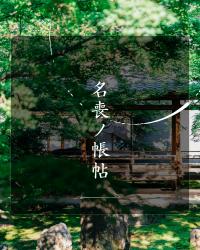前髪を隔てた向こう側。
隙間から見える自分の顔をこれほどまでに近くに寄れば、否応なしに洗面所の鏡に映る自分自身と目が合う。
その瞬間、毎朝のことながら何とも言えない居心地の悪さが胸の奥に広がっていく。
気づけば、自然とため息がこぼれ落ちていた。
言葉にならない不満や不安が形を変えて吐き出される。
「洗面所の鏡って、なぜか自分がちょっとだけ可愛く見える気がするんだよね。」と姉はいつも不思議そうに、けれど嬉しそうに笑いながら言う。
だけど僕にとって洗面所の鏡は、他の鏡と何ら変わりはない。
僕の顔がよく見えたことなんて一度も起きたことがない。
むしろ、鏡に映る自分がただただ現実を突き付けてくるのみ。
姉が言うように盛れなんて現象は起きたためしがない。
僕にだけには自分の粗を強調させて映しているのではとしか思えない。
鏡にすら嫌われているんだなと自分の顔から視線を外す。
肌が色白なせいで目元のクマが余計に目立っているのではないか。
いつものように眼鏡を手に取り、慣れた動作で耳にかける。
先程よりクリアになった視界。
鼻が低く、落ちてきた眼鏡をなおす。
鏡の自分と目を合わせないように洗面所を出た。
眼鏡のレンズと前髪。
この2種類のフィルターがあれば、周囲の人と目を合わせることがなくてすむ。
僕の存在を隠してくれる頼もしい防護壁だ。
新しい学期の始まりだというだけでも十分に憂鬱なのに、これから始まる日々を想像しただけで押しつぶされそうになる。
それでも学校を休むことはできない。
小さな声で「行ってきます」と呟いて玄関を出た。
家のドアが静かに閉まる音と、容赦なく照り付ける太陽の眩しさに目を細める。
視線を地面へ落とし、歩き始めた。
新学期の朝、校舎の掲示板にクラス分けの紙が張り出されるその瞬間は、全学年の生徒たちが一斉に集まってくる。
そため、昇降口前はまるで人混みの渦のようになってしまい、僕にとっては息苦しくて逃げ出したくなるほど嫌な時間になる。
こんな混雑の中で無理に人とぶつかりながら紙を見に行くくらいなら、学校の指定メールアドレスにPDFファイルでクラス分けを送ってくれればどれだけ楽だろうと、思うけれど、そんな配慮はまったくない。
人混みを避けるために、わざわざ遠回りして時間をずらして登校したのに、校舎の前に着いてみれば、掲示板の前にはまだたくさんの生徒が群がっていた。
もっと道草を食いながら来るべきだった。
また戻るのも面倒だ。
もうすでに3回目になるため息を静かに吐き出しながら、誰かと待ち合わせをしているような雰囲気を装うことにした。
耳に差し込んだイヤホンから流れる曲を適当に変え、スマホの画面を意味もなくタップして、周囲の視線を避けるための演技に徹する。
掲示板の前では、友達同士で集まっている生徒たちが、誰が同じクラスになったとか、誰と離れてしまったとか、そんな話題で楽しそうに盛り上がっているのだと思う。
その輪を作る友達もおらず、輪の中に入ったこともない僕は、ただ遠くからその様子を眺めるしかなかった。
羨ましいなんて思うのはとっくの昔に諦めた。
クラス替えというちょっとしたイベントだけであんなに騒げる陽キャたちの姿を横目で見ながら、僕はできるだけ目立たないように肩をすぼめて、存在感を消すようにしてその場に立ち尽くしていた。
掲示板の前にいた生徒たちの数が少しずつ減ってきたのを見計らって、僕はそっとイヤホンを外してポケットにしまい、スマホの電源を切る。
校則で、校内でのスマートフォンの使用は固く禁じられていて、見つかればすぐに注意と反省文になるため、僕はその規則をきちんと守るようにしていた。
校舎の中ではイヤホンで音楽を聴きながら時間を潰すという僕にとっての数少ない逃げ道が使えなくなってしまう。
もっと早く知っていれば、この学校を受験することはしなかっただろう。
僕のリサーチ不足のせいなのので残り2年をどう過ごすか考えないと。
去年は居心地の悪さを感じてはいたが、なんとか乗りkることができたのだ。
今年も同じようにすればいいだけだと自分を励ます。
以前、陽キャの生徒の中には、校内でスマホを使っているところを先生に見つかってしまっていた。
その生徒が反省文を書いている最中にもかかわらず、周囲の友達から「もっと上手く隠して使えよ、バレるなんてダサいぞ」と冗談交じりに茶化されていて、まるで罰を受けることすらも一種のイベントのように楽しんでいるようだった。
少しだけ羨ましいと思う気持ちが胸の奥に芽生えたけれど、僕にはそんな大胆さも器用さもなくて、ただ真面目に規則を守ることしかできなかった。
僕はゆっくりと深呼吸をして、息を整えてから、覚悟を決めるように校門をくぐり抜けた。
掲示板に貼られたクラス分けの紙を前にして、僕──甘楽 澪は、自分の名前を見つけるために一つひとつのクラスを丁寧に確認していったけれど、そこで最初に目に入ったのは、僕の名前ではなく、別の名前だった。
その名前は、昨年同じクラスで、僕のことを何かと気にかけてくれていた唯一の存在──廿楽 陸翔のもので、彼の名前を見つけた瞬間、胸の奥が少しだけざわついた。
振り返ってみれば去年は、先生以外の誰かとまともに会話を交わした記憶があるのは廿楽君だけだった。
彼の存在が僕にとってどれほど貴重だったかを改めて思い知らされる。
「違うんだ……。」
それは誰に向けたわけでもなく、ただ小さく呟いただけの僕の声。
只のひとりごとだったのに、それは、ちょうどそのとき肩に軽く重みをかけてきた誰かの耳にも届いてしまったようだった。
僕は思わずびくりと体をこわばらせた。
「違うって、どういうこと?」
そう肩に手を置いたままの人物が僕の呟きを拾って問いかけてきた。
その声は、聞き慣れた優しい響きだった。
横を見ると、そこに立っていたのは、やはり廿楽君本人だった。
「あ……廿楽くん、おはよう。」
驚きと少しの緊張を混ぜながら言葉を返した。
僕は、掲示板に貼られた2組の名簿に彼の名前を見つけたことを伝える。
「おー、俺もさっき見たよ!俺、文系だから1組から3組のどこかになるって思ってたんだけど、やっぱり気になってさ。澪は理系だったよな?ってことは、4組か5組のどっちかか。離れちゃうの、ちょっと寂しいな〜」
廿楽君は気さくに話しかけてくれて、去年と変わらない屈託のない笑顔を浮かべている。
僕は、理系のクラスである4組か5組にいるはずらしい。
知らずに1組から順番に確認していたことが急に恥ずかしくなってしまい、3組を飛ばして慌てて4組の名簿に目を走らせた。
4組の名簿には僕の名前が見当たらなかったから、理系の最後のクラスである5組にいることはほぼ確定だろう。
それでも念のために、掲示板に貼られた5組を順番に目で追っていくと、ようやく自分の名前を見つけることができた。
これで自分の名前が無かったら悲しいのもあるが、名前がなかったことを先生に伝えたときの先生のヤバいという引きつった顔。
中学のころの経験を思い出しただけで気が滅入る。
「5組なら体育の授業は一緒になるかもしれないな!先輩たちの話だと、文系と理系で分かれてても週に2回は体育の合同授業があるらしいから、またよろしくな!」
そんな僕のことはお構いなしに、廿楽君は明るく言ってくれる。
そんな彼とクラスが分かれてしまったことに寂しさを感じる。
理性と文系の混合クラスがあったら良かったのに。
彼はきっと新しいクラスにもすぐに打ち解け、友達ができて、楽しく過ごせるはず。それなのに、もうクラスメイトですらなくなった僕のことまで気にかけてくれるなんて嬉しかった。
僕はただ小さく頷くだけで、廿楽君の言葉に応えるのが精一杯だった。
ちょうどいいタイミングで廿楽君は友達に声をかけられ、僕はそれをきっかけに自然な流れでその場を離れる。
僕は無言のまま靴を履き替え、誰にも気づかれないようにそっと階段を上って、2階の一番奥にある自分の新しいクラスを目指して、足早に歩き始めた。
1組から順に並ぶ教室の前を通り過ぎて、廊下の一番奥にある5組まで歩いていかなければならない。
鞄の持ち手をぎゅっと握り締めて、競歩のような速さで廊下にいる同級生たちの間をすり抜けながら、教室へと向かった。
教室の扉をそっと開けて中に入ると、そこには去年のクラスで見かけたことのある顔が何人かいた。
少しだけ安心する気持ちと、同時に気づかれたくないという複雑な思いが胸の中で交差した。
彼らが僕のことを覚えているかどうかなんて、確かめる方法もない。
話しかけたところでウザがられたり、気持ち悪がられたりするのが落ちである。
そもそも僕の存在が彼らの記憶に残っている可能性は低いだろうと結論付けた。
教室の前方に貼り出された名簿で自分の名前を探し、ようやく見つけた席は、廊下側の一番後ろ。
教室の後方にあるドアから出入りするにはちょうどよく、僕のように目立ちたくない人間にはぴったりの場所だった。
鞄をそっと机の横に掛けて、机の上に腕を伸ばして突っ伏した。
教室内の笑い声や話し声といった騒がしさが逆に僕の存在をかき消してくれる。
僕は机に伏せたまま、担任の先生が教室に来るまでの時間をやり過ごした。
「澪ってさ、静かだけど話すと意外と面白いよな」
そんな何気ない廿楽君の言葉が、ふと頭の中に蘇ってきた。
その記憶を振り払うように、僕はそっと首を横に振った。
あの一言が、どれほど僕の心を温めてくれたか、彼はきっと知らない。
自然と頭の中に浮かんでくるのは、廿楽君と過ごした時間ばかり。
他に思い出せる人がおらず、彼の笑顔や声、ちょっとした仕草が、まるで染みついたように僕の記憶の中で鮮明に思い出せる。
僕にとっては宝物のような思い出たち。
だけど、彼にとってはきっと、何気ない日常のひとコマでしかないだろう。
特別な意味なんて持っていないのかもしれないと思うと、胸の奥がじわりと痛んだ。
そんな去年の廿楽君に思いをはせていた僕の耳に、担任の先生の声が届いた。
その内容は、いきなりの自己紹介。
教壇の前に立って、ひとりずつ話すという形式に、僕の心臓はどくんと大きく跳ねた。
全員の視線を浴びながら自己紹介をしなければならないことは、僕にとってはまさに地獄そのもので、逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。
出席番号順に呼ばれていく中で、心の準備をする間もなく、僕の番はすぐにやってきてしまった。
僕の名前が呼ばれた瞬間、頭の中が真っ白になった。
足が重たく感じながらもなんとか教壇の前まで歩いてく。
教室のどこを見ればいいのか分からず、視線が宙をさまよった末に、結局僕は床に目を落とし、誰とも目を合わせないようにした。
手のひらにはじっとりと汗がにじんでいて、震える声で「あー、えっと……甘楽 澪です。1年間よろしくお願いします」とだけ絞り出すのが精一杯だった。
緊張で口の中が乾ききっていて、絞り出すように発した自己紹介が、果たしてクラスメイトたちにちゃんと届いていたのかは分からない。
でも、教室のあちこちから小さな拍手が聞こえてきて、僕は、まるで逃げるように足早に自分の席へ戻り、深く息を吐き出した。
僕の番が終わったあとも、クラスメイトたちは順番に教壇の前へと立ち、それぞれの言葉で自己紹介をしていった。
誰もが、趣味や部活、好きなことを堂々と話していて、僕のように最低限の言葉だけで済ませた人はひとりもいなかった。
この先、彼らと話すことなんてきっとないだろうと思う。
でも、もしかしたら僕に話しかけてくれる人がいるかもしれないという淡い期待のもと、クラスメイトたちの名前と顔を一致させるために僕は真剣に耳を傾けた。
この自己紹介の場以外で、彼らの名前を知る機会なんてないだろうから。
隙間から見える自分の顔をこれほどまでに近くに寄れば、否応なしに洗面所の鏡に映る自分自身と目が合う。
その瞬間、毎朝のことながら何とも言えない居心地の悪さが胸の奥に広がっていく。
気づけば、自然とため息がこぼれ落ちていた。
言葉にならない不満や不安が形を変えて吐き出される。
「洗面所の鏡って、なぜか自分がちょっとだけ可愛く見える気がするんだよね。」と姉はいつも不思議そうに、けれど嬉しそうに笑いながら言う。
だけど僕にとって洗面所の鏡は、他の鏡と何ら変わりはない。
僕の顔がよく見えたことなんて一度も起きたことがない。
むしろ、鏡に映る自分がただただ現実を突き付けてくるのみ。
姉が言うように盛れなんて現象は起きたためしがない。
僕にだけには自分の粗を強調させて映しているのではとしか思えない。
鏡にすら嫌われているんだなと自分の顔から視線を外す。
肌が色白なせいで目元のクマが余計に目立っているのではないか。
いつものように眼鏡を手に取り、慣れた動作で耳にかける。
先程よりクリアになった視界。
鼻が低く、落ちてきた眼鏡をなおす。
鏡の自分と目を合わせないように洗面所を出た。
眼鏡のレンズと前髪。
この2種類のフィルターがあれば、周囲の人と目を合わせることがなくてすむ。
僕の存在を隠してくれる頼もしい防護壁だ。
新しい学期の始まりだというだけでも十分に憂鬱なのに、これから始まる日々を想像しただけで押しつぶされそうになる。
それでも学校を休むことはできない。
小さな声で「行ってきます」と呟いて玄関を出た。
家のドアが静かに閉まる音と、容赦なく照り付ける太陽の眩しさに目を細める。
視線を地面へ落とし、歩き始めた。
新学期の朝、校舎の掲示板にクラス分けの紙が張り出されるその瞬間は、全学年の生徒たちが一斉に集まってくる。
そため、昇降口前はまるで人混みの渦のようになってしまい、僕にとっては息苦しくて逃げ出したくなるほど嫌な時間になる。
こんな混雑の中で無理に人とぶつかりながら紙を見に行くくらいなら、学校の指定メールアドレスにPDFファイルでクラス分けを送ってくれればどれだけ楽だろうと、思うけれど、そんな配慮はまったくない。
人混みを避けるために、わざわざ遠回りして時間をずらして登校したのに、校舎の前に着いてみれば、掲示板の前にはまだたくさんの生徒が群がっていた。
もっと道草を食いながら来るべきだった。
また戻るのも面倒だ。
もうすでに3回目になるため息を静かに吐き出しながら、誰かと待ち合わせをしているような雰囲気を装うことにした。
耳に差し込んだイヤホンから流れる曲を適当に変え、スマホの画面を意味もなくタップして、周囲の視線を避けるための演技に徹する。
掲示板の前では、友達同士で集まっている生徒たちが、誰が同じクラスになったとか、誰と離れてしまったとか、そんな話題で楽しそうに盛り上がっているのだと思う。
その輪を作る友達もおらず、輪の中に入ったこともない僕は、ただ遠くからその様子を眺めるしかなかった。
羨ましいなんて思うのはとっくの昔に諦めた。
クラス替えというちょっとしたイベントだけであんなに騒げる陽キャたちの姿を横目で見ながら、僕はできるだけ目立たないように肩をすぼめて、存在感を消すようにしてその場に立ち尽くしていた。
掲示板の前にいた生徒たちの数が少しずつ減ってきたのを見計らって、僕はそっとイヤホンを外してポケットにしまい、スマホの電源を切る。
校則で、校内でのスマートフォンの使用は固く禁じられていて、見つかればすぐに注意と反省文になるため、僕はその規則をきちんと守るようにしていた。
校舎の中ではイヤホンで音楽を聴きながら時間を潰すという僕にとっての数少ない逃げ道が使えなくなってしまう。
もっと早く知っていれば、この学校を受験することはしなかっただろう。
僕のリサーチ不足のせいなのので残り2年をどう過ごすか考えないと。
去年は居心地の悪さを感じてはいたが、なんとか乗りkることができたのだ。
今年も同じようにすればいいだけだと自分を励ます。
以前、陽キャの生徒の中には、校内でスマホを使っているところを先生に見つかってしまっていた。
その生徒が反省文を書いている最中にもかかわらず、周囲の友達から「もっと上手く隠して使えよ、バレるなんてダサいぞ」と冗談交じりに茶化されていて、まるで罰を受けることすらも一種のイベントのように楽しんでいるようだった。
少しだけ羨ましいと思う気持ちが胸の奥に芽生えたけれど、僕にはそんな大胆さも器用さもなくて、ただ真面目に規則を守ることしかできなかった。
僕はゆっくりと深呼吸をして、息を整えてから、覚悟を決めるように校門をくぐり抜けた。
掲示板に貼られたクラス分けの紙を前にして、僕──甘楽 澪は、自分の名前を見つけるために一つひとつのクラスを丁寧に確認していったけれど、そこで最初に目に入ったのは、僕の名前ではなく、別の名前だった。
その名前は、昨年同じクラスで、僕のことを何かと気にかけてくれていた唯一の存在──廿楽 陸翔のもので、彼の名前を見つけた瞬間、胸の奥が少しだけざわついた。
振り返ってみれば去年は、先生以外の誰かとまともに会話を交わした記憶があるのは廿楽君だけだった。
彼の存在が僕にとってどれほど貴重だったかを改めて思い知らされる。
「違うんだ……。」
それは誰に向けたわけでもなく、ただ小さく呟いただけの僕の声。
只のひとりごとだったのに、それは、ちょうどそのとき肩に軽く重みをかけてきた誰かの耳にも届いてしまったようだった。
僕は思わずびくりと体をこわばらせた。
「違うって、どういうこと?」
そう肩に手を置いたままの人物が僕の呟きを拾って問いかけてきた。
その声は、聞き慣れた優しい響きだった。
横を見ると、そこに立っていたのは、やはり廿楽君本人だった。
「あ……廿楽くん、おはよう。」
驚きと少しの緊張を混ぜながら言葉を返した。
僕は、掲示板に貼られた2組の名簿に彼の名前を見つけたことを伝える。
「おー、俺もさっき見たよ!俺、文系だから1組から3組のどこかになるって思ってたんだけど、やっぱり気になってさ。澪は理系だったよな?ってことは、4組か5組のどっちかか。離れちゃうの、ちょっと寂しいな〜」
廿楽君は気さくに話しかけてくれて、去年と変わらない屈託のない笑顔を浮かべている。
僕は、理系のクラスである4組か5組にいるはずらしい。
知らずに1組から順番に確認していたことが急に恥ずかしくなってしまい、3組を飛ばして慌てて4組の名簿に目を走らせた。
4組の名簿には僕の名前が見当たらなかったから、理系の最後のクラスである5組にいることはほぼ確定だろう。
それでも念のために、掲示板に貼られた5組を順番に目で追っていくと、ようやく自分の名前を見つけることができた。
これで自分の名前が無かったら悲しいのもあるが、名前がなかったことを先生に伝えたときの先生のヤバいという引きつった顔。
中学のころの経験を思い出しただけで気が滅入る。
「5組なら体育の授業は一緒になるかもしれないな!先輩たちの話だと、文系と理系で分かれてても週に2回は体育の合同授業があるらしいから、またよろしくな!」
そんな僕のことはお構いなしに、廿楽君は明るく言ってくれる。
そんな彼とクラスが分かれてしまったことに寂しさを感じる。
理性と文系の混合クラスがあったら良かったのに。
彼はきっと新しいクラスにもすぐに打ち解け、友達ができて、楽しく過ごせるはず。それなのに、もうクラスメイトですらなくなった僕のことまで気にかけてくれるなんて嬉しかった。
僕はただ小さく頷くだけで、廿楽君の言葉に応えるのが精一杯だった。
ちょうどいいタイミングで廿楽君は友達に声をかけられ、僕はそれをきっかけに自然な流れでその場を離れる。
僕は無言のまま靴を履き替え、誰にも気づかれないようにそっと階段を上って、2階の一番奥にある自分の新しいクラスを目指して、足早に歩き始めた。
1組から順に並ぶ教室の前を通り過ぎて、廊下の一番奥にある5組まで歩いていかなければならない。
鞄の持ち手をぎゅっと握り締めて、競歩のような速さで廊下にいる同級生たちの間をすり抜けながら、教室へと向かった。
教室の扉をそっと開けて中に入ると、そこには去年のクラスで見かけたことのある顔が何人かいた。
少しだけ安心する気持ちと、同時に気づかれたくないという複雑な思いが胸の中で交差した。
彼らが僕のことを覚えているかどうかなんて、確かめる方法もない。
話しかけたところでウザがられたり、気持ち悪がられたりするのが落ちである。
そもそも僕の存在が彼らの記憶に残っている可能性は低いだろうと結論付けた。
教室の前方に貼り出された名簿で自分の名前を探し、ようやく見つけた席は、廊下側の一番後ろ。
教室の後方にあるドアから出入りするにはちょうどよく、僕のように目立ちたくない人間にはぴったりの場所だった。
鞄をそっと机の横に掛けて、机の上に腕を伸ばして突っ伏した。
教室内の笑い声や話し声といった騒がしさが逆に僕の存在をかき消してくれる。
僕は机に伏せたまま、担任の先生が教室に来るまでの時間をやり過ごした。
「澪ってさ、静かだけど話すと意外と面白いよな」
そんな何気ない廿楽君の言葉が、ふと頭の中に蘇ってきた。
その記憶を振り払うように、僕はそっと首を横に振った。
あの一言が、どれほど僕の心を温めてくれたか、彼はきっと知らない。
自然と頭の中に浮かんでくるのは、廿楽君と過ごした時間ばかり。
他に思い出せる人がおらず、彼の笑顔や声、ちょっとした仕草が、まるで染みついたように僕の記憶の中で鮮明に思い出せる。
僕にとっては宝物のような思い出たち。
だけど、彼にとってはきっと、何気ない日常のひとコマでしかないだろう。
特別な意味なんて持っていないのかもしれないと思うと、胸の奥がじわりと痛んだ。
そんな去年の廿楽君に思いをはせていた僕の耳に、担任の先生の声が届いた。
その内容は、いきなりの自己紹介。
教壇の前に立って、ひとりずつ話すという形式に、僕の心臓はどくんと大きく跳ねた。
全員の視線を浴びながら自己紹介をしなければならないことは、僕にとってはまさに地獄そのもので、逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。
出席番号順に呼ばれていく中で、心の準備をする間もなく、僕の番はすぐにやってきてしまった。
僕の名前が呼ばれた瞬間、頭の中が真っ白になった。
足が重たく感じながらもなんとか教壇の前まで歩いてく。
教室のどこを見ればいいのか分からず、視線が宙をさまよった末に、結局僕は床に目を落とし、誰とも目を合わせないようにした。
手のひらにはじっとりと汗がにじんでいて、震える声で「あー、えっと……甘楽 澪です。1年間よろしくお願いします」とだけ絞り出すのが精一杯だった。
緊張で口の中が乾ききっていて、絞り出すように発した自己紹介が、果たしてクラスメイトたちにちゃんと届いていたのかは分からない。
でも、教室のあちこちから小さな拍手が聞こえてきて、僕は、まるで逃げるように足早に自分の席へ戻り、深く息を吐き出した。
僕の番が終わったあとも、クラスメイトたちは順番に教壇の前へと立ち、それぞれの言葉で自己紹介をしていった。
誰もが、趣味や部活、好きなことを堂々と話していて、僕のように最低限の言葉だけで済ませた人はひとりもいなかった。
この先、彼らと話すことなんてきっとないだろうと思う。
でも、もしかしたら僕に話しかけてくれる人がいるかもしれないという淡い期待のもと、クラスメイトたちの名前と顔を一致させるために僕は真剣に耳を傾けた。
この自己紹介の場以外で、彼らの名前を知る機会なんてないだろうから。