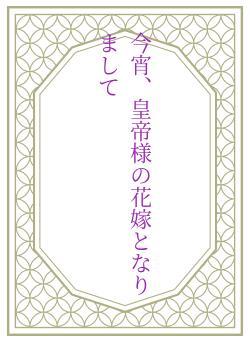疲れた、、、
私の中はそんな平凡な言葉でいっぱいになった。
来る日も来る日も残業、残業、パワハラ、セクハラ、また残業、、、
私の人生はこんなものなのかという諦めが心の中を渦巻く。
まだ新入社員で社会に憧れていた自分が懐かしい。
「はぁ、なんでこんな事になったんだろう、、、いっそのこと、いっぱい遊んで、遊びまくりたい。」
私が思わずそんな言葉が口からこぼれ空気に溶けていった。
電車が来るまであと何時間あるんだろう。
セクハラ上司のせいで終電を逃してしまった。
きっかけはわからない、しかし私が他の人とは違う扱いをされているということは誰が見ても明白だった。
もう、全てがどうでもいい、そんな言葉で思考が埋め尽くされた。
「もしも〜し。」
私は、空耳かと思った。
なぜなら、私以外いない電車のホームから声がした気がしたからだ。
「もしも〜し、聞いてますか?」
バッと振り返ってみると、そこには誰もいなかった。
「なんだ、いたずらか、、、」
そう私が安心して前を向くと、目の前にふよふよと浮いた"なにか"がいた。
私は思わず叫んでしまおうとした。
しかし、体は言うことを聞かず、口をハクハクと開閉するしかなかった。
そんな私に見かねたのか、"なにか"は私にそっと近づき話しかけてきた。
「お姉さん、大丈夫?」
私は思わず、その問いかけに答えてしまった。
「えぇ、大丈夫、、、」
そんな私の反応をみて満足したのか、"なにか"は自己紹介をしてきた。
「ではでは、気を取り直して、こんばんわ。お姉さん。いい夜だね。」
「こ、こんばんわ。」
「ボクに名前はないから、気軽に好きな名前で呼んでね!」
「わかりました、、、」
私は、緊張がほぐれてきて"なにか"を観察する余裕がでてきた。
そして、よく見てみるとあることに気がついた。
それはこの子が、男の子だということだ。
短い黒髪に、黒耀の瞳、身長は私よりも少し小さいくらいの風貌をしていた。
その姿に私はなんとなく見覚えがあった気がした。
しかし、気のせいかと思った。
なぜなら、私によくわからない"なにか"の知り合いはいなかったからだ。
「お姉さん、おねーさん、聞いてる?」
「あっあぁ、聞いてるよ!」
どうしよう、、、
思わずうなずいてしまった。
考え事いていて、全然話し聞けてなかったのに。
私が心の中で焦っていると、”なにか”は私のことを知るよしもなく、いきなり手を引っ張ってきた。
私はその奇行に、思わずビックリしてしまった。
グイッ!
「な、なに!?」
「なにって、、、お姉さんが言ったんだよ?」
私が、言った?
いったいなにを、言ったのだろう。
私が困惑していると、焦れったく思ったのかその”なにか”は言ってきた。
「だ〜から!お姉さんが、『いっそのこと、いっぱい遊んで、遊びまくりたい。』って言ったんだよ?」
「あっ、、、」
私は、その時驚きに満ちた顔になっていたと思う。
なぜなら、この”なにか”が私のひとり言を最初から聞いていたことの気がついてしまったからだ。
私が、言ったことに思いあったことに気がついたのか、”なにか”は満足気に頷いて、言ってきた。
「それじゃ、行くよ!!」
私達は駅のホームから暗闇に溶けていった。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
私達は走っていた。
どこに行くわけでもなく、ただ、なんとなく。
しかし、私はこの状況を楽しんでいた。
こんなに爽快なことは久しぶりだった。
だから、私は聞いてみた。
「ねぇ、ハァッハァッ、どこに、向かってるの、、、?」
私が問いかけると、彼は言ってきた。
「ん〜、ただ気の向くままどこでもない何処かに向かってるんだよ。」
「ハハッ、なにそれ。」
私はその言葉に少し面白おかしくなってしまった。
なぜなら、私の人生でこんなにもよくわからないことは生まれて初めてだったからだ。
そうして、幾分かたったころ、彼は止まって提案をしてきた。
「ねぇ、お姉さん。ボクと、”いけないこと”しない?」
「い、”いけないこと”、、、?」
私が身構えていると、彼は私の手を引きあるところに連れて行った。
*
そうして、連れてこられた場所は、、、、
「う〜ん、美味しい!!」
なんとラーメン屋さんだった。
たしかに、深夜にこんな高カロリーなもの食べるのは、”いけないこと”だわ。
私が納得していると、彼はさらにご飯まで注文していた。
「おじさん、ご飯大盛りで!」
私は疑問に思ったことがあったので聞いてみた。
「ねぇ、君は幽霊なんじゃないの?」
多分、きっとそうなのだろうと彼と過ごしていく中で気がついた。
なぜなら、電車のホームでふよふよと浮いていたし、なにより手を引っ張ってきたときにとっても冷たかった。
しかし、私の考えとは別に彼は、濁した答えを言ってきた。
「ん〜、なんて言えば良いのかな、多分?幽霊なのかな。」
「多分?」
彼は幽霊なのにバクバクと食欲旺盛に、山盛りご飯を食べながらいってきた。
「そう、多分。だって、気がついたときにはお姉さんの前にいたし。」
「そう、なんだ。」
私は、彼が幽霊だと認めたことで、なんとなく心がぽっかり空いた気持ちになった。
「まぁ、そんなことは良いんだけどね!それよりも、次はなにしたい?」
彼は、私の心の穴を払拭するかのように聞いてきた。
私は考えて、考えた。
そうして、あることをしたいことに気がついた。
「私、いっぱい、いっぱい遊びたい。」
思わずこんな、答えでもないような答えがポロッと口からこぼれた。
しかし、そんな答えにも彼はいいねと言ってくれた。
「いいね!じゃあ、そうだな〜。、、、、
公園に行こう!!」
*
「わぁ〜公園とかいつ以来だろう。」
私は思わずそんな言葉が口から出てきた。
しかし、そんな私よりも、はしゃいでいたのが彼だった。
「やばい!ねぇねぇ、シーソー乗ろうよ!!」
私は少し恥ずかしくもあったが、彼の姿を見ていると、そんなちっぽけなプライドはどこかにいってしまいそうになった。
しかし、私の心のストッパーが遊ぶことを躊躇させた。
なぜなら、こんなところを誰かに見られたら、私は恥ずかしくて死んでしまいそうになってしまうからだ。
彼はそんな私の姿を見て、一瞬なにかを考えるような素振りを見せた。
そして、いたく嫌なほどの沈黙が公園に漂った。
「ねぇ、お姉さん。」
そんな沈黙を破ったのは彼だった。
私はその呼びかけに、思わず俯いていた顔をあげてしまった。
顔を上げると、そこには彼の真剣で私の心を見透かすような顔があった。
そして、目があうと彼はゆっくり口を開けて言った。
「お姉さんはさ。なにをそんなに怖がっているの?」
私はその言葉に、心のうちが本当に伝わっているのではないかと疑ってしまった。
なぜなら、私は確かに恐れているからだ。
しかし、そのことを彼に知られるのは嫌だった。
「そんな、怖がってなんか、、、君の、気の所為、じゃない?」
私が言葉を濁し、この話題から話をそらそうとすると、彼は待ったをかけるようにさらに言葉を積み重ねた。
「ううん。気の所為なんかじゃないよ。」
「君に私のなにがわかるの。会ってから1日もたってないのに、、、」
私は思わずそんな、突き放すような言葉を彼に放ってしまった。
彼は一瞬傷ついたような顔をすると、依然として言ってきた。
「確かに、お姉さんと出会ったのは数時間にも満たないよ。」
「だったら!私なん「でも!」」
彼は私の声に被せるように言ってきた。
「でも、それでも、お姉さんがなにかに怖がっていることはわかるよ、、、」
彼はさっきまでの勢いが何処かに言ったように静かに、なにかに語りかけるように話した。
「ねぇ、ボクに言ってよ。ボクは幽霊だから、すぐに消えるから。泡のように消える存在だから。」
泣きそうな声。
私は彼の言葉を聞いてそんなことを思った。
そして、次に襲ってきたのは、彼にそんな顔をさせてしまったという、後悔だった。
こんなにも、私のやりたいことを聞いてくれたのに、私はなんてひどいことをしてしまったのだろう、、、
「ご、ごめんさない。そんな顔をさせるつもりはなかったの、、、」
私は、咄嗟に誤った。
でも、私は気づいていた。
そんなことで、言ってしまったことは消えないのだということを。
だから、私は彼の真摯な声に耳を傾けようと思った。
はぐらかして、誤魔化して、濁して。
そんなことはいつもの私と、何ら変わりがないと思ったからだ。
「ねぇ、聞いてくれる?私の話。」
私がそう言うと、彼は悲しそうな顔から一点、嬉しそうな顔つきになった。
「うん!もちろん。」
*
私が、物心ついた頃、私の両親は不仲だった。
だから、両親が離婚するのには時間はかからなかった。
私は、母に引き取られた。
しかし、母はホストぐるいだった。
貢いで、貢いで、貢いで。
蒸発した。
そして母は、よくわからない全身が真っ黒な人たちに連れ去られてしまった。
私は、親戚の家に預けられた。
親戚は、私を空気のように扱った。
だから、私も親戚のことはただの保護者だと思うようにした。
でもね、良いこともあったの。
それはね、親戚がかっていた犬と友だちになったこと。
でも、たった1年で事故で死んじゃった。
そこからはなんのことはない平凡な日々が続いた。
そして、大学に行って社会人になった。
しかし、私の入社ンした会社は表向きはホワイト企業をかかげていたが、実際はとてつもなくブラックだった。
残業、セクハラ、パワハラは当たり前。
上はなにもしない。
そんな不条理がはびこっていた。
だから、私は心を殺して、自分の意見を言わないようになった。
そうすれば、傷つかなくてすむから、生きていけるから。
*
「——これが私の話し。だから、私はねヒトの皮を被ったモノが恐いの。そして、また大切なものを失うかもしれないことがとても怖い。」
そうして私は、彼に私の過去を話した。
彼はこんな話を聞いてどう思っただろうか、失望したかな?
でも、こんな話今まで誰にも話したことがなかったから、スッキリした。
そんなことを思いながら、彼の方に目を向けると彼は、なんと泣いてくれていた。
私は、その姿に驚いてしまった。
「ど、どうしたの?ごめん、話が不快だったかな。」
私がそう言うと、彼はブンブンと頭を振った。
「そんなことない!ただ、なんかなんか泣けてきただけ。」
「そっか、それなら良かった?のかな。」
そして、彼が落ち着くと、彼は改めて話しだした。
「ねぇ、お姉さん。話してくれてありがとうね。」
私はその言葉に少し驚愕してしまった。
だって、こんな話普通は引く人のほうが多いと思ったからだ。
そして、彼は私に言ってきた。
「お姉さんさ、少しは周りを頼ってみたら?」
「頼るって、誰に?そんな相手私にはいないよ。」
私がそう返すと彼は、首を横に振った。
「そんなことはないよ、きっといるよ。周りに助けてくれる人。」
「、、、、ねぇ、それって、あなたじゃだめなの?」
思わずそんな言葉が出てしまった。
なぜだかはわからない。
でも、そうしないと彼がどこか手の届かないところまでいってしまいそうだと感じたからだ。
しかし、そんな私の心を知る由もなく彼は否といった。
「だめだよ。ボクはいなくなっちゃうからね。だから、強く生きてね、澪。」
なんで、私の名前、、、
しかし彼はそんな言葉を残すと、彼は空気に溶けていくように体がボロボロと崩れていった。
私は焦った。
そして、叫んだ。
「待って!まだききたいことが、、、!」
私が泣きそうになっていると、彼は最後に言った。
「大丈夫、大丈夫。澪は強い子だよ。」
「強くなんてないよ!」
「それは、どうかな?あっ、そうだ。ボクと仲良くしてくれてありが、とう。」
「あっ、、、、」
そうして、彼は溶けていった。
私は実感もわかないまま、駅のホームに着いていた。
私が放心していると、どうやら始発の電車が来るような時間になっていたようだ。
朝日が、眩しい、、、
彼はなんていうかな。
ただ単純に、きれいだね!っていうのかな。
あぁ、聞きたいこときけなかったな。
そんな懺悔をしていると、私の頭の中に強く響いた。
”強く生きて!”
強く、、、いきる。
そうだ、私は強く生きないと。
彼が最後に願ったことだから。
私はそんな思いとともに、一歩踏み出した。
私の中はそんな平凡な言葉でいっぱいになった。
来る日も来る日も残業、残業、パワハラ、セクハラ、また残業、、、
私の人生はこんなものなのかという諦めが心の中を渦巻く。
まだ新入社員で社会に憧れていた自分が懐かしい。
「はぁ、なんでこんな事になったんだろう、、、いっそのこと、いっぱい遊んで、遊びまくりたい。」
私が思わずそんな言葉が口からこぼれ空気に溶けていった。
電車が来るまであと何時間あるんだろう。
セクハラ上司のせいで終電を逃してしまった。
きっかけはわからない、しかし私が他の人とは違う扱いをされているということは誰が見ても明白だった。
もう、全てがどうでもいい、そんな言葉で思考が埋め尽くされた。
「もしも〜し。」
私は、空耳かと思った。
なぜなら、私以外いない電車のホームから声がした気がしたからだ。
「もしも〜し、聞いてますか?」
バッと振り返ってみると、そこには誰もいなかった。
「なんだ、いたずらか、、、」
そう私が安心して前を向くと、目の前にふよふよと浮いた"なにか"がいた。
私は思わず叫んでしまおうとした。
しかし、体は言うことを聞かず、口をハクハクと開閉するしかなかった。
そんな私に見かねたのか、"なにか"は私にそっと近づき話しかけてきた。
「お姉さん、大丈夫?」
私は思わず、その問いかけに答えてしまった。
「えぇ、大丈夫、、、」
そんな私の反応をみて満足したのか、"なにか"は自己紹介をしてきた。
「ではでは、気を取り直して、こんばんわ。お姉さん。いい夜だね。」
「こ、こんばんわ。」
「ボクに名前はないから、気軽に好きな名前で呼んでね!」
「わかりました、、、」
私は、緊張がほぐれてきて"なにか"を観察する余裕がでてきた。
そして、よく見てみるとあることに気がついた。
それはこの子が、男の子だということだ。
短い黒髪に、黒耀の瞳、身長は私よりも少し小さいくらいの風貌をしていた。
その姿に私はなんとなく見覚えがあった気がした。
しかし、気のせいかと思った。
なぜなら、私によくわからない"なにか"の知り合いはいなかったからだ。
「お姉さん、おねーさん、聞いてる?」
「あっあぁ、聞いてるよ!」
どうしよう、、、
思わずうなずいてしまった。
考え事いていて、全然話し聞けてなかったのに。
私が心の中で焦っていると、”なにか”は私のことを知るよしもなく、いきなり手を引っ張ってきた。
私はその奇行に、思わずビックリしてしまった。
グイッ!
「な、なに!?」
「なにって、、、お姉さんが言ったんだよ?」
私が、言った?
いったいなにを、言ったのだろう。
私が困惑していると、焦れったく思ったのかその”なにか”は言ってきた。
「だ〜から!お姉さんが、『いっそのこと、いっぱい遊んで、遊びまくりたい。』って言ったんだよ?」
「あっ、、、」
私は、その時驚きに満ちた顔になっていたと思う。
なぜなら、この”なにか”が私のひとり言を最初から聞いていたことの気がついてしまったからだ。
私が、言ったことに思いあったことに気がついたのか、”なにか”は満足気に頷いて、言ってきた。
「それじゃ、行くよ!!」
私達は駅のホームから暗闇に溶けていった。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
私達は走っていた。
どこに行くわけでもなく、ただ、なんとなく。
しかし、私はこの状況を楽しんでいた。
こんなに爽快なことは久しぶりだった。
だから、私は聞いてみた。
「ねぇ、ハァッハァッ、どこに、向かってるの、、、?」
私が問いかけると、彼は言ってきた。
「ん〜、ただ気の向くままどこでもない何処かに向かってるんだよ。」
「ハハッ、なにそれ。」
私はその言葉に少し面白おかしくなってしまった。
なぜなら、私の人生でこんなにもよくわからないことは生まれて初めてだったからだ。
そうして、幾分かたったころ、彼は止まって提案をしてきた。
「ねぇ、お姉さん。ボクと、”いけないこと”しない?」
「い、”いけないこと”、、、?」
私が身構えていると、彼は私の手を引きあるところに連れて行った。
*
そうして、連れてこられた場所は、、、、
「う〜ん、美味しい!!」
なんとラーメン屋さんだった。
たしかに、深夜にこんな高カロリーなもの食べるのは、”いけないこと”だわ。
私が納得していると、彼はさらにご飯まで注文していた。
「おじさん、ご飯大盛りで!」
私は疑問に思ったことがあったので聞いてみた。
「ねぇ、君は幽霊なんじゃないの?」
多分、きっとそうなのだろうと彼と過ごしていく中で気がついた。
なぜなら、電車のホームでふよふよと浮いていたし、なにより手を引っ張ってきたときにとっても冷たかった。
しかし、私の考えとは別に彼は、濁した答えを言ってきた。
「ん〜、なんて言えば良いのかな、多分?幽霊なのかな。」
「多分?」
彼は幽霊なのにバクバクと食欲旺盛に、山盛りご飯を食べながらいってきた。
「そう、多分。だって、気がついたときにはお姉さんの前にいたし。」
「そう、なんだ。」
私は、彼が幽霊だと認めたことで、なんとなく心がぽっかり空いた気持ちになった。
「まぁ、そんなことは良いんだけどね!それよりも、次はなにしたい?」
彼は、私の心の穴を払拭するかのように聞いてきた。
私は考えて、考えた。
そうして、あることをしたいことに気がついた。
「私、いっぱい、いっぱい遊びたい。」
思わずこんな、答えでもないような答えがポロッと口からこぼれた。
しかし、そんな答えにも彼はいいねと言ってくれた。
「いいね!じゃあ、そうだな〜。、、、、
公園に行こう!!」
*
「わぁ〜公園とかいつ以来だろう。」
私は思わずそんな言葉が口から出てきた。
しかし、そんな私よりも、はしゃいでいたのが彼だった。
「やばい!ねぇねぇ、シーソー乗ろうよ!!」
私は少し恥ずかしくもあったが、彼の姿を見ていると、そんなちっぽけなプライドはどこかにいってしまいそうになった。
しかし、私の心のストッパーが遊ぶことを躊躇させた。
なぜなら、こんなところを誰かに見られたら、私は恥ずかしくて死んでしまいそうになってしまうからだ。
彼はそんな私の姿を見て、一瞬なにかを考えるような素振りを見せた。
そして、いたく嫌なほどの沈黙が公園に漂った。
「ねぇ、お姉さん。」
そんな沈黙を破ったのは彼だった。
私はその呼びかけに、思わず俯いていた顔をあげてしまった。
顔を上げると、そこには彼の真剣で私の心を見透かすような顔があった。
そして、目があうと彼はゆっくり口を開けて言った。
「お姉さんはさ。なにをそんなに怖がっているの?」
私はその言葉に、心のうちが本当に伝わっているのではないかと疑ってしまった。
なぜなら、私は確かに恐れているからだ。
しかし、そのことを彼に知られるのは嫌だった。
「そんな、怖がってなんか、、、君の、気の所為、じゃない?」
私が言葉を濁し、この話題から話をそらそうとすると、彼は待ったをかけるようにさらに言葉を積み重ねた。
「ううん。気の所為なんかじゃないよ。」
「君に私のなにがわかるの。会ってから1日もたってないのに、、、」
私は思わずそんな、突き放すような言葉を彼に放ってしまった。
彼は一瞬傷ついたような顔をすると、依然として言ってきた。
「確かに、お姉さんと出会ったのは数時間にも満たないよ。」
「だったら!私なん「でも!」」
彼は私の声に被せるように言ってきた。
「でも、それでも、お姉さんがなにかに怖がっていることはわかるよ、、、」
彼はさっきまでの勢いが何処かに言ったように静かに、なにかに語りかけるように話した。
「ねぇ、ボクに言ってよ。ボクは幽霊だから、すぐに消えるから。泡のように消える存在だから。」
泣きそうな声。
私は彼の言葉を聞いてそんなことを思った。
そして、次に襲ってきたのは、彼にそんな顔をさせてしまったという、後悔だった。
こんなにも、私のやりたいことを聞いてくれたのに、私はなんてひどいことをしてしまったのだろう、、、
「ご、ごめんさない。そんな顔をさせるつもりはなかったの、、、」
私は、咄嗟に誤った。
でも、私は気づいていた。
そんなことで、言ってしまったことは消えないのだということを。
だから、私は彼の真摯な声に耳を傾けようと思った。
はぐらかして、誤魔化して、濁して。
そんなことはいつもの私と、何ら変わりがないと思ったからだ。
「ねぇ、聞いてくれる?私の話。」
私がそう言うと、彼は悲しそうな顔から一点、嬉しそうな顔つきになった。
「うん!もちろん。」
*
私が、物心ついた頃、私の両親は不仲だった。
だから、両親が離婚するのには時間はかからなかった。
私は、母に引き取られた。
しかし、母はホストぐるいだった。
貢いで、貢いで、貢いで。
蒸発した。
そして母は、よくわからない全身が真っ黒な人たちに連れ去られてしまった。
私は、親戚の家に預けられた。
親戚は、私を空気のように扱った。
だから、私も親戚のことはただの保護者だと思うようにした。
でもね、良いこともあったの。
それはね、親戚がかっていた犬と友だちになったこと。
でも、たった1年で事故で死んじゃった。
そこからはなんのことはない平凡な日々が続いた。
そして、大学に行って社会人になった。
しかし、私の入社ンした会社は表向きはホワイト企業をかかげていたが、実際はとてつもなくブラックだった。
残業、セクハラ、パワハラは当たり前。
上はなにもしない。
そんな不条理がはびこっていた。
だから、私は心を殺して、自分の意見を言わないようになった。
そうすれば、傷つかなくてすむから、生きていけるから。
*
「——これが私の話し。だから、私はねヒトの皮を被ったモノが恐いの。そして、また大切なものを失うかもしれないことがとても怖い。」
そうして私は、彼に私の過去を話した。
彼はこんな話を聞いてどう思っただろうか、失望したかな?
でも、こんな話今まで誰にも話したことがなかったから、スッキリした。
そんなことを思いながら、彼の方に目を向けると彼は、なんと泣いてくれていた。
私は、その姿に驚いてしまった。
「ど、どうしたの?ごめん、話が不快だったかな。」
私がそう言うと、彼はブンブンと頭を振った。
「そんなことない!ただ、なんかなんか泣けてきただけ。」
「そっか、それなら良かった?のかな。」
そして、彼が落ち着くと、彼は改めて話しだした。
「ねぇ、お姉さん。話してくれてありがとうね。」
私はその言葉に少し驚愕してしまった。
だって、こんな話普通は引く人のほうが多いと思ったからだ。
そして、彼は私に言ってきた。
「お姉さんさ、少しは周りを頼ってみたら?」
「頼るって、誰に?そんな相手私にはいないよ。」
私がそう返すと彼は、首を横に振った。
「そんなことはないよ、きっといるよ。周りに助けてくれる人。」
「、、、、ねぇ、それって、あなたじゃだめなの?」
思わずそんな言葉が出てしまった。
なぜだかはわからない。
でも、そうしないと彼がどこか手の届かないところまでいってしまいそうだと感じたからだ。
しかし、そんな私の心を知る由もなく彼は否といった。
「だめだよ。ボクはいなくなっちゃうからね。だから、強く生きてね、澪。」
なんで、私の名前、、、
しかし彼はそんな言葉を残すと、彼は空気に溶けていくように体がボロボロと崩れていった。
私は焦った。
そして、叫んだ。
「待って!まだききたいことが、、、!」
私が泣きそうになっていると、彼は最後に言った。
「大丈夫、大丈夫。澪は強い子だよ。」
「強くなんてないよ!」
「それは、どうかな?あっ、そうだ。ボクと仲良くしてくれてありが、とう。」
「あっ、、、、」
そうして、彼は溶けていった。
私は実感もわかないまま、駅のホームに着いていた。
私が放心していると、どうやら始発の電車が来るような時間になっていたようだ。
朝日が、眩しい、、、
彼はなんていうかな。
ただ単純に、きれいだね!っていうのかな。
あぁ、聞きたいこときけなかったな。
そんな懺悔をしていると、私の頭の中に強く響いた。
”強く生きて!”
強く、、、いきる。
そうだ、私は強く生きないと。
彼が最後に願ったことだから。
私はそんな思いとともに、一歩踏み出した。