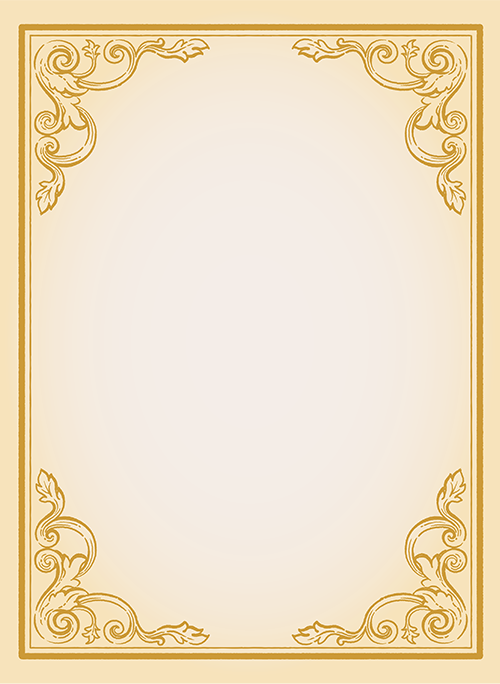6時。
空はすっかり明るくなっていた。
けれど、光が強くなればなるほど、夜の魔法は静かに解けていく気がした。
私たちは、駅へと向かって歩いた。
肩が少し触れ合う距離。だけど、言葉はほとんどなかった。
たった一晩の出来事なのに、何かが始まって、でも何かが終わるような、そんな不思議な沈黙だった。
改札の前で、俊さんが立ち止まった。
「俺、反対方向だから。……じゃーね、真央ちゃん」
そう言って、いつものようににいっと笑う。
その笑顔が、どうしようもなくまぶしくて、少しだけ苦しかった。
「……はい。また」
ぎこちなく手を振ったその瞬間、心のどこかがふっと浮いた気がした。
電車が走り出しても、俊さんはホームに立ったまま、ずっと手を振っていた。
朝日が彼の横顔を照らし、耳元の銀色のピアスが、きらりと光る。
その輝きだけが、いつまでもまぶたに焼きついて離れなかった。
*
座席に身を預けてから、ようやくスマホを取り出す。
画面は、真っ黒。
0%のまま、うんともすんとも言わなかった。
でも、不思議と息がしやすかった。
何十件も来ているはずの着信も、叱責の言葉も、届かないこの静けさが、私にはちょうどよかった。
……そういえば。
俊さんと、連絡先を交換するの、忘れてた。
あれだけ長い時間を一緒にいたのに。
あれだけ、心を開きかけていたのに。
次、会える保証なんて、どこにもない。
だけど私は、電車の揺れに身をまかせながら、
どうしようもなく胸をときめかせていた。
*
家に着いた途端、母にこっぴどく叱られた。
父には、呆れたようにため息をつかれた。
「どういうつもりなの」「大学生になったからって大人になったつもり?」
そんな言葉が、頭の中でいつまでも反響していた。
だけど、私はただ静かにうなずいた。
反抗する気力も、正当化する言い訳もなかった。
でも、心のどこかで、こうも思っていた。
──これが、私の人生で、はじめての反抗だったのかもしれない。
ネオンがちかちかと瞬く夜の街も、
しんと静まり返った深夜のホームも、
カラオケの密室でふたり叫んだロックバンドも、
真っ赤に染まった朝焼けも。
そして。
少し寂しそうに笑った、金髪の彼も──
ぜんぶ、ぜんぶ、私の「はじめて」だった。
部屋のベッドに倒れ込んで、ぽろぽろと涙がこぼれた。
でも、それは悲しみからじゃない。
きっと……うれしかったから。
*
──それから、すぐのことだった。
インカレサークル『Miracles☆』は、解散したと風の噂で聞いた。
たったひと晩だけ関わった、あの場所。
俊さんの笑い声も、誰かの歌声も、もう戻らない。
朝日を背にして「これからも一緒に楽しもうよ」って笑った彼は、もしかして、ほんとうはもう、何かを決めていたのだろうか。
その笑顔が、思い出のなかでふいに遠くなる。
すうっと、背中が冷えていくような気がした。
……自分でも驚いた。
思っていた以上に、私は彼との未来に、期待してたんだ。
でも、終電を逃したあの日が、
ほんとうに「すれ違っただけの一夜」だったのだとしたら。
もう二度と、彼と交わることはないのかもしれない。
それでも。
それでも私は、電車のホームに立つたび、
あの朝みたいな空気を感じるたびに、
つい探してしまうのだ。
銀色のピアス。
金色の髪。
私に手を差し伸べてくれた、誰かの姿を。
──あえて、0%のスマホを手にしたまま。
空はすっかり明るくなっていた。
けれど、光が強くなればなるほど、夜の魔法は静かに解けていく気がした。
私たちは、駅へと向かって歩いた。
肩が少し触れ合う距離。だけど、言葉はほとんどなかった。
たった一晩の出来事なのに、何かが始まって、でも何かが終わるような、そんな不思議な沈黙だった。
改札の前で、俊さんが立ち止まった。
「俺、反対方向だから。……じゃーね、真央ちゃん」
そう言って、いつものようににいっと笑う。
その笑顔が、どうしようもなくまぶしくて、少しだけ苦しかった。
「……はい。また」
ぎこちなく手を振ったその瞬間、心のどこかがふっと浮いた気がした。
電車が走り出しても、俊さんはホームに立ったまま、ずっと手を振っていた。
朝日が彼の横顔を照らし、耳元の銀色のピアスが、きらりと光る。
その輝きだけが、いつまでもまぶたに焼きついて離れなかった。
*
座席に身を預けてから、ようやくスマホを取り出す。
画面は、真っ黒。
0%のまま、うんともすんとも言わなかった。
でも、不思議と息がしやすかった。
何十件も来ているはずの着信も、叱責の言葉も、届かないこの静けさが、私にはちょうどよかった。
……そういえば。
俊さんと、連絡先を交換するの、忘れてた。
あれだけ長い時間を一緒にいたのに。
あれだけ、心を開きかけていたのに。
次、会える保証なんて、どこにもない。
だけど私は、電車の揺れに身をまかせながら、
どうしようもなく胸をときめかせていた。
*
家に着いた途端、母にこっぴどく叱られた。
父には、呆れたようにため息をつかれた。
「どういうつもりなの」「大学生になったからって大人になったつもり?」
そんな言葉が、頭の中でいつまでも反響していた。
だけど、私はただ静かにうなずいた。
反抗する気力も、正当化する言い訳もなかった。
でも、心のどこかで、こうも思っていた。
──これが、私の人生で、はじめての反抗だったのかもしれない。
ネオンがちかちかと瞬く夜の街も、
しんと静まり返った深夜のホームも、
カラオケの密室でふたり叫んだロックバンドも、
真っ赤に染まった朝焼けも。
そして。
少し寂しそうに笑った、金髪の彼も──
ぜんぶ、ぜんぶ、私の「はじめて」だった。
部屋のベッドに倒れ込んで、ぽろぽろと涙がこぼれた。
でも、それは悲しみからじゃない。
きっと……うれしかったから。
*
──それから、すぐのことだった。
インカレサークル『Miracles☆』は、解散したと風の噂で聞いた。
たったひと晩だけ関わった、あの場所。
俊さんの笑い声も、誰かの歌声も、もう戻らない。
朝日を背にして「これからも一緒に楽しもうよ」って笑った彼は、もしかして、ほんとうはもう、何かを決めていたのだろうか。
その笑顔が、思い出のなかでふいに遠くなる。
すうっと、背中が冷えていくような気がした。
……自分でも驚いた。
思っていた以上に、私は彼との未来に、期待してたんだ。
でも、終電を逃したあの日が、
ほんとうに「すれ違っただけの一夜」だったのだとしたら。
もう二度と、彼と交わることはないのかもしれない。
それでも。
それでも私は、電車のホームに立つたび、
あの朝みたいな空気を感じるたびに、
つい探してしまうのだ。
銀色のピアス。
金色の髪。
私に手を差し伸べてくれた、誰かの姿を。
──あえて、0%のスマホを手にしたまま。