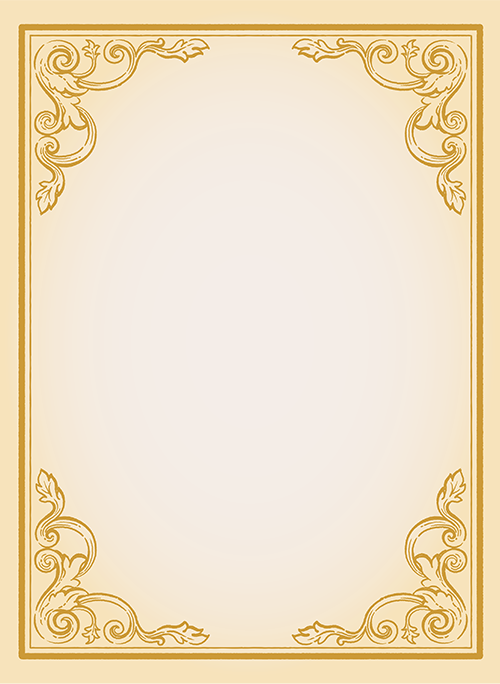「これから、どうする? ネカフェかカラオケなら深夜もやってるけど」
「ネカフェは……行ったことがないので、怖いから……カラオケにします」
思わずそう言ってしまった私に、俊さんはくすっと笑って言った。
「真央ちゃん、もしかして……お嬢様?」
「ち、ちがいますっ」
ぶんぶんと首を振ったけれど、否定すればするほど、なんだか自分が浮いているような気がしてしまう。
でも、笑いながら歩く彼の後ろ姿が、どこか頼もしくて。
私はそっとその背中を追いかけた。
カラオケの受付で「フリータイムでお願いします」と言う彼に、どきりとする。
朝5時まで、フリータイム。
入店時刻は、00時20分。
長時間、ふたりきり……ってこと……?
喉の奥がひゅっとなって、変な汗が出る。
密室。ふたり。長時間。
変なこと、されないよね……? いや、そんな人じゃないと思うけど……!
ドキドキしながら通された部屋は、狭くて薄暗くて、それなのにやけに明るく感じた。
彼がリモコンをいじっているあいだ、私はそっと検索欄に指をのばす。
……入れたのは、back ya loserの『バカやろう』。
さっきまでの自分を、ぶん殴ってやりたいくらい、叫びたかったから。
曲が始まってすぐ、隣で彼が目を丸くした。
「えっ、それ好きなの?」
「え……はい。たまたま聴いて、なんか、元気でるので……」
「真央ちゃん、案外ロックだな」
いたずらっぽく笑った彼が、マイクを片手にこぶしを突き上げる。
「じゃ、一緒に歌おうぜ」
「えっ、えっ、ちょっと……!」
戸惑う間もなく、前奏が始まった。
割れるようなドラムの音。からだの奥まで、振動が伝わっていく。
そして──音楽に合わせて、ふたりの声が重なった。
「バカやろう!!」
叫んだ声が響いた瞬間、なんだか心がふわっと軽くなった。
「……真央ちゃん、やるじゃん」
「俊さんこそ」
私たちは視線を合わせて、けらけらと笑った。
音程もリズムもめちゃくちゃだったけど、それでよかった。
私たちは、自由だった。
「じゃ、次は……『アホンダラ』行くか!」
リモコンを操る彼の指先が、やけにスムーズで笑ってしまった。
交互に曲を入れては、ふたりで熱唱して、時々笑って、ハモったりして──
気づけば、私は歌うことよりも、彼の笑顔ばかり見ていた。
……眠いな、と思ったときには、もう意識が遠のいていた。
*
はっと目を覚ましたとき、部屋は薄暗いままだった。
画面には、再生が終わったままのカラオケの待機画面。
時計は、4時30分を指していた。
「……わ、寝ちゃってた……!すみません!」
慌てて体を起こすと、肩にかけられていた上着がふわりと落ちる。
俊さんの、だった。
「よく眠れた?……気持ち良さそうだったよ」
そう言って微笑む彼の顔が、あまりにやさしくて、私はまた顔が熱くなる。
「……すみません……」
「謝らなくていいのに」
そして、ぽつりとつぶやくように言った。
「俺、真央ちゃんが終電逃してくれて、よかったかも」
心臓が、どくんと弾む。
「……え……?」
言葉がうまく出てこない。そんな私に、彼は静かに語り出した。
「俺さ、高校まで男子校だったんだ。校則も厳しくて、門限もガチガチ。でも、大学で上京してきて、ぜんぶ自由になった。最初は戸惑ったけど、……楽しかったよ、世界が広がるのって」
その横顔は、どこか懐かしさを帯びていて、まるで過去の自分に話しかけているようだった。
「真央ちゃんの世界も、これからもっと広がると思う。でも、できればさ、俺にもその世界、ちょっと見せてよ。……俺も、真央ちゃんが知ってる世界、知りたいし」
その言葉があたたかすぎて、胸の奥がじん、とした。
「……はい。私でよければ……!」
そう答える声が、わずかに震えていたのは、たぶん気のせいじゃなかった。
*
5時。
カラオケを出ると、外はまだ真っ暗だった。
けれど駅の案内表示には、「始発運行中」の文字。
「帰れるね」
私が言うと、俊さんは空を見上げて、ふっと言った。
「……どうせなら、さ。日の出も一緒に見ない?」
「え……」
お母さんに怒られる。まっさきに、そう思った。
でも、そのあとすぐに「いいかも」と思った自分がいた。
「……はい。見たいです」
歩道橋へとふたりで登る。
だんだんと明るくなる空の下、言葉はなくても、不思議と寂しくなかった。
5時55分。
水平線の向こう、夜が音もなくほどけていく。
赤く染まりはじめた空が、ゆっくりと世界を照らし出す。
風の匂いも、鳥の声も、車の音も、ぜんぶが少しずつ動き出していて──その光景が、どうしようもなく、胸に染みた。
今まで見たどんな景色より、眩しかった。
たった一晩だけの自由が、こんなにやさしいなんて、知らなかった。
気づいたときには、涙がひとしずく、頬をすべっていた。
私は息を吸い込んで、背筋を伸ばす。
「……いろんなこと、楽しめました。ありがとうございました」
そう言って、ぺこりと頭を下げると──
俊さんが、肩越しに小さく笑った。
「……過去形? これからも一緒に楽しもうよ」
朝日を背にしたその笑顔は、どこまでも透明で、
まるで新しい朝そのものみたいだった。
「ネカフェは……行ったことがないので、怖いから……カラオケにします」
思わずそう言ってしまった私に、俊さんはくすっと笑って言った。
「真央ちゃん、もしかして……お嬢様?」
「ち、ちがいますっ」
ぶんぶんと首を振ったけれど、否定すればするほど、なんだか自分が浮いているような気がしてしまう。
でも、笑いながら歩く彼の後ろ姿が、どこか頼もしくて。
私はそっとその背中を追いかけた。
カラオケの受付で「フリータイムでお願いします」と言う彼に、どきりとする。
朝5時まで、フリータイム。
入店時刻は、00時20分。
長時間、ふたりきり……ってこと……?
喉の奥がひゅっとなって、変な汗が出る。
密室。ふたり。長時間。
変なこと、されないよね……? いや、そんな人じゃないと思うけど……!
ドキドキしながら通された部屋は、狭くて薄暗くて、それなのにやけに明るく感じた。
彼がリモコンをいじっているあいだ、私はそっと検索欄に指をのばす。
……入れたのは、back ya loserの『バカやろう』。
さっきまでの自分を、ぶん殴ってやりたいくらい、叫びたかったから。
曲が始まってすぐ、隣で彼が目を丸くした。
「えっ、それ好きなの?」
「え……はい。たまたま聴いて、なんか、元気でるので……」
「真央ちゃん、案外ロックだな」
いたずらっぽく笑った彼が、マイクを片手にこぶしを突き上げる。
「じゃ、一緒に歌おうぜ」
「えっ、えっ、ちょっと……!」
戸惑う間もなく、前奏が始まった。
割れるようなドラムの音。からだの奥まで、振動が伝わっていく。
そして──音楽に合わせて、ふたりの声が重なった。
「バカやろう!!」
叫んだ声が響いた瞬間、なんだか心がふわっと軽くなった。
「……真央ちゃん、やるじゃん」
「俊さんこそ」
私たちは視線を合わせて、けらけらと笑った。
音程もリズムもめちゃくちゃだったけど、それでよかった。
私たちは、自由だった。
「じゃ、次は……『アホンダラ』行くか!」
リモコンを操る彼の指先が、やけにスムーズで笑ってしまった。
交互に曲を入れては、ふたりで熱唱して、時々笑って、ハモったりして──
気づけば、私は歌うことよりも、彼の笑顔ばかり見ていた。
……眠いな、と思ったときには、もう意識が遠のいていた。
*
はっと目を覚ましたとき、部屋は薄暗いままだった。
画面には、再生が終わったままのカラオケの待機画面。
時計は、4時30分を指していた。
「……わ、寝ちゃってた……!すみません!」
慌てて体を起こすと、肩にかけられていた上着がふわりと落ちる。
俊さんの、だった。
「よく眠れた?……気持ち良さそうだったよ」
そう言って微笑む彼の顔が、あまりにやさしくて、私はまた顔が熱くなる。
「……すみません……」
「謝らなくていいのに」
そして、ぽつりとつぶやくように言った。
「俺、真央ちゃんが終電逃してくれて、よかったかも」
心臓が、どくんと弾む。
「……え……?」
言葉がうまく出てこない。そんな私に、彼は静かに語り出した。
「俺さ、高校まで男子校だったんだ。校則も厳しくて、門限もガチガチ。でも、大学で上京してきて、ぜんぶ自由になった。最初は戸惑ったけど、……楽しかったよ、世界が広がるのって」
その横顔は、どこか懐かしさを帯びていて、まるで過去の自分に話しかけているようだった。
「真央ちゃんの世界も、これからもっと広がると思う。でも、できればさ、俺にもその世界、ちょっと見せてよ。……俺も、真央ちゃんが知ってる世界、知りたいし」
その言葉があたたかすぎて、胸の奥がじん、とした。
「……はい。私でよければ……!」
そう答える声が、わずかに震えていたのは、たぶん気のせいじゃなかった。
*
5時。
カラオケを出ると、外はまだ真っ暗だった。
けれど駅の案内表示には、「始発運行中」の文字。
「帰れるね」
私が言うと、俊さんは空を見上げて、ふっと言った。
「……どうせなら、さ。日の出も一緒に見ない?」
「え……」
お母さんに怒られる。まっさきに、そう思った。
でも、そのあとすぐに「いいかも」と思った自分がいた。
「……はい。見たいです」
歩道橋へとふたりで登る。
だんだんと明るくなる空の下、言葉はなくても、不思議と寂しくなかった。
5時55分。
水平線の向こう、夜が音もなくほどけていく。
赤く染まりはじめた空が、ゆっくりと世界を照らし出す。
風の匂いも、鳥の声も、車の音も、ぜんぶが少しずつ動き出していて──その光景が、どうしようもなく、胸に染みた。
今まで見たどんな景色より、眩しかった。
たった一晩だけの自由が、こんなにやさしいなんて、知らなかった。
気づいたときには、涙がひとしずく、頬をすべっていた。
私は息を吸い込んで、背筋を伸ばす。
「……いろんなこと、楽しめました。ありがとうございました」
そう言って、ぺこりと頭を下げると──
俊さんが、肩越しに小さく笑った。
「……過去形? これからも一緒に楽しもうよ」
朝日を背にしたその笑顔は、どこまでも透明で、
まるで新しい朝そのものみたいだった。