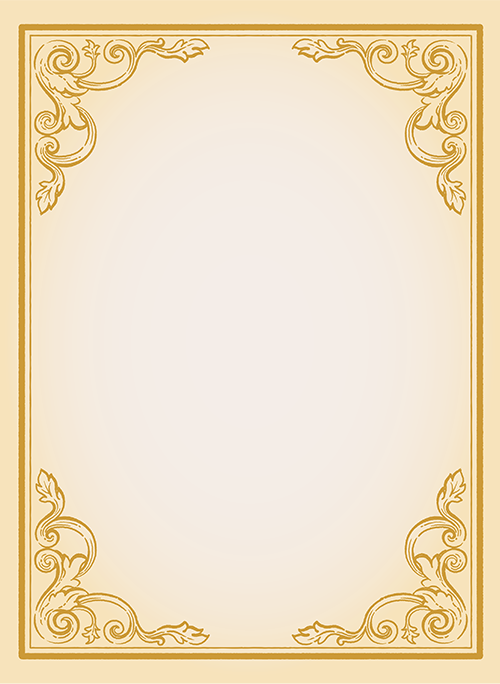居酒屋を出ると、夜のざわめきが押し寄せてきた。
──23時45分。
客引きが通行人に声をかける声。酔っ払いたちがふらふらと歩く足音。
どこか遠くでサイレンが鳴っていて、排気ガスのにおいが鼻をかすめた。
こんな深夜の景色を、私は今まで見たことがなかった。
思わず足を止めて、ぼんやりと立ち尽くしてしまう。
そのとき、彼──俊さんが、ぱっと私の手を放し、にいっと笑った。
「きみ、真央ちゃんだっけ? 自己紹介のとき言ってたよね」
「は、はい!」
まさか名前を覚えられているなんて思わなくて、声が裏返る。
「……えっと、『俊』さん、ですよね?」
「当たり。俺の名前、知ってたんだ?」
「さっき誰かが呼んでたので……」
「そっか。じゃ、覚えておいて」
ネオンに照らされた彼の髪が、金色にきらめく。
その横顔は、さっきまでの明るさとはうらはらに、どこか大人びて見えた。
もっと見ていたい。
そんな気持ちが芽生えたその瞬間、彼が小走りに駆け出す。
「真央ちゃん、走って! 終電、間に合わなくなっちゃうよ?」
「──あ! そうでした!」
「まさか、忘れてた?」
振り返った俊が、にやりと笑う。
その軽やかな背中を追いかけるように、私は息を切らしながら走った。
──そっか。大学に入って体育の授業がなくなってから、ほとんど走ってなかった。
そんなことを後悔しているうちに、街の喧騒は後ろへ遠ざかり、目の前に駅の灯りが見えてきた。
改札を抜け、ホームへ。
俊の背中が、夜の闇をまっすぐ割って進んでいく。まるで、道を照らす騎士みたいだった。
「さ、早く乗りな」
「ありがとうございます!」
そう言った瞬間、無情にも、電車の発車ベルが鳴った。
「こちら、最終電車です」
ガタン、ゴトン。
電車は私たちの目の前をすり抜け、遠ざかっていった。
──23時58分。
生ぬるい春の風が、むわりと吹き抜ける。
「さて、どうしよっか」
俊は両手を頭の後ろで組み、あっけらかんと笑った。
「ど、どうしよう……」
スマホを取り出す。……けれど、画面は黒いまま。電源が入らない。頭が真っ白になった。
「電池、切れた?」
「はい……」
「どっかで充電器借りなきゃな。でもさ、あえて『そのまま』ってのは、どう?」
「そのまま……?」
思わず首をかしげると、彼はふっと、少し寂しげな笑みを浮かべた。
「うん。あえて、0%のまま。真央ちゃん、さっきからずっとスマホ気にしてたじゃん。なんか……縛られてるのかなって」
「縛られてる……」
「ちがった?」
その言葉が、痛いほど図星だった。
母の存在に怯えて、ずっとスマホの画面を気にしていた。
でも、それを認めるのが恥ずかしくて、声が出せなかった。
そんな私をちらりと見ながら、俊が続ける。
「真央ちゃん、自己紹介のとき言ってたよね。『いろんなことを楽しみたいから来ました』って」
「……はい」
「俺、正直ちょっとびっくりしたんだよ。
うちに来る子って、恋人ほしいとか、飲みたいとか、そんなんばっかだからさ。
真央ちゃん、純粋でいいなって思った」
言い終えた彼は、ふっと笑う。
その笑顔が、少しだけ陰って見えて、胸の奥がきゅっとなった。
「実はさ。俺もおんなじ気持ちで、このサークルを立ち上げたんだ。『いろんなことを楽しみたい』って。……ま、最初だけだったけど」
「……そうだったんですね」
鼓動が速くなっているのを感じながら、私は絞り出すように言った。
すると、彼も同じくらいの声で、ぽそりと呟く。
「だから……真央ちゃんは、俺がずっと探してた『メンバー』ってこと」
その言葉に、顔が一気に熱くなる。
俊さんの耳も、ほんのり赤く染まっていた。
深夜の風が、ふたりのあいだをそっと吹き抜けていった。
──23時45分。
客引きが通行人に声をかける声。酔っ払いたちがふらふらと歩く足音。
どこか遠くでサイレンが鳴っていて、排気ガスのにおいが鼻をかすめた。
こんな深夜の景色を、私は今まで見たことがなかった。
思わず足を止めて、ぼんやりと立ち尽くしてしまう。
そのとき、彼──俊さんが、ぱっと私の手を放し、にいっと笑った。
「きみ、真央ちゃんだっけ? 自己紹介のとき言ってたよね」
「は、はい!」
まさか名前を覚えられているなんて思わなくて、声が裏返る。
「……えっと、『俊』さん、ですよね?」
「当たり。俺の名前、知ってたんだ?」
「さっき誰かが呼んでたので……」
「そっか。じゃ、覚えておいて」
ネオンに照らされた彼の髪が、金色にきらめく。
その横顔は、さっきまでの明るさとはうらはらに、どこか大人びて見えた。
もっと見ていたい。
そんな気持ちが芽生えたその瞬間、彼が小走りに駆け出す。
「真央ちゃん、走って! 終電、間に合わなくなっちゃうよ?」
「──あ! そうでした!」
「まさか、忘れてた?」
振り返った俊が、にやりと笑う。
その軽やかな背中を追いかけるように、私は息を切らしながら走った。
──そっか。大学に入って体育の授業がなくなってから、ほとんど走ってなかった。
そんなことを後悔しているうちに、街の喧騒は後ろへ遠ざかり、目の前に駅の灯りが見えてきた。
改札を抜け、ホームへ。
俊の背中が、夜の闇をまっすぐ割って進んでいく。まるで、道を照らす騎士みたいだった。
「さ、早く乗りな」
「ありがとうございます!」
そう言った瞬間、無情にも、電車の発車ベルが鳴った。
「こちら、最終電車です」
ガタン、ゴトン。
電車は私たちの目の前をすり抜け、遠ざかっていった。
──23時58分。
生ぬるい春の風が、むわりと吹き抜ける。
「さて、どうしよっか」
俊は両手を頭の後ろで組み、あっけらかんと笑った。
「ど、どうしよう……」
スマホを取り出す。……けれど、画面は黒いまま。電源が入らない。頭が真っ白になった。
「電池、切れた?」
「はい……」
「どっかで充電器借りなきゃな。でもさ、あえて『そのまま』ってのは、どう?」
「そのまま……?」
思わず首をかしげると、彼はふっと、少し寂しげな笑みを浮かべた。
「うん。あえて、0%のまま。真央ちゃん、さっきからずっとスマホ気にしてたじゃん。なんか……縛られてるのかなって」
「縛られてる……」
「ちがった?」
その言葉が、痛いほど図星だった。
母の存在に怯えて、ずっとスマホの画面を気にしていた。
でも、それを認めるのが恥ずかしくて、声が出せなかった。
そんな私をちらりと見ながら、俊が続ける。
「真央ちゃん、自己紹介のとき言ってたよね。『いろんなことを楽しみたいから来ました』って」
「……はい」
「俺、正直ちょっとびっくりしたんだよ。
うちに来る子って、恋人ほしいとか、飲みたいとか、そんなんばっかだからさ。
真央ちゃん、純粋でいいなって思った」
言い終えた彼は、ふっと笑う。
その笑顔が、少しだけ陰って見えて、胸の奥がきゅっとなった。
「実はさ。俺もおんなじ気持ちで、このサークルを立ち上げたんだ。『いろんなことを楽しみたい』って。……ま、最初だけだったけど」
「……そうだったんですね」
鼓動が速くなっているのを感じながら、私は絞り出すように言った。
すると、彼も同じくらいの声で、ぽそりと呟く。
「だから……真央ちゃんは、俺がずっと探してた『メンバー』ってこと」
その言葉に、顔が一気に熱くなる。
俊さんの耳も、ほんのり赤く染まっていた。
深夜の風が、ふたりのあいだをそっと吹き抜けていった。