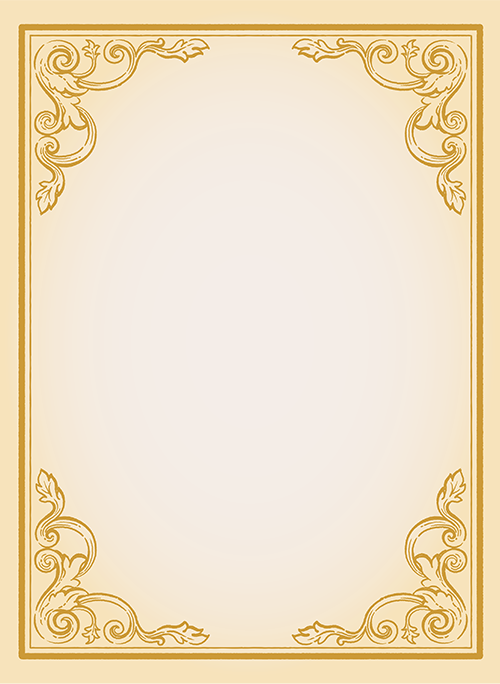──どうしよう、これはもう、絶体絶命。
夜の空気は、生ぬるくて少し苦い。
私は居酒屋の壁にもたれかかりながら、スマホの画面を睨んでいた。
23時30分。
着信履歴は、すでに二十八件を超えている。すべて──母から。
「……ぜったい、怒られる……」
指先が震える。心臓の音ばかりが耳に響いて、手足から体温が抜けていくようだった。
大学に入ってからもずっと守ってきた「22時門限」を、今夜、初めて破ってしまった。
背後では、乾いた笑い声が波のように重なり合っている。
金髪の男子が、どこか演技がかった調子で立ち上がった。
「改めまして~!インカレサークル、Miracles☆にようこそ~~!」
店内の拍手と歓声が、一斉に沸き上がる。
ジョッキを打ち鳴らす音。甲高い笑い声。床に落ちた氷の破片が、ぴちゃりと音を立てた。
みんな、まだ飲み足りなさそうにしてる。
門限とか、親の目とか、そんなものはこの場に存在しないみたいだった。
──どうして、私だけ、取り残されたみたいな気持ちになるんだろう。
体が動かない。早く帰らなきゃいけないのに、焦りだけが、喉の奥に積もっていく。
「もうお開きの時間だよ~!」
「まだまだいけるってば~!」
「やめとけ、バカ~!」
酔った声たちが宙を舞うなか、私はずっとスマホを握りしめていた。
そのとき。
さっきまで場を盛り上げていた金髪の男子が、ひょいと私の前に現れた。
近くで見ると、まぶしさを孕んだような顔立ちだった。
グレーのフーディにだぼだぼのパンツ。耳にはピアスが五つ。だけど、その声は驚くほどやわらかかった。
「ねぇ、大丈夫? 終電、まだ間に合う?」
ふいに胸の奥がぎゅっとなった。
「えっと……たぶん、もう……まずいです」
「じゃあ、行こ。帰ろ」
彼は軽やかにそう言って、出入口を指差した。
笑ったその横顔が、不思議なくらい澄んで見えた。
「……ありがとうございます」
そう言って頭を下げると、彼の表情がすっと真剣になる。
「この時間、女の子がひとりで歩くのは危ないよ。送ってく」
「えっ……そんな、でも──」
「いいから」
その瞬間、背中越しにからかうような声が飛んできた。
「俊、また抜け駆けかよ~!」 「お持ち帰り〜?」
一瞬で顔が熱くなって、心臓がばくんと大きく鳴った。
だけどその「俊」と呼ばれた彼は、振り返らずに言った。
「ちげーし」
そのまま、私の手首を軽く引いて、夜の街へと歩き出した。
夜の空気は、生ぬるくて少し苦い。
私は居酒屋の壁にもたれかかりながら、スマホの画面を睨んでいた。
23時30分。
着信履歴は、すでに二十八件を超えている。すべて──母から。
「……ぜったい、怒られる……」
指先が震える。心臓の音ばかりが耳に響いて、手足から体温が抜けていくようだった。
大学に入ってからもずっと守ってきた「22時門限」を、今夜、初めて破ってしまった。
背後では、乾いた笑い声が波のように重なり合っている。
金髪の男子が、どこか演技がかった調子で立ち上がった。
「改めまして~!インカレサークル、Miracles☆にようこそ~~!」
店内の拍手と歓声が、一斉に沸き上がる。
ジョッキを打ち鳴らす音。甲高い笑い声。床に落ちた氷の破片が、ぴちゃりと音を立てた。
みんな、まだ飲み足りなさそうにしてる。
門限とか、親の目とか、そんなものはこの場に存在しないみたいだった。
──どうして、私だけ、取り残されたみたいな気持ちになるんだろう。
体が動かない。早く帰らなきゃいけないのに、焦りだけが、喉の奥に積もっていく。
「もうお開きの時間だよ~!」
「まだまだいけるってば~!」
「やめとけ、バカ~!」
酔った声たちが宙を舞うなか、私はずっとスマホを握りしめていた。
そのとき。
さっきまで場を盛り上げていた金髪の男子が、ひょいと私の前に現れた。
近くで見ると、まぶしさを孕んだような顔立ちだった。
グレーのフーディにだぼだぼのパンツ。耳にはピアスが五つ。だけど、その声は驚くほどやわらかかった。
「ねぇ、大丈夫? 終電、まだ間に合う?」
ふいに胸の奥がぎゅっとなった。
「えっと……たぶん、もう……まずいです」
「じゃあ、行こ。帰ろ」
彼は軽やかにそう言って、出入口を指差した。
笑ったその横顔が、不思議なくらい澄んで見えた。
「……ありがとうございます」
そう言って頭を下げると、彼の表情がすっと真剣になる。
「この時間、女の子がひとりで歩くのは危ないよ。送ってく」
「えっ……そんな、でも──」
「いいから」
その瞬間、背中越しにからかうような声が飛んできた。
「俊、また抜け駆けかよ~!」 「お持ち帰り〜?」
一瞬で顔が熱くなって、心臓がばくんと大きく鳴った。
だけどその「俊」と呼ばれた彼は、振り返らずに言った。
「ちげーし」
そのまま、私の手首を軽く引いて、夜の街へと歩き出した。