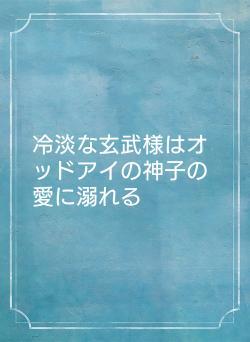✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱
「残念でしたね」
左京と右京は目が虚ろになっている頼久に同情の眼差しを向けてしまった。
「運命の相手だったらこう〜偶然の奇跡みたいな感じで出会えるかもしれないっスよ〜」
「前をみろ、馬鹿者」
右京は運転中に体をうねうねさせる。
「へいへ〜い。……ったく、姉ちゃんはいちいちうるせーなぁ。……ん?…アーーッ!!」
「うるさいぞ」
右京は突然、大声で騒ぐ。左京は呆れるが聞かない。
「よよよ頼久!前の横断歩道にあのお嬢様いるーー!!」
頼久はハッとし椿の姿を見つける。
駅が近いため人が沢山いる中にいた。
青信号になると椿は走って行ってしまった。
「椿!」
「え、頼久様?」
頼久が椿に追いつく。
椿は「どうしてここに?」と聞きたそうだ。
「やっと会えた……」
頼久は汗だくで目が不安そうにしている椿にハンカチで顔を拭く。
「何か困っているなら助けになる。まずはどこか適当なカフェにでも行かないか?」
「はい、ありがとうございます」
頼久の優しさが身に沁《し》みる。
「適当なカフェとは……」
頼久とカフェを訪れたのだが、駅近くとあって大きなホテルのカフェ。
宿泊者以外も利用できるカフェだが、かなり高級そうだった。
「花京院《うち》が経営しているホテルが近くにあって良かった」
「うち?頼久様は一体?」
「そんなことより甘い物は好きか?アフタヌーンティーセットでも頼むか?」
頼久にはぐらかされてしまう。聞いてはいけないことだろうと聞かないことにした。
「甘い物は好物ですが、夕食が食べられませんので今日は飲み物だけいただきます」
「甘い物は好物…今日はか……。わかった」
何か変なことでも言っただろうかと不安になる。
「で、そんなに汗だくになってどうしたんだ?」
「……昨晩、パーティーで落とし物をしたみたいで…家にはなかったのでパーティー会場までの道のりを辿って探していました」
「車で会場まで来たんだろう、道中に落ちてるはずがない」
「あ……」
椿は学校もだが基本的には歩いて移動するので、すっかり忘れていた。
残るはパーティー会場内だが、おそらく処分されているだろうと考え、顔が暗くなる。
「その落とし物はどんな物だ?」
「赤い林檎のキーホルダーです。もう鳴らなくなってしまいましたが小さな鈴が付いていました」
頼久は椿の前にキーホルダーを差し出す。
「えっ!キーホルダー!……どうして……」
「うちの車内に落ちていた。お前のだとは思ったが違っていたらと思ってな」
椿はキーホルダーを受け取ると大事そうに両手でキーホルダーを包む。
「そんなに大事な物か?」
頼久から見ればその辺にでも売ってそうな、500円でお釣りがくるような安物だ。
「これは母が亡くなる前に初めて二人で旅行に行った時に買ってもらったキーホルダーなんです」
椿は安心からか涙を流す。
「母上が……」
「はい。もう手元には母の思い出の物はこれしか残ってなくて……」
母との思い出は今でも大切に残っている。だが、物として残るだけで安心感がある。
椿はキーホルダーの変化に気づく。
「余計なことをしてしまったか?」
「いいえ、いいえ!お気遣いありがとうございます!」
キーホルダーは平べったい赤い林檎に鈴が付いているシンプルな物。
年数が経っていたためキーホルダーの金具部分が錆びていたり、林檎の部分に落ちない汚れがあったのだが頼久の手により新品のように綺麗になっていた。
「本当にありがとうございます。昨晩からお世話になってばかりで…私からも何かお礼をさせてください。私にできることなら何でもします」
「なんでもか……」
頼久は少し考える。
「だったら俺の恋人になってくれないか。ゆくゆくは結婚も考えている」
「恋び……けっ……こん……」
「お前の気持ち優先でいい。嫌なら断ってくれ」
驚きはしたものの、息を整えながら頼久といると暖かく安らぎ、そして優しい人……。
私なんかを?と不安もあったが、頼久と一緒にいたい気持ちが勝った。
「はい、喜んで。」
椿の気持ちは決まった。
晴れて恋人となった二人の空気が暖かく優しい雰囲気なものに変わっていった。
「残念でしたね」
左京と右京は目が虚ろになっている頼久に同情の眼差しを向けてしまった。
「運命の相手だったらこう〜偶然の奇跡みたいな感じで出会えるかもしれないっスよ〜」
「前をみろ、馬鹿者」
右京は運転中に体をうねうねさせる。
「へいへ〜い。……ったく、姉ちゃんはいちいちうるせーなぁ。……ん?…アーーッ!!」
「うるさいぞ」
右京は突然、大声で騒ぐ。左京は呆れるが聞かない。
「よよよ頼久!前の横断歩道にあのお嬢様いるーー!!」
頼久はハッとし椿の姿を見つける。
駅が近いため人が沢山いる中にいた。
青信号になると椿は走って行ってしまった。
「椿!」
「え、頼久様?」
頼久が椿に追いつく。
椿は「どうしてここに?」と聞きたそうだ。
「やっと会えた……」
頼久は汗だくで目が不安そうにしている椿にハンカチで顔を拭く。
「何か困っているなら助けになる。まずはどこか適当なカフェにでも行かないか?」
「はい、ありがとうございます」
頼久の優しさが身に沁《し》みる。
「適当なカフェとは……」
頼久とカフェを訪れたのだが、駅近くとあって大きなホテルのカフェ。
宿泊者以外も利用できるカフェだが、かなり高級そうだった。
「花京院《うち》が経営しているホテルが近くにあって良かった」
「うち?頼久様は一体?」
「そんなことより甘い物は好きか?アフタヌーンティーセットでも頼むか?」
頼久にはぐらかされてしまう。聞いてはいけないことだろうと聞かないことにした。
「甘い物は好物ですが、夕食が食べられませんので今日は飲み物だけいただきます」
「甘い物は好物…今日はか……。わかった」
何か変なことでも言っただろうかと不安になる。
「で、そんなに汗だくになってどうしたんだ?」
「……昨晩、パーティーで落とし物をしたみたいで…家にはなかったのでパーティー会場までの道のりを辿って探していました」
「車で会場まで来たんだろう、道中に落ちてるはずがない」
「あ……」
椿は学校もだが基本的には歩いて移動するので、すっかり忘れていた。
残るはパーティー会場内だが、おそらく処分されているだろうと考え、顔が暗くなる。
「その落とし物はどんな物だ?」
「赤い林檎のキーホルダーです。もう鳴らなくなってしまいましたが小さな鈴が付いていました」
頼久は椿の前にキーホルダーを差し出す。
「えっ!キーホルダー!……どうして……」
「うちの車内に落ちていた。お前のだとは思ったが違っていたらと思ってな」
椿はキーホルダーを受け取ると大事そうに両手でキーホルダーを包む。
「そんなに大事な物か?」
頼久から見ればその辺にでも売ってそうな、500円でお釣りがくるような安物だ。
「これは母が亡くなる前に初めて二人で旅行に行った時に買ってもらったキーホルダーなんです」
椿は安心からか涙を流す。
「母上が……」
「はい。もう手元には母の思い出の物はこれしか残ってなくて……」
母との思い出は今でも大切に残っている。だが、物として残るだけで安心感がある。
椿はキーホルダーの変化に気づく。
「余計なことをしてしまったか?」
「いいえ、いいえ!お気遣いありがとうございます!」
キーホルダーは平べったい赤い林檎に鈴が付いているシンプルな物。
年数が経っていたためキーホルダーの金具部分が錆びていたり、林檎の部分に落ちない汚れがあったのだが頼久の手により新品のように綺麗になっていた。
「本当にありがとうございます。昨晩からお世話になってばかりで…私からも何かお礼をさせてください。私にできることなら何でもします」
「なんでもか……」
頼久は少し考える。
「だったら俺の恋人になってくれないか。ゆくゆくは結婚も考えている」
「恋び……けっ……こん……」
「お前の気持ち優先でいい。嫌なら断ってくれ」
驚きはしたものの、息を整えながら頼久といると暖かく安らぎ、そして優しい人……。
私なんかを?と不安もあったが、頼久と一緒にいたい気持ちが勝った。
「はい、喜んで。」
椿の気持ちは決まった。
晴れて恋人となった二人の空気が暖かく優しい雰囲気なものに変わっていった。