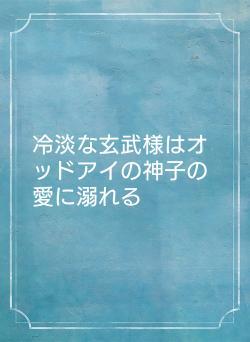妃月は車内で祖父に今日行けないこと、使用人には来客があることを連絡し、ヘアセットとメイクをバッチリキメる。
家は茶道の家元、自分の点てたお茶と美しい着物姿で頼久を魅了させる作戦だ。
汐倉の屋敷に着くと使用人に案内させ、妃月は着替え。
使用人に椿は帰っているかと聞けば、知らないという。
使用人も椿には興味がないのだから仕方ない。
来客が帰るまで屋敷に入れないように伝え、頼久の元へ。
頼久の執事は別室で待ってもらっている。
「お待たせ致しました」
黄色の派手すぎない大人っぽい柄や帯、簪をチョイス。
「椿は?」
「椿は帰って来てないようです」
「そうか」
立ち上がり帰ろうとする頼久。
「ゆっくりお茶でも飲んで待ってはいかがですか?汐倉家は大手の茶道の家元です。ご存じでいらっしゃいますか?」
「知っている。いくつかの流派の一つだったな。椿も茶道を?」
頼久は座りなおす。
「ええ、まだ未熟ですが頑張っております」
「そうか。椿の点てたお茶はさぞ美味いのだろうな」
フッと笑う頼久。
(なによ、さっきから口を開けば椿、椿って…私の前くらい気を使いなさいよ!本当に椿《あいつ》許せない!)
「今日は私で我慢してくださいませ。ところで私の着物はいかがですか?」
「……よく似合っている」
「ありがとうございますぅ〜!」
頼久は社交辞令のつもりだったが妃月は本気にした。
「椿とはどちらで?」
「昨晩のパーティーでな」
「…そ、そうなんですね〜」
椿の話題など虫唾が走るが、共通の話題がない。
「頼久様は苗字をお尋ねしても?花京院家主催のパーティーに参加されていたということは、それなりの家柄でいらっしゃいますよね?」
「……俺は俺だ。何者でもない」
「そうですわね〜失礼しましたわ〜」
一番聞きたかったことをはぐかされてしまう。
「椿に何か大事なご用ですか?私が変わりにお伝え致しますわ」
「いや、必要ない」
「椿はスマホを持っていないのか?」
妃月から質問すれば答えている状態だった頼久が妃月に質問する。
「はい。うちは18歳からと決まりです。友人やゲームなどでうつつを抜かしていては茶道の修行はできませんからね」
実際はそんな決まりはなく、椿には与えていないだけだ。
「そうか。椿と連絡出来ないのは困るな」
顎に手を置き、少し考える頼久。
妃月はチャンスとばかりに声を弾ませる。
「私は18でスマホを持っています。椿の変わりに連絡役を請け負いますわ」
連絡先のメモを渡そうとするが手で制止されてしまう。
「また校門の前で待っていればいい」
頼久としてはスマホを贈りたいが家の都合ならと諦めた。
妃月が引き留めるのも聞かず、用無しだと言わんばかりに、頼久は再び立ち上がり帰ろうとする。
「頼久様、なぜそんなに椿ばかりを気になさっているのですか?まさか恋仲で?」
「いや、まだ婚約者ではない」
「こんっ………」
妃月は絶句した。
(まだって何?恋人じゃなくて婚約者って言ったわよね。飛びすぎじゃない!)
頼久は帰って行ったが、頼久は妃月に素っ気なく、すぐ目を反らして興味なさそうだった。妃月は連絡先も家柄もわからず、思い通りに行かなかったことに腹を立てた。
「椿、椿、椿ってあんなのどこがいいのよ!私の邪魔をする椿、ムカつく!お母様に言いつけてキツくお仕置きしてもらわなくちゃ!!」
もちろん妃月も参加し鬱憤を晴らすつもりだ。
家は茶道の家元、自分の点てたお茶と美しい着物姿で頼久を魅了させる作戦だ。
汐倉の屋敷に着くと使用人に案内させ、妃月は着替え。
使用人に椿は帰っているかと聞けば、知らないという。
使用人も椿には興味がないのだから仕方ない。
来客が帰るまで屋敷に入れないように伝え、頼久の元へ。
頼久の執事は別室で待ってもらっている。
「お待たせ致しました」
黄色の派手すぎない大人っぽい柄や帯、簪をチョイス。
「椿は?」
「椿は帰って来てないようです」
「そうか」
立ち上がり帰ろうとする頼久。
「ゆっくりお茶でも飲んで待ってはいかがですか?汐倉家は大手の茶道の家元です。ご存じでいらっしゃいますか?」
「知っている。いくつかの流派の一つだったな。椿も茶道を?」
頼久は座りなおす。
「ええ、まだ未熟ですが頑張っております」
「そうか。椿の点てたお茶はさぞ美味いのだろうな」
フッと笑う頼久。
(なによ、さっきから口を開けば椿、椿って…私の前くらい気を使いなさいよ!本当に椿《あいつ》許せない!)
「今日は私で我慢してくださいませ。ところで私の着物はいかがですか?」
「……よく似合っている」
「ありがとうございますぅ〜!」
頼久は社交辞令のつもりだったが妃月は本気にした。
「椿とはどちらで?」
「昨晩のパーティーでな」
「…そ、そうなんですね〜」
椿の話題など虫唾が走るが、共通の話題がない。
「頼久様は苗字をお尋ねしても?花京院家主催のパーティーに参加されていたということは、それなりの家柄でいらっしゃいますよね?」
「……俺は俺だ。何者でもない」
「そうですわね〜失礼しましたわ〜」
一番聞きたかったことをはぐかされてしまう。
「椿に何か大事なご用ですか?私が変わりにお伝え致しますわ」
「いや、必要ない」
「椿はスマホを持っていないのか?」
妃月から質問すれば答えている状態だった頼久が妃月に質問する。
「はい。うちは18歳からと決まりです。友人やゲームなどでうつつを抜かしていては茶道の修行はできませんからね」
実際はそんな決まりはなく、椿には与えていないだけだ。
「そうか。椿と連絡出来ないのは困るな」
顎に手を置き、少し考える頼久。
妃月はチャンスとばかりに声を弾ませる。
「私は18でスマホを持っています。椿の変わりに連絡役を請け負いますわ」
連絡先のメモを渡そうとするが手で制止されてしまう。
「また校門の前で待っていればいい」
頼久としてはスマホを贈りたいが家の都合ならと諦めた。
妃月が引き留めるのも聞かず、用無しだと言わんばかりに、頼久は再び立ち上がり帰ろうとする。
「頼久様、なぜそんなに椿ばかりを気になさっているのですか?まさか恋仲で?」
「いや、まだ婚約者ではない」
「こんっ………」
妃月は絶句した。
(まだって何?恋人じゃなくて婚約者って言ったわよね。飛びすぎじゃない!)
頼久は帰って行ったが、頼久は妃月に素っ気なく、すぐ目を反らして興味なさそうだった。妃月は連絡先も家柄もわからず、思い通りに行かなかったことに腹を立てた。
「椿、椿、椿ってあんなのどこがいいのよ!私の邪魔をする椿、ムカつく!お母様に言いつけてキツくお仕置きしてもらわなくちゃ!!」
もちろん妃月も参加し鬱憤を晴らすつもりだ。