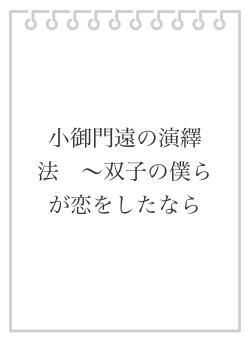樹が自販機で飲料を調達して戻ると、香は膝の上にふたつのビニール袋を乗っけていた。中に何やら、四角いパックが入っている。樹はペットボトルの蓋をあけながら、かすかに眉を寄せて香を見下ろした。
「なんだ、それ」
「貰った」
香はぺかっとした笑顔を樹に向けた。かわいいなおい。じゃなくて。
「は?」
知らない人からものを貰っちゃいけません、と習わなかったのか。香は袋を広げて中を示し、「さくらんぼ。佐藤錦だって」と嬉しそうに言った。お前食事制限中じゃなかったのか、と、水を指すことは流石に言わない。果物はセーフかもしれないし。ふたつの袋のうちひとつを差し出して、「ほら」と香は言葉を続けた。
「たまにさ、一緒になるおばあさんがいるじゃん? おっきな白い犬連れてる」
言われれば、心当たりはあった。そもそも人の日課などそう時間がずれるようなものではなく、毎日同じ場所を走っていれば見る顔ぶれも決まりきってくる。小柄な初老女性の姿を思い出し、樹は「ああ」と頷いた。香はいつも明るく挨拶をして、樹はその後ろをお座なりな会釈とともに通り過ぎる。
「そのひとがね、『毎日精が出るわね~』って、くれた」
香が居なかったら、恐らく会釈すらしなかった。つまりこれは香に渡されたものなのだ。それでも差し出されれば受け取るほかなく、袋を開けて中を覗き込むと、よく熟れたさくらんぼがぎっしりとパックに詰まっているのが見えた。香はパックを目線の位置まで掲げ、至極嬉しそうににこにこと笑う。
「すげー美味しそう! さくらんぼなんて、普段そんな食べないよね? ありがたいなー」
えへへと幸せそうに相好を崩す香になら、なるほど貢ぎがいもあるものと言うものだ。樹は少し考えて、香が掲げたパックの上に、受け取ったばかりの袋を置いた。
「じゃあ、これも持って帰れば」
「……へ?」
「こんなん持って帰ったら、何言われるかわかんねーし」
母親に見咎められることを思うと、今からうんざりした気分になる。香は理解できないと言いたげにきょとんと樹を見上げて、大きな目をぱしぱし瞬いた。
「何言われるか、って。普通に貰ったって言えばいいじゃん?」
心底から不思議そうな声音だった。
なるほど香はいかにも周りから可愛がられそうで、見知らぬ誰かに応援され貢がれるということも、はじめての経験ではないのだろう。まあこんだけ可愛い見た目をしてればな。しかしながらそれは、香のような輩の特権なのだ。
「じゃあ聞くけど。お前、俺がひとりで走ってるの見て、なんか渡そうと思うか?」
無言でまじまじと見つめるな。
「……あー、うん」
そんで言いづらそうに目線を逸らすな。
「樹は、そう、パッと見ちょっと、怖いからね……?」
しかもなんだそれフォローのつもりか。というか、パッと見で怖いと思われていたのか。今更に衝撃を受けながら、樹はそのまま袋から手を離した。
「って、いや、待って。置かないで!」
「なんで」
惜しくないわけではないが、香の手に渡ったほうが、贈り主もきっと嬉しいだろう。けれども香は思いの外必死に、「だめだって!」と声を大きくした。
「だってこれ、樹にも、って貰ったやつだもん。俺が両方貰うのは絶対おかしい」
「そりゃ一緒に走ってるの見てんだから、そうは言うだろうけど。俺に、ってのはあくまでついでだろ」
「ついでじゃないよ!」
強く言い切られて、樹は思わず目を瞬いた。
「ついでじゃない。ちゃんと、『あっちの子は甘いもの好きかしら』って気にしてたもん。だから樹が受け取ってくれなきゃ駄目なの。俺、『あいつあれで甘いもの好きだから喜びます』って、はっきり言っちゃったんだから。次会ったときに、ちゃんと食べた感想言わないとだめ!」
そんなのお前が勝手に言ったんだろ、とは、言えなかった。
たしかに樹は甘いものが好きだし、だから、さくらんぼのそれもよく熟れた佐藤錦なんて、言わずもがなの大好物なのだ。樹は仕方なく、香の手のパックの上に置いた袋を再度持ち上げた。
「……そこまで言うなら」
「よしよし」
屈んで屈んで、と声を掛けられて上体を屈めると、いい子いい子、と頭をなでられる。なんだこいつ。嫌な感じがちっともしないのが不思議だった。ともかく可愛いのが狡いのだ。邪険にできない。というかそろそろわかってきたけど、こいつ、自分が可愛いってわかってやってるよな? 香はにこにこ邪気無く笑ったまま、「うんうん」と嬉しそうに頷いて言った。
「応援はさ、届くべきところに届かないと」
思わず、眉が寄る。
「応援?」
「うん。あれ? 言わなかったっけ? 『応援してるから頑張って』って」
果たしてそれは、部活動のユニフォームを着ているわけでもない、ただ走っているだけの高校生二人にかけるにふさわしい言葉だろうか。──もしかして、知られているのか? 将棋のファン層は一定年齢以上の男女が多く、ありえない話ではまったくない。いやでも、それよりは……考えて黙りこんだ樹の前で、香は「あれ」と不思議そうに目を瞬いた。
「……嬉しくない?」
「あんまり」
と答えたものの、実際は『ちっとも』だというのは、傍からも明らかだったのだろう。香は不思議そうなまま、「へー?」と首を傾けた。
「俺は、嬉しいけどな。さくらんぼは勿論だけどさー、声かけて貰えるだけでもテンション上がる」
マジか。『鬱陶しいとしか思わない』とか言ったら人非人扱いされそうな純粋さだ、と、樹はこっそり驚嘆した。
「あ、それとも、頑張ってるひとに『頑張れ』っていうのはおかしいみたいな、そういうの? 頑張れって言われたくない?」
「あー……」
一時期流行ったなそれ。
「いや別に。『頑張れ』がおかしいとは思わないけど」
「あ、だよね!? 良かった、俺あれで『頑張れ』って言ってもらえなくなったのちょっと残念で……」
「いや、そうでもなくて。『頑張れ』だろうとなんだろうと、全部同じに無意味だろ」
「……へ?」
香は、『頑張れ』と言われたい側の人間なのか。とするとこれを言っても理解されないだろうな、と思いながらも、もはや誤魔化しようもなく樹は続けた。
「応援する奴が、なにかしてくれるわけじゃないんだからさ。だから応援ってのは、『頑張れ』だろうとなんだろうと平等に無意味だろ。だって、戦うのは、俺ひとりなんだから」
応援してると微笑む誰かが、頑張れと強く声を張る誰かが、盤の上に手を出せるわけもない。いや出してきたら叩き落とすけど。
「応援なんて、応援する側の自己満足だ。それ以上のものにはならない」
たとえ周りがどれだけ『応援』しようと、戦場に立つ誰かを、かわりに支えることはできない。樹を勝たせるのは、樹自身でしかないのだ。己としてはごく普通のことをつまらなく口にしたところで、香がぽかんと目を見開いているのを見て少し慌てた。言い過ぎた。
「……って、俺は思うけど」
ごく個人的な意見です。あなたを否定するつもりなんて一切ございません、と、いつも通りの逃げの一手だ。どうして香相手だと、必要以上に逃げてしまいがちなのだろう。言葉を切って伺った先で、香が、大きな目をぱしぱし瞬かせた。
「……まじかあ」
ぽかんとした顔が見上げてくるのを見ると、なんだか申し訳ないような気分になる。己が間違っているとは思わないが、おそらく、ごく一般的に見て、香のほうが正しいのだ。少なくとも好まれはする。余計なことを言わなければよかった、と後悔する樹の前で、香の黒々とした瞳が樹を捉えた。
「でも、……それってさあ」
ふっ、と、うつくしい顔に影が差す。
「さみしく、ないの?」
さみしい?
ひどく不釣り合いな言葉をぶつけられた、という気がした。随分久々に聞いたから、咄嗟に意味が掴めない気さえした。
さみしい。
それはいったい、どんな感覚だっただろう?
「俺は、頑張れ、って、言ってもらえるのが嬉しいよ。俺が嬉しければさ、俺が貰った応援は無意味じゃないし。……たしかにさ、戦うのは俺ひとりだけど」
香の声が、初夏の風でざわりと揺れる。
「頑張れ、って言葉は。俺を、ひとりじゃなくしてくれる気がする」
盤の上で、『ひとりじゃない』だなんて。
そんなこと、思いたいと思ったこともなかった。ひとりであるのが当然だからだ。そして、ひとりであることで弱くなる、ということが、樹にはちっとも理解できないからだ。あるいは、と樹は考える。
本当に、そんな言葉が、盤上の誰かを『ひとりじゃなく』してくれたなら──どうして柾は、そこを去らなければならなかったというのだろう? 頷いてやれない樹を見上げて、香はそれこそ『さみしそう』な顔で、誤魔化すように小さく笑う。
(……ああ、そうか)
一拍置いて、理解が驚きを連れてくる。
樹の話ではないのだ。そしてある意味では、樹は正しく香の心情を理解していた。
(こいつは、……そうか)
香はその、応援されるべき彼の戦場で。
──さみしい、と。
その応援を受けてなお、ひとりだと、そう思うことが確かにあるのだ。