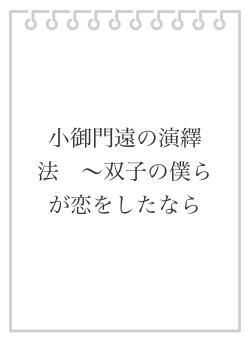他のすべてを省みない在り方を、ひとはあまりに容易く狂気と見做す。
樹からしてみれば、ただの配分の問題だ。ひとつに傾ければ、成果も大きい。問題はその『大きい』が決して確定ではないということ、そしてそうである以上、ひとつに傾けることそのものが多大な恐怖を齎すということだった。ごく単純な、リスクとリターンの問題だ。大概の物事において、かけた時間は正直なのだ。無論、かけかたというものは存在するし、適性というものも悲しいかな大いに関係するのであるが。
リスク管理を考えるなら、樹のようにひとつのことへ全振りする生き方は、人生そのものを賭けたギャンブルであるというふうに見えるのだろう。そう考えればたしかに、樹が身を浸し続けているのは、狂気の沙汰と言われてもおかしくない類の賭けだった。なるほど樹は狂っている。
「ほんと、どうしてこんな子になっちゃったのかしら」
けれども、樹の人生は、ギャンブルという意味では確実に勝利を収めてもいるのだ。少なくともため息とともに『こんな子』だなどと言われる謂れはない、と思いつつ、樹は母親の言葉を聞いていた。
「すっかり引きこもりになっちゃって……やっぱりもうひとり、そう、女の子を作っておけばよかった! 男の子はやっぱり駄目ね、大きくなったらちっとも可愛げがなくて」
「……今から作れば?」
「そういうところが可愛くないって言ってるの」
残業続きの父親と、大学に入って以降サークルだバイトだと忙しい柾がめっきり夕食時に顔を出さないから、必然的に食卓はふたりきりになる。樹があまりに口を開かないせいで母親がテレビと会話しているだけのような食卓ではあるが、樹が居るおかげでかなしい中年女性の独り言にならずに済んでいるのだから、正直感謝して欲しいぐらいだ。
と言ったら明日から夕食がないだろうから、絶対に口には出さないけれど。
「まあ、柾はともかく、樹の可愛げがないのは赤ちゃんのときからだけど」
思う間にも、母親の愚痴は続いている。
「それにしたって、あなたもちょっとは大人になって、そう、もうちょっと愛想よくできてもいいんじゃない? ていうかあなた、この間、ネットで解説に呼ばれてたわよね。どうしてそういうの教えないの?」
相槌なんかひとつも必要とせず、ぽんぽん飛ぶ話題についていけない。というか、なんでそんなことをいちいち報告しなきゃならないというのか。
「柾に聞いて吃驚したわよ。しかも見てみたら、全部聞き手の方に話を振ってもらってて、見ててハラハラしたわよ。ちゃんとお礼した? 菓子折りのひとつでも渡したほうが良かったりしない?」
「……なんで見るかな」
「親ですもの。気になるに決まってるでしょう」
非常に迷惑だからやめて欲しい、とは言わなかったが顔に出ていた。
「ああもう、またそんな顔して。あなたね、あれだってお金貰ってるんでしょう?」
「……聞き手の人だって貰ってる。向こうのほうがベテランだし」
「でも、貴方のほうが貰ってるんでしょう」
それは知らない。
「そもそもね、あれ、あんまり良い習慣じゃないと思うわよ。若い女性におじさんの接待させてるみたいでねえ……」
と、今度はそもそもの将棋界の慣習そのものに対する文句がはじまった。その点については気持ちはわからなくもないが、樹に言われてもどうしようもない。樹本人としては、正直なところ、聞き手が女性ではない──男性棋士とのダブル解説という形のほうがやりやすいぐらいなのだ。といったら今度は『男子校になんて行かせるんじゃなかった』の愚痴がはじまりそうだから口にはしないが。
ともかく、樹としては、貰っているぶんの仕事はやっているつもりだった。聞かれたことには答えているし、間違ったことも言っていない。『解説』の仕事でフリートークのネタまで仕込んでいく義理はない。『船明ちゃんは愛想とかオブラートとかを持ち合わせてないから』『Xでも基本一言だからな』とかよくコメントやらスレッドやらで言われているのも知ってはいるが、そもそもそういうサービスやらトークの上手さやらを棋士に求めるほうが間違っているのだ。
……とはいえ、そう言い切るのにも多少の無理はある。将棋だって、つまるところは興行だ。スポンサーが金を出すのはファンが金を落とすからで、ファンサービスは仕事のうちなのだ。樹は「しょうがないだろ、商売なんだから」とため息を吐いた。
「女流は、ああいうのも含めて仕事なんだ。……つーか、そういう仕事が嫌なら勝てばいいんだよ。勝ってる棋士は、女流だろうと、対局が忙しくて解説の仕事なんて受けてる暇が無いんだから。だから俺だって、ほとんど来ないだろ、ああいう仕事」
「言われてみればそうね」
「俺は、愛想がいいとか喋りが上手いとか、そういうので食っていこうと思ってないからいいんだよ。そっちに力を入れるぐらいなら研究する。強いことのほうが価値がある。当たり前だろ」
たとえ興行だとしても、強いことが、至上の価値だ。
ただ強いだけでいいし、だから、勝つことだけが全てなのだ。ファンを楽しませることに意義がある、とするならば、樹はただ勝つことでしかそれに応えられない人間だった。というより、本来は、すべての棋士がそうであるのだ。
だから皆、ただ勝ちたくて勝つために、あの盤の前に座るのだろう。
「……強いこと、ねえ」
あくまで樹は真っ当なことを言ったつもりで、けれども母親は、諦めたような呆れたようなため息で樹に応じた。
「別にいいのよ。勿論、勝つのが一番ですもの。間違ってないわ。……でも、じゃあ、貴方、楽しいの?」
「……は?」
「柾と二人、ここで指してたときは、貴方達、ずっと楽しそうだった。だから心配してなかったの。……柾が」
続けてくれてればよかったのに、と、流石の母親も、それを口にすることはできなかったようだった。
楽しい。『対局が楽しみ』という誰かの、というか沓谷の、朗らかな声を思い出した。楽しい? そんな感覚はどこにもなかった。樹の中にはただ、勝利への渇望が、『勝ちたい』という、自分でもどうしようもない欲望があるだけだ。
何を犠牲にしてでも、誰を打ちのめしてでも。そこに楽しさがあるわけがない。
楽しさがあっていいわけがない。
「……まあ、柾は、ちゃんと大学を楽しんでるみたいだから、それはそれでいいんだけどね。今日は研究室に泊まり込みで帰ってこないらしいし」
「……それは楽しんでるって言えるのか?」
「さあ。でも楽しそうだったわよ、実験がどうとかって。こっちの心配なんか知りもしないの。ほんとに男の子って……」
と、いつものように話題はループして、樹は彼女を慰める言葉をひとつも持たない。正直なところもう諦めて欲しい。親孝行は金ですると決めているから許してくれ、と言ったら嘆かれるを通り越して殴られそうだな、と思いながら、樹は黙々と箸を動かすことに終止したのだった。