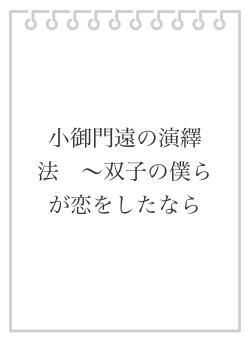待ち合わせは交差点付近の駐車場。時間までに来なかったら先に走りはじめる。雨の日は休み。ゴールは公園。馬鹿げた全力疾走はやめて自分のペースで走る。公園の自販機で、ドリンクを一本買ってふたりで分ける。
一週間ほどで、そういうルールが定まった。
その日は香の番だったから、樹はベンチに座って香を待つ間、息を整えながら目を閉じていた。改めて並んで走ってみれば、体力の差は歴然だった。トレーニングでもした方がいいのかと思ってしまうぐらいだ。
(いや、ないけどさ)
将棋の片手間でなにかやったところで、香に叶うはずもない。とりあえず朝走る分には問題ないからいいのだ、と己を慰めたところで、ぴとっと頬に冷たいものが当てられた。
「隙あり!」
子どもか。
ぐったりとしたまま顔を上げると、反応の薄さが不服なのだろう、香はむうっと唇を尖らせていた。だからなんでそういう顔が似合うんだ? 高校生男子だよなお前?
「樹って感度死んでるの?」
「……いや普通に冷たいけど」
「じゃあ死んでるのは表情筋?」
そちらはなんとも否定出来ない。ぐっと眉を寄せた樹に「眉間だけ生きてる」とけらけら笑って、香は樹の隣に腰を下ろした。ペットボトルの蓋を開けて一口飲んで、「はい」と此方に渡してくる。
「暖かくなってきたねえ」
んん、と腕を伸ばす姿が、日向の猫みたいだった。
樹の表情筋が死に気味だとしたら、香の表情筋はきっと酷使されすぎている。ただ寛いでいる今でさえ、唇は緩やかに持ち上がり目は細められ、正しく『穏やかな笑み』とでも言うべきものが、顔全体に広がっているのだ。ありていに言って眩しい。受け取ったドリンクを飲みながらぼんやりとその横顔を眺めていると、ぱっとこっちを見た彼が「そういえば」と口を開いた。
「樹、何聴いてたの?」
「……あ?」
「前はさ。走ってるとき、イヤホンしてたじゃん」
「ああ」
ウェアのポケットに視線を落とす。今だって、待ち合わせている場所までは、音楽を聞きながら走っているのだ。ノーミュージックノーライフというわけではなく、そのほうが集中できるというだけの理由ではあるが。
「別に、何ってほどじゃないけど。適当に……アニソンとか?」
「アニソン!? その顔で!?」
だから『その顔』ってどんな顔だ?
「……聞いてる曲に顔は関係ねえだろ」
というか、アニソンを聞いていなさそうな顔、というのがどういう顔だ。比較的理系オタクっぽい見た目の輩が多い、と言われる棋士の中では、眼鏡がないぶんオタクっぽさは薄いと自分では思っているが。
「そうだけどさ。意外っていうか……え? アニメとか見るの?」
「まあ、たまには」
たまに、と言ってはみたが、正確を期すなら『ごく稀に』だ。本はそれなりに読むが、アニメはそのオマケ程度にしか見ない。それでもプレイリストがアニソンばかりになっていくのは、ごく単純に、そのオマケ程度のアニメからしか音楽というもの摂取しないからなのだ。意外だ、と顔に大書きしながら、香は言った。
「樹がアニオタっていうのは、考えてなかった……」
「オタクってほどじゃない」
「因みに、最近見たアニメのうちおすすめとかある?」
「聞けよ」
香の恐るべきマイペースさにも、そろそろ慣れた。うんざりした顔を作りながら、中身が半分になったペットボトルを戻しつつ答える。
「……あー、ガンダルの最新作とか? 曲は良かった。内容は、好み別れそうだけど」
有名なロボットアニメシリーズだから、聞いたことぐらいはあるだろう。主題歌がたしかプレイリストに入っていたはず、と、樹はスマートフォンを取り出した。
「聴くか?」
「え、いいの? 俺、シリーズひとつも見たことないよ」
なるほど香は見た目通りというべきか、アニメ方面の素養はないらしい。
「俺もこれしか見てねえし。曲聴くのには関係ないだろ」
繰り返すが樹はオタクというほどではなく、このアニメを見たのはその高名すぎるシリーズ名に惹かれたからではなくて、曲を手掛けていたのがよく聞くアーティストだったからだ。差し出したイヤホンを香が受け取るのを見て、ふと、彼のポケットからはみ出しているイヤホンに気がついた。
「じゃあ、交換な」
「──へ?」
香が聴いている間は暇になるのだし、という程度の認識で、香のポケットからもイヤホンを引っ張りだす。樹が渡したイヤホンを耳に装着しかけていた香が、珍しく焦った様子でぱっと顔を上げた。
「え。あ、っ、ちょ、待って!」
止められるほどやりたくなる、という心理が、己にもあったことに驚いた。樹の尻尾のように見える髪が、驚いて跳ねた身体と一緒に跳ねるのが可愛い。何にそんなに焦っているのか知らないが、アニソンと比して聞かれて困る音楽なんてそうは無いだろう、という偏見のまま、樹は耳にイヤホンを突っ込んだ。
そして聞こえてきた、低く唸るような男声が、咄嗟に、理解できなかった。
「……?」
英語だ、ということだけはどうにかわかった。だみ声と言うのに近い、叩きつけるような台詞。ピアノの旋律と重厚なストリングスに、朗々と歌い上げる艶やかな男性ボーカルが被さってくる。アニソンじゃない。というか、所謂Jポップのたぐいではない。これは……
「……オペラ?」
樹の知識では、クラシック風で歌が入っている曲を表す単語がそれしか無かった。
「い、いや、ミュージカルだけど……」
ミュージカル。言われて頭に浮かんだのは、小学生の時に見た劇団四季のライオン・キングだった。多分違う。ともかく普段はあまり聴かない類の音楽で、けれども妙に、引き込まれるような力があった。
Jealousy、という単語が、いやに強く耳にこびりつく。
なんにせよ自分たちの世代が好んで聴く音楽とはあまり思えず、眉を寄せたままの樹に言い訳するように、香はきょろきょろと視線を動かした。
「え、えっと。まあ、なんだ、事情がね?」
見事なぐらい、何の説明にもなっていなかった。つついて苛めたくなる狼狽えっぷりだな、と思いながら尋ねる。
「……一曲しか入ってねえの?」
「……うう。はい。事情が」
なるほど。伺うような上目遣いがいかにも『聞かないでくれ』と言っていたからそれ以上は触れずに、樹は耳に届く音に集中した。
歌詞はほとんど聞き取れないのに、恋の歌だということだけははっきりわかった。
幸せな歌ではない。後半、ストリングスの盛り上がりに重なって響く朗々たる男性ボーカルは、歌詞を超越した切なさを孕んで聞こえた。声を通して空気を震わせるのは嘆きであり、途方も無い絶望とともに歌われる『I Love You』が、心を抉るかのように歌いあげられる。ラブ・ソングというにはあまりに切ない、一方的な曲に聞こえた。
まるで、決して得られないとわかりきっている愛を乞うような。決して手に入らないものを、それでも願わずにいられないような。
「叩きこんでるんだ」
切々とした歌声に紛れるように、香の声が聞こえてくる。
「身体の全部……頭から、爪先まで。心臓から、指の先っぽまで……血が巡るより自然になるぐらい、身体の全部に刻みこみなさい、って、言われたから。頭で理解するだけじゃ足りない。身体が覚えたってまだ駄目なんだって」
一度聞いただけでも耳に残るような、強く力のあるフレーズだった。このあまりに強い曲を、耳にこびりつく『Jealousy』と『I Love You』を、彼は一体幾度聞いたのだろう。
これから、幾度だなんて思わなくなるほどに聞くのだろう。それは、と、樹は目を眇めて香を見た。聞かれてしまったら吹っ切れたのか、香はついと樹から視線を逸し、樹のイヤホンを耳につけている。
「……わ、ほんとだ。すげー、アニソンだ!」
アニソンってなんか『アニソン』ってすぐわかるよねえなんでかなあ、と、いつもの調子で軽く笑う。その楽しげな横顔と耳元に流れ続ける重苦しい曲のギャップが、これをひたすら、走る時も歩くときも、移動中ももしかしたら寝ている間も聞くのかもしれない彼の姿が、ちっとも脳内で繋がらなかった。
心臓まで、ひとつの音楽を染みこませる、だなんて。
「樹はこういうの聞くんだ。ね、曲名教えてよ。これ結構好きかも」
そんなのは、狂気の沙汰にほかならない──と。
「……あ、ああ」
思ったことを気づかれないように慌てて答えた。そんなふうに音楽を身に叩き込むなんて、常人のやることではありえない。
狂っている、と。
ひとからそう思われているばかりだった樹は、目の前の少年が、己と同じたぐいの狂者であるのだと、そのとき気づいた。
一週間ほどで、そういうルールが定まった。
その日は香の番だったから、樹はベンチに座って香を待つ間、息を整えながら目を閉じていた。改めて並んで走ってみれば、体力の差は歴然だった。トレーニングでもした方がいいのかと思ってしまうぐらいだ。
(いや、ないけどさ)
将棋の片手間でなにかやったところで、香に叶うはずもない。とりあえず朝走る分には問題ないからいいのだ、と己を慰めたところで、ぴとっと頬に冷たいものが当てられた。
「隙あり!」
子どもか。
ぐったりとしたまま顔を上げると、反応の薄さが不服なのだろう、香はむうっと唇を尖らせていた。だからなんでそういう顔が似合うんだ? 高校生男子だよなお前?
「樹って感度死んでるの?」
「……いや普通に冷たいけど」
「じゃあ死んでるのは表情筋?」
そちらはなんとも否定出来ない。ぐっと眉を寄せた樹に「眉間だけ生きてる」とけらけら笑って、香は樹の隣に腰を下ろした。ペットボトルの蓋を開けて一口飲んで、「はい」と此方に渡してくる。
「暖かくなってきたねえ」
んん、と腕を伸ばす姿が、日向の猫みたいだった。
樹の表情筋が死に気味だとしたら、香の表情筋はきっと酷使されすぎている。ただ寛いでいる今でさえ、唇は緩やかに持ち上がり目は細められ、正しく『穏やかな笑み』とでも言うべきものが、顔全体に広がっているのだ。ありていに言って眩しい。受け取ったドリンクを飲みながらぼんやりとその横顔を眺めていると、ぱっとこっちを見た彼が「そういえば」と口を開いた。
「樹、何聴いてたの?」
「……あ?」
「前はさ。走ってるとき、イヤホンしてたじゃん」
「ああ」
ウェアのポケットに視線を落とす。今だって、待ち合わせている場所までは、音楽を聞きながら走っているのだ。ノーミュージックノーライフというわけではなく、そのほうが集中できるというだけの理由ではあるが。
「別に、何ってほどじゃないけど。適当に……アニソンとか?」
「アニソン!? その顔で!?」
だから『その顔』ってどんな顔だ?
「……聞いてる曲に顔は関係ねえだろ」
というか、アニソンを聞いていなさそうな顔、というのがどういう顔だ。比較的理系オタクっぽい見た目の輩が多い、と言われる棋士の中では、眼鏡がないぶんオタクっぽさは薄いと自分では思っているが。
「そうだけどさ。意外っていうか……え? アニメとか見るの?」
「まあ、たまには」
たまに、と言ってはみたが、正確を期すなら『ごく稀に』だ。本はそれなりに読むが、アニメはそのオマケ程度にしか見ない。それでもプレイリストがアニソンばかりになっていくのは、ごく単純に、そのオマケ程度のアニメからしか音楽というもの摂取しないからなのだ。意外だ、と顔に大書きしながら、香は言った。
「樹がアニオタっていうのは、考えてなかった……」
「オタクってほどじゃない」
「因みに、最近見たアニメのうちおすすめとかある?」
「聞けよ」
香の恐るべきマイペースさにも、そろそろ慣れた。うんざりした顔を作りながら、中身が半分になったペットボトルを戻しつつ答える。
「……あー、ガンダルの最新作とか? 曲は良かった。内容は、好み別れそうだけど」
有名なロボットアニメシリーズだから、聞いたことぐらいはあるだろう。主題歌がたしかプレイリストに入っていたはず、と、樹はスマートフォンを取り出した。
「聴くか?」
「え、いいの? 俺、シリーズひとつも見たことないよ」
なるほど香は見た目通りというべきか、アニメ方面の素養はないらしい。
「俺もこれしか見てねえし。曲聴くのには関係ないだろ」
繰り返すが樹はオタクというほどではなく、このアニメを見たのはその高名すぎるシリーズ名に惹かれたからではなくて、曲を手掛けていたのがよく聞くアーティストだったからだ。差し出したイヤホンを香が受け取るのを見て、ふと、彼のポケットからはみ出しているイヤホンに気がついた。
「じゃあ、交換な」
「──へ?」
香が聴いている間は暇になるのだし、という程度の認識で、香のポケットからもイヤホンを引っ張りだす。樹が渡したイヤホンを耳に装着しかけていた香が、珍しく焦った様子でぱっと顔を上げた。
「え。あ、っ、ちょ、待って!」
止められるほどやりたくなる、という心理が、己にもあったことに驚いた。樹の尻尾のように見える髪が、驚いて跳ねた身体と一緒に跳ねるのが可愛い。何にそんなに焦っているのか知らないが、アニソンと比して聞かれて困る音楽なんてそうは無いだろう、という偏見のまま、樹は耳にイヤホンを突っ込んだ。
そして聞こえてきた、低く唸るような男声が、咄嗟に、理解できなかった。
「……?」
英語だ、ということだけはどうにかわかった。だみ声と言うのに近い、叩きつけるような台詞。ピアノの旋律と重厚なストリングスに、朗々と歌い上げる艶やかな男性ボーカルが被さってくる。アニソンじゃない。というか、所謂Jポップのたぐいではない。これは……
「……オペラ?」
樹の知識では、クラシック風で歌が入っている曲を表す単語がそれしか無かった。
「い、いや、ミュージカルだけど……」
ミュージカル。言われて頭に浮かんだのは、小学生の時に見た劇団四季のライオン・キングだった。多分違う。ともかく普段はあまり聴かない類の音楽で、けれども妙に、引き込まれるような力があった。
Jealousy、という単語が、いやに強く耳にこびりつく。
なんにせよ自分たちの世代が好んで聴く音楽とはあまり思えず、眉を寄せたままの樹に言い訳するように、香はきょろきょろと視線を動かした。
「え、えっと。まあ、なんだ、事情がね?」
見事なぐらい、何の説明にもなっていなかった。つついて苛めたくなる狼狽えっぷりだな、と思いながら尋ねる。
「……一曲しか入ってねえの?」
「……うう。はい。事情が」
なるほど。伺うような上目遣いがいかにも『聞かないでくれ』と言っていたからそれ以上は触れずに、樹は耳に届く音に集中した。
歌詞はほとんど聞き取れないのに、恋の歌だということだけははっきりわかった。
幸せな歌ではない。後半、ストリングスの盛り上がりに重なって響く朗々たる男性ボーカルは、歌詞を超越した切なさを孕んで聞こえた。声を通して空気を震わせるのは嘆きであり、途方も無い絶望とともに歌われる『I Love You』が、心を抉るかのように歌いあげられる。ラブ・ソングというにはあまりに切ない、一方的な曲に聞こえた。
まるで、決して得られないとわかりきっている愛を乞うような。決して手に入らないものを、それでも願わずにいられないような。
「叩きこんでるんだ」
切々とした歌声に紛れるように、香の声が聞こえてくる。
「身体の全部……頭から、爪先まで。心臓から、指の先っぽまで……血が巡るより自然になるぐらい、身体の全部に刻みこみなさい、って、言われたから。頭で理解するだけじゃ足りない。身体が覚えたってまだ駄目なんだって」
一度聞いただけでも耳に残るような、強く力のあるフレーズだった。このあまりに強い曲を、耳にこびりつく『Jealousy』と『I Love You』を、彼は一体幾度聞いたのだろう。
これから、幾度だなんて思わなくなるほどに聞くのだろう。それは、と、樹は目を眇めて香を見た。聞かれてしまったら吹っ切れたのか、香はついと樹から視線を逸し、樹のイヤホンを耳につけている。
「……わ、ほんとだ。すげー、アニソンだ!」
アニソンってなんか『アニソン』ってすぐわかるよねえなんでかなあ、と、いつもの調子で軽く笑う。その楽しげな横顔と耳元に流れ続ける重苦しい曲のギャップが、これをひたすら、走る時も歩くときも、移動中ももしかしたら寝ている間も聞くのかもしれない彼の姿が、ちっとも脳内で繋がらなかった。
心臓まで、ひとつの音楽を染みこませる、だなんて。
「樹はこういうの聞くんだ。ね、曲名教えてよ。これ結構好きかも」
そんなのは、狂気の沙汰にほかならない──と。
「……あ、ああ」
思ったことを気づかれないように慌てて答えた。そんなふうに音楽を身に叩き込むなんて、常人のやることではありえない。
狂っている、と。
ひとからそう思われているばかりだった樹は、目の前の少年が、己と同じたぐいの狂者であるのだと、そのとき気づいた。