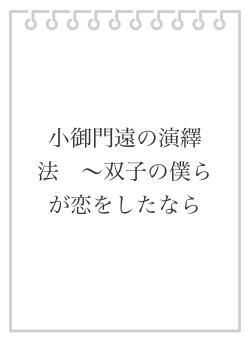※ ※ ※
その日の対局は、夕刻に終わった。
「くっそ、お前マジなんなの? 年下の可愛げみたいなものどっかに忘れてきたの?」
「そういう逆川さんは、年上の余裕とかをお忘れですけど」
「うるせぇ天才」
「……一応言いますけど、それ、言ってて虚しくならないですか」
「うるせぇばか」
これでもう二十五なんだよなこの人、とは言わない。勝負の世界に生きている人間なんて、多かれ少なかれ子供っぽいのだ。逆川が特別わかりやすい、というだけで。
とはいえ感想戦も終わって対局室から出てきた以上、こちらに付き合ってやる義理はない。どうやって逃げるかと算段を立て始めたところで、割って入る呼び声があった。
「逆川さん」
控えめで穏やかな、けれども真っ直ぐに相手に届くような声だった。
逆川と樹の低レベルな言い合いを終わらせてくれる呼び声に、助かった、と思いながら視線を向ける。珍しくも感謝なんかを乗せそうになった舌先はしかし、声の主を確認して微かに強張った。
「あれ、沓谷さん。今日対局ですか?」
「はい」
逆川の声が、すこし、遠くに聞こえた。視線の先に佇む男──沓谷雪人は、樹の姿を認めて穏やかに微笑む。
「船明。久しぶりだね」
細い銀縁の眼鏡を掛けた、いかにも人の良さそうな顔。樹は軽く頭を下げて、ごく短く応じた。
「どうも」
「調子良さそうじゃないか」
「……はあ。まあ」
「あ、いや。船明に、調子が悪かった時期なんてないか」
樹の無愛想な反応に気を悪くするでもなく沓谷は笑って、その親しげとも言える口調に、逆川が軽く目を瞬く。そうして、思い出した所作で「ああ」と手を叩いた。
「そっか。沓谷さん、船明と同期ですもんね」
「はい」
プロ棋士になるには、まず、奨励会というプロ養成機関に所属する必要がある。
奨励会には段位別のリーグが存在し、四段への昇格がイコールで『プロ入り』だった。三段から四段へ昇格できるのは上位二名と定められていて、沓谷と樹は、同じ期に三段リーグを抜けてプロ入りした、故に『同期』と呼ばれる仲である。
けれども、ふたりのキャリアはといえば、見事に正反対だった。
現在二十六歳の沓谷は、当時二十三歳。奨励会には年齢上限が存在し、二十六歳まで四段に上がることが出来なかったものは、プロへの道を絶たれることとなる。三段リーグ入りが早く注目されていたものの、昇段以降停滞し、高校生のうちのデビューすら逃した沓谷と、奨励会入会以降一度として停滞すること無く昇段を続け、史上最年少となる十四歳と三ヶ月でのプロ入りを決めた樹の対比は、当時はそれなりに話題になった。
三段リーグでの直接対決では沓谷が勝利していた、というのも、話題に拍車をかけた一因かもしれない。そのうえ見るからに無表情で無愛想、喋らせても面白みのない樹に比べて、有名大学に通う沓谷は見た目も爽やかな『イケメン』で、常に人当たりのいい笑顔を浮かべた、語り口も軽妙な好青年だった。
何もかもが、正反対に見えるふたりだったのだ。
とはいえ因縁の相手と囁きたがる周囲を尻目に、プロ入り以降のふたりは、一度も盤を挟んで向かい合ったことがない。故に、こうして顔を合わせるまで、樹はほとんど彼のことを思い出さなかった。黙りこくる樹を尻目に、人当たりがいい同士の逆川と沓谷は和やかに会話を続けた。
「船明と逆川さん……あ、新人王戦の予選ですか」
「です。一応言っとくと、俺の負け」
「あら」
「ま、周りから見りゃ順当でしょうが。沓谷さんは勝ち進んでるんでしたっけ?」
「はい、一応。──あ、船明」
話し好き同士仲良くやってくれ、と、こっそりと立ち去ろうとして失敗した。見咎められて呼び止められて、名指しされては無視もできない。樹は舌打ちを押し殺し、改めて沓谷へと視線を向ける。
「……なんですか」
「いや。当たれるといいな。新人王戦」
新人王戦は、トーナメント形式で行われる。沓谷と樹が配置されたのはちょうど反対側で、ふたりが当たるためには、互いが決勝まで勝ち進む必要があるのだった。
つまり沓谷は、決勝で会おうと言っているのだ。──なのに、と、樹は目を眇めて沓谷を見る。
沓谷の声は、不思議だった。自分に決勝まで行けるはずがないと言いたげな謙遜と、決勝で当然当たるだろうと言いたげな自負が、矛盾しているのにたしかに両立している。どういう技術だ、と思いながら、仕方なく樹は口を開いた。
「はい」
頷き、思い出して付け加える。
「沓谷さんは、今年で最後でしたっけ」
『新人』の名で制限されるのは、年齢と段位だ。二十六歳以下で五段以下。プロ入りが遅かった沓谷はもう『新人』の資格を失うのだ。樹が口にしたのはただの事実で、けれども恐らく、余計な一言の部類だった。わかっていてわざわざ口にしたのは、反応が見たかったからに他ならない。ひたと視線を向ける樹の前で、沓谷は軽く瞬いた。
「よく覚えてるな、そんなこと」
驚きはすぐに、ごくごく穏やかに微笑みへと取って代わる。
「そうだね──だからまあ、獲れたら勿論嬉しいけど」
さらりと乾いた、嫌味のない口調。好青年を絵に描いたみたいな『沓谷雪人』は、揺らがない。
「それよりも、今の船明と打ってみたいよ。だから、うん、対局そのもののほうが楽しみだな」
嘘つけ、と。
思ったけれど流石に口に出さずに、樹はついと視線を逸らした。
その日の対局は、夕刻に終わった。
「くっそ、お前マジなんなの? 年下の可愛げみたいなものどっかに忘れてきたの?」
「そういう逆川さんは、年上の余裕とかをお忘れですけど」
「うるせぇ天才」
「……一応言いますけど、それ、言ってて虚しくならないですか」
「うるせぇばか」
これでもう二十五なんだよなこの人、とは言わない。勝負の世界に生きている人間なんて、多かれ少なかれ子供っぽいのだ。逆川が特別わかりやすい、というだけで。
とはいえ感想戦も終わって対局室から出てきた以上、こちらに付き合ってやる義理はない。どうやって逃げるかと算段を立て始めたところで、割って入る呼び声があった。
「逆川さん」
控えめで穏やかな、けれども真っ直ぐに相手に届くような声だった。
逆川と樹の低レベルな言い合いを終わらせてくれる呼び声に、助かった、と思いながら視線を向ける。珍しくも感謝なんかを乗せそうになった舌先はしかし、声の主を確認して微かに強張った。
「あれ、沓谷さん。今日対局ですか?」
「はい」
逆川の声が、すこし、遠くに聞こえた。視線の先に佇む男──沓谷雪人は、樹の姿を認めて穏やかに微笑む。
「船明。久しぶりだね」
細い銀縁の眼鏡を掛けた、いかにも人の良さそうな顔。樹は軽く頭を下げて、ごく短く応じた。
「どうも」
「調子良さそうじゃないか」
「……はあ。まあ」
「あ、いや。船明に、調子が悪かった時期なんてないか」
樹の無愛想な反応に気を悪くするでもなく沓谷は笑って、その親しげとも言える口調に、逆川が軽く目を瞬く。そうして、思い出した所作で「ああ」と手を叩いた。
「そっか。沓谷さん、船明と同期ですもんね」
「はい」
プロ棋士になるには、まず、奨励会というプロ養成機関に所属する必要がある。
奨励会には段位別のリーグが存在し、四段への昇格がイコールで『プロ入り』だった。三段から四段へ昇格できるのは上位二名と定められていて、沓谷と樹は、同じ期に三段リーグを抜けてプロ入りした、故に『同期』と呼ばれる仲である。
けれども、ふたりのキャリアはといえば、見事に正反対だった。
現在二十六歳の沓谷は、当時二十三歳。奨励会には年齢上限が存在し、二十六歳まで四段に上がることが出来なかったものは、プロへの道を絶たれることとなる。三段リーグ入りが早く注目されていたものの、昇段以降停滞し、高校生のうちのデビューすら逃した沓谷と、奨励会入会以降一度として停滞すること無く昇段を続け、史上最年少となる十四歳と三ヶ月でのプロ入りを決めた樹の対比は、当時はそれなりに話題になった。
三段リーグでの直接対決では沓谷が勝利していた、というのも、話題に拍車をかけた一因かもしれない。そのうえ見るからに無表情で無愛想、喋らせても面白みのない樹に比べて、有名大学に通う沓谷は見た目も爽やかな『イケメン』で、常に人当たりのいい笑顔を浮かべた、語り口も軽妙な好青年だった。
何もかもが、正反対に見えるふたりだったのだ。
とはいえ因縁の相手と囁きたがる周囲を尻目に、プロ入り以降のふたりは、一度も盤を挟んで向かい合ったことがない。故に、こうして顔を合わせるまで、樹はほとんど彼のことを思い出さなかった。黙りこくる樹を尻目に、人当たりがいい同士の逆川と沓谷は和やかに会話を続けた。
「船明と逆川さん……あ、新人王戦の予選ですか」
「です。一応言っとくと、俺の負け」
「あら」
「ま、周りから見りゃ順当でしょうが。沓谷さんは勝ち進んでるんでしたっけ?」
「はい、一応。──あ、船明」
話し好き同士仲良くやってくれ、と、こっそりと立ち去ろうとして失敗した。見咎められて呼び止められて、名指しされては無視もできない。樹は舌打ちを押し殺し、改めて沓谷へと視線を向ける。
「……なんですか」
「いや。当たれるといいな。新人王戦」
新人王戦は、トーナメント形式で行われる。沓谷と樹が配置されたのはちょうど反対側で、ふたりが当たるためには、互いが決勝まで勝ち進む必要があるのだった。
つまり沓谷は、決勝で会おうと言っているのだ。──なのに、と、樹は目を眇めて沓谷を見る。
沓谷の声は、不思議だった。自分に決勝まで行けるはずがないと言いたげな謙遜と、決勝で当然当たるだろうと言いたげな自負が、矛盾しているのにたしかに両立している。どういう技術だ、と思いながら、仕方なく樹は口を開いた。
「はい」
頷き、思い出して付け加える。
「沓谷さんは、今年で最後でしたっけ」
『新人』の名で制限されるのは、年齢と段位だ。二十六歳以下で五段以下。プロ入りが遅かった沓谷はもう『新人』の資格を失うのだ。樹が口にしたのはただの事実で、けれども恐らく、余計な一言の部類だった。わかっていてわざわざ口にしたのは、反応が見たかったからに他ならない。ひたと視線を向ける樹の前で、沓谷は軽く瞬いた。
「よく覚えてるな、そんなこと」
驚きはすぐに、ごくごく穏やかに微笑みへと取って代わる。
「そうだね──だからまあ、獲れたら勿論嬉しいけど」
さらりと乾いた、嫌味のない口調。好青年を絵に描いたみたいな『沓谷雪人』は、揺らがない。
「それよりも、今の船明と打ってみたいよ。だから、うん、対局そのもののほうが楽しみだな」
嘘つけ、と。
思ったけれど流石に口に出さずに、樹はついと視線を逸らした。