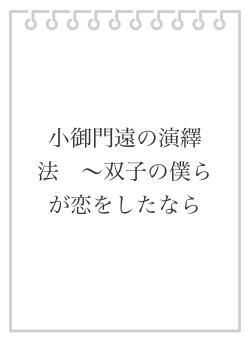※ ※ ※
「……よかった」
言葉とともに彼が笑って、樹は思わず視線を逸らした。よかった、と、多分彼より樹のほうが強く思っていた。彼が来てくれてよかった。
あの日から、きっかり一週間。約束の金曜日。昨夜崩れた天気はどうにか持ち直して、雨の気配は薄い曇り空が広がっている。樹はいつもより少し早く家を出て、あの日彼が立っていた場所で、彼の訪れを待っていた。
「この間は、……えっと、ごめん。びっくりしたよね?」
「……おう」
目の前に彼が立っているのが、現実だという気がしなかった。
一週間。一週間ずっと、考えた。もちろんそればかり考えていたわけではないけれど、それでも多分、かなりの時間を費やしたと思う。対局がなくて本当に良かった。ともかくそうやって、考えて出した結論のとおりに、樹は彼を待っていた。
(もう、逃げられない)
どうやら他の答えはなかった、というより、最初からわかりきっていたのだ。彼が樹を捕まえたあの日、対局翌日で疲れきっていたはずの樹を日課に駆り立てたのは、間違いなく彼の存在だった。間を空けてしまうことで、彼に誤解を与えること──樹が彼の存在を疎んじたと思われること──が、たしかに樹は嫌だったのだ。
それはつまり、樹が、彼と疎遠になりたくなかったということだった。
樹の側には距離を詰める気はなかったが、彼の側が詰めてきてしまった以上、こちらが腹をくくるしか無い。逃げるか向かい合うかの二択を散々考えて、樹は結局、向かい合うことを選択した。
改めて顔を合わせると、目線の高さが違うことがよくわかる。大きな瞳を少し見下ろす形になりながら、樹はそっと唇を開いた。
「樹」
「え?」
声が震えなくてよかった。ばくばく鳴る心臓は肺まで震わせてしまうかのようで、樹は本気で、そのせいで声がみっともなく震えてしまうのを案じていたのだ。とにかく良かった、と思う樹の前で、彼が大きくきらきらとした瞳を瞬かせる。その瞳に浮かんだ疑問に答えるように、樹は続けた。
「俺の名前。樹。樹木の樹で、イツキ。年は十八で、高三。それと……自己紹介って何が必要なんだ?」
なるべくゆっくり喋ろう、と思っていたはずなのに、どうしても急いて早口になった。そのうえ言うつもりだったことを忘れてしまって、最後には疑問形になる始末だ。頭を抱えたくなる樹の前で、彼はもう一度瞬いて、こてんと首を傾けて言った。
「……えーと、好きな食べ物とか?」
なるほど。趣味、或いは『苗字は?』と問われていたら困っただろうから、彼の言葉はありがたかった。
「甘いもの全般。特に和菓子」
「そ、その顔で甘党なんだ!?」
驚かれた。
その顔、と言われても、自分の顔がどう見えるかなんて樹は知らないし興味もない。頭が重い感じが嫌で月一で切りに行く髪は洒落っ気のひとつもない短髪で、目付きが悪いと言われることの多い目はただの細い一重。総じて何の変哲もない顔だ、と、自分ではそう思っている。『性格悪そう』と評されることも無くはないが、そう言ってくる輩はだいたい樹の性格を承知した上で言っている──けれども、もし彼にもそう思われたのなら少し嫌だな、と、樹は微かに眉を寄せた。
「悪いかよ。……それで? お前は?」
それでも『悪いか』と言ってしまう己の性格は、悪いというよりは残念だ。ともあれ、樹のことなんかどうでもいいのだ。本題とばかりに尋ねた樹をじっと見上げて、彼はその小さな唇を開いた。
「かおる」
樹が苗字を言わなかったからか、彼もまた苗字を告げなかった。
「普通に、匂いの意味の……なんて説明したらいいんだ?」
「香車の香?」
「あ、そうそれ。それで、カオル」
いい名前だ、と思う。香車は真っ直ぐにしか進めない愚直な、けれども、詰めのときにあると心強い駒だ。なにより、樹に真っ直ぐに向かってきた彼の姿にぴったり合致している。字面の美しさもいい。ひとりで勝手に論評し納得する樹の前で、香は続ける。
「十七で高三……同い年か。好きな食べ物は……うーん、俺も、甘いものはだいたいなんでも好きなんだけど。今はちょっと、考えたくない、というか」
好きなもののことを考えたくない、とはどういうわけだ。樹の顔に浮かぶ疑問を読み取ったように、香は慌てた様子でぱたぱた手を振った。
「あ、病気とかじゃないよ。減量っていうか……体作り?」
「減量?」
「うん」
減量が必要そうな体格には全く見えないが。
「走ってるのも?」
「うん、……うん? どうだろ。減量のため、ってよりは、体力作りってか……スタミナつけるっていうか? うーん。でもまあ、最終的な目的は一緒になるのかなあ」
自分自身と会話するような曖昧な喋り方はどこか女子めいていた。将棋という完全な男社会と男子校しか知らない樹が女子となんかまともに会話をしたことがあるわけはなく、つまりはただの偏見であるが。本来であれば苦手なタイプの喋り方の筈なのに、不思議と腹は立たなかった。
「まあ、そんな感じ。……樹は?」
いつき、の響きがなんだかひどくむずむずとする。
苗字ではなく名前を告げたのは、『船明』という姓では珍しすぎて、検索でもされた日には一発で個人を特定されてしまうからである。彼に己のことを知られないようにする、と言うのは、樹が決めた方針のうちひとつだった。
彼の前の樹は、ただの、どこにでもいる高校生。そういうことにしよう、と決めたのは、クラスメイトとの会話がどうしても尾を引いているからだった。奇しくも同い年だった彼と、受験のプレッシャーがない身の上を明かすことで疎遠になることが避けられたであろうだけで、その方針に間違いはなかったと思う。
とはいえ、己で決めたとはいえ、家族以外にはまるで呼ばれることのない名前で呼ばれると、違和感はどうしても拭い切れなかった。むず痒いような心地を覚えながら樹は答える。
「運動不足解消」
朝のランニングをはじめたのはプロ入りする前だったが、その目的は将棋にあった。
長時間、タイトル戦ともなれば二日に渡って指し続ける棋士という仕事には、周りが思う以上に体力勝負のところがあるのだ。脳が糖分を欲しがるから、という理由でどうしても甘味を多く摂取する傾向にある己の体型維持のため、という意図もあった。
「え。てことは、他にはなんもスポーツしてないの?」
「おう」
「それでそんな細いの?」
細いという表現に、樹はごく微かに頬を引きつらせた。
事実である。樹の脚や腕は、我ながらどうかと思うほど細かった。骨が太いからか華奢という印象にならないのが救いではあるが、身長があるせいで一層細く見えるのはどうにかならないものかと思ってはいた。コンプレックスというほどではないが、指摘されて面白い点でもない。
「なんもしてないから、だろ」
わかっている。樹の身体にはつまり、筋肉というものが足りないのだ。棋士の中にはフットサルやテニスを嗜むものも多いが、樹はその手の誘いの一切を拒否している。興味が無いからだ。突き詰めれば将棋しかない樹の側には彼に語るべきことはなにもなく、だから樹は彼に尋ねた。
「そっちは?」
咄嗟に名前が口にできなくて、ぶっきらぼうな調子になる。失敗した、という思いを押し殺し、樹は続けた。
「そう言うってことは、なんかやってんの」
「え? うん」
香が、あっさりと頷く。
隠すべきことなんてなにもないんだな、と、眩しく思った。そうだろう。己を殊更に隠したがるのは、負い目か下心のある人間だけだ。羨ましい、とは極力思わないようにと思いながら、樹は続けて尋ねた。
「何」
「内緒」
「は?」
はっきりときっぱりと、一瞬前の感嘆をくるりと覆されて面食らう。ということは、隠すようなことだということか。己は隠しているくせにすこし傷ついて、ぱちぱち瞬く樹の前で、香はつんと唇を尖らせた。
その子どもっぽい表情に、なんだこいつ、と、樹はただひたすらにびっくりした。
同い年の男のくせに、そんな顔をして見せられるのか。そのうえ似合うとかどういうことだ。未知の生き物を眺めているような気分の樹の前で、表情と同じ、拗ねたような顔で香は言った。
「『そっち』ってなに? 俺ちゃんと名前言ったよね」
そして──そこを、咎めてくるのか。
樹が何処で手を抜いたのか、はっきりと見えているかのようだった。樹が甘えたところを見逃さないのが、はじめて言葉を交わした(否、交わしてはいない。一方的に話しかけられた)日のことを思い出させて目眩がする。樹は咄嗟に顔を顰め、それでも仕方なく言い直した。
「……香、は」
くそ。照れる。舌を噛みそうだ。
「何、やってんの」
他人を名前で呼ぶという習慣がそもそもないから、居心地が悪くてしょうがない。引きつりそうになる口元を必死で抑えこんだせいで普段より一層悪い顔になっているだろう樹を見上げて、香はニッと、びっくりするぐらい意地悪に笑った。
(……は?)
表情の移り変わりが鮮やかで強烈で、強烈過ぎて、目が眩む。目の前がチカチカするような感覚に瞬く樹の前で、香はもう一度、飛び跳ねるような調子で言った。
「──内緒!」
今度は、なんだこいつ、とすら思わなかった。
なにも、考えられなかったのだ。考えるのをやめたら何も残らないはずの樹なのに。絶句する樹をただ悪戯に見上げて、香はにやにやと続ける。
「別に、呼んだら言うって言ってないし!」
「……な、」
「へへー。っていうか、そろそろ走らないと遅刻しない? 大丈夫?」
見た目よりよほどいい性格をしていそうだ、というのは思いっきり掴まれて転ばされた時から想像してはいた。そもそもが、初対面で挑発してくるような男なのだ。けれどもどうやら想像以上だ、と認識を上書きする樹の前で、香はごくマイペースに身体をほぐしはじめた。
しっかりと足の腱を伸ばし、足首を回して関節を柔らかくする。
準備動作の手順が決まりきっていて手馴れているのが、なるほどスポーツをする人間の所作だった。樹にはそもそも準備体操という概念がない……などと、観察してしまったのはおそらく、一種の現実逃避だった。
「よし。じゃ、お先に!」
まだ混乱から抜け出せない樹へと言い捨てて、香がぱっと身体を翻す。
振られた腕の指先が流れるようで、憤るより先に思わず見惚れた。空中に決まりきった一番きれいな線があって、ただそれを、定められた所作でなぞっている。そういう、訓練されたうつくしさのある動きだった。
ぽかんと見送って、はっと気がついて、慌てて香の背中を追いかける。
良かった、と、もう一度思った。ほっとしていた。きちんと言葉を交わせた。そして香に、どうやら、今のところは嫌われずにすんだ。
その程度のことで一仕事終えたような気分になる自分のことが、はじめて、情けないなと少し思った。
「……よかった」
言葉とともに彼が笑って、樹は思わず視線を逸らした。よかった、と、多分彼より樹のほうが強く思っていた。彼が来てくれてよかった。
あの日から、きっかり一週間。約束の金曜日。昨夜崩れた天気はどうにか持ち直して、雨の気配は薄い曇り空が広がっている。樹はいつもより少し早く家を出て、あの日彼が立っていた場所で、彼の訪れを待っていた。
「この間は、……えっと、ごめん。びっくりしたよね?」
「……おう」
目の前に彼が立っているのが、現実だという気がしなかった。
一週間。一週間ずっと、考えた。もちろんそればかり考えていたわけではないけれど、それでも多分、かなりの時間を費やしたと思う。対局がなくて本当に良かった。ともかくそうやって、考えて出した結論のとおりに、樹は彼を待っていた。
(もう、逃げられない)
どうやら他の答えはなかった、というより、最初からわかりきっていたのだ。彼が樹を捕まえたあの日、対局翌日で疲れきっていたはずの樹を日課に駆り立てたのは、間違いなく彼の存在だった。間を空けてしまうことで、彼に誤解を与えること──樹が彼の存在を疎んじたと思われること──が、たしかに樹は嫌だったのだ。
それはつまり、樹が、彼と疎遠になりたくなかったということだった。
樹の側には距離を詰める気はなかったが、彼の側が詰めてきてしまった以上、こちらが腹をくくるしか無い。逃げるか向かい合うかの二択を散々考えて、樹は結局、向かい合うことを選択した。
改めて顔を合わせると、目線の高さが違うことがよくわかる。大きな瞳を少し見下ろす形になりながら、樹はそっと唇を開いた。
「樹」
「え?」
声が震えなくてよかった。ばくばく鳴る心臓は肺まで震わせてしまうかのようで、樹は本気で、そのせいで声がみっともなく震えてしまうのを案じていたのだ。とにかく良かった、と思う樹の前で、彼が大きくきらきらとした瞳を瞬かせる。その瞳に浮かんだ疑問に答えるように、樹は続けた。
「俺の名前。樹。樹木の樹で、イツキ。年は十八で、高三。それと……自己紹介って何が必要なんだ?」
なるべくゆっくり喋ろう、と思っていたはずなのに、どうしても急いて早口になった。そのうえ言うつもりだったことを忘れてしまって、最後には疑問形になる始末だ。頭を抱えたくなる樹の前で、彼はもう一度瞬いて、こてんと首を傾けて言った。
「……えーと、好きな食べ物とか?」
なるほど。趣味、或いは『苗字は?』と問われていたら困っただろうから、彼の言葉はありがたかった。
「甘いもの全般。特に和菓子」
「そ、その顔で甘党なんだ!?」
驚かれた。
その顔、と言われても、自分の顔がどう見えるかなんて樹は知らないし興味もない。頭が重い感じが嫌で月一で切りに行く髪は洒落っ気のひとつもない短髪で、目付きが悪いと言われることの多い目はただの細い一重。総じて何の変哲もない顔だ、と、自分ではそう思っている。『性格悪そう』と評されることも無くはないが、そう言ってくる輩はだいたい樹の性格を承知した上で言っている──けれども、もし彼にもそう思われたのなら少し嫌だな、と、樹は微かに眉を寄せた。
「悪いかよ。……それで? お前は?」
それでも『悪いか』と言ってしまう己の性格は、悪いというよりは残念だ。ともあれ、樹のことなんかどうでもいいのだ。本題とばかりに尋ねた樹をじっと見上げて、彼はその小さな唇を開いた。
「かおる」
樹が苗字を言わなかったからか、彼もまた苗字を告げなかった。
「普通に、匂いの意味の……なんて説明したらいいんだ?」
「香車の香?」
「あ、そうそれ。それで、カオル」
いい名前だ、と思う。香車は真っ直ぐにしか進めない愚直な、けれども、詰めのときにあると心強い駒だ。なにより、樹に真っ直ぐに向かってきた彼の姿にぴったり合致している。字面の美しさもいい。ひとりで勝手に論評し納得する樹の前で、香は続ける。
「十七で高三……同い年か。好きな食べ物は……うーん、俺も、甘いものはだいたいなんでも好きなんだけど。今はちょっと、考えたくない、というか」
好きなもののことを考えたくない、とはどういうわけだ。樹の顔に浮かぶ疑問を読み取ったように、香は慌てた様子でぱたぱた手を振った。
「あ、病気とかじゃないよ。減量っていうか……体作り?」
「減量?」
「うん」
減量が必要そうな体格には全く見えないが。
「走ってるのも?」
「うん、……うん? どうだろ。減量のため、ってよりは、体力作りってか……スタミナつけるっていうか? うーん。でもまあ、最終的な目的は一緒になるのかなあ」
自分自身と会話するような曖昧な喋り方はどこか女子めいていた。将棋という完全な男社会と男子校しか知らない樹が女子となんかまともに会話をしたことがあるわけはなく、つまりはただの偏見であるが。本来であれば苦手なタイプの喋り方の筈なのに、不思議と腹は立たなかった。
「まあ、そんな感じ。……樹は?」
いつき、の響きがなんだかひどくむずむずとする。
苗字ではなく名前を告げたのは、『船明』という姓では珍しすぎて、検索でもされた日には一発で個人を特定されてしまうからである。彼に己のことを知られないようにする、と言うのは、樹が決めた方針のうちひとつだった。
彼の前の樹は、ただの、どこにでもいる高校生。そういうことにしよう、と決めたのは、クラスメイトとの会話がどうしても尾を引いているからだった。奇しくも同い年だった彼と、受験のプレッシャーがない身の上を明かすことで疎遠になることが避けられたであろうだけで、その方針に間違いはなかったと思う。
とはいえ、己で決めたとはいえ、家族以外にはまるで呼ばれることのない名前で呼ばれると、違和感はどうしても拭い切れなかった。むず痒いような心地を覚えながら樹は答える。
「運動不足解消」
朝のランニングをはじめたのはプロ入りする前だったが、その目的は将棋にあった。
長時間、タイトル戦ともなれば二日に渡って指し続ける棋士という仕事には、周りが思う以上に体力勝負のところがあるのだ。脳が糖分を欲しがるから、という理由でどうしても甘味を多く摂取する傾向にある己の体型維持のため、という意図もあった。
「え。てことは、他にはなんもスポーツしてないの?」
「おう」
「それでそんな細いの?」
細いという表現に、樹はごく微かに頬を引きつらせた。
事実である。樹の脚や腕は、我ながらどうかと思うほど細かった。骨が太いからか華奢という印象にならないのが救いではあるが、身長があるせいで一層細く見えるのはどうにかならないものかと思ってはいた。コンプレックスというほどではないが、指摘されて面白い点でもない。
「なんもしてないから、だろ」
わかっている。樹の身体にはつまり、筋肉というものが足りないのだ。棋士の中にはフットサルやテニスを嗜むものも多いが、樹はその手の誘いの一切を拒否している。興味が無いからだ。突き詰めれば将棋しかない樹の側には彼に語るべきことはなにもなく、だから樹は彼に尋ねた。
「そっちは?」
咄嗟に名前が口にできなくて、ぶっきらぼうな調子になる。失敗した、という思いを押し殺し、樹は続けた。
「そう言うってことは、なんかやってんの」
「え? うん」
香が、あっさりと頷く。
隠すべきことなんてなにもないんだな、と、眩しく思った。そうだろう。己を殊更に隠したがるのは、負い目か下心のある人間だけだ。羨ましい、とは極力思わないようにと思いながら、樹は続けて尋ねた。
「何」
「内緒」
「は?」
はっきりときっぱりと、一瞬前の感嘆をくるりと覆されて面食らう。ということは、隠すようなことだということか。己は隠しているくせにすこし傷ついて、ぱちぱち瞬く樹の前で、香はつんと唇を尖らせた。
その子どもっぽい表情に、なんだこいつ、と、樹はただひたすらにびっくりした。
同い年の男のくせに、そんな顔をして見せられるのか。そのうえ似合うとかどういうことだ。未知の生き物を眺めているような気分の樹の前で、表情と同じ、拗ねたような顔で香は言った。
「『そっち』ってなに? 俺ちゃんと名前言ったよね」
そして──そこを、咎めてくるのか。
樹が何処で手を抜いたのか、はっきりと見えているかのようだった。樹が甘えたところを見逃さないのが、はじめて言葉を交わした(否、交わしてはいない。一方的に話しかけられた)日のことを思い出させて目眩がする。樹は咄嗟に顔を顰め、それでも仕方なく言い直した。
「……香、は」
くそ。照れる。舌を噛みそうだ。
「何、やってんの」
他人を名前で呼ぶという習慣がそもそもないから、居心地が悪くてしょうがない。引きつりそうになる口元を必死で抑えこんだせいで普段より一層悪い顔になっているだろう樹を見上げて、香はニッと、びっくりするぐらい意地悪に笑った。
(……は?)
表情の移り変わりが鮮やかで強烈で、強烈過ぎて、目が眩む。目の前がチカチカするような感覚に瞬く樹の前で、香はもう一度、飛び跳ねるような調子で言った。
「──内緒!」
今度は、なんだこいつ、とすら思わなかった。
なにも、考えられなかったのだ。考えるのをやめたら何も残らないはずの樹なのに。絶句する樹をただ悪戯に見上げて、香はにやにやと続ける。
「別に、呼んだら言うって言ってないし!」
「……な、」
「へへー。っていうか、そろそろ走らないと遅刻しない? 大丈夫?」
見た目よりよほどいい性格をしていそうだ、というのは思いっきり掴まれて転ばされた時から想像してはいた。そもそもが、初対面で挑発してくるような男なのだ。けれどもどうやら想像以上だ、と認識を上書きする樹の前で、香はごくマイペースに身体をほぐしはじめた。
しっかりと足の腱を伸ばし、足首を回して関節を柔らかくする。
準備動作の手順が決まりきっていて手馴れているのが、なるほどスポーツをする人間の所作だった。樹にはそもそも準備体操という概念がない……などと、観察してしまったのはおそらく、一種の現実逃避だった。
「よし。じゃ、お先に!」
まだ混乱から抜け出せない樹へと言い捨てて、香がぱっと身体を翻す。
振られた腕の指先が流れるようで、憤るより先に思わず見惚れた。空中に決まりきった一番きれいな線があって、ただそれを、定められた所作でなぞっている。そういう、訓練されたうつくしさのある動きだった。
ぽかんと見送って、はっと気がついて、慌てて香の背中を追いかける。
良かった、と、もう一度思った。ほっとしていた。きちんと言葉を交わせた。そして香に、どうやら、今のところは嫌われずにすんだ。
その程度のことで一仕事終えたような気分になる自分のことが、はじめて、情けないなと少し思った。