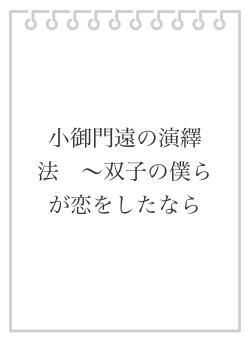JR千駄ヶ谷駅を出て、徒歩十分。
『将棋会館』という堂々たる表書きを横目に中に入り、ワイヤレスのイヤホンを耳から外す。エレベーターで四階まで上がって入口の扉をくぐると、正面に掲げられたホワイトボードが目に入った。部屋名ごとに区切られた一角に、ごく簡素なゴシック体で刻まれた己の名前が貼られている。
「──『銀沙』、か」
小さく呟く。そのまま左に進んで入った部屋からは、藺草の匂いと、仄かな煙草の香りがした。
先客がいる。
「おはようございます」
声をかけると、男の視線がこちらを向いた。樹より七つ上の男──逆川が、すんと鼻を鳴らして樹を見上げる。
「なに。お前、朝帰り?」
「は?」
唐突な、そしてあまりにも不躾な言葉だった。
咄嗟に浮かんできたのは、朝会った彼の姿である。約束の金曜日。樹の表情がなにか思い当たったふうにでも見えたのだろう、誂い半ばだった逆川の眉が軽く上がった。
「は? おいおい、悪い女に騙されてるんじゃないだろうな。柾が泣くぞ?」
「え」
一転、真面目に案じる顔になった逆川が何を言いたいのかがさっぱりわからない。
「いや、なんですか、いきなり」
眉を寄せて見下ろすと、逆川はごくごく真面目な顔で樹を見上げた。
「だって、お前の性格に付き合える女とか、金目当て以外に考えらんねーもん」
自分がまともな性格をしているとは間違っても思わないが、きっぱりと言われれば流石に腹も立つ。売られた喧嘩は買う性分だ。樹は逆川を見下す目線で見下ろして応じた。
「金すら目当てにされないひとに言われたくないですけど」
プロ棋士の主たる収入源は、勿論、対局料である。勝ち進めば進むほどに一局あたりの対局料も上がるから、棋士の収入は、傍目からでもそれなりに明らかだった。樹の言葉に、逆川は「ぐっ」とわざとらしく呻いて懐を抑える。
「……そういうとこが性格悪ィってんだよ」
「先にふっかけてきたのはそっちでしょう」
呆れながら逆川の隣を通りぬけ、盤を挟んだ向かい側に座る。
「って、そういう話じゃなくて。女? 何の話ですか」
対局前の面倒な会話ほど不毛なものもないが、不名誉な噂をばら撒かれる前に、なんでそんな話になったのかをはっきりさせなければならない。うんざりとした調子を隠さずに再び尋ねると、逆川は「そうそう」とこちらに身を乗り出してきた。
「だってお前、匂いがさ」
「匂い?」
鼻先に蘇ったのは、ぴんとつめたい冬の匂いだった。
水の匂いに近い、けれども水よりは余程乾いている、つめたく硬質な『冬の』としか形容できない匂い。けれどもその、ほんとうにささやかな匂いが移っているとはとても思えずに、樹は己の手首を鼻先に引き寄せた。
別に、なにか変わった匂いはしない。強いて言うなら、朝シャワーを浴びてきた分、石鹸の匂いがいつもより強いだろうか?
「……あ」
そういうことか。
「え、お前マジで心当たり」
「違います。朝、走って、汗かいたんで」
詰め寄ってこようとする逆川の目の前に掌を翳して、殊更に平坦さを保って答える。
「シャワー浴びてきたから、それでしょう。……石鹸の匂いぐらいで『朝帰り』って、ちょっと発想が下世話過ぎません?」
嘘は言っていない、というかそもそも、疚しいことなんてひとつもないのだ。逆川はぽかんと目を見開いて、呆気にとられたような調子で言った。
「……走って?」
「はい」
「なんで?」
「朝走るの、日課なんで」
逆川の身体から、見る間に力が抜けていく。嘘は言っていないし疚しいこともない、のに、騙したような気分になるのは何故だろう。思ったけれど、表情にはひとつも出さなかった。ポーカーフェイスは、勝負の世界で生きる人間の基本技能だ。
「は。……そりゃまた」
元気だねえ、と。
言葉だけは感心しているようで、声には呆れとやっかみのほうが余程多く含まれている。つまりは『余裕だねえ』と言いたい彼は、そんな己を戒めるように一度俯いてから、時計を見やって居住まいを正した。
逆川は、気のいい男だった。『性格が悪い』とからかいながら樹に絡んでくるし、樹も彼のことは嫌いではない。交流がある先輩の名を聞かれたら挙げる程度には親しくしているし、逆川の側も、奨励会時代から柾と樹の兄弟を知っているからか、柾に代わって樹のフォローをしようとしてくれているフシがある。
それでも逆川が樹に向ける感情に、妬みが存在しないということはあり得ない。中学生デビュー、最年少プロ棋士、というラベルには、それだけの力が存在するのだ。
その手の視線には、もう、流石に慣れていた。時間を確認し、樹もまた背筋を伸ばして、真っ直ぐに盤面と向かい合った。
九かける九の盤面が、つめたそうだと樹は思う。
寸分の狂いもなく升目が引かれた表面は明るい色味で、側面には木目がくっきりと浮き出て、細かな傷やくすみが長い年月を感じさせる。大切に使われてきた道具ならではの、或いはせめて木材ならではの柔らかさや温かみを感じてもいいはずのそれを前にしたとき、けれども樹はいつも、つめたそうだと思うのだ。
九かける九の、つめたい戦場。
「……さて」
逆川が、ふっと息を吐く。
時間だった。いつの間にか部屋に入ってきていた、同じ部屋で対局するもう一組と、記録係の奨励会員。ぴんと空気が塗り替わった部屋で、逆川が静かに口を開いた。
「はじめようか」
「はい」
そのときほかのすべては失われ、九かける九の、盤の上だけが全てになる。ごく自然に切り替わるはずの意識の端で、樹はけれど、朝のことを思い出していた。
約束の金曜日。
ここに来る前、樹はあの日と同じ場所で、あの日と同じように、彼に会っていた。