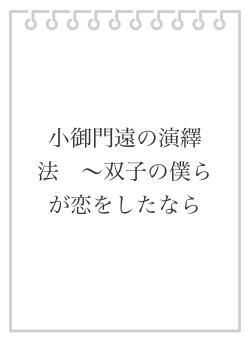(……また、随分、懐かしい夢を見たもんだ)
がたんと大きく電車が揺れて、樹はいつ閉じたのかもわからない瞼を持ち上げた。
祖父のことを思い出したのは、きっと、桜のせいだろう。思いながら視線を上げて、車内の駅名表示を確認して安堵する。目的地まではあと一駅──どうやら、乗り過ごしたわけではなかったらしい。
都内にある穏やかな校風の私立男子校が、樹の現在の所属先だった。高校受験を回避するために中高一貫校に入っておく、というのは奨励会に所属する場合によくとられる選択肢だ。柾が通っていたからという理由で深く考えずに進んだ学校はそれなりに高偏差値だったが、放任傾向で課題が少ないのが樹にあっていて、どうにか辞めずに続けることができていた。
(いやまあ、中学のうちにプロになったんだから、高校に上がらなくったって良かったんだけどな)
いわば保険の選択肢だったのだから、かけ続ける必要はない。今でこそ学歴のある棋士も珍しくはないが、プロ棋士と学生との両立は、決して容易いことではないのだ。
それでも樹が高校に進学することを選んだのは、やはり、ここが柾が過ごした学び舎だったからなのかもしれない。といっても、柾が過ごしたような輝かしい青春、『沢山の友人と学校行事に全力』みたいな生活が送れるわけもなく(別に送りたくもなく)、ただ身体を運んで無為に時間を過ごすだけになってしまっているのだが。
ともあれ、教室に入って席に座りさえすれば、出席したことにだけはなる。さて寝るか、とイヤホンを外したところで、「お」と前から声を掛けられて顔を上げた。
「船明じゃん。今日は休みじゃないんだ?」
無遠慮な声が、寝不足の頭に痛みを齎す。
思わず睨みつけそうになるのをすんでの所で堪え、樹は「ああ」と小さく頷いた。一応進学校を名乗っている学校内で、進学予定のない樹の立ち位置は少し特殊だ。最も授業が楽という理由で選んだ私大文系クラスは、それでも三学年というだけあって、去年までとは少し違う緊張感をはらんでいるような気がした。
「昨日、試合だったんだよな。連日とかじゃないのか?」
若くしてプロ入りし、ニュースに取り上げられることもある樹の存在は、同学年ぐらいには知れている。ごく軽く尋ねてくる相手に、どこまでの真剣さで応じたらいいのかわからずに、ごく淡々と樹は答えた。
「……一つの対局に二日かけることはあるけど、そういうのは決勝とかだから。普通の対局は一日で終わる」
千日手指し直しになれば翌朝までかかることもあるが、千日手、という単語を彼は知らないだろう。そもそも将棋のルールを知っているのかどうか、と思った先で、「へー」と薄い相槌を打った彼は、「で」とついでのように問いを足した。
「昨日は? 勝ったの」
たいして興味もなさそうな口調で、実際、然程の興味もないのだろう。ただ、そういう流れになったから、だらだらと会話を繋ぐためだけに尋ねている。不毛な会話だ。と思いながら、樹はごく短く応じた。
「一応」
「おお」
すげーとぱちぱち拍手されても反応に困る。昨日の試合がどういう立ち位置のものかも、勝率がどれぐらいある相手とのものかも知らないで、すごいのかすごくないのかの判断なんて出来ないだろうに。とはいえ、祝われているからには礼は必要か。樹は平坦に「どうも」と呟いた。正直なところ一刻も早く会話を切り上げて寝たい……が、その前に。
「それより、昨日、課題とか出てたら教えてほしいんだけど」
卒業まであと一年を切るところまで来たからには、柾の言う通り卒業はしたい。樹の問いに、名前も知らないクラスメイトは、「ああ」とごく軽く頷いた。スマートフォンを取り出してくりくり弄る。
「……えーっと。英語と数学で出たわ。メモあるけど、いる?」
「もらえると助かる」
「いくらまで出す?」
今までと少しも変わらないごく軽い口調で言われ、樹は軽く目を瞬いた。
「だってお前、稼いでんだろ?」
声がすこし、歪んで聞こえた。
樹は微かに目を瞬き、その軽い笑みが浮かぶ顔を観察するように見なおす。明るく人好きのする笑顔。気さくな口調。口の中に見える舌が赤い、と思った。
「将棋のプロとか、よくわかんねーけど、一回試合するだけで、何十万とか貰えるんだよな? 受験もしないんだろ? じゃあなんで学校来てんの。課題だって、別に出さなくていいんじゃねーの。内申稼ぐ意味だって無いだろ?」
軽い口調と唇に剥いた笑いの中に、あまりに明白な悪意がある。樹はほんの一呼吸の間だけ動きを止めて、すぐに「まあ」と頷いた。
「それもそうだ」
こういうときの穏便な対処法が、樹には未だによくわからない。
そんなには稼いでない? 何十万は言い過ぎ? ――反吐が出そうだ。謙遜や誤魔化しで上手く流す気が全くない樹に出来る唯一の対処は真正直に返すことだけで、この態度が相手の神経を逆撫でするのがわかっていたところで、性根は変えられないし変える気もないのだ。樹の答えに、彼は「へぇ」と唇を歪めた。
いい御身分だな、という本音が、口に出されなくてもわかった。
こっちはお前が遊び呆けていた小中時代を将棋一色で過ごし、今もなおお前らが予備校やらでダラダラ受験勉強している以上に日々頭を絞っていて、その対価として現在の立場と相応の金額とを受け取っているのだ──とは、樹は言わない。金銭的に不自由のない家庭で育っているうえ、物欲というものがひとより薄い樹には、稼ぎたいという思いも遊びたいという思いも、はっきり言えばほぼ存在しないからだ。
住んでいる世界が違う相手との対話ほど不毛なものはない。だから代わりに頬杖をついて、樹は小さく笑みを浮かべた。
「お前の言うとおりだよ。大学なんて行かなくたって、なんなら今すぐ辞めたっていいんだけど、親が卒業しろってうるさいんだ。金で毎回売ってくれるんなら助かるぐらいだよ。逆に聞くか。月いくらなら働いてくれる?」
俺のために。
とまでは流石に言わなかったが、立ち位置が完全に逆転したことは、彼の側にもわかっただろう。友人関係を構築して毎回頭を下げるより、金で買うほうがよっぽど楽だ、というのは、偽らざる樹の本音である。とはいえこんな言い方をされて頷く輩が居るはずもなく、目の前の彼があからさまに鼻白んで身体を退いた。
「……んだよ、それ」
小さな舌打ち。
「くそ。……冗談に決まってんだろ!」
苛立ったふうな言葉とともにスマートフォンの画面を付き出して、あからさまに見下す目を樹へ向ける。『空気が読めない』、あるいは『頭がおかしい』あたりのレッテルを貼って、相手を己より劣っていると見做して嘲るものの、つまりはただの去勢に満ちた眼差しだった。樹はその手の視線にすっかり慣れているから、突き出されたスマートフォンの画面だけをありがたく確認し、手元のノートに書き付ける。
「どうも」
樹が言うと、彼は返事もなくスマートフォンを手元に戻し、くるりと上体を前へ向け直した。その背中ははっきりと樹を拒絶していて、もう彼は樹に話しかけてこないだろうなと思ったけれど、もちろん、さして気にもなりはしなかった。
プロ棋士というラベルの物珍しさは、あたりまえに周りを惹きつける。
下世話な好奇心と、あわよくばの下心。もっと率直な妬みに僻み。彼らの視線は不躾な興味に満ち満ちていて、けれども樹の側にその興味に応えてやる気が一切ないから、最初から傾いた土台の上で、人間関係は積み上がる間もなく崩壊していく。
樹の存在は、なぜだか分からないが、ただそこにあるだけで、人の劣等感を刺激するのだ。だから樹に関わる人間は、どうにかして樹より優位に立とうとする。今の彼のように。
(馬鹿らしい)
湧いてきた欠伸とともに、樹は机の上に上体を突っ伏した。祖父の『あげてはならないもの』という言葉を思い出して、ほんとうにほんの少しだけ、申し訳ないような気分になる。祖父はきっと樹の、此処で『馬鹿らしい』と思ってしまうようなところこそを、直したいと思っていたのだろう。
それでも樹にはもう、九かける九の盤の上以外で、どうやって他人と付き合えば良いのかがわからないのだ。そしてそれで、ちっとも構わないと思っている。
(……ああ、でも)
ふっ、と、冬の匂いを思い出した。
待っていた、と樹に告げた彼はきっと、樹のことを知らないだろう。同年代に知れ渡っているほどの名前ではなく、それでなくても彼は、将棋なんかちっとも興味がなさそうに見えたから。
(……知られたく、ないな)
どうしてそう思うのかもわからないまま。
樹はすっかり睡魔に飲まれて、何もかもわからなくなってただ、眠りにおちる寸前まで、彼の持つつめたい気配のことだけを、ただぼんやりと考えていた。