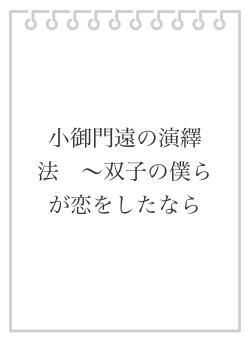帰宅し、シャワーを浴びてからダイニングに入ると、パンの焼けるいい匂いが鼻を擽った。
「ああ、おかえり。樹」
朗らかな声に、咄嗟に眉が寄る。ダイニングテーブルに腰掛けるなんでもない姿がやけに癇に障って、樹は苛立ちを隠さずに言った。
「……今期は一限無いから楽でいい、とか、言ってなかったっけ」
都内の私立大学に通う四つ上の兄・柾はごく普通の学生だが、講義もないのに朝早く起きてくるほど勤勉ではない。おかげで最近は顔を合わせずに済んでいたのに、と思いながら、樹は柾とは視線を合わせずにキッチンに入った。
「午後提出のレポート、忘れてたんだよ。気付いて飛び起きて、半分書いたとこ」
「へえ」
そう言われたところで樹の側には特に感想もなく、返事は限りなく投げやりになる。冷蔵庫から取り出したドリンクを一気に煽ると、冷たさが喉を滑り落ちていった。
眠い、と、漸く自覚がついてくる。濡れた髪をタオルで拭いながらダイニングに戻ると、柾がちょうど焼けたパンにマーガリンを塗りつけているところだった。
空腹のはずなのに、食欲が沸かない。寝直すか、と欠伸をかみ殺したところで、「樹」と穏やかに呼び止められた。
「食べないのか?」
「……腹、減ってない」
「そんなわけないだろ。昨日、遅くまでかかったんだろう?」
今度こそ、堪えきれずに舌を打ってしまった。
「関係ないだろ」
「またそういう……朝起きたらお前がいなくて、吃驚したよ。まさか、まだ終わってないのかって。でも、結果見たら普通に終わってるし」
喋りながら、柾の手がマーマレードの瓶を引き寄せる。つんと甘い匂いが鼻をついて、胃袋より先に頭が反応する気配がした。脳には、糖分が必要だ。
「まさか、対局の次の日まで、走ってるなんて思わないだろ。──ほら」
分厚くマーマレードが塗りたくられたトーストが、当然みたいに差し出される。
「それで、学校には行かないなんて言わせないからな」
柾の言うことは、何から何まで真っ当だった。
毎朝のランニングは中学以来続けている日課ではあったが、深夜まで及んだ対局の翌日に、疲労困憊した身体を押してまでやるようなものではない。というか、今までは当然、対局の前後は休んでいたのだ。
それなのに今日樹が走った理由を、当然ながら、柾は知らない。言うつもりもない。脳にふっと清冽な冬の気配、そしてひどく必死に樹を呼び止めた声が浮かんだ。
君を、待ってた。
「せっかく三年まで上がったんだ、卒業したいだろ。ただでも対局の日は休まなきゃならないんだから、出席日数は稼いどいたほうがいい」
思い出してどうしてか苦しいような心地になる樹に気づくわけもなく、柾は滔々と言葉を続ける。教え諭すような言葉には反発しか覚えなかったが、言い返すのも億劫で黙っていた。なにせ正しい。正論に屁理屈で返すのは得意だったが、疲れ切った朝にまで、ただただ真っ当な兄を相手にやりたいことではなかった。
仕方なく、椅子に腰を下ろす。差し出されたトーストを無言で受け取って一気に噛み砕くと、暴力的なまでの甘さが、脳を叩き起こすようだった。突き刺すみたいに甘い。でもこれぐらい甘くないと樹には物足りないのだ、と、承知している塗り方だった。
「よしよし。いい子だな」
子どもを褒めるみたいな口調に流石に文句を言いたくなったが、にこにことこちらを見ている兄にひとつの効果もないことは、実行しなくても明らかだ。樹はトーストの残りを口に押し込んだ。乱暴に椅子を引いて立ち上がる。
「樹」
ひとつも揺らぐところなんてないみたいな、穏やかな声だった。礼の一つもないのか、と、柾は言わない。代わりに何を言いたがっているのかがわかったから、樹は立ち止まりも振り返りもしなかった。
この上、『おめでとう』だなんて言われたら。
悔しくないのか、と──同じように将棋をやっていたはずなのに、いまはすっかり『応援する』立場になっている己が嫌じゃないのか、と、彼を問い詰めないでいる自信がなかった。
将棋をはじめたのは、兄がやっていたからだった。
その兄が将棋をはじめたのは、有段者である祖父の影響だったから、回り回って祖父の影響と言ってもいいかもしれない。少なくとも、インタビューに答えるときは、樹は兄ではなく祖父のことを理由に上げる。
けれども、樹の体感としては、やはり『兄が』やっていたからというのが正しかった。
樹は、幼少期から、まわりと上手くやれない子どもだった。
樹はとにかく一人遊びが好きで、なにかに集中しているときに、それを妨害されるとひどい癇癪を起こした。教師相手にも言葉巧みに言い返して手を焼かせ、同年代相手では言い込めて泣かせてしまうことも多々あった。
そのうえ樹は、自分が悪いとはすこしも思わなかった。理解力の乏しい相手との会話は樹を苛立たせ、同じ年頃の子どもたちが当然に楽しんでいることが、ひとつも楽しいようには思えなかったからだ。
そんな態度で人と接する子どもが、周りから好かれるはずもない。そのうえ樹は、嫌われたりいじめられたりして傷つくような殊勝さを持ち合わせていなかったものだから、物心ついたころからずっと、当たり前のように孤立していた。両親すらほとほと手を焼いて、困らせているのも樹にはわかって、けれども己を改めようとは思わなかった。周りに誰も居ないほうが静かでいい、と、本気でそう思うような子どもだったのだ。
そんな樹が、唯一遊び相手として認めていたのが柾だった。
柾は樹の目から見ても賢く、そのうえ穏やかで優しくて、樹がやりたいことに辛抱強く付き合ってくれた。樹がとくにハマったのは、昔父親がやっていたという古いアナログボードゲーム類だった。そうしてオセロをはじめとした様々なゲームを楽しむ中で、樹は将棋に出会ったのだ。
祖父の家で、祖父と盤を挟んで座る兄に漂う緊張感が、まず樹の目を引いた。
横から覗き込んだ盤と駒はまず、そのきっちりとした見目で樹の興味を引いた。すると父が横でルールを教えてくれて、その複雑さにすぐに引き込まれた。
ボードゲームにも、いろいろな種類がある。特にそのゲーム性を左右するのは、運要素の有無だろう。樹が好きなのは専らその運要素が排除されたゲームで、そういう意味でも、将棋は樹の好みにあっていた。
体格も運も、小手先の技術も介入しない、ごく純粋な知のみが求められる遊戯だった。
駒の動かし方と勝敗の決め方、それだけを覚え、樹は柾に勝負を挑んだ。そして負けた。当たり前だ。
祖父から手ほどきを受けていた柾はその頃既にそれなりの腕になっていて、駒落ちもせず挑めるような相手ではそもそもなかった。
けれども樹には、そんな前提は関係なかった。
己の玉が詰んだとき、まだ『詰む』という言葉すら知らなかった樹は、気づかぬうちにぼろぼろ涙をこぼしていた。今まで柾とたくさんボードゲームをやってきて、一度も泣いたことがない樹が、だ。両親と柾はひどく仰天し、慌てて「どうしたの」と聞いてきたけれど答えられなかった。自分でも、自分に何が起きたのかわからなかったのだ。
自分のことが、はじめて、途方も無い愚か者に思えた。腹の底になにか、熱い塊でも飲み込んだようだった。こんな思いははじめてだった。
「──悔しいか?」
横から祖父に尋ねられ、はじめて、胸と腹との間あたりにある熱い塊、途方も無い苦しさの名前を知った。悔しい。泣いた目も、その奥の頭の焼けるように熱くて、くるしい、と、はじめて切実にそう思った。くるしい。つらい。樹の前で、祖父がまた、盤の上に駒を並べていく音が聞こえた。
悔しいのは、負けたことではなかった。
何もわからなかった。このゲームのことが。広く深い森に迷い込み、出口が見えない。こんなに小さい盤の上だけが戦場なのに。
こんな、寄る辺ない気持ちになったのははじめてだった。
そのとき、──ぱち、ぱち、と、小さく、音が響いた。
駒を並べ直す音だった。聞くうちに、自然と頭が上がっていた。いつの間にか、向かい側の席に、柾ではなく祖父が座っている。その節くれ立った手が、あまりにきれいな手つきで駒を動かすのに、樹はふっと目を引かれた。
そうして、一度初期配置に駒を並べ直したあと、祖父は自陣の駒を盤上から取り除いていく。王と歩以外の駒をすべて取り除いたところで、「さて」と祖父は笑った。
「もう一局。やろうか、樹」
はい、と、言ったときには勝手に背筋が伸びていた。
お願いします、と頭を下げたのは、柾の見様見真似だったけれど、満足気に祖父は笑った。
それから、柾と樹は、家ではふたりで対局し、祖父の家に行くたび祖父から将棋の手ほどきを受けた。
楽しかった。柾がそう思っているのがわかったし、樹にとっても、将棋より面白いものはなにもなかった。なにせ将棋には果てがなかった。ふたりで競って詰将棋を解き、プロ棋士が書いた将棋の定跡本を読んでは実際に駒を並べて試し、そしてなによりひたすら盤を囲んだ。
そんな生活をしていれば当然というべきか、ふたりは、見る間に強くなっていった。柾は小学生対象の大会でそれなりの成績を残すようになり、将棋教室に通いはじめ、小六のとき、祖父の伝手で奨励会──プロ棋士を目指す少年少女が入る組織だ──に入会した。樹は柾と同じルートを柾より早く駆け抜けて、ついに奨励会のクラスはすぐに柾とおなじになった。
──そして、その日が訪れた。
負けました、と柾は言った。
その声が、震えていた。毎日のように盤を囲んで、樹が勝つのは勿論はじめてではなかった。けれどもそのとき、きっと柾は、実力の差を痛感したのだ。なにせその頃の樹はもう、祖父にも勝てるようになっていた。樹はすぐさま感想戦をやろうとしたが、柾はゆるりと首を振った。
「今日はもう、やめとく」
それが『今日は』ではないことが、そのとき、樹にははっきりわかった。わかったけれど何もできなかった。樹の愕然とした顔で、柾もまた、樹がわかってしまったことがわかっただろう。柾は困ったように微笑んだ。
そして、そのシーズンで柾は奨励会を退会し、以降、樹と指すことはなくなった。
「……私は、お前たちに、あげてはならないものを、あげてしまったのかな」
そう言ったのは、病に倒れ、入院することになった祖父だった。
柾が将棋をやめ、樹が相変わらず友達の一人も作らずに将棋に邁進していることを、両親から聞いたのだろう。奨励会の中でも樹は特別幼く、将棋の師匠や兄姉弟子をはじめとした皆は樹を気にかけてくれたが、『親しい友人』といえるような相手はできなかった。
もう駒も持てない祖父の前に、それでも持参の将棋盤を広げ、「そんなことない」と樹は答えた。
事実として、そんなことは絶対になかった。将棋をやっていなければ、樹がすこしは穏やかで人当たりのいい、普通の子どもになっていた──というのは、間違いなく幻想だった。樹と柾が、昔のように、ただ仲の良い兄弟でいられただろう、ということも。
将棋をやっていようといなかろうと、樹の内面は変わらなかったはずだ。将棋が樹を激しくした面はあっただろうが、その激しさは、そして孤独であることをちっとも厭わない気性は、元々樹が抱いていたものに他ならなかった。
だからきっと樹は、将棋と出会っていなくても、他のなにかにその生来の苛烈さを発揮し、変わらずひとりで生きていただろう。ただ最初に出会ったのが将棋だったから、将棋だけが、そして、将棋を与えてくれた祖父と柾だけが、樹にとっての特別になった。
──特別だったのに。
ぱち、ぱち、と、あの日祖父がしてくれたように駒を並べながら、樹は言った。
「柾は馬鹿だ。……俺より弱くたって、十分強いのに」
祖父は笑った。
「違うだろう、樹」
嗜めるような、愛おしむような声だった。
「そういうときは、ちゃんと、『また指したい』と言いなさい」
樹は口元を引き結んで何も答えず、祖父はそれ以上を口にしなかった。かわりに祖父の口が「2六歩」と動き、樹はその通りに駒を動かした。静かで穏やかな午後だった。
祖父が他界したのは、それからまもなくの、三年前の春のこと。
──樹が、十五歳と三ヶ月でプロ入りを決める、約半年前の事だった。