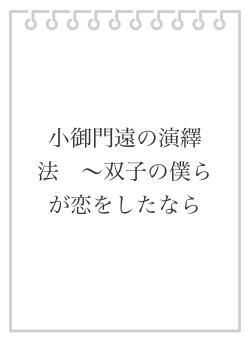薄っすらと白い膜が張った道が、氷の上みたいだなと少し思った。
冬の夜は長く、空は未だ暗い。流石に走る気にはならずに、踏みしめるみたいにゆっくり歩いた。ぴんとつめたい冬の空気を抜けて、桜並木の下に辿り着く。
はら、と、白い欠片が降ってくる。
雪だった。視線の先で、香がついと視線を上げる。雪を受け止めるように掌を翳してから、視線を樹に戻して微かに笑った。
歩み寄って、口を開く。
「……お疲れ」
「ありがと」
ふわ、と、互いの唇から吐息が溢れて、顔を見合わせて少し笑った。歩こっか、と香が言って、樹は小さく頷く。
ふわふわと落ちてくる雪は、雪というより粉砂糖か何かのようだった。静かだった。静かで、張り詰めていて、満たされていた。言葉なんて要らないような気がした。
けれども、言葉がないとわかりあえないのも確かだった。隣を歩く香を横目で見ながら、樹はそうっと、なるべくこの空気を壊さないようにと思いながら口を開く。
「……ほんとうは」
「ごめん」
重なった。
香がちらっとこちらを見上げて、先を譲ると目線で示す。香は視線を樹から外して前を向き、「ごめん」ともう一度繰り返した。
「知ってたんだ。樹のこと。最初から」
そうだろうなと思っていた。
「テレビで見て、……同い年だって聞いて、気になって」
昨日、樹が己の職業を告げたとき、それどころではなかったとはいえ、香はちっとも驚いていなかった。
「盤の前の樹は、なんだろう、すっごく、強く見えたんだ。揺るぎないっていうか……そう、『怖いものなんてなんにもない』みたいな。俺はさ、前も言ったみたいにあんまりメンタル強くないっていうか……あんまり、勝ちたいとか、考えたことなかったから。勝つか負けるかしかない世界にいる樹が見てる世界は、一体どんな感じなんだろうって、……どうしたら樹みたいに強くなれるんだろう、って。まあ、話してるうちに、そういうこと、あんまり考えなくなってったんだけどさ」
そんな風に、思っていたのか、と。
予想できる範囲だったとはいえ、驚いた。そうか。人々が樹に抱く劣等感と同じものを、純粋な羨望という形で香が抱いていた、というのは、どうしても不思議な感じがした。
「とにかく、……そう、だから、会ったのも偶然じゃないんだ。Xに上がってた写真見て、この辺の人なんだって思って、会いに来た」
近所に住んでいた、というのはただしく偶然だろうが、場所が特定できるような写真を上げた記憶はなかったので少し戸惑う。
「写真、って。なんの?」
「桜の写真」
「ああ」
樹のXは、基本的には将棋の話ばかりだが、極稀に日常の一言めいたものを呟くことがある。春先にランニングコースで桜の蕾を見つけたのもそういう極稀に気が向いたタイミングで、樹は翌日わざわざスマートフォンを持ち出し、写真をとってXに上げた。
「……近所の写真なんて上げるもんじゃねえな」
「俺写真とかツイートするときは検閲入るよ」
「すげえ」
有名人様はさすがというべきか、それとも香があまり信用されていないのか。ふんわりとした沈黙が落ちて、樹は香から視線を外して「俺は」と言う。
「スケート・フランス? を、偶然見て。それまでは知らなかった、お前のこと」
オリンピックシーズンで加熱する報道を思えば、よくも知らずにいられたものだ。香が、小さく唇を尖らせる。
「自分で言うのもなんだけど、俺、結構有名人なんだけどなー」
「わかってる。俺が悪い」
「いや、ごめん。嘘だよ。樹が俺のこと知らないってわかってたし、そのほうが楽だったから。いいんだ。……っていうか」
香はすこし視線を伏せて、形の良い眉をひっそりと寄せた。
「それより、なにより、……先に謝らなきゃいけなかった。いきなり『もう会わない』とか言って、ほんとごめん」
樹は思わず香の顔に視線を向けて、香はまっすぐ前を向いていた。口から白い息がこぼれ落ち、その吐息とともに香は続ける。
「てか、そっか。フランスのやつ、見られてたのか。……じゃあ、わかると思うけど。ひどかったでしょ、俺。ジャンプも駄目ならステップはバテバテで……あ、いや、しょうがないんだよ。ジャンプはクリーンに下りるのが一番体力使わないんだ。だから、コケればコケるほど後半きついの。後半リカバリするって、言うほど簡単じゃないんだよ? ……じゃ、なくて」
ふっ、と、小さく笑う。
「あれで、思い知ったんだ。俺は樹みたいに強くなれない。そしたらもう、樹に会うのも怖くなっちゃってさ。俺が弱いってこと、思い知らされ続ける気がして。だから、逃げたの。ごめん」
逃げた、と、口にされると、『もう会わない』を目にした瞬間の痛みが蘇るような気がして、樹はぐっと息を詰めた。香がどんな戦場で戦っているのを知って、己の言葉たちの軽率さを後悔しながら、来るはずのない香を待っていた。
頑張れ、と。
ひとりで頑張る、という香の意志を挫く言葉だったとしても、樹はそれを言うべきだった。『頑張れ』と言うべきだったのだ、と、繰り返し、繰り返し、噛みしめるみたいに後悔した。
「いや、……うん。よく……はないけど、まあ、いいよ。お前のこと何も知らないのに、好き勝手言ってたのはこっちだし」
何をやっているのかはわからないけれど、同じような戦場に立っている。そういう思い込みで無神経なことを言った自覚はあるし、何より。
「……それに、その、香の、フランスでの試合を見て」
フィギュアスケートというものを、きちんと見るのははじめてだった。ルールのひとつも知らないまま、樹の目は画面に釘付けになった。
香は最初のジャンプで転倒し、それでも直ぐに立ち上がって演技を続けた。途中から、疲れているのが素人目にもわかった。解説は耳に入らなかったけれど、きっと途中のスピンの回転は足りず、ジャンプの加点はひくく、ステップのレベルはひとつ落ちている、そういう演技だったのだろうと思う。
それでも香の顔は、最後まで、ひとつも諦めていなかった。
「はじめて、『頑張れ』って」
拳を握って、生中継ではないとっくに終わった試合に向かって、はじめて樹はそう言っていた。本人には伝えられなかった言葉を、届かないとわかりきっているのに、口にせずにはいられなかったのだ。
「気づいたら、そう言ってた。……それで、はじめて、わかったんだ。応援する側が、どんな思いで『頑張れ』って言ってるのか」
応援に、勝敗を左右するだけの力は存在しない。
樹を勝たせることができるのは、香を勝たせることができるのは、どうしたって自分たちだけだ。
それでも、祈らずにはいられない。
「そしたらもう、避けられてるってわかっても、応援しに行きたくなった。意味がなくたっていいと思ったよ。調べて、チケット買って。……ショートのほうは対局と被ってたから行けなくて、結果だけ、対局が終わったあとに見て。……会場で、迷ってたんだよな。頑張れって、メッセージで送っていいのかどうか。……そしたら、その瞬間、前送ったメッセージに既読がついて」
見ているのだ、と思ったら、矢も盾もたまらない気持ちになった。納得したように、香が頷く。
「そっか。それで、電話してくれたんだ」
いつしか、雪が止んでいた。
「……ありがとう。樹が電話してくれなかったら、俺きっと、ひとつも上手くできなかった。樹が俺に、ひとりきりの盤上がどれだけ怖くたって、それでも、勝ちたいと思わなきゃだめなんだって教えてくれた。それでもまだ怖がる俺を応援してくれた」
香の目が、真っ直ぐに樹を突き刺した。
「やっとだよ。やっとだ。──昨日、樹が、『戦う側の人間だ』って言ってくれて、俺はやっと、ちゃんとした選手に……戦う人間に、なれたんだ」
握った手を引き寄せられて、香の胸のあたりで、ぎゅっと両手で握られる。
「そしてわかった。勝ちたいと思うことと、楽しいことは、両立する。……楽しかったよ。昨日は俺、ひとりじゃなかった。会場皆が俺の味方で、俺、すごく楽しかった。樹のおかげで。……そんで、うん、だからさ」
にへ、と、照れたみたいに相好を崩す。
「これからも、よろしく」
俺だって。
そちらが『樹のおかげで』というなら、樹だって、香のお陰で知ったことがいくらでもあった。なるほどたしかに樹は自他共に認める強いメンタルの持ち主で、己が勝つことを疑わないし、『怖いものなんてなんにもない』。
そうなったのがいつからか、今の樹にはわかっていた。柾が盤の前から去ったとき──樹は勝利を手に入れて、自分が、ひとりきりで戦える人間だということを知った。ひとりきりで戦い続けなければならないと思った。そしてそれを──ひとりきりだということを、さみしいとも、かなしいとも思わなかった。
家族のことも他人のことも、兄のことも先輩のことも同期のことも突き放し、盤の上以外の世界に見向きもせずに、たったひとりで立っていた。
そんな樹の世界に、ひっそりとつめたい冬の匂いとともに、きらきら光る雪の結晶みたいに香は舞い降りた。
香が樹に与えてくれたもののことを──ひとりじゃない、と思えたことが、たしかに自分の力になった日のことを、いつかは香に伝えられたらいいと思う。このままこの気持ちから目を逸らし続けたらそのうち香が咎めてくるから、なるべくはやく、咎められる前に。
……けれども、今はまだ無理だ。早速逃げの思考になりながら、樹は香を見下ろして頷いた。
「……おう」
「って、それだけ!? なんかもっと言うことあると思うけどな俺!」
──と思っていたら、早速咎められた。少なくともこういう場においては樹より香のほうが百倍ぐらい強い、と思いながら、樹は「……言うことって?」と顔を顰める。
嫌な予感がする、と少し思う。この感じに、なんだか覚えがあった。連絡先を交換した時と同じパターンにハマるやつじゃないか?
「もっとさ! 樹はどう思ってるのかみたいな、そういうのがあるべきじゃない!?」
ねえ! と、香が見上げてくる。あざとくて可愛くて、なんだそれ、と、樹は思った。どう思ってるのかなんて、そんなの、何から言ったらいいんだ? かわいいとかきれいだとか、シラフじゃ言えないような台詞を使わないで、どうやって?
暗かった空にはじわじわと光が差し始め、夜は朝へと移り変わる。その柔らかくあたたかい変化の中で、香の瞳が、光を受けてきらきら煌めいた。きれいで、きれいで、樹はなんだか胸の奥が掴まれるような心地になる。
「……ねえ、樹」
あるでしょ、言いたいこと。そうやって、少し悪戯めいて笑う顔が好きだ、と、思った。ほんとうに。
つめたい世界で、きらきらと輝いて見えたひと。
つめたい世界で、ひとりじゃないと教えてくれたひと。
「あー、……」
けれども、『好きだ』なんて、口に出せるはずがない。
「そうだ、……オリンピック、流石に見には行けねえけど。応援してるから」
代わりに樹は、嘘ではない、当り障りのないことを口にした。樹がきょとんと瞬いて、「え」と小さく首を傾げる。
「そっち!? あ、いや、そうじゃなくて……え? 見に来ないの?」
「いや、そりゃそうだろ。イタリアだぞ?」
「え、でも、スケートの日程、対局ないでしょ?」
いつの間に調べたんだ。思わず狼狽えて、樹は「だって」と首をふる。
「チケットとか」
「それは俺がどうにかする。……って言ったら」
伺うような上目遣い。う、と、樹は思わず小さく詰まった。我儘を言われてみたい、と、想った自分を呪った。いやだってこんなの。
「……来てくれる? 樹」
どう考えても、逆らえない。樹が小さく頷くと、香はぱあっと、光が射したみたいに笑った。嬉しい、とにこにこする彼のためならなんでもできるような気がした……実際、今からパスポートと飛行機をとることが可能なのかさえ、樹にはさっぱりわからなかったが。けれども彼が望むのだ、なんとかするしかないのだろう。
樹も香も、ひとりきりでさみしい盤上で、とほうもなく孤独に戦うけれど。
それでも、あのつめたい盤の上で、香が樹を思い出せばいいと思う。香のことを思い出したいと思う。
それぞれの盤上で戦っているお互いのことを、思い出せたらいいと思うのだ。
「……樹」
香が、改まった様子でこちらの名を呼んで、手を差し出す。樹はその、樹のものより少し小さい掌を握った。つめたい掌が、徐々にあたたまっていくのを感じる。
「──俺、きっと勝つよ。一番いい色のメダルを獲る」
握った手を引き寄せられて、香の胸のあたりで、ぎゅっと両手で握られる。
「……俺も」
その力強さに押し出されるみたいに、言葉が出た。
「俺も、勝つ。名人……っつってもわからないだろうけど、きっと獲る」
名人に挑戦するにはまず順位戦のランクを上げる必要があるから、最低でも数年かかる話だ。それでも、途方もない未来だとは思わなかった。
「うん」
香が、笑う。
「頑張って。頑張ろうね、樹」
この笑顔を、きっと思い出すだろうと思った。
いつか樹が盤の上で追いつめられたとき、ひとりきりの戦場で折れそうになったとき、樹はきっと、香が応援してくれていることを思い出す。
それだけのことが。
指し手を教えてくれるわけでもない、なにをしてくれるわけでもない、それでも価値のあることだと思えた。頷いて手を握り返し、すっかりあたたまった手のひらの熱を、ひどく大切なもののように思って──樹はふと身体を屈め、握られた手を自分の方へと引き寄せて、その軽く握られた指先に、小さな、誓うような口づけを落としたのだった。