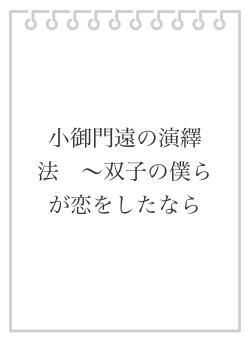名前がコールされると同時に、氷を蹴った。
漆黒のタキシードを模した衣装の胸元は大きく開いて、真紅のフリルで襟元を派手に彩っている。香の年齢を鑑みれば随分と大人びたデザインは、ジュニア時代との差を印象づけるためだった。オールバックにした前髪のうち一房だけ顔の横に零しているのは映画のヒロインへのオマージュで、長い後ろ髪は襟元と同じ真紅のリボンでひとつに括っている。
第六グループの、最終滑走。
現時点でのトップは、当然ながら、ショート・フリーともに完璧な演技を見せた白神一夏である。ショートの時点で、白神と香の点差は二十。どう考えても逆転優勝は不可能な点差だ、と、香は意識しなかった。
香の武器は、四回転ループと、基礎点が一・一倍される後半に組み込んだ四回転サルコウ、そして三回転アクセル―一回転ループ―三回転サルコウの三連続ジャンプだ。四回転がトータル四つの構成は、基礎点では決して白神に劣っていない。
身体を解すようにリンクを一周し、中央でくっと、己の身体を抱くようなボーズで止まった。少し顔を上向かせ、瞼を閉じる。
──曲は、跳ねるような旋律とともにはじまった。
ミュージカル映画、『ムーラン・ルージュ』より、『タンゴ・ロクサーヌ』。まずは最初のジャンプ、この試合では香だけが構成に組み込んでいる、四回転ループだ。ショートプログラムでは堪えきれず転倒してしまったけれど、これを決めなければ勝機はない。
客席全体に、固唾を飲んで見守るような空気があった。今この場で、リンクを見守っている誰もが、ジャンプの成功を祈っている。
そうして踏み切った瞬間に、香は殆ど、その成功を確信した。
フィギュアスケートの採点では、各演技要素に、基礎点の他に『加点』というものが存在する。恣意的と誹りを受けることもあるその採点方式を、けれども仕方ないものだと香は思う。
はっきりとした基準を設けることが難しい、うつくしいジャンプというものは、たしかに盤上に存在するのだ。
そして今、そういう手応えが確かにあった。練習でだってめったに出来なかったレベルの、高いジャンプ、軸のぶれない回転、そしてクリーンな着氷!
わっ、と、高く歓声が響いて、同時にピアノの低音がリズムを刻み始め、高いストリングスの旋律に合わせて、香は一気に加速していく。二つ目のジャンプ。
四回転サルコウ―三回転トゥループのコンビネーションジャンプ──成功!
その瞬間に、会場を、一気に塗り替えたような気がした。勢いに乗った、としか言いようがなかった。三つ目の四回転、単独での四回転トゥループジャンプも危なげなく決めて、香は音楽に合わせてゆったりと速度を落とし、きゅっとエッジを聞かせて動きを止めた。
(……ああ)
つめたい、と、もう思わなかった。盤上はたしかに戦場だ。戦場だけれど。
(もう──俺の、戦場だ)
右手の人差指をぴんと立てて、口元に当ててニッと微笑む。
きゃあっ、と、黄色いとしか表現できない歓声が響いた。可愛いだろう。こういう茶目っ気のある表情は香の十八番で、ここまでのジャンプが決まっていないといまひとつ盛り上がらないけど、ここまで空気ができ上がっていたらもう、盛り上がるなんてものじゃない。客席はすっかり香に魅了され、その心地良い視線を一身に受けながら香は滑る。
タンゴに相応しい振付の繋ぎの後に三回転ルッツ、最初の主題とともに盛り上がる曲に合わせて、間髪入れずのフライングシットスピンのフライングは高く、軸には一切のブレがない。
ゆったりとした繋ぎのステップとともに後半に入り、最初のジャンプは最後の四回転。
四回転サルコウ──成功!
(来た)
真っ白でつめたい、孤独な戦場──では、もう、ない。会場の全てはもう、香の味方だった。応援が力になる。歓声が、拍手が、香の背中を押すようだった。皆が香を見て、その一挙手一投足に見惚れている。身体が軽い。香はぐんぐん加速して、三回転(トリプル)ルッツ―三回転ループのコンビネーションジャンプも乱れなく決める。しっとりとしたピアノの旋律に乗って踏まれるサーキュラーステップはゆっくりとしたテンポで、だからこそ丁寧に踏まないとみっともなく見える──と言われて、それでも上手く動かせなかった身体が今、まるで自分のものじゃないみたいに、指のすみまではっきりとわかった。
──楽しい、と。
湧き上がってくる気持ちがあった。じわじわと、思い出すように思った。楽しい。久しぶりの、随分と懐かしいような、けれどまっさらに新しい感情があった。
盤上は戦場で、だけど香はひとりじゃなくて、──スケートは、ああ、こんなに楽しい!
いつもは意識できないレベルまで感じ取れる指先が辿るラインが、宙にうつくしい軌跡を残す。そしてそのステップの終わりに、一切の予備動作なく、流れるように組み込まれた三回転アクセル―一回転ループ―三回転サルコウ。音楽に合わせて回転速度を落としながらドーナツ型にレッグを掴むキャメルスピンは、ポジションのチェンジも滑らかにできた。
氷上に、歌声が鳴り響く。
切々と歌い上げられる、恋の歌。数シーズン前から使用が許可された『声入り』の曲を存分に活かしたステップの途中で、流石に指先が重くなる。主人公がヒロインへの愛を切々と歌い上げるフレーズとともに、香は微かに顔を歪めた。
体力の限界が、近いのだ。
(あと、すこしだ)
泣いても笑っても、あとすこし。このステップが最大の見せ場だ。疲れた素振りなんて見せちゃいけない。ここがこの曲の肝なのだ。絶対に手にはいらないものを求める歌。愛している。信じてくれ、愛しているんだ、と。
恋愛のことを、香はまだ、よくわからないけれど。
頑張れ、と。
声が、聞こえた気がした。うん、大丈夫。聞こえてる。頑張るよ。頑張れなんて天地がひっくり返ったって言わないみたいな顔してたお前が、俺のためにそう言ってくれたから。
そうして最後の力を振り絞って、香はどうにかステップを踏み終える。
三回転アクセル。
歓声はもはや、曲を掻き消すほどになっていた。まだ曲の途中なのに誰もが立ち上がり、大きく手を打ち鳴らし、香の演技を讃えている。そうしてリンクの真ん中で行われる最後の演技要素──足換えのコンビネーションスピンに、歓声と拍手は、雨のように強く降り注いだ。
そうして、訪れた曲の終わりとともに。
香は高く、高く、拳を掲げた。がたがたと椅子が鳴る音は大きく、けれども拍手と歓声に紛れてしまう。投げ込まれる花、花、花。鳴り止まない拍手。
総立ち。
完璧だった。ひとつのミスもなく、ひとつの取りこぼしもなく、香はすべてを演じきった。ガッツポーズののち、顔を覆っていた掌を持ち上げる。
歓声のシャワーに応えるようにぐるりと回って、両手を広げて。
(──あ)
豆粒みたいな観客の中に、運命みたいに、彼を見つけた。立ち上がって、手を打ち鳴らしている。絶対そんなことをするようなタイプに見えないのに。
そんな一生懸命拍手して、しばらく筋肉痛で駒が持てなくなっても知らないぞ、と。
思ったら、思わず笑っていた。少し気が抜けたみたいな笑顔で大きく手を振って、最後に一礼して、香はリンクをあとにする。
終わった、と。
噛みしめるように思って、一度だけきつく目を閉じた。
漆黒のタキシードを模した衣装の胸元は大きく開いて、真紅のフリルで襟元を派手に彩っている。香の年齢を鑑みれば随分と大人びたデザインは、ジュニア時代との差を印象づけるためだった。オールバックにした前髪のうち一房だけ顔の横に零しているのは映画のヒロインへのオマージュで、長い後ろ髪は襟元と同じ真紅のリボンでひとつに括っている。
第六グループの、最終滑走。
現時点でのトップは、当然ながら、ショート・フリーともに完璧な演技を見せた白神一夏である。ショートの時点で、白神と香の点差は二十。どう考えても逆転優勝は不可能な点差だ、と、香は意識しなかった。
香の武器は、四回転ループと、基礎点が一・一倍される後半に組み込んだ四回転サルコウ、そして三回転アクセル―一回転ループ―三回転サルコウの三連続ジャンプだ。四回転がトータル四つの構成は、基礎点では決して白神に劣っていない。
身体を解すようにリンクを一周し、中央でくっと、己の身体を抱くようなボーズで止まった。少し顔を上向かせ、瞼を閉じる。
──曲は、跳ねるような旋律とともにはじまった。
ミュージカル映画、『ムーラン・ルージュ』より、『タンゴ・ロクサーヌ』。まずは最初のジャンプ、この試合では香だけが構成に組み込んでいる、四回転ループだ。ショートプログラムでは堪えきれず転倒してしまったけれど、これを決めなければ勝機はない。
客席全体に、固唾を飲んで見守るような空気があった。今この場で、リンクを見守っている誰もが、ジャンプの成功を祈っている。
そうして踏み切った瞬間に、香は殆ど、その成功を確信した。
フィギュアスケートの採点では、各演技要素に、基礎点の他に『加点』というものが存在する。恣意的と誹りを受けることもあるその採点方式を、けれども仕方ないものだと香は思う。
はっきりとした基準を設けることが難しい、うつくしいジャンプというものは、たしかに盤上に存在するのだ。
そして今、そういう手応えが確かにあった。練習でだってめったに出来なかったレベルの、高いジャンプ、軸のぶれない回転、そしてクリーンな着氷!
わっ、と、高く歓声が響いて、同時にピアノの低音がリズムを刻み始め、高いストリングスの旋律に合わせて、香は一気に加速していく。二つ目のジャンプ。
四回転サルコウ―三回転トゥループのコンビネーションジャンプ──成功!
その瞬間に、会場を、一気に塗り替えたような気がした。勢いに乗った、としか言いようがなかった。三つ目の四回転、単独での四回転トゥループジャンプも危なげなく決めて、香は音楽に合わせてゆったりと速度を落とし、きゅっとエッジを聞かせて動きを止めた。
(……ああ)
つめたい、と、もう思わなかった。盤上はたしかに戦場だ。戦場だけれど。
(もう──俺の、戦場だ)
右手の人差指をぴんと立てて、口元に当ててニッと微笑む。
きゃあっ、と、黄色いとしか表現できない歓声が響いた。可愛いだろう。こういう茶目っ気のある表情は香の十八番で、ここまでのジャンプが決まっていないといまひとつ盛り上がらないけど、ここまで空気ができ上がっていたらもう、盛り上がるなんてものじゃない。客席はすっかり香に魅了され、その心地良い視線を一身に受けながら香は滑る。
タンゴに相応しい振付の繋ぎの後に三回転ルッツ、最初の主題とともに盛り上がる曲に合わせて、間髪入れずのフライングシットスピンのフライングは高く、軸には一切のブレがない。
ゆったりとした繋ぎのステップとともに後半に入り、最初のジャンプは最後の四回転。
四回転サルコウ──成功!
(来た)
真っ白でつめたい、孤独な戦場──では、もう、ない。会場の全てはもう、香の味方だった。応援が力になる。歓声が、拍手が、香の背中を押すようだった。皆が香を見て、その一挙手一投足に見惚れている。身体が軽い。香はぐんぐん加速して、三回転(トリプル)ルッツ―三回転ループのコンビネーションジャンプも乱れなく決める。しっとりとしたピアノの旋律に乗って踏まれるサーキュラーステップはゆっくりとしたテンポで、だからこそ丁寧に踏まないとみっともなく見える──と言われて、それでも上手く動かせなかった身体が今、まるで自分のものじゃないみたいに、指のすみまではっきりとわかった。
──楽しい、と。
湧き上がってくる気持ちがあった。じわじわと、思い出すように思った。楽しい。久しぶりの、随分と懐かしいような、けれどまっさらに新しい感情があった。
盤上は戦場で、だけど香はひとりじゃなくて、──スケートは、ああ、こんなに楽しい!
いつもは意識できないレベルまで感じ取れる指先が辿るラインが、宙にうつくしい軌跡を残す。そしてそのステップの終わりに、一切の予備動作なく、流れるように組み込まれた三回転アクセル―一回転ループ―三回転サルコウ。音楽に合わせて回転速度を落としながらドーナツ型にレッグを掴むキャメルスピンは、ポジションのチェンジも滑らかにできた。
氷上に、歌声が鳴り響く。
切々と歌い上げられる、恋の歌。数シーズン前から使用が許可された『声入り』の曲を存分に活かしたステップの途中で、流石に指先が重くなる。主人公がヒロインへの愛を切々と歌い上げるフレーズとともに、香は微かに顔を歪めた。
体力の限界が、近いのだ。
(あと、すこしだ)
泣いても笑っても、あとすこし。このステップが最大の見せ場だ。疲れた素振りなんて見せちゃいけない。ここがこの曲の肝なのだ。絶対に手にはいらないものを求める歌。愛している。信じてくれ、愛しているんだ、と。
恋愛のことを、香はまだ、よくわからないけれど。
頑張れ、と。
声が、聞こえた気がした。うん、大丈夫。聞こえてる。頑張るよ。頑張れなんて天地がひっくり返ったって言わないみたいな顔してたお前が、俺のためにそう言ってくれたから。
そうして最後の力を振り絞って、香はどうにかステップを踏み終える。
三回転アクセル。
歓声はもはや、曲を掻き消すほどになっていた。まだ曲の途中なのに誰もが立ち上がり、大きく手を打ち鳴らし、香の演技を讃えている。そうしてリンクの真ん中で行われる最後の演技要素──足換えのコンビネーションスピンに、歓声と拍手は、雨のように強く降り注いだ。
そうして、訪れた曲の終わりとともに。
香は高く、高く、拳を掲げた。がたがたと椅子が鳴る音は大きく、けれども拍手と歓声に紛れてしまう。投げ込まれる花、花、花。鳴り止まない拍手。
総立ち。
完璧だった。ひとつのミスもなく、ひとつの取りこぼしもなく、香はすべてを演じきった。ガッツポーズののち、顔を覆っていた掌を持ち上げる。
歓声のシャワーに応えるようにぐるりと回って、両手を広げて。
(──あ)
豆粒みたいな観客の中に、運命みたいに、彼を見つけた。立ち上がって、手を打ち鳴らしている。絶対そんなことをするようなタイプに見えないのに。
そんな一生懸命拍手して、しばらく筋肉痛で駒が持てなくなっても知らないぞ、と。
思ったら、思わず笑っていた。少し気が抜けたみたいな笑顔で大きく手を振って、最後に一礼して、香はリンクをあとにする。
終わった、と。
噛みしめるように思って、一度だけきつく目を閉じた。