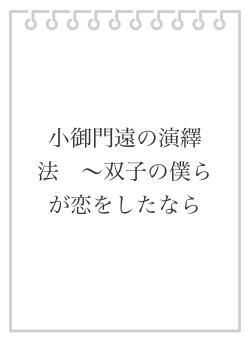十二月二十三日。
クリスマス・イブを翌日に控えた平日。朝方観測された初雪は積もるほどではなく、昼間の雨で流れて消えた。夜にはふたたび雪となるでしょう……とアナウンサーが言う、しんとした、冬が満ちているような日だった。
万雷の拍手が、遠く聞こえる。
イヤホンを耳に突っ込んでかき消そうとしても、ちっとも消えてくれない拍手だった。男子フリースケーティング。最終グループの第一滑走は、ショートプログラムで自己最高に近い点数を叩き出し、当然のように一位を獲得した白神一夏だった。
ミスター・パーフェクトは伊達ではない。彼はきっと、フリースケーティングでもミスをしなかったのだろう。とすればもしかしたら、自己最高を更新しているかもしれない。それはつまり世界新ということだ……ぐるぐると考える香の耳に届く拍手は鳴り止まず、ぎゅっと両手を握って目を瞑る。
(……苦しい)
褒められるのが、嬉しかった。
真っ白な盤の上で、綺麗な衣装を着て、可愛いとか美しいとか言われるのが嬉しかった。歓声と拍手。注目されるのが好きで、可愛い自分が好きで、ただ滑るのが好きだった。みんなが自分を見ているのが、綺麗だと、可愛いと、そう思っているのが好きだったのだ。
けれどももう、それは、過去形だった。
変わったのは周りだろうか。それとも香自身だろうか。
(苦しい。……ああ、嫌だ。怖い。寒い……)
ひとりだ、と。
強く、香は思った。香は今、どうしようもなくひとりきりだった。
(『だって、戦うのは、俺ひとりなんだから』……ああほんと、そのとおりだ。樹はいつだって正しくて強くて、……本当だ。『頑張れ』なんて)
応援の言葉なんて、たくさん貰った。頑張ってください。応援してます。グランプリ・ファイナルに出場できなかったのは残念ですけど、オリンピックで匂坂選手の姿が見れるよう祈ってます……
(なんて、無意味だ)
盤の上で、かつて香は、ひとりではないと思っていた。皆が香のことを見つめている。皆が香のことを応援している。皆が香がいい演技ができるようにと祈っている。だから香はひとりじゃない、と。
思えていたのは、──そこがきっと、香にとってまだ、戦場ではなかったからだ。
あのころ、盤の上は香の『舞台』だった。応援してくれる皆はすべて観客だった。勝ちたいと思う気持ちより、魅せたいと思う気持ちがあった。だから盤上はあたたかい、居心地の良い場所だったのだ。
(でも、……今は)
変わったのは、きっと、香なのだろう。
けれどももう、どうしようもない。変化は不可逆で、香はあの頃には戻れない。指先が震える。時間は刻々と迫ってくる。
寒い、と。
思って、ポケットから、スマートフォンを取り出した。『もう会わない』の一言の後に送られてきたメッセージは、ずっと未読のままにしてあった。抱えていた頭を持ち上げ、頭が働かないままに開いた画面で、今更にそのメッセージ画面をひらいた。
何かあったのか、の一言には、追加のメッセージのひとつもない。
樹はもう、香のことを、覚えてすらいないのかもしれない。自分以外の誰をも必要としないひと。樹の徹底した姿勢は香を打ちのめすばかりで、香はそれでもまだ、その強さにあやかりたがるみたいに画面をなぞった。
強く、なりたかった。勝負に押しつぶされないぐらいに強く。ひとりでも怖くないぐらいに強く。けれども香は結局どちらの強さも手に入れられなくて、ひとりじゃないと思いたがっている。
(樹)
思った瞬間に、手の中のスマートフォンがふるりと震えた。
画面に映る名前に、目を見開く。
間違って通話を推してしまったのかと思い、たしかに向こうからの着信だと確認して息が止まりそうになる。運命か? それとも、二ヶ月ぶりについた既読に、偶然気が付いたとでも言うのだろうか。思いながらイヤホンを耳から外し、震える指で通話ボタンをタップする。拍手はまだ聞こえてくる。
スマートフォンを耳に押し当てると、ざらりとした、低い、なんの感情も篭ってないみたいな声が聞こえた。
『もしもし』
二ヶ月ぶりに聞く声に、こんなときだというのに、なのか、こんなときだからこそ、なのか、涙が出そうになるぐらいにほっとした。自分で拒絶したくせに。
『もしもし。……おい、聞いてんのか?』
声音に少し不機嫌が滲んで、香は慌てて口を開く。会わない、と、自分で送ったことを忘れていた。
「き、聞いてる! 聞いてるから、切らないで」
信じられないほど早口になった。助けて。助けて欲しい。思うままに口を開いていた。
「樹」
ひとりきりだ。
今香はひとりきりで、さみしくて、恐ろしい。だから、ひとりじゃないと思いたかった。一人じゃないと思わせて欲しかった。
「寒い」
ずっと寒いんだ。ねえ、樹。樹は何も答えなくて、でも、きちんと聞いてくれているのはわかった。寒い。手を握ってもらったのに、ちっともあたたかくならなくて。
「盤上は寒いよ。だから」
ひとりきりで。誰もいなくて。誰の助けも借りられなくて。万雷の拍手は香ではない誰かを讃えて──香はきっと、どんなに頑張っても、全力を尽くしても、きっと、白神一夏には叶わない。
わかりきっていた。
わかりきっていたから、今まで、勝ちたいなんて思ったことがなかったのに。
「だから、ねえ」
腹の底に、黒い塊がある。
コーチはそれを、『不安』だと言った。今の香には、違うとわかる。不安じゃない。
これは、欲だ。
──勝ちたい、という、欲望だ。
それを抱いた瞬間に、盤上は舞台から戦場になり、香はとほうもなく孤独になった。つめたい盤上。さみしくておそろしくて、だから香は、勝ちたいなんて思いたくなかったのに。
樹のせいだ、と、思った。勝ちたいなんて思いたくなかった香に、勝ちたいと思って当然だと思わせたのは樹の姿だ。だからこの苦しみは、この寒さは全部樹のせいなのだ。だから樹は香を助けるべきだ。無茶なことを思いながら、責任とれ馬鹿、ぐらいの気分で発したはずの言葉は、びっくりするほど弱々しい、縋り付くみたいな色を帯びた。
「勝てるって、言って」
言ってから、何を言ってるんだ、と、自分で自分に呆れた。
いきなりそんなことを言われて、樹はさぞ面食らっているだろう。当たり前だ。樹は香のことを知らないし、香が何故こんなに切羽詰っているのかも、当たり前にわからない。
それでも。
わからなくてもいい。お座なりでもいい。樹のあの、なんにも怖くないみたいな顔で、平坦な声音で、『勝てる』と言ってくれればそれだけで。
『……香』
戸惑いも呆れも見せない樹の声が、ただ静かに香を呼んだ。他の何をも耳に入れないように、香はその、低くてざらりとした声に意識を集中する。なんでもいいから喋って。歓声が、音楽が、なんにも聞こえなくなるように。
『遊家名人、って、知ってるか』
そうして研ぎ澄ました聴覚が拾い上げた言葉が、咄嗟に、理解できなかった。
「……え?」
『遊家将貴名人。たぶん、今一番有名な将棋の棋士なんだけど』
どの世界にも、『生きた伝説』が存在する。フィギュアスケートにおけるそれが白神一夏であるなら、将棋におけるそれが遊家将貴である、ということぐらいは香も知っていた。わけがわからないままに頷く。
「し、……知ってるけど。CMで見た」
『そりゃ良かった。で、俺、実は将棋の棋士なんだけど。一昨年プロ入りしたばっかなんだけどさ、ひと月前、そのひとと対局する機会があって』
あんまりあっさり言われたから、驚きどころを見失った。実は将棋の棋士なんだけど、って、そんなあっさり言えるならなんで今まで言わなかったの、と、追求することもできないまま、香はただ樹の声を聞く。
聞いているうちに、じわじわと、強張った身体が解けていく。
『まあ、当然っては言いたくねえけど、負けて。七十五手で。序盤からガン攻めで、優勢のつもりだったのに、四十八手目に、ちっとも想定してない桂を打たれて……ただ捨てで、何考えて打った手か全然わかんなくて。とりあえずで対処した手が間違いで、そっから好守が逆転して。がんがん王手かけられて、必死で応じてるうちに盤面はどんどん悪くなってって』
樹が何を言っているのかちっとも理解できなかったけれど、ただその声を聞いているうちに落ち着いた。樹が香に何か、伝えようとしてくれていることがわかった。
無責任な『勝てる』の代わりに、樹は己の隠していた部分を開示してまで、香に何かを告げようとしている。
『……将棋って普通、百手ぐらいはかかるもんなんだよな。その対局は七十五手で、ぶっちゃけ短い方で。つまりそれが、俺の限界だった。勝てなかった。完敗だったよ。終わった後、いい対局だった、って、言われた。あの遊家名人に若手らしく挑んだいい局だった、って。……なあ香』
どう思う、と聞かれて、「え」と間抜けな声が出た。え。どう思う、と言われても。
『最初から勝てない相手だった、とか。しょうがねえ、とか。いい試合ができたんだから充分だ、とか』
どこかで聞いたような台詞の連なりに、ぐりっと抉られたような心地になった。勝てない相手だ。しょうがない。精一杯出来たんだからそれでいい?
『そう思うか? ……思うわけねえよな。思うわけ、ねえんだよ。どんな相手だろうと。全力を出し切れようがなんだろうが、負けりゃ悔しい。当たり前だろ。どんな相手だろうと。神様相手だろうと』
そうだ、と、臓腑の奥深く、ドス黒い欲望の奥が疼いた。そうだ。悔しいのだ。悔しかったのだ。
勝ちたかったら、悔しかったのだ。
『盤上で。おんなじ盤の上で、勝てねえって思ったら終わりだろ』
なあ香、と。
樹の声が少しやわらかく、ふっ、と、香のこころに触れたがるみたいな色を帯びた。なあ香。
『勝てる、なんて。俺が言ってやれるわけないだろ。馬鹿かお前?』
優しい声音で言うことじゃない。と思うのに、びっくりするぐらい優しいと思った。ほんとうだ。そんなことを、樹が言ってくれるわけがなかった。そんなことにすら思い至らなかった。
勝てる、とは、樹は絶対に言ってくれないけど。
『……それを知ってんのは、お前だけだよ。お前はさ』
樹は、香が誰かを知らない。香が立っている戦場を知らない。
『怖くたって、戦う側の。──俺と同じ側の、人間だろ?』
けれども彼はずっと、香のことを、樹本人と同じ側の人間だと──なにかに本気である側の人間だと扱ってくれていた。そのとおりだ、と、香は思った。
そのとおりだ。つめたい銀盤の上で、やっぱり香はひとりきりだ。己以外の誰をも頼りにできない戦場で戦うのだから、誰も香に、『勝てる』だなんて言ってくれない。香を勝たせることができるのは香だけで、そして確かに──香は、戦う側の、勝ちたいと願う側の人間なのだった。
さむくて、つめたくて、さみしくて。
樹はずっとそういう場所で戦ってきて、だから樹は、強いのだ。樹のように強くあろうとするならば、香もおなじように、さむくてつめたい盤上で、ひとりで強く立たねばならない。でもそれがさっきよりは寂しくない、と、香は思った。
──盤上で。おんなじ盤の上で、勝てねえって思ったら終わりだろ。
そうだ。白神一夏は偉大な先輩で生きた伝説で世界の頂点に立つスケーターだけど、同じように盤の上に立って、同じルールで滑っているのだ。滑りだすより前に、勝てないと思う道理はない。勝てないだなんて思わなくていいのだ。
勝ちたい、と、噛みしめるように思った。
「……うん」
頷く声はもう震えなかった。ありがとう、と告げるより前に、『でも』と樹の声が割って入る。
でも?
『でも、……勝てる、っては、言ってやれねえけど。……あー、なんだ』
唐突に歯切れが悪くなって、香はきょとんと目を瞬く。しばらくごにょごにょと言葉を濁した後、樹は言った。
『見てる』
言葉が、張り詰めた銀盤を揺らし、どこまでもさざめいていくような気がした。
「……え?」
見てる? ……見ている? どういうことだ、見てるって何をだ。何をだもなにも、この状況で考えられることは一つしかない。そのひとつが受け入れられない香に畳み掛けるように、照れ隠しも明らかな早口で樹は言った。
『お前のこと、ずっと見てる。それが力になるって言ったのはお前だろ。……俺はお前を見てるよ。お前が勝てるように願ってる。応援してるよ』
「ま、」
ずっと見てる? 応援してる?
「待って、どういう……え?」
わっ、と、先程よりは控えめな歓声が耳に届いた。もしかしたら、スマートフォンの向こうからも。
「樹、……今、何処に居るの?」
『何処、って』
はじめて、樹の声音がちょっと笑った。
『代々木だけど』
代々木第一体育館。
会場であるリンクの上では、今まさしく、最終グループ六人のうち二人が滑り終えたところだった。
クリスマス・イブを翌日に控えた平日。朝方観測された初雪は積もるほどではなく、昼間の雨で流れて消えた。夜にはふたたび雪となるでしょう……とアナウンサーが言う、しんとした、冬が満ちているような日だった。
万雷の拍手が、遠く聞こえる。
イヤホンを耳に突っ込んでかき消そうとしても、ちっとも消えてくれない拍手だった。男子フリースケーティング。最終グループの第一滑走は、ショートプログラムで自己最高に近い点数を叩き出し、当然のように一位を獲得した白神一夏だった。
ミスター・パーフェクトは伊達ではない。彼はきっと、フリースケーティングでもミスをしなかったのだろう。とすればもしかしたら、自己最高を更新しているかもしれない。それはつまり世界新ということだ……ぐるぐると考える香の耳に届く拍手は鳴り止まず、ぎゅっと両手を握って目を瞑る。
(……苦しい)
褒められるのが、嬉しかった。
真っ白な盤の上で、綺麗な衣装を着て、可愛いとか美しいとか言われるのが嬉しかった。歓声と拍手。注目されるのが好きで、可愛い自分が好きで、ただ滑るのが好きだった。みんなが自分を見ているのが、綺麗だと、可愛いと、そう思っているのが好きだったのだ。
けれどももう、それは、過去形だった。
変わったのは周りだろうか。それとも香自身だろうか。
(苦しい。……ああ、嫌だ。怖い。寒い……)
ひとりだ、と。
強く、香は思った。香は今、どうしようもなくひとりきりだった。
(『だって、戦うのは、俺ひとりなんだから』……ああほんと、そのとおりだ。樹はいつだって正しくて強くて、……本当だ。『頑張れ』なんて)
応援の言葉なんて、たくさん貰った。頑張ってください。応援してます。グランプリ・ファイナルに出場できなかったのは残念ですけど、オリンピックで匂坂選手の姿が見れるよう祈ってます……
(なんて、無意味だ)
盤の上で、かつて香は、ひとりではないと思っていた。皆が香のことを見つめている。皆が香のことを応援している。皆が香がいい演技ができるようにと祈っている。だから香はひとりじゃない、と。
思えていたのは、──そこがきっと、香にとってまだ、戦場ではなかったからだ。
あのころ、盤の上は香の『舞台』だった。応援してくれる皆はすべて観客だった。勝ちたいと思う気持ちより、魅せたいと思う気持ちがあった。だから盤上はあたたかい、居心地の良い場所だったのだ。
(でも、……今は)
変わったのは、きっと、香なのだろう。
けれどももう、どうしようもない。変化は不可逆で、香はあの頃には戻れない。指先が震える。時間は刻々と迫ってくる。
寒い、と。
思って、ポケットから、スマートフォンを取り出した。『もう会わない』の一言の後に送られてきたメッセージは、ずっと未読のままにしてあった。抱えていた頭を持ち上げ、頭が働かないままに開いた画面で、今更にそのメッセージ画面をひらいた。
何かあったのか、の一言には、追加のメッセージのひとつもない。
樹はもう、香のことを、覚えてすらいないのかもしれない。自分以外の誰をも必要としないひと。樹の徹底した姿勢は香を打ちのめすばかりで、香はそれでもまだ、その強さにあやかりたがるみたいに画面をなぞった。
強く、なりたかった。勝負に押しつぶされないぐらいに強く。ひとりでも怖くないぐらいに強く。けれども香は結局どちらの強さも手に入れられなくて、ひとりじゃないと思いたがっている。
(樹)
思った瞬間に、手の中のスマートフォンがふるりと震えた。
画面に映る名前に、目を見開く。
間違って通話を推してしまったのかと思い、たしかに向こうからの着信だと確認して息が止まりそうになる。運命か? それとも、二ヶ月ぶりについた既読に、偶然気が付いたとでも言うのだろうか。思いながらイヤホンを耳から外し、震える指で通話ボタンをタップする。拍手はまだ聞こえてくる。
スマートフォンを耳に押し当てると、ざらりとした、低い、なんの感情も篭ってないみたいな声が聞こえた。
『もしもし』
二ヶ月ぶりに聞く声に、こんなときだというのに、なのか、こんなときだからこそ、なのか、涙が出そうになるぐらいにほっとした。自分で拒絶したくせに。
『もしもし。……おい、聞いてんのか?』
声音に少し不機嫌が滲んで、香は慌てて口を開く。会わない、と、自分で送ったことを忘れていた。
「き、聞いてる! 聞いてるから、切らないで」
信じられないほど早口になった。助けて。助けて欲しい。思うままに口を開いていた。
「樹」
ひとりきりだ。
今香はひとりきりで、さみしくて、恐ろしい。だから、ひとりじゃないと思いたかった。一人じゃないと思わせて欲しかった。
「寒い」
ずっと寒いんだ。ねえ、樹。樹は何も答えなくて、でも、きちんと聞いてくれているのはわかった。寒い。手を握ってもらったのに、ちっともあたたかくならなくて。
「盤上は寒いよ。だから」
ひとりきりで。誰もいなくて。誰の助けも借りられなくて。万雷の拍手は香ではない誰かを讃えて──香はきっと、どんなに頑張っても、全力を尽くしても、きっと、白神一夏には叶わない。
わかりきっていた。
わかりきっていたから、今まで、勝ちたいなんて思ったことがなかったのに。
「だから、ねえ」
腹の底に、黒い塊がある。
コーチはそれを、『不安』だと言った。今の香には、違うとわかる。不安じゃない。
これは、欲だ。
──勝ちたい、という、欲望だ。
それを抱いた瞬間に、盤上は舞台から戦場になり、香はとほうもなく孤独になった。つめたい盤上。さみしくておそろしくて、だから香は、勝ちたいなんて思いたくなかったのに。
樹のせいだ、と、思った。勝ちたいなんて思いたくなかった香に、勝ちたいと思って当然だと思わせたのは樹の姿だ。だからこの苦しみは、この寒さは全部樹のせいなのだ。だから樹は香を助けるべきだ。無茶なことを思いながら、責任とれ馬鹿、ぐらいの気分で発したはずの言葉は、びっくりするほど弱々しい、縋り付くみたいな色を帯びた。
「勝てるって、言って」
言ってから、何を言ってるんだ、と、自分で自分に呆れた。
いきなりそんなことを言われて、樹はさぞ面食らっているだろう。当たり前だ。樹は香のことを知らないし、香が何故こんなに切羽詰っているのかも、当たり前にわからない。
それでも。
わからなくてもいい。お座なりでもいい。樹のあの、なんにも怖くないみたいな顔で、平坦な声音で、『勝てる』と言ってくれればそれだけで。
『……香』
戸惑いも呆れも見せない樹の声が、ただ静かに香を呼んだ。他の何をも耳に入れないように、香はその、低くてざらりとした声に意識を集中する。なんでもいいから喋って。歓声が、音楽が、なんにも聞こえなくなるように。
『遊家名人、って、知ってるか』
そうして研ぎ澄ました聴覚が拾い上げた言葉が、咄嗟に、理解できなかった。
「……え?」
『遊家将貴名人。たぶん、今一番有名な将棋の棋士なんだけど』
どの世界にも、『生きた伝説』が存在する。フィギュアスケートにおけるそれが白神一夏であるなら、将棋におけるそれが遊家将貴である、ということぐらいは香も知っていた。わけがわからないままに頷く。
「し、……知ってるけど。CMで見た」
『そりゃ良かった。で、俺、実は将棋の棋士なんだけど。一昨年プロ入りしたばっかなんだけどさ、ひと月前、そのひとと対局する機会があって』
あんまりあっさり言われたから、驚きどころを見失った。実は将棋の棋士なんだけど、って、そんなあっさり言えるならなんで今まで言わなかったの、と、追求することもできないまま、香はただ樹の声を聞く。
聞いているうちに、じわじわと、強張った身体が解けていく。
『まあ、当然っては言いたくねえけど、負けて。七十五手で。序盤からガン攻めで、優勢のつもりだったのに、四十八手目に、ちっとも想定してない桂を打たれて……ただ捨てで、何考えて打った手か全然わかんなくて。とりあえずで対処した手が間違いで、そっから好守が逆転して。がんがん王手かけられて、必死で応じてるうちに盤面はどんどん悪くなってって』
樹が何を言っているのかちっとも理解できなかったけれど、ただその声を聞いているうちに落ち着いた。樹が香に何か、伝えようとしてくれていることがわかった。
無責任な『勝てる』の代わりに、樹は己の隠していた部分を開示してまで、香に何かを告げようとしている。
『……将棋って普通、百手ぐらいはかかるもんなんだよな。その対局は七十五手で、ぶっちゃけ短い方で。つまりそれが、俺の限界だった。勝てなかった。完敗だったよ。終わった後、いい対局だった、って、言われた。あの遊家名人に若手らしく挑んだいい局だった、って。……なあ香』
どう思う、と聞かれて、「え」と間抜けな声が出た。え。どう思う、と言われても。
『最初から勝てない相手だった、とか。しょうがねえ、とか。いい試合ができたんだから充分だ、とか』
どこかで聞いたような台詞の連なりに、ぐりっと抉られたような心地になった。勝てない相手だ。しょうがない。精一杯出来たんだからそれでいい?
『そう思うか? ……思うわけねえよな。思うわけ、ねえんだよ。どんな相手だろうと。全力を出し切れようがなんだろうが、負けりゃ悔しい。当たり前だろ。どんな相手だろうと。神様相手だろうと』
そうだ、と、臓腑の奥深く、ドス黒い欲望の奥が疼いた。そうだ。悔しいのだ。悔しかったのだ。
勝ちたかったら、悔しかったのだ。
『盤上で。おんなじ盤の上で、勝てねえって思ったら終わりだろ』
なあ香、と。
樹の声が少しやわらかく、ふっ、と、香のこころに触れたがるみたいな色を帯びた。なあ香。
『勝てる、なんて。俺が言ってやれるわけないだろ。馬鹿かお前?』
優しい声音で言うことじゃない。と思うのに、びっくりするぐらい優しいと思った。ほんとうだ。そんなことを、樹が言ってくれるわけがなかった。そんなことにすら思い至らなかった。
勝てる、とは、樹は絶対に言ってくれないけど。
『……それを知ってんのは、お前だけだよ。お前はさ』
樹は、香が誰かを知らない。香が立っている戦場を知らない。
『怖くたって、戦う側の。──俺と同じ側の、人間だろ?』
けれども彼はずっと、香のことを、樹本人と同じ側の人間だと──なにかに本気である側の人間だと扱ってくれていた。そのとおりだ、と、香は思った。
そのとおりだ。つめたい銀盤の上で、やっぱり香はひとりきりだ。己以外の誰をも頼りにできない戦場で戦うのだから、誰も香に、『勝てる』だなんて言ってくれない。香を勝たせることができるのは香だけで、そして確かに──香は、戦う側の、勝ちたいと願う側の人間なのだった。
さむくて、つめたくて、さみしくて。
樹はずっとそういう場所で戦ってきて、だから樹は、強いのだ。樹のように強くあろうとするならば、香もおなじように、さむくてつめたい盤上で、ひとりで強く立たねばならない。でもそれがさっきよりは寂しくない、と、香は思った。
──盤上で。おんなじ盤の上で、勝てねえって思ったら終わりだろ。
そうだ。白神一夏は偉大な先輩で生きた伝説で世界の頂点に立つスケーターだけど、同じように盤の上に立って、同じルールで滑っているのだ。滑りだすより前に、勝てないと思う道理はない。勝てないだなんて思わなくていいのだ。
勝ちたい、と、噛みしめるように思った。
「……うん」
頷く声はもう震えなかった。ありがとう、と告げるより前に、『でも』と樹の声が割って入る。
でも?
『でも、……勝てる、っては、言ってやれねえけど。……あー、なんだ』
唐突に歯切れが悪くなって、香はきょとんと目を瞬く。しばらくごにょごにょと言葉を濁した後、樹は言った。
『見てる』
言葉が、張り詰めた銀盤を揺らし、どこまでもさざめいていくような気がした。
「……え?」
見てる? ……見ている? どういうことだ、見てるって何をだ。何をだもなにも、この状況で考えられることは一つしかない。そのひとつが受け入れられない香に畳み掛けるように、照れ隠しも明らかな早口で樹は言った。
『お前のこと、ずっと見てる。それが力になるって言ったのはお前だろ。……俺はお前を見てるよ。お前が勝てるように願ってる。応援してるよ』
「ま、」
ずっと見てる? 応援してる?
「待って、どういう……え?」
わっ、と、先程よりは控えめな歓声が耳に届いた。もしかしたら、スマートフォンの向こうからも。
「樹、……今、何処に居るの?」
『何処、って』
はじめて、樹の声音がちょっと笑った。
『代々木だけど』
代々木第一体育館。
会場であるリンクの上では、今まさしく、最終グループ六人のうち二人が滑り終えたところだった。