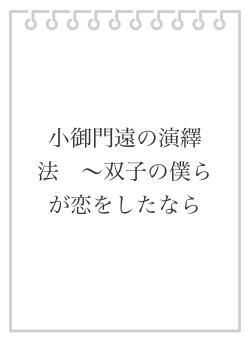匂坂香が彼のことを知ったのは、春のことだった。
香は決断を迫られていた。それなりに大切なたぐいの決断だ。ソファーの上でぐったりとしながら、ずっとそれを考えていた。リビングでは祖父がテレビをつけていて、ぐったりとしている香を見て「おい」と声をかけてきた。
「……なに」
放っておいて欲しい気分だったけれど、呼ばれたからには顔を上げざるを得なかった。そうしてテレビの画面を見て、香は一つ目を瞬いた。
画面の中には、スーツ姿の少年がいた。
「こいつ。去年の新人なんだがな。香と同い年だとよ」
と言われても、ぱっと見ではなにをしているのかもわからなかった。盤面が映って、はじめて、将棋だということがわかる。
「……同い年?」
ということは、まだ中学生か。
「え、これ、プロなんだよね? そんな若くてなれるもんなの」
「お前だって、人のことは言えんだろ」
そうだろうか。香にはあまり、そんな気はしなかった。香がやっているのは、部活の延長みたいなものだ。少しばかり特殊で、人より多くの時間を割いていて、ちょっと才能があったから注目されているだけの部活。
プロ、というのとは、多分違う。少なくとも、香にはそこまでの気持ちはない。
「なれるもんか、っつったらまあ、なれるもんだ。中学生でプロんなったのはコイツで五人目だ。十五歳と三ヶ月」
香はますます驚いた。
香もちょうど、彼と同じ十五歳だった。つまりこの画面の中の彼は、今の香と同じぐらいの年でプロに入ることを決めたのだ。ひたすらにびっくりする香の視線の先で、ぴんと背筋を伸ばし、着慣れないはずのスーツをきちんと着こなして、彼はあまりに落ち着き払った所作で駒を動かした。
「……ねえ、爺ちゃん」
「ん?」
「強いの? こいつ」
盤面を見たところで、香には何が起きているのかさっぱりわからない。というか駒の動かし方すら知らない。香の問いに祖父は「さて」と顎を撫でた。
「まだ序盤だからな。この対局がどうなるかはわからんが……強いはそりゃ、勿論、強いだろうよ。プロになれるのは年間四人だ。三段リーグを一期で抜けたってんだから、まあ、所謂『天才』ってやつだろうなあ」
祖父が何を言っているのかよくわからなかったけれど、強い、ということはわかった。そうだろうと思った。
香も一応、勝負の世界の隅っこにいる。だから、わかるのだ。彼は強い。そういう空気。屈さない空気みたいなものを、彼は確かに持っていた。
「……爺ちゃん」
「なんだよ。気になったか? 将棋やるってんなら、相手になるぞ」
香の名前をつけたのは祖父だった。香車は真っ直ぐにしか進めない駒で、その潔さが好きなのだと祖父は言っていた。肝心の香は頭を使うことがからきしで、将棋のルールも覚えずに育ってしまったけど。そして今も将棋そのものにはちっとも興味が無いから慌てて首を振った。
「やらないよ! そうじゃなくて」
ルールなんてひとつもわからないのに、真っ直ぐに盤を見据える彼の横顔から目が離せない。揺るぎない、と、思った。二回りは上に見える対局相手を前に一歩も怯まず、静かに盤の上を見つめている。
「こいつ、なんて言うの。名前」
話してみたい、と、思った。
聞いてみたかった。ひどく静かな無表情に。意志の強そうな形の良い眉に。
「うん? 船明、だよ。船明樹。しかしまた、えらい珍しい名字だな」
船明樹。
テレビに映る横顔を、じっと見つめていた。樹。ぴんと伸びた背筋に、どっしりと構えた姿にぴったりの名前だなと思った。樹。
──ねえ、樹。
樹の盤上は、どういう場所なの?
* * *
香がはじめて氷の上に立ったのは、親の都合で東京に引っ越してきた年のことだった。
六歳だった。氷の上に立ったのが先だったのか、それともテレビで選手を見たのが先だったのか、香にそのあたりの記憶はない。ただ物心がついた頃にはすっかり夢中になっていて、そして香には幸運にも、才能というものが存在していたらしい。
筋が良いですよ、とコーチに褒められて、母親がすっかりその気になって、香は本格的にスケートをはじめた。
滑るのは楽しくて、褒められるのは嬉しかった。試合に出るぐらいになると、特別に衣装を仕立てて、綺麗な振付をつけてもらえるのがまた嬉しかった。
かわいい、と、すごい、と言ってもらえるのが好きだった。
銀盤の上で、香は、自分が世界で一番可愛いような気がしていた。だってみんなそう言ってくれたのだ。この子は魅せ方を知ってる。天性のものだ。これは特別な才能ですよ、とコーチが言った。嬉しかった。
たくさんの人に見られるのが、応援されるのが、拍手で讃えられるのが好きだった。誰だってそうだろう、と香は思う。注目されたり褒められたりするのが嫌いな人間なんて居ない。そうして周りの期待に応え、たくさんの拍手と歓声に応え続けているうちに、香はいつの間にか、『ジュニア日本代表』という位置に立っていた。
そのときはじめて、あれ、と思った。
テレビや雑誌の取材が入り、香はどんどん注目されるようになっていった。なにせ香は可愛かったし、自分を可愛く見せる方法を知っていたし、大人受けする所作を心得ていた。可愛がられたかったからだ。盤の上にとどまらない世界で、香の名前はどんどん広まっていった。
そして十五歳になった二月、香ははじめて、世界ジュニア選手権の表彰台に立った。
たくさんのカメラに囲まれて、香はすっかり混乱した。新時代のエース。テレビに映る自分の姿にびっくりしたし、そこで解説者がしたり顔で言う台詞に更にびっくりした。
『彼は現在十五歳。ミラノ・コルティナオリンピックの前年、二〇二五年の七月には十七歳で、出場規定をクリアしています。メダルの可能性も充分にある選手だと思いますよ』
へ? と、思わず口に出していた。ミラノ・コルティナオリンピック? メダル? 何言ってるんだこいつ、と、真面目に思った。そもそもオリンピックなんて遠い先の話だ。そのうえフィギュアスケート男子は現在黄金期と呼ばれるほど人材豊富で、ミラノ・コルティナオリンピック開催時の大本命は、なんといっても現在のエース、オリンピックのときには二十三歳という丁度いい年齢を迎える白神(しらかみ)一夏(いつか)に決まっている。
(そう。白神さんがいるんだから)
どの世界にも『生きた伝説』というものがいるのなら、男子フィギュアスケートにおけるそれは、白神一夏という名前をしている。美形というより美男子と言ったほうがいいような顔立ちに、すらりと手足の伸びた長身。トゥループ、サルコウ、ループ、フリップの四種類の四回転を武器に戦う彼は、とにかく失敗しない『ミスター・パーフェクト』として、ショートプログラム・フリープログラム・トータルのすべてで歴代記録を更新した、既に神格化されているとすら言えるスケーターだった。
そんな彼を筆頭に、男子フィギュアスケート界には世界でもトップクラスの選手が既に大勢存在している。香がオリンピックを目指すにしても、それはミラノ・コルティナではなくその四年後になるだろう、と。
そう漠然と思っていたのに、翌日、香はコーチに言われた。
『四回転の練習をトレーニングに組み込みましょう。貴方は男の子にしては成長がはやいほうだし、体力もある。オリンピックを目指せるわ』
嫌だと言える雰囲気ではなかった。
無理だろう、とは思っていたが、そこまで積極的に拒みたいわけでもなかった。四回転が跳べるように慣れば注目度は上がるし、より沢山の人に見てもらえる。香は注目されるのが好きだ。視線を浴びるのも、万雷の拍手を浴びるのも、頑張ってと手を振られるのも、可愛いと黄色い声を上げられるのも。だからそのときは、あまり深く考えていなかった。
樹のことを知ったのもちょうどその時期だ。
プロの世界で戦っている彼に刺激を受けた、のかもしれない。ともかく彼のことを知って、やってみようと言う気になった。オリンピックを目指す。まず世界ジュニアで表彰台のてっぺんを。スケーティングに磨きをかけ、四回転ジャンプの練習を増やし、体力づくりのメニューを加えた。はじめて、練習がきついと思った。元から甘いものは食べ過ぎるなと言われていたけれど、一切制限されるようになったのもキツかった。口に入れるもの全部をコントロールされていたのだ。少し後悔したけど、回り始めた歯車はもう、香ひとりでは止められなかった。
そして一年は、見る間に過ぎた。
ジュニア・グランプリファイナルで三位入賞。十五歳の誕生日を迎え、世界ジュニア選手権に出場した。
結果は、二位だった。
ジャンプにひとつ、ミスが出たのだ。後半の最初に組み込んだ四回転ジャンプ。基礎点が大きいぶん損失も大きく、香の手には銀色のメダルが齎された。去年より一つ、色の良くなったメダル。十分な成果だろうと思って、インタビューを受けて、驚いた。
彼らの目は、香を責めていた。
え、と、きょとんとするような気分になった。ひとつミスがあって、銀メダルで、でも香は満足していた。そのひとつのミス以外は上手く滑れたと思ったし、ステップだって上手く踏めた。表彰台のてっぺんじゃないけど、充分に出しきれた演技だったのだ。充分じゃないか、と、香は思った。
なんでそんな顔するの。俺、綺麗だったでしょう?
けれども彼らは、香の口から『金メダル』の言葉を引き出したがった。一番じゃないメダルの色に思うところがあるかと尋ね、次の目標はなにかと尋ねた。
そうか、と。
納得し、己の身体を包むひんやりとしたものに、はじめて気がついた。そうか。そうなのか。
(……勝たないと、だめなんだ)
その、瞬間に。
香は己の立っている場所が、氷の上が、銀色の盤上が──とほうもなくつめたい、ひどく孤独な場所であるように思えた。
それからの一年もまた勝ちきれず、銀色と銅色のメダルを増やすだけに終わった香は、それでもオリンピックに向けて、シニアへと競技の軸足を移すことになった。
(だから、……会いたいって、思ったんだ。会って、話を聞いてみたかった。俺と同い年で、多分、俺よりずっとつめたい場所にいるひと……)
愛想のないXに偶然上げられた写真がどうやら近所の桜並木らしいと気付いたとき、ばかみたいだけど、運命だなんて思ったのだ。居てもたってもいられなくなって、たぶん朝の写真だろうと見当をつけて、ランニングのふりをして家を出た。
そうして満開の桜の下で、運命みたいに、彼を見つけた。
(テレビとかネットとかで見るのと全然違って、……びっくりした。無表情だけど無口ってほどじゃなくて、俺を見てぽかんってして、……そう、俺のことを、知らなかったんだ。そんな気はしてたけど。無口なんじゃなくて、人が苦手なんだって直ぐにわかった。喋るのが苦手で)
はじめて、樹が話しかけてきた時のことを思い出す。
(可愛かったな)
不本意です、と、顔全体に書いてあるみたいだった。予想していたのと全然違った。もっと超然としているのかと思っていたらそんなことは全然なくて、樹はただの、人付き合いが苦手な、無愛想な高校生だった。香のやることなすことに、いちいちうろたえるのが可愛かった。いかにも人慣れしてません、みたいな、誰とも猫みたいで。
だからすぐ、最初の目的は忘れてしまった。
(可愛かったんだ。……ああ、なんだ、って。ちょっと、ほっとした。普通のやつじゃん、って。たまに、ひやっとすることはあったけど……)
つめたい世界に住んでいる、と、思い出させられる会話はあった。彼の強さを、精神的強靭さを見せつけられることもあったけれど、シーズンが始まる前までは、気にすることなく話して居られた。今思えばおかしな話だ。香が知りたかったのは、彼の、そちら側の部分であったはずなのに。
けれどもシーズンが始まると、そのつめたさは、一気に香を包み込んで押し流した。
シニア初挑戦。オリンピックシーズン。結果が強く要求されるシーズンは、香にとってはじめての世界だった。前哨戦となるネーベルホルン杯で、はじめて取り入れた四回転ループはどうにか着氷したものの、コンビネーションジャンプを纏めきれずに五位に終わった。
(なんだ、これ)
その頃から、感じたことのない苦しさを、腹の中に抱え込む日が増えた。じくじくとしたそれは正体が知れぬまま香の精神を蝕み、眠れない夜が重なった。ぎゅっと己の身体を抱いても、底冷えするようなつめたさを感じた。
練習でしか解消されないたぐいの不安だ、と。
コーチは言って、香はそれに納得した。不安。そうだ。求められる結果の大きさに比例して不安が肥大しているのだ、と思った。香は一層練習に打ち込み、それと同時に、こっそりとチェックしている樹の戦績で、彼が新人王戦というトーナメントで勝ち進み、決勝を迎えていることを知った。
三番勝負。一勝一敗。最後の一局は、偶然にも、香にとってのグランプリシリーズ初戦、スケート・フランスと同じ日程だった。
つめたい戦場の香りがする。
その張り詰めた、凛とした、──怖いものなんてなにもないみたいな横顔が、怖かった。彼の強さを見ていると、香は、己の弱さが引きずり出されるような感じがしたのだ。腹の奥がぐるぐるとして、苦しくて、手足がつめたくなるような感じがした。
(いやだ。……だってそんなの、怖いよ)
思い知らされたく、なかったのだ。
樹は強く、香は弱かった。
それはつまり、香が、本来なら、この場所に立っていていい人間ではないということだった。
一人で戦えもしないくせに、こんな場所にいるのが悪いのだ、と。
樹はもちろん、そんなことを言ったりしない。樹は無愛想ではっきりモノを言うけれど、その厳しさを他人に向けることはなかった。彼が香を応援してくれなかったのは彼の誠実さの現れだったし、事実として、彼が香に向ける気遣いは、ほとんど香を応援してくれているようなものだった。
だから、すべての問題は、香の側にある。
そうして、樹が新人王を獲得した日、香は二つのジャンプで転倒し──オリンピック出場への選考基準の一つである『グランプリ・ファイナルへの出場』を、初戦にして、ほぼ絶望的なものとした。