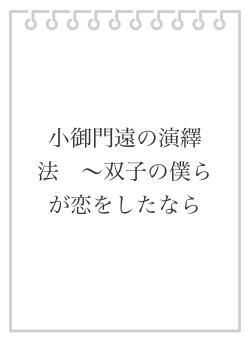新人王戦決勝の勝負は、一局目を樹が、二局目を沓谷が制して、第三局までもつれ込んだ。
大阪に発つ日の朝、樹は香に会えなかった。すっかり忙しくなった香が、また海外に飛んでいたからだ。
(……元気、なかったよな)
決勝戦三番勝負の一局目、勝って帰った樹の数日後に帰国した香の顔色は、明らかに冴えないものだった。
『おめでと、樹。樹はやっぱり、強いんだねえ』
樹の側の結果は、メッセージで『勝った』とだけ伝えていた。試合があると言った以上、報告するのが義務だろうと思ったからだ。香の側からの返信はなかった。
お前は、と。
聞くのが正しいのか、聞かない気遣いが必要なのか、その判断すらつかない己に愕然とした。何か言うべきだ、と思ったけれど何も言えなくて、ドイツはもう寒かったよー、と当り障りのないことを言う香に相槌しか打てないでいるうちに、尋ねるタイミングを完全に逸した。
そうこうしているうちに二局目で負けて、樹の側に余裕がなくなった。
負け、は、駄目だ。樹は負けるのが上手くない。負け、という事実に付き合うのが上手くないのだ。プロ棋士の勝率はトップ棋士でも約七割、勝ち続けるということなど当然あり得ない。
それでも『負け』は、樹の精神からあらゆる余裕を奪っていく。
日課は続けていたものの、沓谷との対局のことが頭から離れない樹と、どこか悄然とした香の間には、今までにない溝が存在した。次はカナダだ、と言った香といつの間にか試合前の習慣になった握手は交わしたけれど、その手は相変わらず、否、もしかしたらあの日よりもずっとつめたく冷えきっていた。
(って、今更気付いてもどうしようもねえけど)
メッセージを送ろうにも、何と送ればいいのかわからなかった。頑張れと言われるのが嬉しい、と言っていた香相手なのだからただ一言そう言えばいい、と、わかっていたのにできなかった。
ひとりだ、と。そしてそれがさみしい、と、香は言う。
樹はそれに、上っ面であろうとも、声を掛けてやることができないのだ。どうしても。
「船明」
声を掛けられて、はっと顔を上げた。
「沓谷さん」
関西将棋会館の、控室だった。一週間ぶりの沓谷は相変わらず穏やかな顔をしていたけれど、その瞳は少し疲れているように見えた。当たり前だ、と、樹は思う。
今この局面に至って、平静な顔をし続けていられるものなど居ない。
一勝一敗。今日勝ったほうが『新人王』だ。
それでも沓谷は、樹に向かって微笑みかける。樹は軽く頭を下げて、それからふと思い立って口を開いた。
「……沓谷さん」
ん、と、樹の側が話し始めたことに驚いたように、沓谷が軽く目を見開く。
「前、『新人王がどうとかより、俺と打ちたい』って言ってましたけど」
沓谷のことが、苦手だった。
棋風が、ではない。盤の上に苦手意識を持ち込むのは愚かなことだった。苦手だ、と思うから苦手になる、という側面はたしかに存在して、だから樹は誰に対しても、人間と将棋を切り離して考えていたいと思う。
樹は、沓谷雪人という人間が苦手だった。
「今でも、そう思ってますか」
樹がそこに居るだけで周りの劣等感を刺激するなら、沓谷と向かい合っているとき、樹はそれこそ劣等感に近いものを抱くのだ。
こんなふうに強くいられる、と言う事実は、樹の神経をささくれ立たせる。ひとりであることに劣等感を抱いたことはないけれど、ひとりでないことが強さに繋がる可能性を、樹は否定しきれない。そして沓谷を目前に置くと、その差を、ひとりである樹とひとりではない沓谷の差を、樹はどうしても強く意識せざるを得なくなるのだ。
奨励会に所属しながら有名大学に進学した彼は、大学での友人も多いと聞いた。棋士仲間の友人も当然多い彼は、対戦相手に気さくに声を掛け、インタビューに卒なく答え、ファンサービスにも熱心で、そのすべてが自然体であるように見せている。
銀縁の眼鏡の奥、ただ柔和さを讃える瞳をじっと見る。沓谷はきょとんと目と瞬き、それからくっと、ひどく楽しそうに笑って口元を抑えた。
「……船明」
「はい」
「お前、ほんと……この局面で、聞くか普通?」
砕けた口調が、珍しい。くつくつと喉を鳴らして笑う沓谷に、樹は答えた。
「今だからです。終わってから聞いたら、ただの嫌味ですから」
「いやお前、そんなこと言ったら、今言うのは挑発だろう?」
終わってから、つまり樹が勝ってからこんなことを尋ねたら、『負けた今でも同じことが言えますか』という意味にしかなり得ない。当たり前に勝つ気なんだもんなあ、と沓谷は笑って、笑いすぎてずれた眼鏡の位置を直して、やっぱり朗らかに、そう、嫌味なぐらいに朗らかに笑った。
「当たり前だろ。……俺はね、船明」
笑みの形に細められた目。真っ直ぐにこちらを見る瞳に、樹はふと、気がついた。
「お前には、絶対に負けたくない」
そうだ、この人はいつだって、真っ直ぐな眼差しを樹に向けていた。歳だって随分違うのに、沓谷はそう、逆川のように、樹を庇護しようとしたりしなかった。
「お前にだけは、勝ちたいんだ。だから、相手がお前で嬉しい。本心だよ、船明」
そして沓谷は、天才だとか神童だとか敵わないとか、そういう一切を口にしなかった。それはつまり沓谷が、樹を恐れなかった、或いは、恐れまいと思っていたということだ。
(……そうか)
そうして、あまりに今更に、樹は気がついた。
(このひとは、……柾に、似てるのか)
似ている──というだけでは、足りなかった。樹はやっと、沓谷に対する苦手意識の根幹にあるものがなんなのかに気がついた。
沓谷は、柾のイフだった。誰とも距離を置く樹とは正反対の、誰からも好かれる兄に、沓谷はよく似ていた。故に、樹は、『柾がもし将棋を続けていたら』『柾がもし、樹の強さを恐れないままでいてくれたら』の──樹が奪ってしまった、あるいは、樹が柾に願っていた柾のイフを、沓谷に見ずにはいられなかった。そして、だから樹は、彼を直視するのが恐ろしく──彼と対局するのが、恐ろしかったのだ。
けれども、と、すっきりした気持ちで樹は思った。
彼はきっと、柾のようにはならないだろう。
それ以上のことは──すごい、とか、そういうことは、思わないようにした。対戦の直前に相手に敬服するなんてそんなこと、絶対にあってはならないことだと知っていた。
そうして、対局がはじまった。
さみしい、とか。ひとりきりだ、とか。
思ったことがなかった。九かける九の盤の上で、樹はいつだってひとりきりだ。
誰だってそうなのだと、思っていた。
ここはつめたい戦場だ。九かける九の盤の上で、誰もがあたりまえにひとりきりだ。誰の助けも借りられない。運のせいにもできない。誰のせいにもできない。勝利も敗北も己ひとりの責任でしかない──樹が立っているのは、そういうつめたい盤上だった。
誰も樹を、助けてなんてくれない。
だから、応援なんて意味が無い。掛けられた言葉も託された思いも、盤上の展開を見守る誰かの視線も、樹の勝利を連れてはこない。勝負を決めるのは当たり前に応援の過多でなく、背負っているものの重さでもなく、捨てたものの数ではなく、これまで歩んできた道のりでもない。
勝利とは、すべての要素から独立した事象なのだ。このつめたい戦場で、勝利を連れてくるのは強さだけだ。
(……って)
ぱちん、と。
沓谷が駒を指す音がする。静かでつめたい盤上に、樹と沓谷だけがいる。
(思ってた、し。多分それは、正しいだろう。盤上に持ち込めるのは自分自身だけで、誰の声も届かない。誰の祈りも意味は無い。ひとりきりで、俺は、そう、それがさみしくなんてない。当たり前だからだ。そして──たぶん、俺が、『ひとりきり』であることを、ちっとも怖いと思わないから)
人々が樹に抱く劣等感の根源は、すべての発露はつまり、その恐れのなさにあるのだ。樹は当たり前にひとりきりで、ひとりきりであることを、恐れない。盤の上であろうとなかろうと、樹はごく当たり前にひとりきりだった。
孤独であることを恐れるのは、本来、人間という動物の性なのだろう。だからある意味では、樹はひととして欠落している。『なんにも怖くみたいな顔』。だから人は樹の、そういうところが恐ろしいのだ。
今樹の目の前にいるのは、盤を挟んで向かい合っているのは、そういう樹を恐れない、恐れまいと思っている沓谷だった。
不思議な感じがした。
沓谷への苦手意識の源泉が──柾と似ている、という事実がわかった瞬間から、樹にとっての沓谷が、やっと沓谷という輪郭を得たようだった。柾とは違う、沓谷という『棋士』。それはつまり、樹が、他人にそれがわかるほどの興味を抱いたという証拠でもあった。
少しずつ、ほぐれるように、周りのことが見えはじめているような感覚があった。
それがどうしてなのか、樹にはわかった。己と向き合うためには他人が必要で、ひとりきりだった樹がちっともやってこなかった、やる必要も感じていなかったそれをさせたのは、ただひとりだとわかっている。
盤面は未だ、想定のうちに収まっている。研究済みの形だ。勝つ、と思う。勝てる、でも、負けない、でもなくて。
樹は勝つ。そう決めて、ひとりきりで、ここにいる。
ひとりだ、と。それがさみしいと、香は言った。樹はそれに頷いてやれなかった。
なあ香。さみしくたって、恐ろしくたって。そういう場所なんだ。盤上はつめたい戦場だ。ひとりきりなんだ。どんなにさみしくたって。
お前は盤上に居てくれない。俺はお前の戦場に居てやれない。
(……でも)
向かい合っている沓谷を、ちらりと見上げた。こちらの視線には気づくことなく、静かに盤面を見下ろしている。彼は多分沢山のひとの期待を背負って、大勢に応援されて此処に座っている。その過多が何かに影響するなんて、樹は勿論思わないけれど。
思わないけれど、それが彼の『強さ』を高めている可能性は、ごく当たり前にあるような気がした。応援そのものに価値はないけれど、応援される側が変わる可能性はあるのだから。そして樹は、その、己にはないものを沓谷が持っているということを、あまり怖くは思わなかった。
勝ってね、と。
香の声が、耳に聞こえた。
ひとりきりで、さみしくなどなくて、でもそこに、目の前に、絶対に負けたくない相手がいるときに。
(そうか、……こういうときに、思い出すのか)
──ひとりじゃない、と。
たぶんそのとき樹は、盤の上でもそれ以外でも──ずいぶん久しぶりに、そう思った。
* * *
対局は、日が暮れた頃に終了した。
ホテルに戻り、きっちりと着込んだ制服の襟元の釦を外す。明日は新幹線の始発で学校に行かねばならないから、今日ははやく休んだほうがいい。そうわかっているのに、奇妙に高揚した精神が、樹から休息を遠ざけていた。
新人王。
いずれ至るべき場所への通過点にすぎない、と、どれだけ自分に言い聞かせたところで、どうしたって気分は高揚した。
詰みが見えたときは、手が震えた。勝利を確信しても、ひとつでも指し間違えればすぐに勝敗は逆転する。一手一手確認しながら詰みを辿る作業は脳が焼ききれるようで、途中からは胃のあたりがぐるぐる疼いてきて、相手が投了を口にしたときには心底ほっとした。
(新人王。──まだ、スタート地点だけど)
名人位を獲得した棋士の殆どが手にしているタイトルを、樹もまたこの手に掴んだのだ。落ち着けというほうが無理な話だった。ごろりとベッドに寝転んでも興奮が覚めることはなく、樹は浮足立った心地を持て余し、部屋の静けさを厭ってテレビの電源を入れた。
テレビなんて滅多に見ることのない樹でも、そのとき、手持ち無沙汰な心地を収める方法がそれだけだった。……とはいえ、偶然にしてはできすぎていたから、もしかしたらその行動は、いつか、運命と呼ばれる類のものであったのかもしれない。
ともあれそのときの樹は何も知らぬままで、画面に映し出されたのは、奇妙に白い映像だった。
何だ、と思い、氷だ、と思う。
鼻先に、つめたい香りが蘇った。
画面の真ん中に、ひとりの少年が佇んでいる。
全身を包む黒い服、胸元にだけ鮮烈な赤。まだその画面が表すものがうまく飲み込めないでいる樹は、一気に顔へと寄せられたカメラ、大きく映し出された少年の顔に、頭を殴られるみたいな衝撃を覚えた。
大阪に発つ日の朝、樹は香に会えなかった。すっかり忙しくなった香が、また海外に飛んでいたからだ。
(……元気、なかったよな)
決勝戦三番勝負の一局目、勝って帰った樹の数日後に帰国した香の顔色は、明らかに冴えないものだった。
『おめでと、樹。樹はやっぱり、強いんだねえ』
樹の側の結果は、メッセージで『勝った』とだけ伝えていた。試合があると言った以上、報告するのが義務だろうと思ったからだ。香の側からの返信はなかった。
お前は、と。
聞くのが正しいのか、聞かない気遣いが必要なのか、その判断すらつかない己に愕然とした。何か言うべきだ、と思ったけれど何も言えなくて、ドイツはもう寒かったよー、と当り障りのないことを言う香に相槌しか打てないでいるうちに、尋ねるタイミングを完全に逸した。
そうこうしているうちに二局目で負けて、樹の側に余裕がなくなった。
負け、は、駄目だ。樹は負けるのが上手くない。負け、という事実に付き合うのが上手くないのだ。プロ棋士の勝率はトップ棋士でも約七割、勝ち続けるということなど当然あり得ない。
それでも『負け』は、樹の精神からあらゆる余裕を奪っていく。
日課は続けていたものの、沓谷との対局のことが頭から離れない樹と、どこか悄然とした香の間には、今までにない溝が存在した。次はカナダだ、と言った香といつの間にか試合前の習慣になった握手は交わしたけれど、その手は相変わらず、否、もしかしたらあの日よりもずっとつめたく冷えきっていた。
(って、今更気付いてもどうしようもねえけど)
メッセージを送ろうにも、何と送ればいいのかわからなかった。頑張れと言われるのが嬉しい、と言っていた香相手なのだからただ一言そう言えばいい、と、わかっていたのにできなかった。
ひとりだ、と。そしてそれがさみしい、と、香は言う。
樹はそれに、上っ面であろうとも、声を掛けてやることができないのだ。どうしても。
「船明」
声を掛けられて、はっと顔を上げた。
「沓谷さん」
関西将棋会館の、控室だった。一週間ぶりの沓谷は相変わらず穏やかな顔をしていたけれど、その瞳は少し疲れているように見えた。当たり前だ、と、樹は思う。
今この局面に至って、平静な顔をし続けていられるものなど居ない。
一勝一敗。今日勝ったほうが『新人王』だ。
それでも沓谷は、樹に向かって微笑みかける。樹は軽く頭を下げて、それからふと思い立って口を開いた。
「……沓谷さん」
ん、と、樹の側が話し始めたことに驚いたように、沓谷が軽く目を見開く。
「前、『新人王がどうとかより、俺と打ちたい』って言ってましたけど」
沓谷のことが、苦手だった。
棋風が、ではない。盤の上に苦手意識を持ち込むのは愚かなことだった。苦手だ、と思うから苦手になる、という側面はたしかに存在して、だから樹は誰に対しても、人間と将棋を切り離して考えていたいと思う。
樹は、沓谷雪人という人間が苦手だった。
「今でも、そう思ってますか」
樹がそこに居るだけで周りの劣等感を刺激するなら、沓谷と向かい合っているとき、樹はそれこそ劣等感に近いものを抱くのだ。
こんなふうに強くいられる、と言う事実は、樹の神経をささくれ立たせる。ひとりであることに劣等感を抱いたことはないけれど、ひとりでないことが強さに繋がる可能性を、樹は否定しきれない。そして沓谷を目前に置くと、その差を、ひとりである樹とひとりではない沓谷の差を、樹はどうしても強く意識せざるを得なくなるのだ。
奨励会に所属しながら有名大学に進学した彼は、大学での友人も多いと聞いた。棋士仲間の友人も当然多い彼は、対戦相手に気さくに声を掛け、インタビューに卒なく答え、ファンサービスにも熱心で、そのすべてが自然体であるように見せている。
銀縁の眼鏡の奥、ただ柔和さを讃える瞳をじっと見る。沓谷はきょとんと目と瞬き、それからくっと、ひどく楽しそうに笑って口元を抑えた。
「……船明」
「はい」
「お前、ほんと……この局面で、聞くか普通?」
砕けた口調が、珍しい。くつくつと喉を鳴らして笑う沓谷に、樹は答えた。
「今だからです。終わってから聞いたら、ただの嫌味ですから」
「いやお前、そんなこと言ったら、今言うのは挑発だろう?」
終わってから、つまり樹が勝ってからこんなことを尋ねたら、『負けた今でも同じことが言えますか』という意味にしかなり得ない。当たり前に勝つ気なんだもんなあ、と沓谷は笑って、笑いすぎてずれた眼鏡の位置を直して、やっぱり朗らかに、そう、嫌味なぐらいに朗らかに笑った。
「当たり前だろ。……俺はね、船明」
笑みの形に細められた目。真っ直ぐにこちらを見る瞳に、樹はふと、気がついた。
「お前には、絶対に負けたくない」
そうだ、この人はいつだって、真っ直ぐな眼差しを樹に向けていた。歳だって随分違うのに、沓谷はそう、逆川のように、樹を庇護しようとしたりしなかった。
「お前にだけは、勝ちたいんだ。だから、相手がお前で嬉しい。本心だよ、船明」
そして沓谷は、天才だとか神童だとか敵わないとか、そういう一切を口にしなかった。それはつまり沓谷が、樹を恐れなかった、或いは、恐れまいと思っていたということだ。
(……そうか)
そうして、あまりに今更に、樹は気がついた。
(このひとは、……柾に、似てるのか)
似ている──というだけでは、足りなかった。樹はやっと、沓谷に対する苦手意識の根幹にあるものがなんなのかに気がついた。
沓谷は、柾のイフだった。誰とも距離を置く樹とは正反対の、誰からも好かれる兄に、沓谷はよく似ていた。故に、樹は、『柾がもし将棋を続けていたら』『柾がもし、樹の強さを恐れないままでいてくれたら』の──樹が奪ってしまった、あるいは、樹が柾に願っていた柾のイフを、沓谷に見ずにはいられなかった。そして、だから樹は、彼を直視するのが恐ろしく──彼と対局するのが、恐ろしかったのだ。
けれども、と、すっきりした気持ちで樹は思った。
彼はきっと、柾のようにはならないだろう。
それ以上のことは──すごい、とか、そういうことは、思わないようにした。対戦の直前に相手に敬服するなんてそんなこと、絶対にあってはならないことだと知っていた。
そうして、対局がはじまった。
さみしい、とか。ひとりきりだ、とか。
思ったことがなかった。九かける九の盤の上で、樹はいつだってひとりきりだ。
誰だってそうなのだと、思っていた。
ここはつめたい戦場だ。九かける九の盤の上で、誰もがあたりまえにひとりきりだ。誰の助けも借りられない。運のせいにもできない。誰のせいにもできない。勝利も敗北も己ひとりの責任でしかない──樹が立っているのは、そういうつめたい盤上だった。
誰も樹を、助けてなんてくれない。
だから、応援なんて意味が無い。掛けられた言葉も託された思いも、盤上の展開を見守る誰かの視線も、樹の勝利を連れてはこない。勝負を決めるのは当たり前に応援の過多でなく、背負っているものの重さでもなく、捨てたものの数ではなく、これまで歩んできた道のりでもない。
勝利とは、すべての要素から独立した事象なのだ。このつめたい戦場で、勝利を連れてくるのは強さだけだ。
(……って)
ぱちん、と。
沓谷が駒を指す音がする。静かでつめたい盤上に、樹と沓谷だけがいる。
(思ってた、し。多分それは、正しいだろう。盤上に持ち込めるのは自分自身だけで、誰の声も届かない。誰の祈りも意味は無い。ひとりきりで、俺は、そう、それがさみしくなんてない。当たり前だからだ。そして──たぶん、俺が、『ひとりきり』であることを、ちっとも怖いと思わないから)
人々が樹に抱く劣等感の根源は、すべての発露はつまり、その恐れのなさにあるのだ。樹は当たり前にひとりきりで、ひとりきりであることを、恐れない。盤の上であろうとなかろうと、樹はごく当たり前にひとりきりだった。
孤独であることを恐れるのは、本来、人間という動物の性なのだろう。だからある意味では、樹はひととして欠落している。『なんにも怖くみたいな顔』。だから人は樹の、そういうところが恐ろしいのだ。
今樹の目の前にいるのは、盤を挟んで向かい合っているのは、そういう樹を恐れない、恐れまいと思っている沓谷だった。
不思議な感じがした。
沓谷への苦手意識の源泉が──柾と似ている、という事実がわかった瞬間から、樹にとっての沓谷が、やっと沓谷という輪郭を得たようだった。柾とは違う、沓谷という『棋士』。それはつまり、樹が、他人にそれがわかるほどの興味を抱いたという証拠でもあった。
少しずつ、ほぐれるように、周りのことが見えはじめているような感覚があった。
それがどうしてなのか、樹にはわかった。己と向き合うためには他人が必要で、ひとりきりだった樹がちっともやってこなかった、やる必要も感じていなかったそれをさせたのは、ただひとりだとわかっている。
盤面は未だ、想定のうちに収まっている。研究済みの形だ。勝つ、と思う。勝てる、でも、負けない、でもなくて。
樹は勝つ。そう決めて、ひとりきりで、ここにいる。
ひとりだ、と。それがさみしいと、香は言った。樹はそれに頷いてやれなかった。
なあ香。さみしくたって、恐ろしくたって。そういう場所なんだ。盤上はつめたい戦場だ。ひとりきりなんだ。どんなにさみしくたって。
お前は盤上に居てくれない。俺はお前の戦場に居てやれない。
(……でも)
向かい合っている沓谷を、ちらりと見上げた。こちらの視線には気づくことなく、静かに盤面を見下ろしている。彼は多分沢山のひとの期待を背負って、大勢に応援されて此処に座っている。その過多が何かに影響するなんて、樹は勿論思わないけれど。
思わないけれど、それが彼の『強さ』を高めている可能性は、ごく当たり前にあるような気がした。応援そのものに価値はないけれど、応援される側が変わる可能性はあるのだから。そして樹は、その、己にはないものを沓谷が持っているということを、あまり怖くは思わなかった。
勝ってね、と。
香の声が、耳に聞こえた。
ひとりきりで、さみしくなどなくて、でもそこに、目の前に、絶対に負けたくない相手がいるときに。
(そうか、……こういうときに、思い出すのか)
──ひとりじゃない、と。
たぶんそのとき樹は、盤の上でもそれ以外でも──ずいぶん久しぶりに、そう思った。
* * *
対局は、日が暮れた頃に終了した。
ホテルに戻り、きっちりと着込んだ制服の襟元の釦を外す。明日は新幹線の始発で学校に行かねばならないから、今日ははやく休んだほうがいい。そうわかっているのに、奇妙に高揚した精神が、樹から休息を遠ざけていた。
新人王。
いずれ至るべき場所への通過点にすぎない、と、どれだけ自分に言い聞かせたところで、どうしたって気分は高揚した。
詰みが見えたときは、手が震えた。勝利を確信しても、ひとつでも指し間違えればすぐに勝敗は逆転する。一手一手確認しながら詰みを辿る作業は脳が焼ききれるようで、途中からは胃のあたりがぐるぐる疼いてきて、相手が投了を口にしたときには心底ほっとした。
(新人王。──まだ、スタート地点だけど)
名人位を獲得した棋士の殆どが手にしているタイトルを、樹もまたこの手に掴んだのだ。落ち着けというほうが無理な話だった。ごろりとベッドに寝転んでも興奮が覚めることはなく、樹は浮足立った心地を持て余し、部屋の静けさを厭ってテレビの電源を入れた。
テレビなんて滅多に見ることのない樹でも、そのとき、手持ち無沙汰な心地を収める方法がそれだけだった。……とはいえ、偶然にしてはできすぎていたから、もしかしたらその行動は、いつか、運命と呼ばれる類のものであったのかもしれない。
ともあれそのときの樹は何も知らぬままで、画面に映し出されたのは、奇妙に白い映像だった。
何だ、と思い、氷だ、と思う。
鼻先に、つめたい香りが蘇った。
画面の真ん中に、ひとりの少年が佇んでいる。
全身を包む黒い服、胸元にだけ鮮烈な赤。まだその画面が表すものがうまく飲み込めないでいる樹は、一気に顔へと寄せられたカメラ、大きく映し出された少年の顔に、頭を殴られるみたいな衝撃を覚えた。