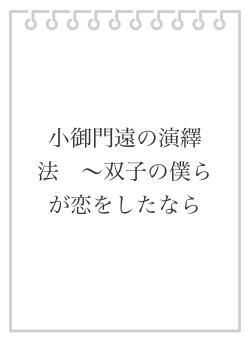一ヶ月の合宿で絞られたらしい香の身体は、ぴんと張った弦かなにかのようだった。柔らかそうだった頬からもまた肉が落ちて、より一層氷めいた印象を樹に与える。
それでも悪戯に微笑めば、香はまるで変わらぬようにも見えた。牛タンとチョコレートを交換し(『樹がどんなに甘党でもこれには音を上げると思う、俺は食べてないけど』と香は言った)、事実甘すぎるそれに目を白黒させる樹を笑う屈託のない顔が、久々に生で見るからか、なんだかチカチカと眩しく見えた。
そうして、夏前と何ら変わらぬ日々は過ぎ──樹が香に告げたのは、暦は九月も半ばに、残暑はそろそろ名残に近くなった日の事だった。
「明日から二日、来ないから」
結局対局の日もその翌日も走る日々を続けて、樹の側がそれを口にするのははじめてだった。香は驚いた顔で目を瞬き、尋ねられる前に樹は続ける。
「明日、大阪で予定……つーか、試合があって。今日行って、明後日に帰る」
新人王戦の、決勝である。
普段の対局は東京・千代田の将棋会館で行われることが多いが、三本勝負で行われるそれは、すべて、大阪にある関西将棋会館で行われる運びになっていた。初日が明日。二局目が再来週で、最終局はその更に一週間後だった。
「試合」
繰り返して、香がようやく飲み込んだ顔になる。一拍遅れて、『なんの?』と聞かれる可能性に気付いてひやりとしたが、香は何も言わなかった。代わりに「明後日……」と呟いて、じわじわと顔を曇らせる。「あー」と唸るように言ってから、香はそっと視線を逸らした。
「明後日から俺、また海外なんだよね……。すれ違いになっちゃうなあ」
帰国して以降、香は明らかに多忙になっていた。もう学校もはじまっているだろうに、そんなに休んで大丈夫なんだろうか、と思いながら尋ねる。
「今度は何処」
「えーっと、ドイツ、の、どっか。移動含めて、一週間かな」
なんともワールドワイドな話である。ていうかどっかって、そんな認識でいいのだろうか?
「また合宿?」
「ううん」
ゆるく振られた首に合わせて、結ばれた尻尾がぱさっと跳ねた。樹ではなく地面を見ながら、香は少し硬い声音で言う。
「俺も、……試合」
朝の空気が、一気に、つめたく張り詰めたような気がした。
ぴりっとした、樹がよく知っている類のつめたさ。僅かに息を呑むと、気づいた香がちらりと視線を寄越して苦笑した。
「あ、いや、大した試合じゃないんだけど。練習に毛が生えたみたいなもんで……そう、だから、楽しみなんだけど。練習の成果が確認できるし」
一瞬だけ瞳が煌めいて、その言葉が嘘ではないことが樹にもわかった。ふわ、と一瞬だけ春めいた空気はけれど、直ぐに「でも」とつめたい否定にかき消される。
「……あー、駄目だ。俺さあ、普段はこんなんだから誤解されるんだけど。実はすげー緊張しいなの! メンタル弱いの!」
それは知らなかった。
そして、意外だった。この樹が振り回されるほどのマイペースなのに。思いが表情に出たのだろう、香は「信じてないな」と可愛くむくれる。そういう顔をするから信じられないわけだけれど、でもおそらく、本当なのだろうとすとんと思った。
くるくる変わる表情の下、マイペースとナルシストで覆い隠した裏側に──というのもすこしおかしいか。マイペースもナルシストも彼の本質で、香は何かを偽るということができる質ではなくて、けれども、見せていない部分はたしかに存在する。そしてその見せていない部分に思いがけない繊細さがある、という事実は、どこか納得できるものであるように思えた。香が返す言葉を探す間に、香はほんとうに少し、もの寂しげな笑みを口元に向ける。
「……だからさ」
さみしくないの、と、聞いてきた顔を思い出した。
そうか、と、納得する思いがあった。香は、さみしいのだ。さみしくて、恐ろしくて、ひとりきりだ、と強く感じる。そしてそれが、ときに、彼の本質を──彼が試合に向かう理由を、覆い隠してしまうのだ。
けれども樹は、そのさみしさが、ひとりきりの恐ろしさが理解できない。なにも言えないままの樹の顔を瞳に映し、香は、さみしさを覆い隠すみたいにぱっと口を開けて、殊更にあっけらかんとした口調で言った。
「だからさ。行く前に、樹の、なんも怖くないみたいな顔見れば、ちょっとは安心できるかもって思ったんだけどなー」
って、なんだその評価は。
「……お前な」
「え? え、待って、俺今すごい褒めたつもりなんだけど!」
その全く悪気のなさそうなところが余計に腹立たしい。『厚顔』或いは『心臓に毛が生えている』と言い換えられる表現がはたしてごく純粋な賛辞に値するのかどうかちょっと考えてみて欲しい、と思ったけれど、己を『緊張しい』と表現する香からしてみたらほんとうに純粋に羨ましいのかもしれない、と愕然とした。まじか。
(それにしたって、『なんにも怖くみたいな顔』とは)
随分と失礼な言い回しで、随分な過大評価を受けたものだと思う。
けれども香にそう見えるなら、そして香がそう思いたいなら別に構わないかという気もした。わたわたと動く香の手を掴んで、その冷たさにびっくりして、掴まれたことにびっくりした顔をする香の顔を見据える。
「へ、何──」
「そう言われても。流石に、顔見せに帰っては来れねえけど」
大阪発の最終新幹線が何時なのか知らないが、対局後に間に合うと言い切れる時間でないことは確かだった。それこそ、千日手になる可能性もあるのだ。終わらせて帰ってくると言えたらいいのに、と、一瞬でも思ったことに驚いた。
「え。あ、うん。それはわかってるっていうか、いや、俺もそこまで我儘じゃないからね!?」
我儘? 樹は香にそんな評価を抱いたことがなかったけれど、この言い回しということは、『我儘だ』と言われ慣れているのだろうか。我儘。正直言われてみたかったが、今は、そしてこれは流石に無理だ。思いながら、樹は言った。
「うん。……だからまあ、今見とけば」
「へ?」
「お前みたいに見応えのある顔じゃねえけど。なんなら触るか?」
十人並みのうえ表情筋が死んでいる樹の顔に価値があるとは思えないが、香が見たいというならいくらでも見ればいいと思う。無表情だからこそ見ると安心する、という言い分は理解できないこともないし。掴んだままだった手を引き寄せて頬に触れさせると、大きく目を見開いた香が、気が抜けたみたいにふにゃっと笑った。
「……なにそれ」
「次善の策」
「難しいこと言わないでよ。え、なにこれ。触る必要なくない?」
言いながらも、香は手を引っ込めなかった。むにっと樹の頬を摘んで、ふへ、と笑う。そうしてしばらくふにふに樹の頬を弄んでから、「ていうか」と笑った顔はもう、いつもの意地悪で悪戯な笑みの香だった。
「ふーん、そっかあ」
相変わらずの変わり身のはやさに、ほっとすると同時にびくっとする。なにか、こんな顔をされるようなことを言っただろうか?
「樹、俺のこと、『見応えのある顔』って思ってたんだ?」
あ、と、思わず目を瞬いた。言ったか? ──たしかに言った。
ふーん、へーえ、とにやにや笑う香に、反論できる言葉がひとつも見つからない。樹に残された選択肢はそうっと視線を逸らすことだけで、香はますます楽しげな声で、「じゃあもっと写真送るから!」と言って笑う。そうしてひとしきりニヤついたのち、香は樹の頬から手を離し、代わりに樹の手をぎゅっと握った。
「……ありがと、樹」
人を気遣ったことがない。
だから樹は、己の行動が正しかったのかを、香の反応でしか計れない。こうして笑ってくれているということは無意味ではなかったのだろうか、と思う樹の前で、香はきゅっと握る手に力を込めた。
「樹はさ、きっと、俺がこんなこと言わなくても大丈夫なんだろうけど」
つめたい手だった。まだつめたいのだ、と思った。樹が手を掴んで頬に触れさせて、表情はいつものものに戻ったけれど、香の手はまだつめたい。
その事実がひんやりと、樹のこころに不安を落とす。けれども香はまるでいつも通りの顔で笑って、明るく朗らかな声音で言った。
「お礼にもならないけど、言わせてよ。……頑張って。勝ってね、樹」