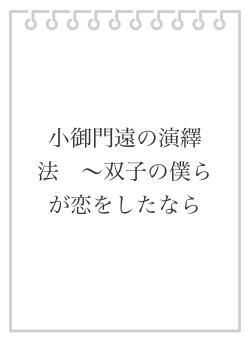香からのメッセージは、二三日に一度、ぽつぽつ届いた。
返信をするときも既読をつけて放置するときもあったが、香は樹の反応の有無を然程気にしなかった。一度やたら気合が入った編みこみに髪飾りをつけて薄化粧まで施したキメ顔が送られてきたときに既読放置したら『感想は!?』という怒ったスタンプ付きの追撃が来たが、『なんの仮装だ』と返したら諦めたらしい。どういう経緯でそんなものを撮る羽目になったのか小一時間問い詰めたいし、なんならその顔は合宿で一緒だとか言う白人の男(ちなみにフランス人らしい)に見せたのかと尋ねたかったが、『どうしてそんなこと聞くの』と言われたときに何も返せないから黙っていた。察せよ。いや察さなくていい。
夏休みは恙無く過ぎていった。子ども向けの将棋イベントに借り出されて熱中症になりかけたり出演したインターネット番組で無愛想さを弄られたりと夏休みらしいトラブルもいくつかあったが、対局成績は順調だった。樹は対局やらそういったイベントやら以外の全ての時間を、無論朝の日課は除いてではあるが、自室でパソコンに向かい合って過ごした。母親が嘆くのも頷ける引きこもりっぷりである。
ふたつあるディスプレイに映しだされているのは、データベース化された対局記録だった。
デジタル化が進化させた数多のものに、ボードゲームは確実に含まれる。嘗ては己の脳で覚えて比較しなければならなかった対局履歴は、今ではクリックひとつで検索できて、その派生もすべて網羅されるのだ。所謂将棋AIの進化も著しく、もはや研究や検討でそれらの力を借りるのは当然を通り越し大前提で、樹も対局料を叩いてかなり高スペックのパソコンを自作している。
そうしてパソコンと向かい合う合間に、或いはイベントや対局へ向かう移動の途中に、樹は香からのメッセージを眺めた。
『あのアニメ今日見終わった! 最終回で号泣して翌日顔腫れたから責任とって』
『で、その顔は?』
あのぱっちりとした目が腫れぼったくなっているのはすこし、いやだいぶ見てみたかったのだが、こののち三日ほど連絡がなかった。どうやら失言だったらしい。
『ちょっと練習行き詰まっててノイローゼになりそうなんだけど、そういうとき樹はどうする?』
『練習する』
『……あーうん樹ってそういう奴だよねわかってた! 練習する!』
見返すだにあまりに素っ気ない返信は我ながらどうかと思うけれど、香は凝りずにメッセージを送り続けてきた。極稀に、ほんとうにたまに、樹からメッセージを送ることもあった。
『牛タン好き?』
『へ? 好きだけど』
『了解』
『いや待って、説明して、あと賞味期限確認して!』
説明はしなかったが賞味期限は確認した。将棋のイベントで仙台に居ますだなんて言えるわけもないし、旅行だなんて言い訳が通用しないぐらいには引きこもりはバレている。買ってから香の食事制限について少し考えたけれど、まあ、甘いモノじゃないし良いだろうと勝手に判断した。よくなかったらそもそもそう言うだろうし。
そんなふうに夏休みを過ごして、新人王戦準決勝の前日、香から、『今日帰った』とメッセージが届いた。
『おかえり』
『明日は朝行くよ!』
『時差ボケは?』
『飛行機でちゃんと寝た』
所謂ドヤ顔風味のスタンプに、それでも少し考えてしまう。少しばかり煮詰まっていたから明日は走らないでおこうか、と思っていた矢先だったし、帰国直後で明らかに疲労しているだろう相手に無理はしてほしくない。どう返事をしたものか、という樹の戸惑いを見透かすみたいに、ぽんとメッセージが追加された。
『でも寝不足だから、もう寝るね。また明日!』
おやすみ、のスタンプ。相変わらずのマイペースに、帰国早々、顔を合わせる前からボディーブローを食らったような気分になった。そうだ香はこういう奴だ──と思うと同時に、なんだか口元がむずむずして手で抑えた。
明日どうやら、一ヶ月ぶりに顔が見られる。
(いやまあ、自撮りで見過ぎてるから、久々って気もしねえけど……)
もうメッセージも増えない画面をぼんやり眺めながら、そうか、と反芻するように考えた。そうか。香はもう日本に居るのか。
明日、会えるのか。
「おい、樹、飯」
その瞬間、ノックもせずに扉が開いて、樹は慌ててLINEの画面を閉じた。勝手に入ってくるな、と文句を言ってやろうとして、扉を開けたままの姿勢でぽかんと目を見開く柾の姿に勢いを削がれて目を瞬く。
「……なんだよ」
驚かれるようなものなんて、なにもないはずだ。普通の高校生の部屋ではないだろうが、普通の棋士の部屋だし、今までだって何度も無断で扉を開けてきた柾だから、見慣れているはずの部屋でもある。樹が訝るような視線を向けると、柾ははっとして目を瞬いた。
「……樹」
「だからなんだよ。飯? すぐ降りるから」
「お前、今」
今? なんだ、と少し考えて、気付いて手元のスマートフォンに視線を落とした。なるほど柾は、樹がディスプレイではなくこちらを見ていたことに驚いたのだ。思わず小さく笑った。
「俺が盤見てないのは、そんなに変か?」
答えを聞かずに立ち上がり、柾のわきをすり抜ける。はっと我に返った柾が、後ろから抱きつくように、樹の首に腕を回してくる。「うお」と流石に足を止めた樹を引き寄せて、軽い口調を装って柾は言った。
「いや、……安心した。とかいって、将棋アプリってオチじゃないよな?」
「……違うって。知り合い」
「将棋の?」
「……違う」
へえ、と、柾はひどくうれしそうに相槌を打った。それ以上は聞いてこないながら、明らかにニヤニヤしている柾に、なんだかむず痒い気持ちになる。
浮かれている。
どうやら自分は、相当明日が楽しみなのだ。メッセージが来る前の、明日の対局を前にしてぐるぐる煮詰まったようになっていた気分は、あっさりとさっぱりと霧散していた。
返信をするときも既読をつけて放置するときもあったが、香は樹の反応の有無を然程気にしなかった。一度やたら気合が入った編みこみに髪飾りをつけて薄化粧まで施したキメ顔が送られてきたときに既読放置したら『感想は!?』という怒ったスタンプ付きの追撃が来たが、『なんの仮装だ』と返したら諦めたらしい。どういう経緯でそんなものを撮る羽目になったのか小一時間問い詰めたいし、なんならその顔は合宿で一緒だとか言う白人の男(ちなみにフランス人らしい)に見せたのかと尋ねたかったが、『どうしてそんなこと聞くの』と言われたときに何も返せないから黙っていた。察せよ。いや察さなくていい。
夏休みは恙無く過ぎていった。子ども向けの将棋イベントに借り出されて熱中症になりかけたり出演したインターネット番組で無愛想さを弄られたりと夏休みらしいトラブルもいくつかあったが、対局成績は順調だった。樹は対局やらそういったイベントやら以外の全ての時間を、無論朝の日課は除いてではあるが、自室でパソコンに向かい合って過ごした。母親が嘆くのも頷ける引きこもりっぷりである。
ふたつあるディスプレイに映しだされているのは、データベース化された対局記録だった。
デジタル化が進化させた数多のものに、ボードゲームは確実に含まれる。嘗ては己の脳で覚えて比較しなければならなかった対局履歴は、今ではクリックひとつで検索できて、その派生もすべて網羅されるのだ。所謂将棋AIの進化も著しく、もはや研究や検討でそれらの力を借りるのは当然を通り越し大前提で、樹も対局料を叩いてかなり高スペックのパソコンを自作している。
そうしてパソコンと向かい合う合間に、或いはイベントや対局へ向かう移動の途中に、樹は香からのメッセージを眺めた。
『あのアニメ今日見終わった! 最終回で号泣して翌日顔腫れたから責任とって』
『で、その顔は?』
あのぱっちりとした目が腫れぼったくなっているのはすこし、いやだいぶ見てみたかったのだが、こののち三日ほど連絡がなかった。どうやら失言だったらしい。
『ちょっと練習行き詰まっててノイローゼになりそうなんだけど、そういうとき樹はどうする?』
『練習する』
『……あーうん樹ってそういう奴だよねわかってた! 練習する!』
見返すだにあまりに素っ気ない返信は我ながらどうかと思うけれど、香は凝りずにメッセージを送り続けてきた。極稀に、ほんとうにたまに、樹からメッセージを送ることもあった。
『牛タン好き?』
『へ? 好きだけど』
『了解』
『いや待って、説明して、あと賞味期限確認して!』
説明はしなかったが賞味期限は確認した。将棋のイベントで仙台に居ますだなんて言えるわけもないし、旅行だなんて言い訳が通用しないぐらいには引きこもりはバレている。買ってから香の食事制限について少し考えたけれど、まあ、甘いモノじゃないし良いだろうと勝手に判断した。よくなかったらそもそもそう言うだろうし。
そんなふうに夏休みを過ごして、新人王戦準決勝の前日、香から、『今日帰った』とメッセージが届いた。
『おかえり』
『明日は朝行くよ!』
『時差ボケは?』
『飛行機でちゃんと寝た』
所謂ドヤ顔風味のスタンプに、それでも少し考えてしまう。少しばかり煮詰まっていたから明日は走らないでおこうか、と思っていた矢先だったし、帰国直後で明らかに疲労しているだろう相手に無理はしてほしくない。どう返事をしたものか、という樹の戸惑いを見透かすみたいに、ぽんとメッセージが追加された。
『でも寝不足だから、もう寝るね。また明日!』
おやすみ、のスタンプ。相変わらずのマイペースに、帰国早々、顔を合わせる前からボディーブローを食らったような気分になった。そうだ香はこういう奴だ──と思うと同時に、なんだか口元がむずむずして手で抑えた。
明日どうやら、一ヶ月ぶりに顔が見られる。
(いやまあ、自撮りで見過ぎてるから、久々って気もしねえけど……)
もうメッセージも増えない画面をぼんやり眺めながら、そうか、と反芻するように考えた。そうか。香はもう日本に居るのか。
明日、会えるのか。
「おい、樹、飯」
その瞬間、ノックもせずに扉が開いて、樹は慌ててLINEの画面を閉じた。勝手に入ってくるな、と文句を言ってやろうとして、扉を開けたままの姿勢でぽかんと目を見開く柾の姿に勢いを削がれて目を瞬く。
「……なんだよ」
驚かれるようなものなんて、なにもないはずだ。普通の高校生の部屋ではないだろうが、普通の棋士の部屋だし、今までだって何度も無断で扉を開けてきた柾だから、見慣れているはずの部屋でもある。樹が訝るような視線を向けると、柾ははっとして目を瞬いた。
「……樹」
「だからなんだよ。飯? すぐ降りるから」
「お前、今」
今? なんだ、と少し考えて、気付いて手元のスマートフォンに視線を落とした。なるほど柾は、樹がディスプレイではなくこちらを見ていたことに驚いたのだ。思わず小さく笑った。
「俺が盤見てないのは、そんなに変か?」
答えを聞かずに立ち上がり、柾のわきをすり抜ける。はっと我に返った柾が、後ろから抱きつくように、樹の首に腕を回してくる。「うお」と流石に足を止めた樹を引き寄せて、軽い口調を装って柾は言った。
「いや、……安心した。とかいって、将棋アプリってオチじゃないよな?」
「……違うって。知り合い」
「将棋の?」
「……違う」
へえ、と、柾はひどくうれしそうに相槌を打った。それ以上は聞いてこないながら、明らかにニヤニヤしている柾に、なんだかむず痒い気持ちになる。
浮かれている。
どうやら自分は、相当明日が楽しみなのだ。メッセージが来る前の、明日の対局を前にしてぐるぐる煮詰まったようになっていた気分は、あっさりとさっぱりと霧散していた。