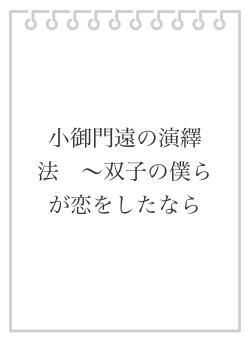梅雨が明けると一気に気温が上がって、それでも、日課は変わらず続いていた。
「ねえ、……あのさあ、樹」
香が言いづらそうに口を開いて、樹はその顎から滴り落ちる汗を見ていた。
「スマホにLINEかインスタ入れてる?」
言葉とともに、ペットボトルを渡される。じわじわと迫り来る夏の気配は、早朝でもふたりをあっさり汗だくにさせた。残り半分を一気に飲み干してから、答える。
「LINEはまあ、入れてるけど」
柾と先輩棋士数名としか繋がっていない、さして利用されていないツールではあるが、スマートフォンの中に存在はする。最後のトークがいつかも覚えちゃいないが。
「じゃあさ、えっと……俺も、繋がっていい?」
「……別にいいけど、なんで今さら。必要か?」
今更何を遠慮されているかのほうがわからないし、今更になって連絡先を欲しがる理由はもっとわからない。樹の淡白な対応に、香はきゅっと眉を寄せた。
「必要か、って。なに、樹は要らないんだ?」
「いや、だって。今まではなくてもよかったわけだろ」
朝に顔を合わせるだけの関係で、たとえ連絡先を知っていたとしても、朝以外に連絡を入れていたとは思えない。家と学校と対局以外に行き場のない樹だが、そのすべての時間を将棋に費やしていると言っても過言ではないのだ。同年代のクラスメイトがやっているように、だらだらと無意味なメッセージなどとても交わしてはいられない。
そしてそれは多分、香もだろうと思っていたのだが。
「あー、そういうこと言う。そっかー、樹はそうなんだー」
低い声音が、『怒っています』と言っている。しかしながら、ここで態度を和らげられるような樹だったらもうちょっと母親を安心させられていたはずで、つまり口から出る言葉は短くそっけないものにしかなり得なかった。
「なにが言いたいんだよ」
たぶんこの、『毎朝』というペースが良かったのだろうなと樹は思う。
互いに『なんだこいつ』と思うことが多くても、そしてそれが時に憤りを連れてきたとしても、一日経つあいだにだいたいのことが冷却されて、翌日にはまた顔を合わせても良いぐあいの気分にはなっている。蟠りを解決せずに流し続けて繰り返した日々もそろそろ三ヶ月、樹は香の驚くべきマイペースとあざとさに慣れたし、香は樹の淡白すぎる対応と口の悪さに慣れた。
慣れたから、香は今更樹の言葉一つに目くじらを立てない。そのかわりちょっと上体を屈めて、指先でちょいと前髪を直した。
そして、下から覗き込むみたいに樹を見上げる。
「──夏休み、ずっといない、って言っても」
なんでこいつは自分が可愛く見える角度ってものがわかってるんだ、と、心底不思議に思った。そのうえなんで同じ男子高校生である樹相手にそれが効果的だと思えるんだ。いや髪結んでピンで留めてって時点で既に樹と同じカテゴリに入る人間とは思えないけど、と、ぐるぐるする樹の前で、こてんと首を傾ける。だからさあお前。
「なくてもいい、って言う?」
などと考えていたせいで、言葉の理解に少しかかった。夏休み。あと一週間も経てば、なるほど大概の高校は夏休みだろう。それがどうしたって?
「え」
やっと、頭が回り始めた。香が対局相手だったら、駒の動かし方すら知らないだろうコイツに負けるんじゃないか? 思いながら、阿呆みたいに言う。
「……ずっと?」
「うん」
「一ヶ月? ……え、どっか行くのか?」
夏休みいっぱい来られない理由なんて、留守にするとしか思えない。
「そう。まあ、合宿みたいなもん?」
なるほど、合宿か。それにしたって、一ヶ月まるまるは想定していなかった。
「どこで」
わざわざ尋ねたのは、夏休みは子ども相手の将棋イベントに駆りだされて遠征することがあるからだった。もし行き先が被ったら顔ぐらいは見に行ってやってもいい……という思惑を叩き潰すように香は答える。
「アメリカ。の、ボストン」
海外を想定していなかったわけではなかったが、それでも、流石に驚いた。咄嗟に地図上の位置がわからず、ただ瞠目して香を見る。相変わらずの上目遣いのまま、香は「で?」と首を傾けた。
「で、って」
「なくてもいい?」
いい、と、言わせてくれる気のない顔だった。けれどもここであっさり折れられる樹だったらもう少し以下略。ぐっと詰まった樹を見上げて、香はわざとらしく目を眇めた。
「……樹?」
じっとりとした目に、脅迫されている。
「あのさあ……俺はね?」
はあ、と、思い切り、これ見よがしにため息をつかれた。自分が可愛いとわかっている香は、自己演出も過剰なのだ。そして似合っている。
「今、こうやって毎日会ってるのにさ。いきなり会わなくなって、連絡先のひとつも知らないってのも、なんか」
ぱし、と、精巧な細工みたいな長い睫毛が上下するのを眺めていた。
「いや、かなあ、って、思ったんだけど?」
可愛らしく見せるための表情、うつくしい顔に嵌めこまれた大きな瞳に、ほんの一瞬だけ影が差す。一度の瞬きで消える程度の、けれどもはっきりと見えたそれに樹が詰めた息を吐くより前に、香は「でもまあ」とわざとらしく明るく声を張った。
「そっか、そういえば、樹は、ひとりでもいいし、さみしくもないんだっけ? うん、別になくていいっていうんなら、夏休み明け、九月に」
「い、っ」
「──い?」
どこまでが作られた顔だろう。ていうかこいつ根に持ってる。盤上でさみしくないのと普段とは別、って一体何を考えてるんだ俺は。
盤上以外でのことなんて、今まで、考えたこともなかったのに?
「……いらない、とは、言ってない」
言わされた。
屈辱だ。くそ、言わされた。そこまで畳み掛けられなくてもちゃんと言った、というのはただの子どもの駄々で、たぶん香は樹がこの顔でこの声で言うところまで見たくてやっている。いい性格だからだ。案の定、香は心底満足したみたいな顔でにぱっと笑った。
「だよね! うんうん。じゃあはい、LINEの画面出して!」
「……おー」
なんとも嬉しそうなことで何よりだ。ぐったりと疲れたような気分とともに樹は返し、ふたりは無事──なんだかこそばゆいような思いとともに、電話番号とメールアドレス、そしてLINEの連絡先を交換した。
「──おい、お前。お前だよお前。船明! 船明樹五段!」
まくし立てるように呼ばれて、やっと樹は顔を上げた。
「お前なんなの? ついに俺の言葉すら聞く価値ないとか思い始めた? さすがの逆川さんも怒るよ?」
「すいません、聞いてませんでした」
「お前なあ」
将棋会館の、控室の一角。今日対局のない樹は、逆川に呼び出されて、わざわざここを訪れていた。将棋盤を挟み、今まさしく別室で行われている対局の検討を行っていたのだが、逆川が黙りこんで考える間、少しばかり注意が逸れていたらしい。
「……で、お前、何見てたの?」
「え?」
「え? じゃねーよ。スマホ見てただろ今。俺の話より大事な要件だったんだろうな?」
大体の要件は逆川の話より大事だろうし、そこは言うなら『この対局より』だろうと思ったが口には出さず、樹は「別に」と短く返した。
「友人からのLINEを見返してただけです」
「友人!? え、お前、友達とか居たんだ?」
「……流石に失礼だと思いません?」
「いや全く」
きっぱり言われてしまえば、怒る気も失せようというものだ。
「え、しかも『見返してた』ってなによ。今来たわけじゃないってこと? 見返すような連絡ってなに?」
答える義理もない質問だが、おそらくこのまま放置してもヒートアップするばかり、どころかスマートフォンを力づくで奪われる可能性すらある。樹は諦めのため息とともに答えた。
「……そいつ、今海外なんで。写真とか送ってくるんですよ」
ちなみに今見ていた写真は、合宿先で一緒になったという白人男性とのツーショットだった。誰だそいつ詳しく説明しろ、とは、勿論言えていない。『樹が聴いてた曲のアニメ一緒に見た!』とのメッセージがついてきたから、『どうだった』とごく短く返したのみだ。解説でもXでも一言の樹が、友人とのメッセージですら一言だと証明された瞬間である。
「へ、海外!? お前の友達が?」
さっきから驚き過ぎじゃないか、というか、樹をほんとうになんだと思っているのだ。
「聞かれる前に言いますけど。アメリカの……ボストンって言ってたかな。あ、写真は見せないんで」
「なんで!?」
「むしろなんで見せると思ったんですか」
メッセージアプリで送られてくる写真は、海外らしい景色も勿論含まれているとはいえ、殆どがその景色を背景とした香の自撮りである。自分を可愛らしく撮る方法を十三分に心得ている男子高校生の写真、なんてものを見せた日には『お前の交友関係どうなってんの?』と根掘り葉掘り関係を聞かれるのは目に見えていた。奪われたら厄介だ、と、樹は素早くスマートフォンを鞄に仕舞う。
「あ、お前! んなことされたら余計気になるだろ!」
「いや、俺の知ったことじゃないんで。……あ、手進みましたね。ほら、やっぱり歩だったじゃないですか」
「うお、まじか。てことは同桂? ──じゃなくて! そうかお前、普通に高校生やれてたんだな……」
感嘆するみたいに言われて、『いや高校のクラスメイトとかじゃないですけど』とは言い辛い。というか香とのことをどう説明していいかがわからない。から、樹は盤面に集中しているふりをして黙っていた。
検討している対局は、新人王戦の予選、準決勝だった。沓谷の対局だ。樹も沓谷も順当に勝ち上がり、互いに準決勝まで駒を進めた。樹の側の対局はまだ先だ。
盤面は、沓谷優勢。沓谷は慎重で粘り強い男だ。ここから覆すのは容易ではない、と、樹は冷静に盤面を見下ろす。逆川と駒を動かして展開を検討しながら、樹はとうに『沓谷だろうな』と目算を立てていた。
「……お前はさあ」
呆れたような逆川の声が聞こえる。
「言っとくけどお前、まだ勝ったわけじゃねえんだからな? 次準決よ?」
「は? わかってますけど」
「わかってて、勝つって思ってるわけだ」
なんでそんなことを聞かれるのだろう、と、いっそ不思議であるような気がした。
「え。だから今日呼んだんじゃないんですか」
この対局の勝者が決勝の相手になるから、逆川は樹を呼んだのだろう。リアルタイムで検討なんてしなくてもあとから棋譜を読むわけだけれど、時間の使い方も含めて、沓谷がどういう将棋をするのかを体感しておくのは悪くない。
「ていうか、なんだろうと、負けるつもりでは指さないでしょう。一応言っておきますけど、次の局の対策もちゃんと考えてますから」
「わかってるよ、んなこと。……ったく。お前はほんと、憎たらしいな」
「はあ」
その憎らしい樹をわざわざ呼び出す逆川はなんなのだろう。喋っている間にも手は進んでいて、じわじわと盤面の優勢が広がっているように見えた。
「サボらねえし、驕らねえし。可愛くねえ」
ぶつぶつと言われる言葉は殆ど褒め言葉であるような気がしたが、特に指摘することでもないから黙っていた。
「いやでも、今日はちょっと可愛いとこ見れたか。友達の写真ねえ……って」
向かい合う先輩を差し置いてスマートフォンを眺めるのは『可愛いところ』という評価でいいんだろうか。
「……お前、その友達って、まさか女じゃないだろうな?」
またか。
と思ったが、なにか考えるより前に、かっと顔に熱が集まるのを感じた。いや待て、その反応はおかしいだろう自分。「は!?」と逆川が大声を上げて立ち上がり、控室じゅうの視線が集まるのに慌てて口を開く。
「違います。アンタそういう発想しか出来ないんですか?」
「いやお前その顔で違うって、ええ、マジで?」
「違います!」
声を荒げたら一層怪しまれるとわかっていたが、他に強い否定の方法がなくてとりあえず大きな声が出る。つーか男だ、と言ったら取り返しがつかないことになりそうな気がする。なんとなく。
そうしてぎゃんぎゃん騒いで控室から追い出された時には対局はもう終わっていて、沓谷の名前のわきにはひとつ、勝ち星を示す白い丸が記されていた。