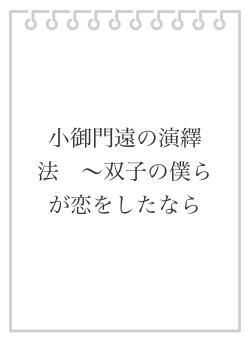強く風が吹いて、最後の桜を散らしていった朝だった。
川沿いの遊歩道。真っ直ぐに伸びた道に沿って等間隔に植えられた桜の木々のうち一本の下に、ひとりの少年が佇んでいる。早朝の道には他に誰の姿もなく、その大きな瞳は、ただ真っ直ぐに樹だけを捉えていた。
(……なんで)
思わず、足を止めていた。混乱していた。彼が樹を見つめる理由が、ただのひとつも思いつかなかった。
どうしていいか、わからなかった。
呆然と立ち尽くしていると、彼が軽く首をかしげるのが見える。樹の反応を測るようにひとつ瞬いてから、彼はまるで、樹を安心させたがるみたいににっこり笑った。
それが却って、樹を混乱させた。もうダメだ。は、と喉から息が溢れる。一歩後ずさり、そのままぱっと踵を返す。思考の入り込む余地が無いまま駈け出した足は、頭よりもずっとわかりやすく、彼から遠ざかりたがっていた。
彼は明らかに、樹のことを待っていた。けれども、樹の側には、彼に応える準備がひとつもなかった。想像もしていなかったのだ。彼が樹に話しかけてくるなんて、天地がひっくり返リでもしない限りあり得ないと決め込んでいた。
だって彼は。
──だから、樹は逃げ出した。
端的に言ってみっともない、あんまりな敵前逃亡だ。けれども他にやりようのひとつも思いつかず、とにもかくにも走りだした樹の背後で、「え、ええ!?」と、慌てたような声が響いた。清冽な朝を凛と切り裂く、大きくてぴんと張った声。
「え、ちょっと! そういうことする!?」
する!? と言われても、してしまったものは仕方がない。というか、他にどういうやり方があったのか教えてほしい。「あーもう!」と叫んだ声がだいぶ遠くなった、と思った瞬間に、がっと背後から迫りくるプレッシャーを感じた。
「──?」
「それは、なくない!?」
追いつかれる。こんなに速く走れたのか。全速力で走りながらでも震えることのない声に、見た目より余程鍛えている、と思った。想像していたよりもずっと。
「それは、ないでしょ! ……あーもう、わかった! 待って! 俺は、君を待ってたんだってば!!」
待ってた。
それは、あまりに明確に、樹の逃げを咎める言葉だった。なんで、と、もう一度思った。天地がひっくり返りでもしないかぎり、あり得ないと思っていた。だって、そうでもしないと。
そうでもしないと、地上に落ちてなんて来ないだろう、と。
馬鹿みたいに、けれどもたしかに、樹はそう信じていたのだ。
──そもそものはじまりは、二週間ほど前のことだった。
あのときはまだ桜が満開で、樹はその舞い落ちる花びらの下を走っていた。早朝の道に人気はなく、樹の耳にはイヤホンから流れる音楽だけが届いていて、だから樹は気が付かなかった。
ふ、と、冬の名残を孕んだ風が、樹の脇を通り抜けた。春爛漫、とでも言うべき景色の中なのに、『冬の』としか言いようのない気配だった。
つめたくて、乾いていて、澄み切っている。
一つの瞬きの後、風の正体は直ぐに知れた。同い年ぐらいの少年が、樹を追い抜いていったのだ。男にしては長い茶色の髪が首のあたりで括られて、尻尾みたいに跳ねるのが見える。追い抜いた直後、彼はちらりとこちらに視線を流して、ぱっちりと大きな瞳に挑発するみたいな色を乗せた。
息が、止まるかと思った。
朝日を浴びてきらきらと白く輝く肌に、色づいて赤い小さな唇。漆黒の瞳はすこし潤んで煌めいて、有り体に言えば彼は、はっとするほどうつくしい顔をしていた。そう、他人の美醜に思うところなどないと思っていたはずの樹が、あっさりと見惚れてしまうぐらいには。
けれども、彼の表情が、そのうつくしさをさっくりと塗り替える。
片側だけにやりと唇を釣り上げたあまりに意地の悪い顔に、我に返るのは即座だった。
負けず嫌いは生まれ持った、もはや自分では制御できない樹の性分だ。足の速さには自負などひとつもなかったが、売られた喧嘩を買わない理由には成り得ない。樹は脚に力を込めて速度を上げ、あっという間に彼に追いついた。
追い抜く瞬間に、彼を見ることはしなかった。
どうせすぐに追い抜いてくるとわかりきっていたし、子どもの遊びにムキになっているわけではないというポーズをとりたかったのだ。もちろん、実際は、ムキどころの話ではなかったわけだけれども。
ともあれ、そうして追い抜いて追い抜かれてを繰り返せば当然のこと、最後にはふたりとも、全身全霊での全力疾走になっていた。桜並木の先にある大きな公園に入ったのは彼のほうがすこし先で、ふたりともごく自然とそこをゴールと認識していたから、彼はいかにも得意気に笑って、樹は小さく舌を打った。
そして、言葉を交わさないままふたりは別れた。
翌日もその翌日も、樹は桜の下で彼を見つけた。追い抜かれて気づくこともあれば、背中を見つけることもあった。どちらにしてもふたりは一度も立ち止まること無く、寧ろ互いの顔を見るたびに速度を上げて、幾度と無く抜いて抜かれたけれど、一度も言葉は交わさなかった。
二週間ずっと、そうだったのだ。
樹はその小さな頭の後ろ、きゅっと縛った茶色い髪が、走るたびにぴょんぴょん跳ねるのを見た。彼が少しだけ樹より小さいことを知った。音楽プレイヤーの音量を絞って、規則正しい、跳ねるみたいな彼の足音を聞いた。少女向けに作られた人形のように整った面立ちの口元が、あくどい子どものように悪戯に微笑むのを、幾度と無く見続けた。
またある日には、彼の向こうに爽やかすぎるぐらいの青空を見た。冬の乾いた薄氷の空ではない、水を含んだ柔らかな青に、彼からする冬の気配の正体が、その白すぎる肌にあるのだと気付いた。肌理細やかなうえに抜けるように白いから、朝の光を反射して、薄く張った氷のように、つめたく澄んで見えるのだ。それなりの速度で走っているのに、その唇から溢れる息はたしかに上がっているのに、その肌だけはちっとも熱を宿すことなく、冷たい白さを保ち続けているのだ。
はたして彼は、人間だろうか?
なんて、馬鹿みたいなことを、樹は多分、殆ど本気で思っていた。彼の名前を知らない。声を聞いたことすらない。それでも毎日顔を合わせて、理由もなく一緒に走っている。
それだけで、よかった。
少なくとも樹は、それだけでいいと思っていたのだ。
──けれども、どうやら彼のほうは、『それでいい』わけではなかったらしい。
『君を、待ってた』
それは、あまりに明確に、樹の逃げを咎める言葉だった。それでも逃げ続ける樹は、どうやら逃げ切れない。せめて体調が万全だったら、と思ったところで後の祭りだ。見た目よりも鍛えている、の印象通り、樹よりも確実に体力のある彼は、着実に距離を詰めてきているようだった。
「ま、っ……て、てば!」
樹の背中に向かって手が伸ばされるのが、見えるはずがないのに、見ているかのようにはっきりわかった。指先が伸ばされ、ついには背中を引っ掻くように掠める。あ、と思った瞬間に、彼の掌がウェアを思い切り鷲掴みにした。
「つっ、か……まえ、た!」
そして急ブレーキ。
「っ、……!?」
ぐんっ、と、強く後ろに引っ張られて、ウェアの喉元がぐいっと締まる。蹈鞴を踏んで踏み留まれずに、樹はそのまま倒れて尻もちをついた。咄嗟に手をつかなかった自分を褒めてやりたい。
とはいえ、尻だろうと痛いものは痛い。微かに顔を顰めながら、樹は真上を見るように顔を上げた。
「ごっ、ごめん!」
後ろから、覗きこむようにして見下ろしてくる。
「大丈夫!? 怪我しなかった!?」
近くで見ると彼の顔は思った以上に小さく、そして、思っていたとおりにうつくしく整っていた。近くで見ても荒れのひとつもない滑らかな頬はやはり氷のように白く、形の良い鼻と口は小さく、黒目の大きなぱっちりとした瞳が、うっすらと潤んできらきら光っている。ちかっ、と、なにかが光を反射して、それが随分明るい色味のピンであることに気がついた。
はっ、と、大きく吐かれた息が鼻先に触れて、自分でもわけがわからないほど動揺する。
「け、」
何か言って、ペースを取り戻さなければ。その一心で口を開いた。
「怪我は、……してない」
樹の言葉に、あからさまにほっとした顔をする。よかった、と小さく囁くように言ってから、彼は強い決意を示すように、きゅっとその小さな唇を一度結んだ。
きらきらとした強い瞳から、目が離せない。やがて唇が解けて、呆然としたままの樹に向かって、彼ははっきりと言葉を落とした。
「あ、あのね。俺、明日から、遠征で!」
用意しておいた台詞を読み上げるような、はきはきとした一本調子だった。
「一週間ちょい、えっと、来週の金曜まで、来れない、んだけど!」
来週の金曜。思わず脳内にカレンダーを浮かべて確認する。対局の日だ。新人王戦トーナメント。二回戦。
「それは、その、そういう理由だから! 金曜からはまた、走るから!」
ぐうっ、と、喉に迫る何かがあった。
樹の動揺には恐らく一切気づかぬまま、ただ言い切ったことに安堵したように息を吐く。はあっと息を吐ききって、彼は、屈めていた上体をぱっと持ち上げた。
「そ、それだけだから! 転ばせてごめん!!」
そうして、呆然とする樹に答える間も与えないまま。
彼が待ってくれたところで樹が何かを口にできていたかはわからないが、ともかく、樹の答えを聞く素振りを一切見せずに、彼は思い切りよく地面を蹴った。
羽が生えているみたいに軽い、重力の存在をちっとも感じさせない動きだった。樹はひたすらに目を見開いて、ぐんぐん遠ざかっていく背中を、座り込んだままでただ見送る。
「……なんだよ、それ」
旋風のように駆け抜けて、身構える間もなく巻き込まれた。彼の姿はもうどこにも居なくて、樹はまるで、なにかに化かされたようだと思う。
現実、だったのだろうか?
目の前では、最後の桜が散っている。夢うつつのような心地で、けれども樹は、彼がここにいたことを認識していた。
彼の言葉を、思い出す。
しばらく来ることができないけれど、それが終わったらまた走りに来る。要約すればそれだけの台詞で、けれども彼がほんとうに伝えたかったことは、もう一歩進んだ先にあるのだとわかっていた。
『だから、その日は変わらず、ここにいて』──と。
そう言いたかったのだとわかるのは、同じだからに他ならなかった。くらくらする頭を叱咤し、樹は小さく舌打ちをした。
どうしてと、この期に及んでも、同じだとわかっても、それでも思った。どうして。思いながら、鼻先に触れる。
つめたそうな肌。水を湛えた瞳。
冬の気配を色濃く持つ彼の息はけれども、当たり前にあたたかかった。