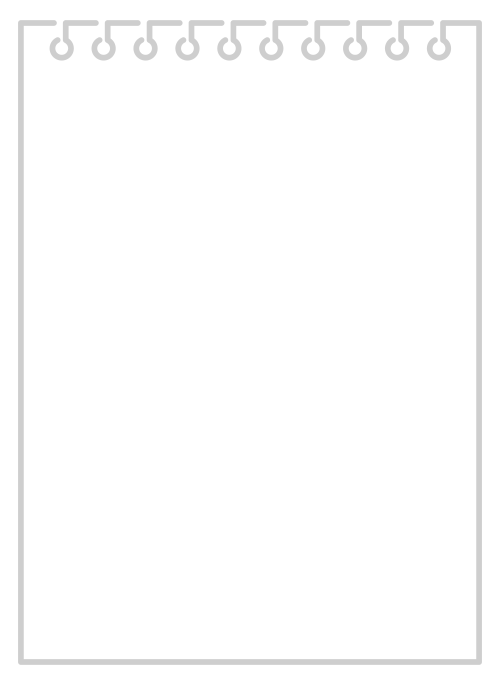お店に入るとおしゃれなBGMが耳をくすぐる。なんだかそわそわした。
西之宮さんはなんてことないように口笛をふきながら店内を見渡している。
なんでこんなことに。そんな気持ちもあったけれど、少し心が躍っていたのも事実だった。僕は正解の道から外れてしまったのだろうか。
「すみません、ショーウィンドウに飾ってある服ってどこにありますか」
そんな声が聞こえて顔を上げた。西之宮さんが店員さんに話しかけている。
店員さんはにこやかに「お持ちしますね」と一度西之宮さんから離れた。
西之宮さんは軽やかに歩きながら僕の方に近寄る。
「よかった、あるって」
「…うん、でもやっぱり着れないよ」
「なんで」
だって決まってるじゃん。僕は、
「僕、男だし」
小さな声で吐かれたその言葉。西之宮さんの眉が八の字になっている。
「うーん、要は今見た目が完全に男だからあれを着たくないってこと?」
僕はその質問に小さく頷いた。
すると西之宮さんは「分かった」と言う。どうするつもりだと身構えているとまたもや僕の手を掴んで歩き出した。
「お客様、お持ちしましたが…」
「すみません、すぐにまた来ますので」
「ちょっ、西之宮さん」
「いいから一回出るよ」
店を出て僕の手を離さないまま歩き続けていく西之宮さん。
細かく波を打っている後ろ髪がゆらゆらと揺れている。毎朝準備大変そうだなとこんなタイミングで変なことを思った。僕なんて髪も短いしメイクなんてしないし、朝の準備なんて5.6分ほどで終わってしまう。
心の奥に潜む願望を表に出さないように鏡と睨めっこする毎日だ。
「ねえ西之宮さん、これからどうするんだよ」
「まあまあ、任せといて」
そう言って入ったのは化粧品だけでなく服や雑貨、あらゆるものが揃うようなお店であった。店内特有の音楽が爆音で響いている。
西之宮さんは迷うことなくカゴを手に取って中を物色し始めた。
「まず髪からだよね。肌白いしブルベって感じするから黒髪のロングとかいいんじゃない」
僕の応答は待たずに袋に入った簡易なウィッグをカゴに入れる。西之宮さんがやろうとしていることを理解した。
「かわいそうとか、変な同情してるならやめてほしい」
「お、アイシャドウこの色似合いそう」
「きいてる?」
「チークは青みが入ってるピンクとかいいよね」
「西之宮さん」
「ああでも、意外とコーラル系とか似合うかも」
「西之宮さんってば」
西之宮さんはあえて無視しているのか真剣にメイク道具を迷っているのか顎に手を置いて2つのチークを手に取り悩んでいた。
僕はため息をつく。そして、ゆっくりと指先をそれに向けた。
「…どちらかといえば青みが入っててあとラメが入ってるからこっちがいい」
西之宮さんが驚いたように僕の方をみる。なんだよ、僕のことだろう僕が一番よく知っている。
西之宮さんは嬉しそうに笑って、右手に持っているチークをカゴに入れた。
「じゃあ、アイシャドウは?」
「これも統一感出したいし、青み系のピンクがいい。でもあんまり紫すぎなくて、儚い感じの」
たくさん並んでいるアイシャドウを指先でさらりと撫でて一つを手に取った。
「これ」
「いいね、似合うと思う」
西之宮さんはそう言ったが似合うかどうかは分からない。だって、ずっと鏡と睨めっこして妄想していただけだったから。
そこから先に進んでは絶対にダメだと思っていた。
「リップは少し艶が入ってるのがいいと思う。まああたしは赤いマットリップ一択だけどね」
赤い唇を少し尖らせた西之宮さん。確かにそれが西之宮さんって感じがする。
僕は笑いを堪えるように口元を手の甲でおさえた。
「なんだよ」
「いや、西之宮さんかわいいなあと思って」
「はあ?」
揶揄われたと思ったのか西之宮さんは軽く拳で僕の肩を殴った。
「素顔知らないくせにそういうこと言うなよ」
「知りたいって言ったらサングラスとってくれるの?」
そう言うと少し言葉を詰まらせて僕から顔を逸らした西之宮さん。そして警戒するようにサングラスを人差し指で押し上げる。
「これがイカしてるから、取らない」
「イカしてる?」
「ナウいってこと」
「ナウい?」
「理解力うんこかよ」
「うんこて…」
しようもない会話をしながら僕は自分好みのリップと重ねるための濃い目の色のティントをカゴに入れた。
カゴに僕の妄想が詰まっていた。
なぜか泣きそうになった。