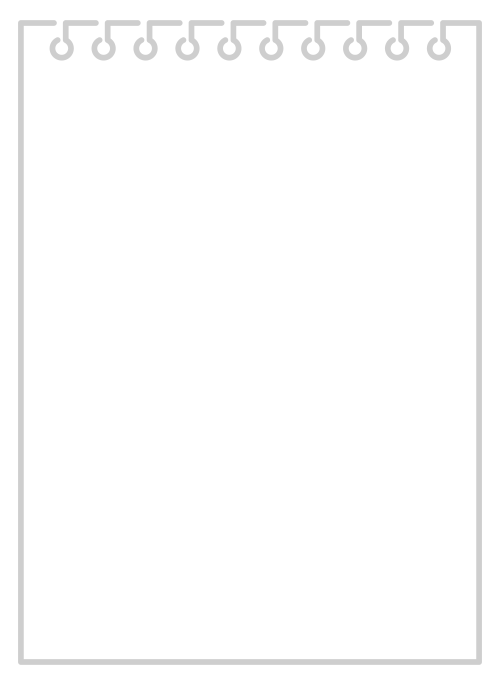「いやあ、あんがとね」
生クリームと苺がこれでもかと入っているクレープを片手に西之宮さんは屈託のない笑みを浮かべる。
「金持ってなかったからクレープ食べたくても食べれなくてさ」
「別にいいけど、まさか」
「ん?」
「いや、なんでもない」
まさか、クレープ食べたすぎてあの公園で泣いていたなんてことあり得るのだろうか。このスケバン女ならそれが本当だとしても大して驚かないかもしれない。
そして僕はふと気がついた。周りの視線が少々いたい。
何せ僕は家からそのまま出てきた部屋着で、隣にはスケバンサングラス女が歩いている。
確かにはたから見れば気になるかもしれない。
僕は若干俯きながらチョコレートバナナのクレープをひと齧りした。あまい。
「西之宮さんってそういうの食べるの意外だね。甘いのとかあまり食べないのかと思った」
「たいしてあたしと喋ったこともないくせになんでそんなこと思うの」
「スケバンだし」
「スケバン関係ねえだろ」
むすっとした声が隣から聞こえて僕は「ごめん」とすぐさま謝った。だって正直僕は西之宮さんのことをよく知らない。毎朝風紀委員として西之宮さんを注意しているだけの存在で、それ以外では関わってことがなかった。
ちらりと隣をみる。隙間から少しだけ瞳が見えた。
「あ」と思わず声がもれた。
「なに」
怪訝な顔をしてこちらを向いたことによってまた濃い茶色がその瞳を隠す。
「なんでもない」
ちくしょう、もう少しで西之宮さんの目が見れそうだったのに。いや別にどうしても見たいってわけじゃないけど。
僕は半ばやけくそになって大口をあけてクレープを頬張った。
そして口の中にめいっぱい広がる甘さを堪能して飲み込む。
ちらりとショーウィンドウに飾られているマネキンに目がいった。思わず足を止める。
パステルカラーの花の刺繍が入った白いスカート。上にはレモンイエローのシンプルなニットにアメリカンレトロなスカーフが首元に巻かれている。
じっとそれを見つめたあと、ガラスに反射した自分の姿を視界にうつした。
ああ、似合わないだろうなって。
「東田?」
「あ、いや、大丈夫」
僕の隣に並んだ西之宮さんが不思議そうに僕の顔を覗き込んだが、すぐさま目を逸らして歩き始める。
いいなあ、僕もサングラスが欲しい。
そんなことを思っていると、僕の腕がぐいっと後ろにひかれた。
「なんだよ」
「さっきの服、着てみようよ」
「はあ?」
声がひっくり返った。そんな僕に西之宮さんは力を弱めることなく僕の体を引きずるように先ほどの場所へ戻そうとする。
全力で拒否した。首をぶんぶんと横に振る。
僕の腕で綱引きをしているような体勢になっている。
周りの目が気になるが今はそれどころじゃない。
「何遠慮してんの、いいから」
「嫌だよ、僕には似合わない」
「着てみないと分かんないでしょ」
「やめろって」
「今しかないんだよ、自分がやりたいって思ったことできるのなんて」
ふと力が抜けた。西之宮さんの手がやっと離れて力なく手の先が地面に向く。
「…どういう意味」
「そのままの意味。大人になっていけばいくほど、何かと理由をつけてやりたいことをやらなくなる」
「なんでそんなこと西之宮さんに分かんの」
「分かるから分かんの、いいから行こう」
再度手を引かれる。優しい力だったけれど僕は振りほどかなかった。