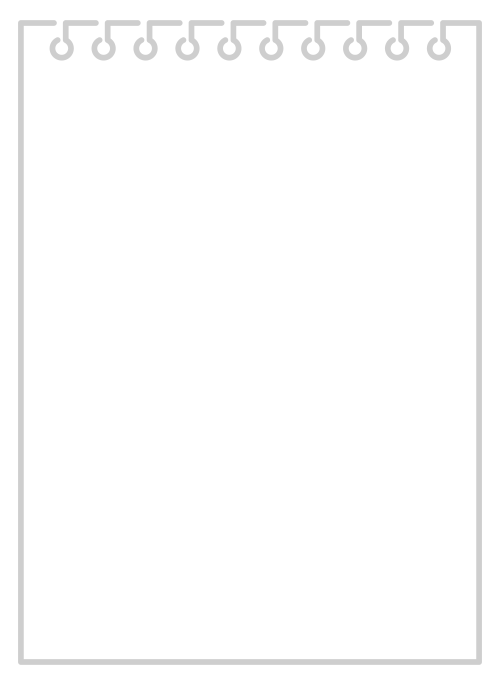僕はおそるおそる西之宮さんが座っている横のブランコに腰をかけた。
「休みの日でもその格好してるんだね、西之宮さん」
「悪い?別に学校の外なんだし風紀とか規則とか言わないで」
「別に何も言ってないじゃん」
「言おうとしてたでしょ」
「してないし、僕だって学校の外に出れば風紀委員長じゃない」
「ふうん、じゃあなんなわけ」
「なにって」
よく分からない質問だ。風紀委員長じゃない僕はそれでも僕で西之宮さんの質問の意図が分からない。
僕は首を傾げる。
西之宮さんはため息をついた。そして大きめのサングラスを人差し指で軽く押し上げてズレをなおした。
いまだに僕は、西之宮さんの瞳を見たことはない。
「あたしは、風紀委員である東田しか知らないけど、他にどんな東田が眠ってんのかって話だよ」
「そんなこと言われたって僕は何もないただの凡人だ。ほら、そこら辺に転がってるだろ、あの小石みたいな感じだよ」
「小石、ねえ。いいじゃん、あたしも小石」
「西之宮さんは違うよ」
「はあ?なんで」
「だってスケバンだし」
「意味分かんないんだけど」
「誰よりも目立って、好きな格好して、自分を貫いてる」
そう僕が言うと、西之宮さんは「けっ」と笑った。
そしてすぐそばに転がっている小石を片手で拾い、ぽんっと軽く投げた。
僕のポケットの中にあるスマホが揺れた。取り出して画面をみる。弟からメッセージがきていた。
ーーーーー【からかってやろうとか、傷つけてやろうとか、そういう気持ちで言ったんじゃない】
僕は静かに画面を暗くした。そんなことは理解している。
「自分は平凡で何もない、それが正解だって必死になってるやつほど、そうはなりきれないんだよ」
西之宮さんがそう言った。
小石の行先をそのサングラスの奥の瞳で見つめているのだろう。何を考えてそんなことを言っているのか僕には分からない。
独り言ような小さな声だった。
「てか、所詮みんな小石だし」
「な、なんだよ、それ」
「小石上等、東田参上ってね」
「何にも響かないんだけど、意味分かんないし」
「くそが」
舌打ちとともにそんな言葉をはかれて、僕はなぜか笑いが込み上げてきた。先ほどまで何にイライラしていたのかすらよく分からなくなっている。
「ねえ東田」
「なんだよ」
「ちょっと今から付き合ってくんない」