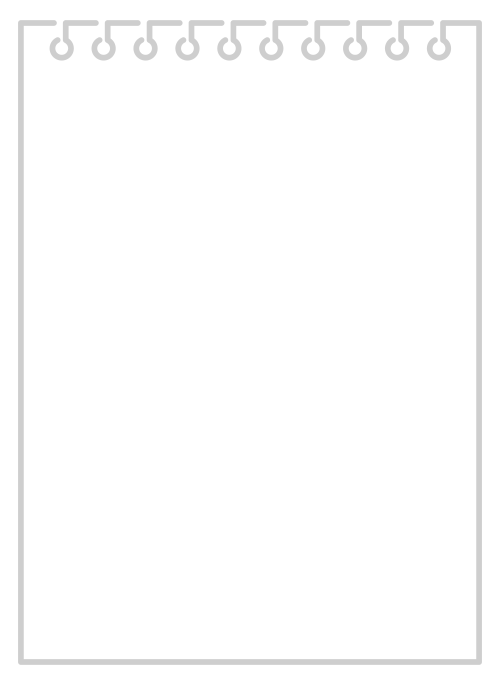「兄貴、前みたいに女性雑誌とか読まなくなったよな」
弟の何気ないひと言に僕は眉間に皺を寄せて弟を睨みつけた。
そして側にあったクッションを弟に投げつける。たいして痛くないくせに大げさに「いった」と反応されイライラが増していく。
「母さんに言ってないだろうな」
「言ってないよ、変に心配するだろうし」
変に心配ってなんだよ。
弟はため息をついて僕の座っているソファの横に腰掛けた。
中学3年生の弟、宏光はなんとなくではあるが僕の心の内に気づいている。
それが分かっているからなるべく話したくない。
「最近、色々あんじゃんLGBTとか、そういうの」
「それがなんだよ」
「いや、兄貴は何なのかなって」
僕はため息をついた。宏光のような年頃は何も考えずすぐに口に出してくる。デリカシーのかけらもないのだろうか。いや、年頃などと言うがこの弟に限っては、だろう。
僕は宏光の質問には答えないで中身の入ってこないテレビへと瞳を向けた。
「小さい頃さ、兄貴がスカート履いて鏡の前で楽しそうにニコニコしてたじゃんそういう願望はもうないの」
「いい加減にしろよ」
「風紀委員長とかよく分かんないことやって内申点あげて、母さんの機嫌とって、それが兄貴のやりたかったこと?」
「うるさい」
僕は大きな声をだした。そして立ち上がって弟を見下ろす。
「学校とかSNSで何を学んだのか知らないけど、人の気持ちに土足でヅカヅカ入ってきて何なんだよ」
「兄貴、俺は別に」
「僕だって分からないさ、自分がどうしたいのか。だから世間一般からみての正解の道に行ってるだけだよ。
なのに毎朝毎朝僕の気持ちをかき乱すようなスケバン女が現れるし、デリカシーのかけらもない弟にクソみたいなこと言われるし、もう限界だ」
僕はそこら辺に転がる石ころだ。
人から干渉もされない、平和で、普通で、人のつま先にトンっと当たってやっと存在に気づく。
それくらい。だからもう僕には構わないでくれ。
「みんな死んじまえ」
思ってもいない言葉が自分の口からもれて、僕は宏光と正面から向き合うことができなくなった。
僕は家を飛び出す。
荒々しく玄関のドアを閉めて、門は開いたままという絶妙な反抗を残して走る。
行くあてもないまま彷徨ってたどり着いたのは駅裏にある小さな公園であった。
ゆっくりと歩いていくと、端にあるブランコに誰かが座っていた。
見覚えのあるセーラー服に、長いスカート。
波打っている髪、前髪は朝よりは少しへしゃげていた。
そして顔を地面に俯かせている。
ブランコを小さく揺らしているため、錆びついた鉄の擦れる音がそこに響いている。
僕は名前を呼んだ。
「西之宮さん?」
顔を俯かせていた西之宮さんは慌てた様子で目元を拭っあとサングラスをかける。
そして顔を上げた。
「うわ、東田」
「呼び捨て…」
僕は顰めっ面のまま西之宮さんを見つめる。先ほど泣いていたような仕草だったが気のせいだろうか。
「何をしているのこんなところで」
「東田こそ、なにやってんの」
「別に、散歩」
「へえ」
その場に変な沈黙がはしる。