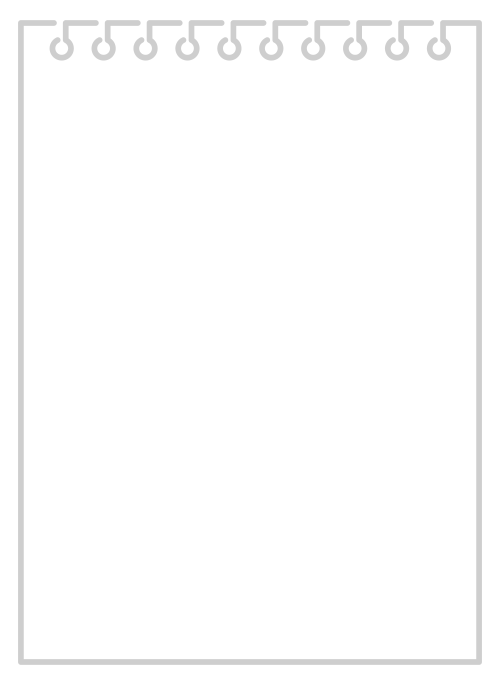どこぞの不良漫画を読んで俺は馬鹿にしていた。
なんで血が出るほど喧嘩して次には協力し合ってんのバカじゃないのって。
「…じゃあ、本当に知らないんだあの子のこと」
「だから知らねえって」
なんとなく気持ちは分かった気がする。ほんの少しだが。
俺はしばらく謹慎となり、原田も同じように謹慎となった。ちなみに髪も黒く染めたため、風紀委員の壁もなんなく突破した原田。
ロッカーを開けて上履きを取り出す際、原田が中を覗き込んだ。
「1日1通はあったのに、さすがにないんだな」
「ラブレター」と付け加えられたそれに俺は苦笑いを浮かべる。
「まあ、当然でしょ」
「なんでちょっと誇らしげなんだよ」
「正直中身も薄っぺらいし、俺のことたいして知りもせずに告白してきたんだろうなって感じだったから最近は読んでもなかったんだ」
「サイコパス南崎…」
「やめろよそれ」
原田は「悪い悪い」と笑いながら俺の肩を軽く叩いた。
不思議だ。あんなことがあって俺たちの上っ面の友情はいとも簡単に消えていくのだろうと思っていた。
存外違っていたらしい。というか、なんとなくそれは嫌だと思った。
幾分か先をいった原田の後を追いかけるように俺は隣に並ぶ。
「南崎」
「ん?」
「悪かったよ、いきなり殴って」
原田は前を見たままぽそぽそとそう言った。
「俺もひどいこと言った。ごめん」
「ああ、金魚のフンな」
「まじごめん」
「いいよ、正直図星だったし。入学したての頃、誰からも好かれて人気者の南崎と友達になっておけば学校生活楽だろうなって思ったのは事実」
「原田…」
「でも、今は違うぜ」
鞄を揺らして、照れくさそうに言葉を紡いでいく原田。なんだか友情とか、本音とか、そういうのはむず痒く訳のわからない感情になる。逃げ出したいのにずっと留まって本音を言い合っていたい。心地悪く、心地いい。矛盾の葛藤。
原田はふっと小さく笑った。
「案外、お前いい子ちゃんになりきれてないんだよ」
「なんだよそれ」
「思ってること、色々あるって顔よくしてるし」
「えっ、顔に出てんの俺」
「大丈夫、俺しか気づいてない」
そう言った原田。チャラくて何も考えていない男だと思っていたことを心の中で謝罪した。
黒く染めたての少し跳ねている髪の毛が歩くたびに揺れているのをぼんやりと見つめる。
どうせ、自分のことなんて分かってくれないとこいつを跳ね除けていたのは俺の方であった。
「ねえ、原田」
「あ?」
「やっぱり俺、スケバンと一緒にいた子探したい」
そう言えば、原田は揶揄うような声色で「へえ」と答える。
「いいぜ、協力する」
「ありがとう」
拳を向けられる。俺はむず痒くも心地いいその青春を味わいながら拳をこつんっと合わせた。