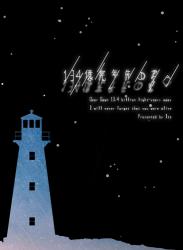「だから違う言いよるやろ!」
吐き捨てるように言い放って、はっとした。静まり返った空気が首の後ろを刺す。皆が私を驚いたように見つめていた。押し問答に夢中になっている間に、いつの間にか人が集まっていたらしい――いや、違う。場所が廊下ではない。私は霞んだ視界を払うように瞬きをし、辺りを見渡した。先程まで目の前にいた彼女はいない。その代わりに机と椅子が規則的に並び、風に煽られたクリーム色のカーテンがばたばたと音を立てていた。その音が妙に耳につく。ここは――見慣れた教室だった。
「高野、なんが違うんか前来て説明せぇ」
教壇に立った先生が教科書に視線を落としながら言う。いつも通りの淡々とした口調だが、感情の起伏がないせいで本気なのか冗談なのか分からない。ただ、怒ってはいるのだろう。その証拠に、先生が口を開いてから一度も視線が合わない。
「……すみません」
「寝んのは自己責任やからええけどな、寝言はうるせぇから喋んな」
「はい。すみません」
ぼそぼそと口の中で呟くように返事をして席に着く。頭が痛い。くすくすと溢れる笑い声の中、斜め右前に座る詩子が唯一心配そうにこちらを窺っていた。その姿の奥に、山梨香織も見えた。視線が交わる前に、目を逸らす。別に注意されたことは堪えていない。本当に堪えているのは、もっと他の、もうどうしようもないことだ。
先生が教科書の三十六ページを開かせて、私のせいで中断していた授業が再開する。皆が黒板に向き直ったのを見届けて、私は重さに耐えかねたように頭を垂れた。
吐き捨てるように言い放って、はっとした。静まり返った空気が首の後ろを刺す。皆が私を驚いたように見つめていた。押し問答に夢中になっている間に、いつの間にか人が集まっていたらしい――いや、違う。場所が廊下ではない。私は霞んだ視界を払うように瞬きをし、辺りを見渡した。先程まで目の前にいた彼女はいない。その代わりに机と椅子が規則的に並び、風に煽られたクリーム色のカーテンがばたばたと音を立てていた。その音が妙に耳につく。ここは――見慣れた教室だった。
「高野、なんが違うんか前来て説明せぇ」
教壇に立った先生が教科書に視線を落としながら言う。いつも通りの淡々とした口調だが、感情の起伏がないせいで本気なのか冗談なのか分からない。ただ、怒ってはいるのだろう。その証拠に、先生が口を開いてから一度も視線が合わない。
「……すみません」
「寝んのは自己責任やからええけどな、寝言はうるせぇから喋んな」
「はい。すみません」
ぼそぼそと口の中で呟くように返事をして席に着く。頭が痛い。くすくすと溢れる笑い声の中、斜め右前に座る詩子が唯一心配そうにこちらを窺っていた。その姿の奥に、山梨香織も見えた。視線が交わる前に、目を逸らす。別に注意されたことは堪えていない。本当に堪えているのは、もっと他の、もうどうしようもないことだ。
先生が教科書の三十六ページを開かせて、私のせいで中断していた授業が再開する。皆が黒板に向き直ったのを見届けて、私は重さに耐えかねたように頭を垂れた。