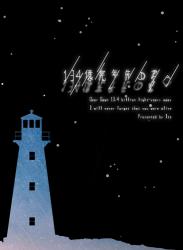全ての色彩が、視界の中心以外、真っ白に弾けた気がした。
そこに鮮やかに映っていたのは、0番に立つ山梨香織だった。センターで、息ができないほど眩しく光るアイドルだった。
「うそ……」
テロップには、〝加入して二ヶ月 センターに大抜擢! 〟と明るい文字が踊っている。
最後列の一番端なんかじゃない。マイクを貰えない子なんかじゃない。爪痕を残そうと媚びる必要もなく、目の前に誰の後ろ姿を見ることもない。全ての期待を受けて立つ、いちばんの特別だった。せめてアイドルとしては劣等生であって欲しいという縋るような微かな祈りが、足元から砕け落ちていく。自分しか知らない心の奥底で、糸が切れてしまった気がした。すとんと、力が抜けたようにへたりこみ、呆然とする。
母が興奮したように何かを言っている。希望を唄った旋律が流れる。それすらももう、聞こえない。ただふわりと羽根を広げるスカートが綺麗で、痛くて、苦しかった。視界が、光だけを残してぼんやりと滲んでいく。
もう、届かない。追いかけていたわけでも、憧れていたわけでもないくせに、そう思う自分に涙が出た。溢れて止まらなかった。悔しいのか、悲しいのか、腹が立つのか、惨めなのか、自分の感情がよく分からない。ただ、言葉にならない小さな泣き声が喉の奥から漏れていく。
「う~~……」
何者にもなれない自分が可哀想だった。この涙も、きっとあの子たちのように美しくはならない。誰にも知られず、無意味なままで落ちていくだけ。無価値で、陳腐で、些末。なのに、まだ私は何者かになれるんじゃないかと期待している。いつか私にも光が当たるんじゃないかと、願ってしまう。本当に特別なものは、自分ではなく他人が価値をつけると知っているのに。
「えぇ? 朱花なんで泣いてるん」
母が驚いたように笑いながら言う。
お母さん、私は山梨香織になりたかった。アイドルになりたかった。平凡で何も成せない人間とは違う、特別でいたかった。それは選ばれた人間だと分かってはいても、いつか選ばれる日を待っていた。
画面の向こうで、山梨香織は微笑む。誰にも平等に、希望を湛えて。それはもう、同じ時間を過ごした同級生には見えなかった。
星が瞬く。きらきら光る。私は曲が終わっても、その残像を見るように、ずっと、ずっと画面越しの世界を眺めていた。
そこに鮮やかに映っていたのは、0番に立つ山梨香織だった。センターで、息ができないほど眩しく光るアイドルだった。
「うそ……」
テロップには、〝加入して二ヶ月 センターに大抜擢! 〟と明るい文字が踊っている。
最後列の一番端なんかじゃない。マイクを貰えない子なんかじゃない。爪痕を残そうと媚びる必要もなく、目の前に誰の後ろ姿を見ることもない。全ての期待を受けて立つ、いちばんの特別だった。せめてアイドルとしては劣等生であって欲しいという縋るような微かな祈りが、足元から砕け落ちていく。自分しか知らない心の奥底で、糸が切れてしまった気がした。すとんと、力が抜けたようにへたりこみ、呆然とする。
母が興奮したように何かを言っている。希望を唄った旋律が流れる。それすらももう、聞こえない。ただふわりと羽根を広げるスカートが綺麗で、痛くて、苦しかった。視界が、光だけを残してぼんやりと滲んでいく。
もう、届かない。追いかけていたわけでも、憧れていたわけでもないくせに、そう思う自分に涙が出た。溢れて止まらなかった。悔しいのか、悲しいのか、腹が立つのか、惨めなのか、自分の感情がよく分からない。ただ、言葉にならない小さな泣き声が喉の奥から漏れていく。
「う~~……」
何者にもなれない自分が可哀想だった。この涙も、きっとあの子たちのように美しくはならない。誰にも知られず、無意味なままで落ちていくだけ。無価値で、陳腐で、些末。なのに、まだ私は何者かになれるんじゃないかと期待している。いつか私にも光が当たるんじゃないかと、願ってしまう。本当に特別なものは、自分ではなく他人が価値をつけると知っているのに。
「えぇ? 朱花なんで泣いてるん」
母が驚いたように笑いながら言う。
お母さん、私は山梨香織になりたかった。アイドルになりたかった。平凡で何も成せない人間とは違う、特別でいたかった。それは選ばれた人間だと分かってはいても、いつか選ばれる日を待っていた。
画面の向こうで、山梨香織は微笑む。誰にも平等に、希望を湛えて。それはもう、同じ時間を過ごした同級生には見えなかった。
星が瞬く。きらきら光る。私は曲が終わっても、その残像を見るように、ずっと、ずっと画面越しの世界を眺めていた。