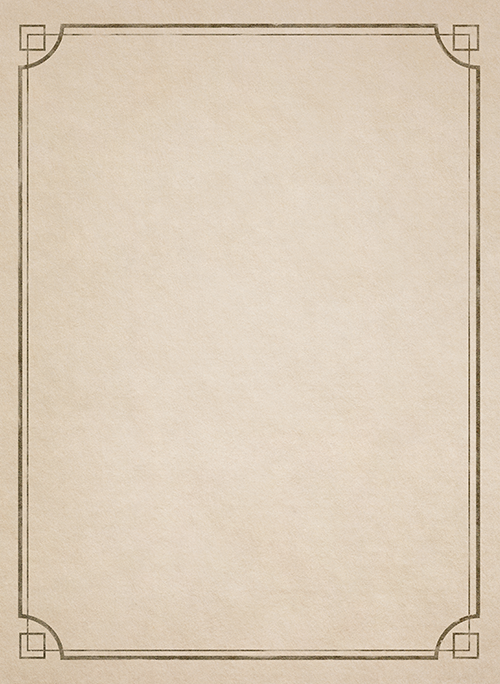「起立、礼、お願いします!」
「よろしくお願いします」
委員長の号令とともに40人の生徒が一斉に挨拶をした。
「はい、よろしく」
5回目にして、はじめて挨拶のやり直しをさせられなかった。全員がしっかりと声を出していたのか鳴瀬が面倒くさくなったのかどちらかは分からない。
「じゃあ、始めよう 5回目の 最後の教育を」
今回はプリントは配られなかった。
「皆、目をつぶれ」
「ちゃんとつぶれよ。薄目のやつがいても気づくからな」
鳴瀬の指示で皆が目をつぶった。
「今から言う質問に正直に答えてほしい」
「この中で1度でも自殺したいと思ったことがある人間は、左手を挙げてくれ」
僕は左手をゆっくりと挙げた。自殺したいと思ったことは1度ばかりか何度もある、何回か分からないくらい。今思えば、どうしてそのようなことで悩んでいたのだろうってレベルの悩みだったけれど、その時は死にたくなるくらい辛かった。
「よし分かった。全員下ろしていいぞ」
鳴瀬の言葉でこの質問の答えが全員YESだったことが分かる。やはり皆、1度は自殺したいと思ったことがあるのか。優れた容姿から男子たちにちやほやされている山橋さんも思ったことがあるんだな、あれだけ美人に生まれておいて何が不満だっていうんだ。
「……自殺したい」
「俺も考えたことはある。当たり前だ」
「そこで今回、君たちに考えてもらいたいのは1つ。自殺は、自分1人だけでするかどうかを決めていいかってことだ。人生は自分のものなんて言葉があるのなら、その最期を決めることも本人の自由なのかどうかを」
この件について発言するものはいなかった。
それほど今回の問題はいつもに比べて難しい。今までで一番想像がしやすく、身近な問題だからだ。
ふいに鳴瀬は話を始める。
「1つ、話をしよう」
「栗山と倉田という2人の男がいたそうだ。この2人は幼馴染みで小、中、高と同じ学校で過ごした。高校を卒業後遠い町に働きに出た栗山、実家の工場を手伝うことにした倉田。そのため2人がしばらく会うことはなかった」
「社会人2年目の倉田は、久しぶりに栗山と再会することになった。彼は一言も話すこともなくベットに横たわっていた」
「自殺だ。会社の重労働に耐えかねて屋上から飛び降りた」
「その日仕事でミスをした栗山は、これ以上迷惑をかけたくないと言って自殺した。そいつのせいで会社はイメージダウン、売上が3分の1まで落ちたと話す社員もいる。勿論、人員が減ったことによる個々の負担は増えるはずだ」
「栗山は迷惑をかけていないのか? みんなに迷惑をかけたくないと言った栗山の願いは叶ったのか?」
「倉田は栗山のことを『あいつは殺人犯だ』と言った。自分で自分自身のことを殺した。それはもう立派な殺人犯だと」
「君たちはどう思う? 自分自身を殺すのは殺人か……?」
自分自身を殺すことも殺人になる。思い出せないけれど、昔見た映画のタイトルもこのような意味が含まれていたような気がしたな。
「そうですね、私も自殺は殺人罪と認めていいと思います。死んだら裁くことはできないけれど」
「そうでも、そうでもしなきゃ、残された人は納得しない。それくらいの覚悟を持って死なないのなら」
口を開いた佐々木さんの言葉には重みがあった。あとから聞いた話だと、佐々木さんはお父さんを自らの手で死を選んだらしい。
「そうだな、自殺は、誰かを悲しませる」
「自殺した人を責めるのもどうかと思う。その人だって、考えて考えて、頑張って、考えて、耐えて、考え抜いて出した答えが自殺だったかも知れない。戦った証拠なのかもしれない」
「だけどな、自殺を美学とするな!!」
「自殺をしたことによって解決した事件は何件ある? 裁かれた悪人は何人いる? 死んだ人間は幸せになれたのか?」
「君たちが自殺しても悲しむ人はいるだろう? 思い浮かべほしい。自分が自殺して誰が悲しむか、その人の悲しむ顔を……」
母、父、弟、祖父母、隣のおばちゃん、友だち、ラーメン屋のタカちゃん。
思い浮かべたらきりがないくらい出てきた。その人たちがどれだけ本当に悲しんでくれるかは分からないけれど。
「思い浮かべたか? そうだよないるよな。悲しむ人はそれぞれにいる」
「絶対に1人はいるからな。少なくとも俺は、ここにいるお前たちの誰かが、亡くなったという報告をされたときに、それが自殺だって知ったら、俺は悲しい。俺の授業は届かなかったのか、俺がもっと伝えていればきっと後悔する」
「だから思い出してほしい。これから君たちが、自殺したいと考えたときは少しだけでもこの授業のことを」
「誰しもが1度は自殺したいと思ったことがあると俺は思っている。君たちが好きな芸能人も、大企業の社長も、きっと自殺したいと思ったことがあるんだということを」
「自殺したいって思うこと自体は悪いことではない、自分自身と向き合っているだからな。後は踏みとどまれるかどうかだ。死にたいと思うことは結構、ただ本当に死んではならない」
「死んだらな、好きな漫画の最終回も知れないぞ。20年間続いた漫画の最終回 気にならないか? 結局、黒幕は誰だったのか? 予想外の人物だぞ? 楽しみじゃないのか?」
「もしかしたら、君らの好きな女優が地元にやってくるかもしれないぞ。会えるかもしれない、ドラマ共演できる可能性だって、ゼロではない」
「何だっていいんだ。下らないことだが、これだけでも君たちの生きる理由はできれば」
「心配しなくていい。自殺なんかしなくてもせいぜい君たちが生きられたとしても、あと80年だ、人間いつかは死ぬのだからさ、自ら死ななくてもいい」
「そろそろ時間になるし、終わるとするか……」
「これで、最後の教育 5回目の授業を終わりとする、はい、号令!」
「起立、礼、ありがとうございました!」
こうして5回目の最後の教育が終わった。
僕はいつもより大きな声を出して挨拶をした。
「よろしくお願いします」
委員長の号令とともに40人の生徒が一斉に挨拶をした。
「はい、よろしく」
5回目にして、はじめて挨拶のやり直しをさせられなかった。全員がしっかりと声を出していたのか鳴瀬が面倒くさくなったのかどちらかは分からない。
「じゃあ、始めよう 5回目の 最後の教育を」
今回はプリントは配られなかった。
「皆、目をつぶれ」
「ちゃんとつぶれよ。薄目のやつがいても気づくからな」
鳴瀬の指示で皆が目をつぶった。
「今から言う質問に正直に答えてほしい」
「この中で1度でも自殺したいと思ったことがある人間は、左手を挙げてくれ」
僕は左手をゆっくりと挙げた。自殺したいと思ったことは1度ばかりか何度もある、何回か分からないくらい。今思えば、どうしてそのようなことで悩んでいたのだろうってレベルの悩みだったけれど、その時は死にたくなるくらい辛かった。
「よし分かった。全員下ろしていいぞ」
鳴瀬の言葉でこの質問の答えが全員YESだったことが分かる。やはり皆、1度は自殺したいと思ったことがあるのか。優れた容姿から男子たちにちやほやされている山橋さんも思ったことがあるんだな、あれだけ美人に生まれておいて何が不満だっていうんだ。
「……自殺したい」
「俺も考えたことはある。当たり前だ」
「そこで今回、君たちに考えてもらいたいのは1つ。自殺は、自分1人だけでするかどうかを決めていいかってことだ。人生は自分のものなんて言葉があるのなら、その最期を決めることも本人の自由なのかどうかを」
この件について発言するものはいなかった。
それほど今回の問題はいつもに比べて難しい。今までで一番想像がしやすく、身近な問題だからだ。
ふいに鳴瀬は話を始める。
「1つ、話をしよう」
「栗山と倉田という2人の男がいたそうだ。この2人は幼馴染みで小、中、高と同じ学校で過ごした。高校を卒業後遠い町に働きに出た栗山、実家の工場を手伝うことにした倉田。そのため2人がしばらく会うことはなかった」
「社会人2年目の倉田は、久しぶりに栗山と再会することになった。彼は一言も話すこともなくベットに横たわっていた」
「自殺だ。会社の重労働に耐えかねて屋上から飛び降りた」
「その日仕事でミスをした栗山は、これ以上迷惑をかけたくないと言って自殺した。そいつのせいで会社はイメージダウン、売上が3分の1まで落ちたと話す社員もいる。勿論、人員が減ったことによる個々の負担は増えるはずだ」
「栗山は迷惑をかけていないのか? みんなに迷惑をかけたくないと言った栗山の願いは叶ったのか?」
「倉田は栗山のことを『あいつは殺人犯だ』と言った。自分で自分自身のことを殺した。それはもう立派な殺人犯だと」
「君たちはどう思う? 自分自身を殺すのは殺人か……?」
自分自身を殺すことも殺人になる。思い出せないけれど、昔見た映画のタイトルもこのような意味が含まれていたような気がしたな。
「そうですね、私も自殺は殺人罪と認めていいと思います。死んだら裁くことはできないけれど」
「そうでも、そうでもしなきゃ、残された人は納得しない。それくらいの覚悟を持って死なないのなら」
口を開いた佐々木さんの言葉には重みがあった。あとから聞いた話だと、佐々木さんはお父さんを自らの手で死を選んだらしい。
「そうだな、自殺は、誰かを悲しませる」
「自殺した人を責めるのもどうかと思う。その人だって、考えて考えて、頑張って、考えて、耐えて、考え抜いて出した答えが自殺だったかも知れない。戦った証拠なのかもしれない」
「だけどな、自殺を美学とするな!!」
「自殺をしたことによって解決した事件は何件ある? 裁かれた悪人は何人いる? 死んだ人間は幸せになれたのか?」
「君たちが自殺しても悲しむ人はいるだろう? 思い浮かべほしい。自分が自殺して誰が悲しむか、その人の悲しむ顔を……」
母、父、弟、祖父母、隣のおばちゃん、友だち、ラーメン屋のタカちゃん。
思い浮かべたらきりがないくらい出てきた。その人たちがどれだけ本当に悲しんでくれるかは分からないけれど。
「思い浮かべたか? そうだよないるよな。悲しむ人はそれぞれにいる」
「絶対に1人はいるからな。少なくとも俺は、ここにいるお前たちの誰かが、亡くなったという報告をされたときに、それが自殺だって知ったら、俺は悲しい。俺の授業は届かなかったのか、俺がもっと伝えていればきっと後悔する」
「だから思い出してほしい。これから君たちが、自殺したいと考えたときは少しだけでもこの授業のことを」
「誰しもが1度は自殺したいと思ったことがあると俺は思っている。君たちが好きな芸能人も、大企業の社長も、きっと自殺したいと思ったことがあるんだということを」
「自殺したいって思うこと自体は悪いことではない、自分自身と向き合っているだからな。後は踏みとどまれるかどうかだ。死にたいと思うことは結構、ただ本当に死んではならない」
「死んだらな、好きな漫画の最終回も知れないぞ。20年間続いた漫画の最終回 気にならないか? 結局、黒幕は誰だったのか? 予想外の人物だぞ? 楽しみじゃないのか?」
「もしかしたら、君らの好きな女優が地元にやってくるかもしれないぞ。会えるかもしれない、ドラマ共演できる可能性だって、ゼロではない」
「何だっていいんだ。下らないことだが、これだけでも君たちの生きる理由はできれば」
「心配しなくていい。自殺なんかしなくてもせいぜい君たちが生きられたとしても、あと80年だ、人間いつかは死ぬのだからさ、自ら死ななくてもいい」
「そろそろ時間になるし、終わるとするか……」
「これで、最後の教育 5回目の授業を終わりとする、はい、号令!」
「起立、礼、ありがとうございました!」
こうして5回目の最後の教育が終わった。
僕はいつもより大きな声を出して挨拶をした。