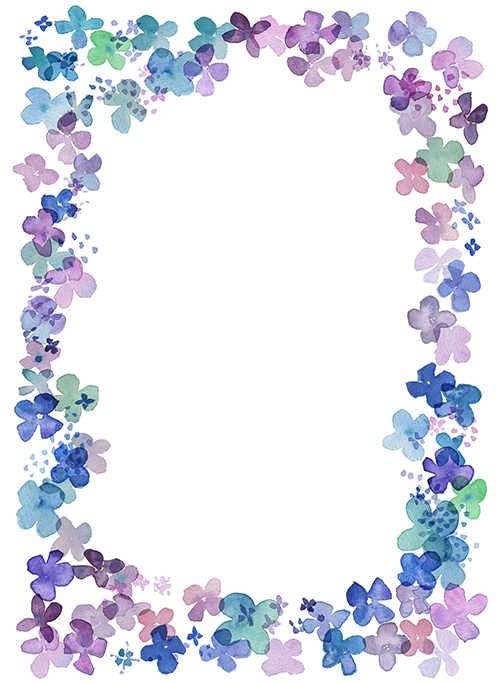あの頃、
初めて出会った君は天使だった。
柔らかい笑顔も、ふわふわとした髪も、色素の薄いまつ毛も、一瞬でも目を離せば何処かに飛んで行ってしまいそうな危うさも。
全部全部愛らしくて、いとおしくて。
『実はぼく、天使なんだ』と冗談を言われた日には、君があまりにも真剣な瞳で言うものだから真に受けてしまって。
私は思わず君を抱きとめて『どこにもいかないで』と懇願した。
君はそんな私に『どこにもいかないよ』と愛おしそうに笑う。
私はその時、人生で初めて頬が熱く焦げてしまいそうな感覚に襲われた。
再び私の目の前に現れた君は、違った。
私はすぐに分かった。君は死神になったんだと。
体に巻かれたローブも、瞳から絶望が零れてきそうな冷淡な表情も、透けた体も。
体は君のままなのに中身だけ何処かに消えてしまったかのような、そんな姿だった。
君は何も知らないようだ、ここがどこなのか、私は誰かのか、そして自分が誰なのか。
せり上がる慟哭を飲み下した私は小さく笑う。
「何処にもいかないでって、約束したでしょ……?」
喉から絞り出した言葉の意味を、君は覚えているだろうか。
高校の最初の一か月というのは噂通りあっという間であった。初めは迷いがちだったこの細い路地も、一か月も歩いていればそこはちゃんと自分の通学路になった。滑りやすい苔を避けるように歩くと、まだ真新しいローファーが軽やかな音を弾ませる。耳元で流れているのはお気に入りの洋楽だった。ベースの低音と、道路を走る抜ける車の音が重なって心地よい。鼻歌を交えながら歩いているとふと違和感を覚えた。耳に神経を集中させると、ボーカルの声に少しノイズが掛かっているような気がする。
「あちゃ~、私昨日充電してなかったっけ」
母親のお古で貰ったこのワイヤレスイヤホンは充電が切れそうになると、黒板を机で引っ搔いたような残酷な音が聞こえてくる。対処法は鼓膜が破壊されないうちに耳から外し、充電することのみ。私はため息を吐くと、ブルートゥースの接続を切った。
しかしこの程度で私の機嫌が損なわれる訳ではない。
だって、
「よっす!」
突然、背中に衝撃が伝わる。吃驚して肩を震わせながら後ろを振り返ると、耳元でピアスを揺らす少女が私の背中を思い切り叩いていた。
「怖いよ、夏帆。あと、そんなに勢い付けたら苔で滑るよ」
「いやいやこの夏帆様の身体能力を見くびるでない」
そう言って胸を張る少女は中学校からの親友夏目夏帆だ。確かに彼女の身体能力は異常だった。握力は60近く、持久走は3年連続学年一位の快挙を達成する彼女は、体は華奢なのに中身はほぼゴリラという残念女子である。
動けないように縄で縛って黙らせれば可憐な美少女という言葉が似あうのに……。しかし本人は私の落胆に気づくことなく、風になびく黒髪を抑えながら笑った。
「蛍、今日はご機嫌だねぇ。もしかして、先輩から連絡来た……?」
「それ聞いちゃう?実は……」
そう溜めると、私はスクールバックからゴソゴソと端末を取り出し、昨日興奮して何枚もスクリーンショットした写真を液晶いっぱいに拡大した。夏帆は一通り目を通すと、声にならない悲鳴をあげる。
「んー、何なに?ほ、う、か、ご、一緒に遊ばない……ってえぇ?!蛍まじ?デート誘われたってこと?」
「どうしよう、私まともな服持ってないよー!」
私の返答に「きゃー」とわざとらしくジタバタした夏帆はまるで自分事のようにキラキラと瞳を輝かせる。そう、私が例えイヤホンの充電が切れようが、車道の泥水が思い切り全身に掛かろうが、菩薩顔で過ごせるのは私の憧れの先輩から放課後のお誘いを受けたからである。
嗚呼、先輩という単語を出す度にシャープな横顔や女子よりも長いまつ毛を思い出す。放課後デート、なんて素敵な響きなんだろう。舌頭に転がせば甘く痺れるような感覚に襲われた。
「やばい、流石にドキドキしてきた」
「だってサッカー部キャプテンでしょ、モテモテだもんね。確実にゲットするよ、これは」
「うーん、でも先輩みたいな人がこんなちんちくりん相手にしてくれるのかなぁ」
自分と先輩が隣に並ぶ姿を想像する。154センチの私のつむじはきっと先輩の横腹くらいだ、あまりにバランスが悪すぎた。
それでもいい、大事なのは顔を見合わせて会話することじゃないし、無理にかがんで気を使わせることでもない。一緒の空間で同じ時を共有することなのだ。顔にじんわりと熱が集まり、思わず両頬に手を当てる。
これはきっと憧れではなく、恋なのだ。うん、そうに違いない。
「蛍なら大丈夫よ!ちなみに先輩のタイプは?」
「えっと……確か、黒のワンピースと長髪が似合う子だったような」
「まじ?あたし、黒のワンピース持ってるよ!放課後、うち寄ってきな」
男前にウインクした彼女の腕を私は手に取りぶんぶんと振る。嗚呼、神様仏様夏帆さま。今日のデートの勝ちの絶対を確信したところで私は、ふと視界の端に映る男女が目に留まった。なんだろう、あれは。黒のパンプスにリクルートスーツを身にまとう女性と、黒のコートを羽織る人。家族、友人ならば会話しながら出勤しているんだろうなで終わるのにどうしてか胸がざわついた。
暫く観察を続けてその違和感の正体がようやく分かった。男性が話しているのに対して女性はまるでそこには誰もいないようにただひたすら歩いているのだ。
「ねぇ夏帆。あれ、ナンパかな?」
「え?あれって……どれ?」
私は眉をひそめながら、指をさす。おかしい、代名詞を使ったとは言え私たちの目の前には一人の女性と全身黒の性別不明の人しかいないのに。夏帆は、まだ分からないというように首を振る。
性別不明の人は女性が忙しそうにヒールを鳴らしているにも関わらず、しつこく話しかけていた。
この光景以外で私がナンパじゃないかと聞けるものは一つもない。
それにも関わらず夏帆は目を細めて辺りを見回してから、再び困惑したように首を傾げた。そんな彼女がもどかしくて、私は早口でまくしたてる。
「あの人だよ。黒い人と通勤中の女の人」
「何言ってるの、蛍。目の前には女の人しかいないよ?」
え、と気の抜けた声が漏れる。
衝撃で足が止まりそうだったけれど、体は勝手に夏帆と同じペースで歩みをやめなかった。やがて女性との距離が無くなると夏帆は私の横腹を肘で小突く。
「ほらー、やっぱり何もないでしょ」
耳打ちの声が不思議と遠かった。私の視線は例の人にくぎ付けだった。おかしい、夏帆は見えていないのか、こんなにも近いのに。首の後ろに冷たい汗が流れる。息が浅くなるのと同時に肩があがっていくのが自分でもわかった。
「……すか、僕は誰ですか?」
一歩、一歩近づくにつれて少し掠れたハスキーな声が聞こえてくる。私は何故かその声に既視感を覚えた。こんな変な人、今まで会ったことはないはずなのに何故だろう。
服も、たまたま全身黒色のコーデだと思っていたが少し違った。頭から垂れる長めのローブが足首まで覆い、全身を黒く見せていたようだ。顔もすっぽり覆ってしまっているせいで良く見えなかった。
彼はもう一度、女性のコートの裾を掴むと懇願するように言う。
「教えてください、僕は誰なんですか。ここは……ここはどこですか?」
最近のナンパ事情はこんなにも奇妙な技を使うのだろうか。記憶喪失を装って女の人を誘おうだなんてなんて質の悪い……新手の嫌がらせのようにも思える。電柱の影から観察していたが、あれだけしつこく絡まれている姿を見ていると段々と女性が気の毒に思えてきた。ただでさえ憂鬱な出勤中にこんなにも粘着に話しかけられたら参ってしまうだろう。逡巡の迷いののち、私は思い切って男の人に声を掛けてみることにした。
「どうしたの、蛍」
私の動きに夏帆が不安そうに尋ねる。私は「大丈夫、少し声を掛けるだけだから」と彼女を電柱の影に待機させた。大丈夫と自分で言っておきながら息苦しいほどの不安が肺をいっぱいにさせる。私は深呼吸をするとお得意のにこやかな人懐こいいつもの笑みを作り、ローファーを鳴らした。
「あのぅ、どうかされましたか?」
黒いローブの影は驚いたように前後に揺れると、ゆっくりと振り返る。こちらを伺うような瞳がローブの下から見えた。
その瞬間、私は叫びたい衝動に襲われた。
逃げ出したくても、足が震えて微動だにできない。その瞬間、街路樹が風に揺れる音も、角を曲がった女性の地面を鳴らす音も、何も聞こえなくなった。無音の世界が、そこには広がっていた。私はただ瞳に涙を溜めながら、彼を見上げる。
なんで
「……君は僕のことが分かるの?」
なんでいるの
「あ……え……」
言葉なんか出てきやしなかった。呻き声に近い音が喉の奥から漏れる。目を何度も瞬かせても、彼の姿が変わることはなかった。
忘れもしない。
夏の名残みたいなラムネの底に沈んでいるビー玉の瞳も、光に透けると透明になる色素の薄いまつ毛も。全部、全部全身にこびりついて離れなくて忘れられなくて。お陰で私は十年も拗らせて。
未だに目を閉じればそこには幼稚園のときのあたたかなひと時と、君の柔らかい笑顔がそこにはあった。
「太陽、なの?」
会えなくなってから何度この名前を口にしただろう。
私が疑うように問うと、彼は無表情のまま距離を詰める。嚙み殺されるんじゃないかと思うくらいの距離で肩を力強く握られた。その手のひらには私を気遣うような力加減は一切ない。期待を込めて君の名前を呼んだ私が間違っていたのだろうか。その瞬間私の思い描いていた太陽は脆いガラスのようにひび割れて砕け散り、目の前にはただ冷徹な目を持った男がいた。
「僕が誰か、分かる?」
冷淡な瞳が一歩、距離を縮める。私はその分一歩、後ずさりをする。息が上手く吸えなくて不規則な呼吸音だけがやけに大きく聞こえた。グラっと突然視界が歪んだ。何が起こったのか分からず数秒硬直したまま瞳だけを動かす。嗚呼、私腰を抜かしたんだ。見上げる彼との距離は更に大きくなり、私はもう何も考えることが出来なかった。私と同じ目線になるためにしゃがみ込んだ彼の黒いローブの後ろには、白く光る大きな鎌が覗いている。
どうやら、私の初恋の相手は死神になってしまったみたいだ。
「いやああああああああああああああ」
ふっと気が緩んだ瞬間、口から出た咆哮が合図だった。私は下半身に力を入れると、立ち上がりその場から全力疾走する。隣を走る車に負けないくらい一生懸命腕を振って、制服のスカートなんか気にせずに全力で地面を蹴り上げる。
とにかく遠くへと逃げたかった。あいつが、あの死神が追い付けないところまで、逃げなければならなかった。
死にたくない。こんなところで死ねない。
「なんで……なんで……」
しかし、私の頭を埋め尽くすのは死というワードだけでは無かった。かぶりを振った私は頭で渦巻く思考を否定する。そんなはずはない、違う。否定の言葉で埋め尽くす度、無数に湧いてくるのは僅かな希望と、抱えきれないほどの絶望だった。
「違う、違う。あれは太陽じゃない……っ」
太陽、その単語が喉を通るたびに頭が思い出すことを拒否する。
幼稚園の時、穏やかな顔で『ほたる』と呼んでいたあの幼馴染が、大鎌を持って焦点の合わない虚ろな瞳で私を見下ろすはずがない。
しかし言葉とは裏腹に、私が違うの言葉を繰り返すたびに、二つの記憶は重なり合い一つの顔になっていく。
「何処にもいかないでって、約束したでしょ……?」
目の縁で零れないように堪えていた涙が、向かい風と一緒に吹き飛んでいく。風で崩れた前髪と、ぐちゃぐちゃになった顔は放課後デートに行くことは愚か、学校に行くことすらできないくらい酷い有様だ。
いっそのことこのまま電車に乗って何処か遠くへ行こう。デートはまた後日に先延ばしにしてもらおう。そしたらまず先輩に謝らなきゃな、夏帆にも迷惑掛けちゃったし。そう思った瞬間、ピピピと警告を伝える電子音が腕から鳴った。
「え、まっ」
「太陽……」
名前を呼ぶと、喉が沁みた。
目が覚めると白い天井が広がっていた。ピンク色のカーテンが視線を遮るように一周していて、意識が覚醒するのに合わせて機械の世話しない音が聞こえてくる。
「っ……腕時計!」
脳に電気が流されたような衝撃で飛び起きる。左腕に目をやるといつものスマートウォッチは外されていた。代わりに私に繋がれていた機械がビビビと物騒な音で騒ぐ。電光板に映る数字は、いつも私が左腕で確認している数字と良く似ていた。
「あ、起きましたか」
視線とは反対の向きから声がして振り返ると、表向きの笑顔を向けてくるナース服の女性がいた。忙しそうに隣のベットの対応をしていて顔はこちらを向いているが、彼女からは正直面倒くさいという感情が滲み出ている。
「あ、山中さん勝手にどこか行かないで‼また転んだらどうするの‼……すみません、霧島さん。すぐそちらに向かい説明いたしますので」
浅いお辞儀をするとその背中はまた百八十度回転する。シャッとカーテンが雑に閉じられた音とほぼ同時に隣から堪忍袋の緒が切れた看護師の怒号が聞こえてきたが、聞かなかったことにしておこう。
「それよりも今は自分の状況整理、だよね」
彼女は『すぐ向かう』と言っていたが、あれは二十分以上来ないパターンだ。未だに続く隣のベットの騒音を聞きそう確信した私は、もう一度白い天井を見て心を落ち着けることにした。
私のところを先ほどの女性の服装ぶりからしてここは病院で間違いないだろう。左隣の機械は恐らく心拍数患者モニターのはずだ。先ほどのけたたましい音は、突然上半身を起き上げたことで心拍数が一時的に上がったか、機械から繋がれているカラーコードが一瞬外れてしまったかの理由で機械が反応したためだと思われる。
「うん、今の状況は理解できた。でも……なんで?」
なんで私は病院にいるの。自分で訪れた記憶もない、だとしたら勝手に運ばれてここに来たの?何とか記憶を掘り起こそうとしても、腕にはめられたスマートウォッチの点滅とピピピという音から先は何も覚えていない。
「蛍ちゃん、お久しぶりだね」
私が眉間に皺を寄せていると突然目の前の視界が開けた。白衣を着用した六十代くらいの男性が皺くちゃの笑みを浮かべながら私の元へ近づいてくる。あの顔どこかで見たような。
「大石先生!ってことはここは大学病院ですか?」
「そう、正解。蛍ちゃんはどこまで覚えてるかな?」
「朝登校してて、叫んで、それから……腕時計が鳴って……」
「その後に君は倒れたんだよ。幸いお友達が一緒だったからすぐ救急車を呼んでくれて、蛍ちゃんは助かったわけ」
そうだ、夏帆。夏帆は無事だろうか、あの死神から逃げられただろうか。幸い運動神経に関して心配するものはないが、それでも死神という未知の生命体に何かされていたらと思うとゾッとする。顔を青くする私に、大石先生は心地の良いハスキーな声を響かせた。
「ちなみにご両親にはもう連絡済みで、今は一時帰宅しているよ」
「え……お母さん来たんですか?」
「あぁ、私が連絡を入れたら血相を変えて飛び込んできたよ。しかもご両親二人揃っていて私も正直驚いたよ」
両親が見舞いに来るなんて期待は、はなからしていない。元々私が幼いときから忙しい人で度々家を留守にするような仕事人間の二人なのだ。私が倒れたところで心配はするが、わざわざ有給消費してまでここに来るような人ではないはずなのに。
私は一体どれほど心配をかけることをしてしまったのだろう。
私が不安と驚きから首をすくめると、大石先生は倍音を維持したまま続ける。
「知っての通り君は生まれつきの心臓病を今まで薬でコントロールしてきた。お陰で少しの運動はできていたし、日常生活も問題なく送れていたね」
そう、私には生まれつき背負わされたハンデがある。それが心臓の病気であった。しかし、物心つくまでに行われた手術により今までは薬と年に1回の通院で現状維持を保ち続けていたのだ。それこそ大石先生の顔を見るまで病気のことを忘れるくらいに。
ハッとしてミニキャビネットに置かれている鉄の塊に触れる。先ほどけたたましい音で鳴いていた時計は赤く点滅していた。このスマートウォッチは私のような心臓病の患者が身に着けるもので、不整脈や何か心臓に不審な動きがあればアラームがなる仕組みだった。私は履歴を確認すると、5月××日8時16分を境に何度も何度も不整脈の文字が連なっている。
「けれど、今回の検査で心臓病の悪化が見られたんだ。去年の定期健診では確認できなかったこともあって、病気の進行はかなり早いと思われる」
「えっ……」
「倒れてから君は三日ほど意識が戻らなかったんだ。その間に使える薬は全部投与した」
「改善されたんですよね?いつもみたいに薬を飲めば」
「顕著な効果は認められなかった」
まるでこの世の絶望を全て詰め込んだその一言に私は顔をあげることができなくなった。
つまり、私は、死ぬの?
死神が持つ大鎌に引き裂かれて死ぬの?
まだ、まだ15歳だよ。高校に入って1か月しか経ってない、まだ青春のせの字も知らないまま私は……。
「先生、私死んじゃうんですか」
震える声で問う。
誰か、誰でもいい。ただ私の言葉を否定してくれればいい。
私が見た幼馴染は幻だって、あんな奴が死神なわけないって言ってくれ。
私はまだ、死にたくない。
僅かな期待を胸に伏していた目を開く。
視界の端でいつも冷静で私の前では感情を露わにしない先生が、静かに腕を脱力させたのが見えた。
「……いつ命が尽きてもおかしくない状態だ」
そこからの記憶はあまりなかった。ただ目の前のカーテンを見つめていたら、段々と部屋に入る光がオレンジ色に染まっていって、夜と夕暮れの境目くらいに再び私の視界は開けた。
「ほたる……?!」
聞きなれた声で初めて親友が来たことを知った。
「よかった、目が覚めたのね。本当によかった」
私の姿を見るなり駆け寄り抱きしめてくる彼女は制服姿だった。きっと学校が終わってから急いで駆けつけてくれたのだろう。申し訳ない。私のすぐ横には彼女の顔があった。ここに来るまでに泣いたのだろうか。目の縁が赤くなっていて、頬骨に涙の痕があるのを私はぼうっと見つめる。
「……夏帆」
彼女の名前を口にした途端、滅多に緩まないはずの涙腺が崩壊した。今日だけでもう二回も涙を流している。堪えなきゃ、これ以上心配を掛けたら駄目だ。溢れるものを抑えるためにぎゅっとシーツを掴む。私の人一倍強がりで、弱みを握られるのが大嫌いだという性格を知っている彼女は、私が目じりを誤魔化すように拭った瞬間目の色を変えて狼狽した。
「本当にどうしたの蛍。何か言われた?もしかして病気……悪化した?」
「ちがうの、違うんだけど違くなくて」
夏帆が来てくれた途端、安堵からまた頭の中がかき混ぜられたように思考がまとまらなくなる。そうか、私ずっと怖かったんだ。もし誰もいないこの部屋に、またあの死神が来たらどうしようって。私は逃げなきゃいけないけれど、今度会ったときは逃げたくないと思ってしまうかもしれないから。
もしかしたら生きたい感情より、太陽と話したい気持ちが勝ってしまうかもしれないから。
目を瞑って情報量を抑えようと思っても、瞼の裏に映るのはあの怪しさと冷淡さを秘めたビー玉の目だった。
私は改めて夏帆に向き合うと、痙攣する喉から声を振り絞った。
「夏帆、信じてくれなくていい。ただ話を聞いてほしいの」
「……分かった」
いつもの様子と違うことに気づいた彼女は崩していた足をわざわざ折りたたんで、私の目を真っすぐ射貫く。
いつでも真っすぐで、根は真面目な彼女のそんなところが今は有難かった。
「あの日、ナンパを見たって言ったでしょ」
「うん。でもあそこには本当に女の人しかいなかったじゃ、」
「あれ、死神だったの」
夏帆の血色のよい肌が途端に生気を失う。そのまま一歩後ずさりした彼女は『えっ』と一言発すると、目を見開いたまま聞いてはいけないものを聞いてしまったかのように息を殺す。
「しかもその死神、実は私の幼馴染そっくりの顔だったんだ」
口に出すと再びフラッシュバックしてくるあの瞬間。間合いに入った刹那のこの世とあの世の間をすり抜けた肌がひやっとする感覚と、見上げたフードの影で浮かび上がる真横に引き伸ばされた口角。強い風が吹いて慌ててフードを押さえつけるほんの僅かな隙に、見えてしまったのだ。
この十年間、一度も忘れることのなかった幼馴染の面影を彷彿とさせる端正な横顔が。
「ほんとベタなおとぎ話かよ~って感じだよね」
この淀んだ空気を何とかしようと思い空笑いしてみるが、彼女は依然深刻そうに俯きながら口に手を当てていた。暫くの静寂の後、顔を上げた親友の瞳は潤んでいた。彼女は受け入れがたいというように首を振って唇を噛む。
「蛍、やだよ……ねぇ、死神って何?本当に死んじゃうの?」
私はそれに無言のまま遠くを見つめる。私にも分からなかった。あれが本当に死神なのかは分からない。何なら私は死神じゃない可能性の方が高いと思っている。それを信じたい。けれど、あんなローブを、あんなに冷酷な瞳を、あんなに鋭利な鎌を、目の当たりにして死神じゃなければ彼は一体何者なの。死神以外に当てはまる名前を必死に探した。見つかりはしなかった。
「夏帆には太陽のこと話したっけ?」
「太陽って……確か、蛍の幼馴染の?」
私は夏帆の問いに頷くと、今まで深く触れてこなかった太陽と私の関係について深く話し始める。
実はこの話をするのには結構勇気が必要だった。何せ、常に強気な私の脆かった時代の話だからだ。けれど、夏帆になら聞いてもらいたいと思えた。息を細く吐き、深呼吸をする。記憶の蓋を開けば、お遊戯室のかび臭い匂いが鼻に充満した。
杉山太陽は私の幼馴染であり、唯一無二の男だった。彼と出会ったのは幼稚園のとき、男勝りな性格の私は当時クラスメイトから村八分にされていた。今考えれば仕方がなかったと思う。みんな同じがいい、可愛いものが正義でそれ以外は悪、が根幹である女児が、外で木登りをすることが好きでフリフリのレースよりも動きやすいズボンの方が好きな私のことを受け入れられるはずがなかった。しかし、当時の私は自分への待遇が悲しくて、また怒りに燃えていた。
自らの正義のみで世界が回っていると考えている彼女らが許せなかったのだ。私は彼女たちがキラキラした指輪が好きという感情と同じくらい、泥臭い外遊びが大好きだった。ただそれだけなのに、まるで私とあなたは違う生き物ねと勝手にタグ付けされて冷遇される世界が苦しかった。
そして同時にもう一人、クラスメイトから仲間外れにされている人がいた。それが太陽だった。
「太陽は名前通り、私の太陽だったの」
「……好きだったの?」
夏帆の言葉に私の脳内では太陽との思い出が湧き出す。
『たいよー……どこにもいかないで』
『どこにもいかないよ。ずっと、ずっとぼくがそばにいるからね』
『ほんとう?』
『うん、ずっとそばにいてだいすきっていう。かみさまに喉をとられちゃっても紙にかいてだいすきっていうし、もし書きすぎて紙がなくなっちゃったら……そしたら心のなかでずーっとだいすきするからね』
『……うん』
『だから、ほたるちゃんもう泣かないよ。わらって』
ただの過去の思い出だった。
ありふれた、幼稚園児の稚拙で脆くてすぐに忘れてしまうようなくだらない会話。
しかしそれが、痛いくらいに眩しく、私をいつまでも過去に縛り付ける。
そのときは漠然と私はきっと将来この人と結婚するんだろうなと思っていた。
「私と太陽は色々あって仲良くなったけど……小学校にあがるタイミングで彼は急に消えちゃった」
「消えたってどういうこと?」
「行方不明になったの。当時私が住んでいた場所は信じられないくらい田舎で、田んぼと山しかないようなところだったからご近所一軒一軒に訪ねては『うちにはいない』って門前払いされて、それから太陽のお母さんはみるみる元気がなくなってっちゃって」
あの日から全てが変わってしまったのだ。
『蛍ちゃん、もうやめにしましょう』、太陽のお母さんは最後にこう言ってつむじを見せた。村一番の美人と評判で、ふっくら艶のあった頬も痩せこけ見る影をなくし、目には青いクマが一生取れないシミみたいに浸み込んでいた。その顔が無理やり笑おうと歪むものだからあの時の私は不気味で仕方なかった。
「太陽さんは結局見つかったの?」
「ううん、未だに見つかってない」
「じゃあ彼はもう」
その言葉の続きを私は分かっていた。それでも認めたくない自分がずっと胸の中を占領していた。
彼はきっと死んでいる。
そんなこと、太陽のお母さんも私も頭では分かっていたはずだ。それでも探し続けたのは、それだけ太陽という存在が体を心を占めていたからだ。それは誰かの止める声も、罵声も、届かないくらい遠く遠くに、しかしたしかに、太陽が私たちに刻み続けてきたものがあったからだった。
「夏帆、ごめんね。今日はもう帰ってもらっていいかな」
「でも……」
「ちょっと一人で……考えたくて」
私が寂しげに、しかし有無を言わさぬ圧力でそう言うと、夏帆は頷き病室をそっと後にした。
半透明の体は明らかに生きているそれではなかった。
私はこれからどうなってしまうのだろう。死神に会おうが会わまいが、もうすぐ死ぬという事実に変わりはなかった。
しかし、もしあの死神にもう一度会えたなら話をしなければならない。
あの日、どうしていなくなったのか。
どうして死神になんてなってしまったのか。
どうしてあの朝、自分が誰なのか尋ねていたのか。
貴方は本当に太陽なのか。
死ぬのは怖かった。でも、あの死神が本当に太陽なら殺されてもいいと思ってしまった。
いや、正確には違う。
例え、太陽の皮を被った死神だとしても、私は迷いながらもきっと抱きしめてしまうだろうから。
そう、これは不可抗力なのだ。
『たいよー』
小さい頃の私がいつまで経っても心の奥で君の名前を呼んでいる。うるさい、もう太陽はいないかもしれないんだよ。何度も唱えたって、幼い私は不思議そうに今の私を見つめている。この子は私の本心を見透かしているのだろう。だから消えないのだ、いつまでもずっと私の中で溢れる言葉はたった一つのなのだ。
『どこにもいかないで』
肺が急激にしぼんで息が吸えなくなる。私はセミロングの髪をぐちゃぐちゃに揉みしだきながら、ベットの上で小さく蹲った。
「なんであんな奴、好きになっちゃったんだろう……」
初めて出会った君は天使だった。
柔らかい笑顔も、ふわふわとした髪も、色素の薄いまつ毛も、一瞬でも目を離せば何処かに飛んで行ってしまいそうな危うさも。
全部全部愛らしくて、いとおしくて。
『実はぼく、天使なんだ』と冗談を言われた日には、君があまりにも真剣な瞳で言うものだから真に受けてしまって。
私は思わず君を抱きとめて『どこにもいかないで』と懇願した。
君はそんな私に『どこにもいかないよ』と愛おしそうに笑う。
私はその時、人生で初めて頬が熱く焦げてしまいそうな感覚に襲われた。
再び私の目の前に現れた君は、違った。
私はすぐに分かった。君は死神になったんだと。
体に巻かれたローブも、瞳から絶望が零れてきそうな冷淡な表情も、透けた体も。
体は君のままなのに中身だけ何処かに消えてしまったかのような、そんな姿だった。
君は何も知らないようだ、ここがどこなのか、私は誰かのか、そして自分が誰なのか。
せり上がる慟哭を飲み下した私は小さく笑う。
「何処にもいかないでって、約束したでしょ……?」
喉から絞り出した言葉の意味を、君は覚えているだろうか。
高校の最初の一か月というのは噂通りあっという間であった。初めは迷いがちだったこの細い路地も、一か月も歩いていればそこはちゃんと自分の通学路になった。滑りやすい苔を避けるように歩くと、まだ真新しいローファーが軽やかな音を弾ませる。耳元で流れているのはお気に入りの洋楽だった。ベースの低音と、道路を走る抜ける車の音が重なって心地よい。鼻歌を交えながら歩いているとふと違和感を覚えた。耳に神経を集中させると、ボーカルの声に少しノイズが掛かっているような気がする。
「あちゃ~、私昨日充電してなかったっけ」
母親のお古で貰ったこのワイヤレスイヤホンは充電が切れそうになると、黒板を机で引っ搔いたような残酷な音が聞こえてくる。対処法は鼓膜が破壊されないうちに耳から外し、充電することのみ。私はため息を吐くと、ブルートゥースの接続を切った。
しかしこの程度で私の機嫌が損なわれる訳ではない。
だって、
「よっす!」
突然、背中に衝撃が伝わる。吃驚して肩を震わせながら後ろを振り返ると、耳元でピアスを揺らす少女が私の背中を思い切り叩いていた。
「怖いよ、夏帆。あと、そんなに勢い付けたら苔で滑るよ」
「いやいやこの夏帆様の身体能力を見くびるでない」
そう言って胸を張る少女は中学校からの親友夏目夏帆だ。確かに彼女の身体能力は異常だった。握力は60近く、持久走は3年連続学年一位の快挙を達成する彼女は、体は華奢なのに中身はほぼゴリラという残念女子である。
動けないように縄で縛って黙らせれば可憐な美少女という言葉が似あうのに……。しかし本人は私の落胆に気づくことなく、風になびく黒髪を抑えながら笑った。
「蛍、今日はご機嫌だねぇ。もしかして、先輩から連絡来た……?」
「それ聞いちゃう?実は……」
そう溜めると、私はスクールバックからゴソゴソと端末を取り出し、昨日興奮して何枚もスクリーンショットした写真を液晶いっぱいに拡大した。夏帆は一通り目を通すと、声にならない悲鳴をあげる。
「んー、何なに?ほ、う、か、ご、一緒に遊ばない……ってえぇ?!蛍まじ?デート誘われたってこと?」
「どうしよう、私まともな服持ってないよー!」
私の返答に「きゃー」とわざとらしくジタバタした夏帆はまるで自分事のようにキラキラと瞳を輝かせる。そう、私が例えイヤホンの充電が切れようが、車道の泥水が思い切り全身に掛かろうが、菩薩顔で過ごせるのは私の憧れの先輩から放課後のお誘いを受けたからである。
嗚呼、先輩という単語を出す度にシャープな横顔や女子よりも長いまつ毛を思い出す。放課後デート、なんて素敵な響きなんだろう。舌頭に転がせば甘く痺れるような感覚に襲われた。
「やばい、流石にドキドキしてきた」
「だってサッカー部キャプテンでしょ、モテモテだもんね。確実にゲットするよ、これは」
「うーん、でも先輩みたいな人がこんなちんちくりん相手にしてくれるのかなぁ」
自分と先輩が隣に並ぶ姿を想像する。154センチの私のつむじはきっと先輩の横腹くらいだ、あまりにバランスが悪すぎた。
それでもいい、大事なのは顔を見合わせて会話することじゃないし、無理にかがんで気を使わせることでもない。一緒の空間で同じ時を共有することなのだ。顔にじんわりと熱が集まり、思わず両頬に手を当てる。
これはきっと憧れではなく、恋なのだ。うん、そうに違いない。
「蛍なら大丈夫よ!ちなみに先輩のタイプは?」
「えっと……確か、黒のワンピースと長髪が似合う子だったような」
「まじ?あたし、黒のワンピース持ってるよ!放課後、うち寄ってきな」
男前にウインクした彼女の腕を私は手に取りぶんぶんと振る。嗚呼、神様仏様夏帆さま。今日のデートの勝ちの絶対を確信したところで私は、ふと視界の端に映る男女が目に留まった。なんだろう、あれは。黒のパンプスにリクルートスーツを身にまとう女性と、黒のコートを羽織る人。家族、友人ならば会話しながら出勤しているんだろうなで終わるのにどうしてか胸がざわついた。
暫く観察を続けてその違和感の正体がようやく分かった。男性が話しているのに対して女性はまるでそこには誰もいないようにただひたすら歩いているのだ。
「ねぇ夏帆。あれ、ナンパかな?」
「え?あれって……どれ?」
私は眉をひそめながら、指をさす。おかしい、代名詞を使ったとは言え私たちの目の前には一人の女性と全身黒の性別不明の人しかいないのに。夏帆は、まだ分からないというように首を振る。
性別不明の人は女性が忙しそうにヒールを鳴らしているにも関わらず、しつこく話しかけていた。
この光景以外で私がナンパじゃないかと聞けるものは一つもない。
それにも関わらず夏帆は目を細めて辺りを見回してから、再び困惑したように首を傾げた。そんな彼女がもどかしくて、私は早口でまくしたてる。
「あの人だよ。黒い人と通勤中の女の人」
「何言ってるの、蛍。目の前には女の人しかいないよ?」
え、と気の抜けた声が漏れる。
衝撃で足が止まりそうだったけれど、体は勝手に夏帆と同じペースで歩みをやめなかった。やがて女性との距離が無くなると夏帆は私の横腹を肘で小突く。
「ほらー、やっぱり何もないでしょ」
耳打ちの声が不思議と遠かった。私の視線は例の人にくぎ付けだった。おかしい、夏帆は見えていないのか、こんなにも近いのに。首の後ろに冷たい汗が流れる。息が浅くなるのと同時に肩があがっていくのが自分でもわかった。
「……すか、僕は誰ですか?」
一歩、一歩近づくにつれて少し掠れたハスキーな声が聞こえてくる。私は何故かその声に既視感を覚えた。こんな変な人、今まで会ったことはないはずなのに何故だろう。
服も、たまたま全身黒色のコーデだと思っていたが少し違った。頭から垂れる長めのローブが足首まで覆い、全身を黒く見せていたようだ。顔もすっぽり覆ってしまっているせいで良く見えなかった。
彼はもう一度、女性のコートの裾を掴むと懇願するように言う。
「教えてください、僕は誰なんですか。ここは……ここはどこですか?」
最近のナンパ事情はこんなにも奇妙な技を使うのだろうか。記憶喪失を装って女の人を誘おうだなんてなんて質の悪い……新手の嫌がらせのようにも思える。電柱の影から観察していたが、あれだけしつこく絡まれている姿を見ていると段々と女性が気の毒に思えてきた。ただでさえ憂鬱な出勤中にこんなにも粘着に話しかけられたら参ってしまうだろう。逡巡の迷いののち、私は思い切って男の人に声を掛けてみることにした。
「どうしたの、蛍」
私の動きに夏帆が不安そうに尋ねる。私は「大丈夫、少し声を掛けるだけだから」と彼女を電柱の影に待機させた。大丈夫と自分で言っておきながら息苦しいほどの不安が肺をいっぱいにさせる。私は深呼吸をするとお得意のにこやかな人懐こいいつもの笑みを作り、ローファーを鳴らした。
「あのぅ、どうかされましたか?」
黒いローブの影は驚いたように前後に揺れると、ゆっくりと振り返る。こちらを伺うような瞳がローブの下から見えた。
その瞬間、私は叫びたい衝動に襲われた。
逃げ出したくても、足が震えて微動だにできない。その瞬間、街路樹が風に揺れる音も、角を曲がった女性の地面を鳴らす音も、何も聞こえなくなった。無音の世界が、そこには広がっていた。私はただ瞳に涙を溜めながら、彼を見上げる。
なんで
「……君は僕のことが分かるの?」
なんでいるの
「あ……え……」
言葉なんか出てきやしなかった。呻き声に近い音が喉の奥から漏れる。目を何度も瞬かせても、彼の姿が変わることはなかった。
忘れもしない。
夏の名残みたいなラムネの底に沈んでいるビー玉の瞳も、光に透けると透明になる色素の薄いまつ毛も。全部、全部全身にこびりついて離れなくて忘れられなくて。お陰で私は十年も拗らせて。
未だに目を閉じればそこには幼稚園のときのあたたかなひと時と、君の柔らかい笑顔がそこにはあった。
「太陽、なの?」
会えなくなってから何度この名前を口にしただろう。
私が疑うように問うと、彼は無表情のまま距離を詰める。嚙み殺されるんじゃないかと思うくらいの距離で肩を力強く握られた。その手のひらには私を気遣うような力加減は一切ない。期待を込めて君の名前を呼んだ私が間違っていたのだろうか。その瞬間私の思い描いていた太陽は脆いガラスのようにひび割れて砕け散り、目の前にはただ冷徹な目を持った男がいた。
「僕が誰か、分かる?」
冷淡な瞳が一歩、距離を縮める。私はその分一歩、後ずさりをする。息が上手く吸えなくて不規則な呼吸音だけがやけに大きく聞こえた。グラっと突然視界が歪んだ。何が起こったのか分からず数秒硬直したまま瞳だけを動かす。嗚呼、私腰を抜かしたんだ。見上げる彼との距離は更に大きくなり、私はもう何も考えることが出来なかった。私と同じ目線になるためにしゃがみ込んだ彼の黒いローブの後ろには、白く光る大きな鎌が覗いている。
どうやら、私の初恋の相手は死神になってしまったみたいだ。
「いやああああああああああああああ」
ふっと気が緩んだ瞬間、口から出た咆哮が合図だった。私は下半身に力を入れると、立ち上がりその場から全力疾走する。隣を走る車に負けないくらい一生懸命腕を振って、制服のスカートなんか気にせずに全力で地面を蹴り上げる。
とにかく遠くへと逃げたかった。あいつが、あの死神が追い付けないところまで、逃げなければならなかった。
死にたくない。こんなところで死ねない。
「なんで……なんで……」
しかし、私の頭を埋め尽くすのは死というワードだけでは無かった。かぶりを振った私は頭で渦巻く思考を否定する。そんなはずはない、違う。否定の言葉で埋め尽くす度、無数に湧いてくるのは僅かな希望と、抱えきれないほどの絶望だった。
「違う、違う。あれは太陽じゃない……っ」
太陽、その単語が喉を通るたびに頭が思い出すことを拒否する。
幼稚園の時、穏やかな顔で『ほたる』と呼んでいたあの幼馴染が、大鎌を持って焦点の合わない虚ろな瞳で私を見下ろすはずがない。
しかし言葉とは裏腹に、私が違うの言葉を繰り返すたびに、二つの記憶は重なり合い一つの顔になっていく。
「何処にもいかないでって、約束したでしょ……?」
目の縁で零れないように堪えていた涙が、向かい風と一緒に吹き飛んでいく。風で崩れた前髪と、ぐちゃぐちゃになった顔は放課後デートに行くことは愚か、学校に行くことすらできないくらい酷い有様だ。
いっそのことこのまま電車に乗って何処か遠くへ行こう。デートはまた後日に先延ばしにしてもらおう。そしたらまず先輩に謝らなきゃな、夏帆にも迷惑掛けちゃったし。そう思った瞬間、ピピピと警告を伝える電子音が腕から鳴った。
「え、まっ」
「太陽……」
名前を呼ぶと、喉が沁みた。
目が覚めると白い天井が広がっていた。ピンク色のカーテンが視線を遮るように一周していて、意識が覚醒するのに合わせて機械の世話しない音が聞こえてくる。
「っ……腕時計!」
脳に電気が流されたような衝撃で飛び起きる。左腕に目をやるといつものスマートウォッチは外されていた。代わりに私に繋がれていた機械がビビビと物騒な音で騒ぐ。電光板に映る数字は、いつも私が左腕で確認している数字と良く似ていた。
「あ、起きましたか」
視線とは反対の向きから声がして振り返ると、表向きの笑顔を向けてくるナース服の女性がいた。忙しそうに隣のベットの対応をしていて顔はこちらを向いているが、彼女からは正直面倒くさいという感情が滲み出ている。
「あ、山中さん勝手にどこか行かないで‼また転んだらどうするの‼……すみません、霧島さん。すぐそちらに向かい説明いたしますので」
浅いお辞儀をするとその背中はまた百八十度回転する。シャッとカーテンが雑に閉じられた音とほぼ同時に隣から堪忍袋の緒が切れた看護師の怒号が聞こえてきたが、聞かなかったことにしておこう。
「それよりも今は自分の状況整理、だよね」
彼女は『すぐ向かう』と言っていたが、あれは二十分以上来ないパターンだ。未だに続く隣のベットの騒音を聞きそう確信した私は、もう一度白い天井を見て心を落ち着けることにした。
私のところを先ほどの女性の服装ぶりからしてここは病院で間違いないだろう。左隣の機械は恐らく心拍数患者モニターのはずだ。先ほどのけたたましい音は、突然上半身を起き上げたことで心拍数が一時的に上がったか、機械から繋がれているカラーコードが一瞬外れてしまったかの理由で機械が反応したためだと思われる。
「うん、今の状況は理解できた。でも……なんで?」
なんで私は病院にいるの。自分で訪れた記憶もない、だとしたら勝手に運ばれてここに来たの?何とか記憶を掘り起こそうとしても、腕にはめられたスマートウォッチの点滅とピピピという音から先は何も覚えていない。
「蛍ちゃん、お久しぶりだね」
私が眉間に皺を寄せていると突然目の前の視界が開けた。白衣を着用した六十代くらいの男性が皺くちゃの笑みを浮かべながら私の元へ近づいてくる。あの顔どこかで見たような。
「大石先生!ってことはここは大学病院ですか?」
「そう、正解。蛍ちゃんはどこまで覚えてるかな?」
「朝登校してて、叫んで、それから……腕時計が鳴って……」
「その後に君は倒れたんだよ。幸いお友達が一緒だったからすぐ救急車を呼んでくれて、蛍ちゃんは助かったわけ」
そうだ、夏帆。夏帆は無事だろうか、あの死神から逃げられただろうか。幸い運動神経に関して心配するものはないが、それでも死神という未知の生命体に何かされていたらと思うとゾッとする。顔を青くする私に、大石先生は心地の良いハスキーな声を響かせた。
「ちなみにご両親にはもう連絡済みで、今は一時帰宅しているよ」
「え……お母さん来たんですか?」
「あぁ、私が連絡を入れたら血相を変えて飛び込んできたよ。しかもご両親二人揃っていて私も正直驚いたよ」
両親が見舞いに来るなんて期待は、はなからしていない。元々私が幼いときから忙しい人で度々家を留守にするような仕事人間の二人なのだ。私が倒れたところで心配はするが、わざわざ有給消費してまでここに来るような人ではないはずなのに。
私は一体どれほど心配をかけることをしてしまったのだろう。
私が不安と驚きから首をすくめると、大石先生は倍音を維持したまま続ける。
「知っての通り君は生まれつきの心臓病を今まで薬でコントロールしてきた。お陰で少しの運動はできていたし、日常生活も問題なく送れていたね」
そう、私には生まれつき背負わされたハンデがある。それが心臓の病気であった。しかし、物心つくまでに行われた手術により今までは薬と年に1回の通院で現状維持を保ち続けていたのだ。それこそ大石先生の顔を見るまで病気のことを忘れるくらいに。
ハッとしてミニキャビネットに置かれている鉄の塊に触れる。先ほどけたたましい音で鳴いていた時計は赤く点滅していた。このスマートウォッチは私のような心臓病の患者が身に着けるもので、不整脈や何か心臓に不審な動きがあればアラームがなる仕組みだった。私は履歴を確認すると、5月××日8時16分を境に何度も何度も不整脈の文字が連なっている。
「けれど、今回の検査で心臓病の悪化が見られたんだ。去年の定期健診では確認できなかったこともあって、病気の進行はかなり早いと思われる」
「えっ……」
「倒れてから君は三日ほど意識が戻らなかったんだ。その間に使える薬は全部投与した」
「改善されたんですよね?いつもみたいに薬を飲めば」
「顕著な効果は認められなかった」
まるでこの世の絶望を全て詰め込んだその一言に私は顔をあげることができなくなった。
つまり、私は、死ぬの?
死神が持つ大鎌に引き裂かれて死ぬの?
まだ、まだ15歳だよ。高校に入って1か月しか経ってない、まだ青春のせの字も知らないまま私は……。
「先生、私死んじゃうんですか」
震える声で問う。
誰か、誰でもいい。ただ私の言葉を否定してくれればいい。
私が見た幼馴染は幻だって、あんな奴が死神なわけないって言ってくれ。
私はまだ、死にたくない。
僅かな期待を胸に伏していた目を開く。
視界の端でいつも冷静で私の前では感情を露わにしない先生が、静かに腕を脱力させたのが見えた。
「……いつ命が尽きてもおかしくない状態だ」
そこからの記憶はあまりなかった。ただ目の前のカーテンを見つめていたら、段々と部屋に入る光がオレンジ色に染まっていって、夜と夕暮れの境目くらいに再び私の視界は開けた。
「ほたる……?!」
聞きなれた声で初めて親友が来たことを知った。
「よかった、目が覚めたのね。本当によかった」
私の姿を見るなり駆け寄り抱きしめてくる彼女は制服姿だった。きっと学校が終わってから急いで駆けつけてくれたのだろう。申し訳ない。私のすぐ横には彼女の顔があった。ここに来るまでに泣いたのだろうか。目の縁が赤くなっていて、頬骨に涙の痕があるのを私はぼうっと見つめる。
「……夏帆」
彼女の名前を口にした途端、滅多に緩まないはずの涙腺が崩壊した。今日だけでもう二回も涙を流している。堪えなきゃ、これ以上心配を掛けたら駄目だ。溢れるものを抑えるためにぎゅっとシーツを掴む。私の人一倍強がりで、弱みを握られるのが大嫌いだという性格を知っている彼女は、私が目じりを誤魔化すように拭った瞬間目の色を変えて狼狽した。
「本当にどうしたの蛍。何か言われた?もしかして病気……悪化した?」
「ちがうの、違うんだけど違くなくて」
夏帆が来てくれた途端、安堵からまた頭の中がかき混ぜられたように思考がまとまらなくなる。そうか、私ずっと怖かったんだ。もし誰もいないこの部屋に、またあの死神が来たらどうしようって。私は逃げなきゃいけないけれど、今度会ったときは逃げたくないと思ってしまうかもしれないから。
もしかしたら生きたい感情より、太陽と話したい気持ちが勝ってしまうかもしれないから。
目を瞑って情報量を抑えようと思っても、瞼の裏に映るのはあの怪しさと冷淡さを秘めたビー玉の目だった。
私は改めて夏帆に向き合うと、痙攣する喉から声を振り絞った。
「夏帆、信じてくれなくていい。ただ話を聞いてほしいの」
「……分かった」
いつもの様子と違うことに気づいた彼女は崩していた足をわざわざ折りたたんで、私の目を真っすぐ射貫く。
いつでも真っすぐで、根は真面目な彼女のそんなところが今は有難かった。
「あの日、ナンパを見たって言ったでしょ」
「うん。でもあそこには本当に女の人しかいなかったじゃ、」
「あれ、死神だったの」
夏帆の血色のよい肌が途端に生気を失う。そのまま一歩後ずさりした彼女は『えっ』と一言発すると、目を見開いたまま聞いてはいけないものを聞いてしまったかのように息を殺す。
「しかもその死神、実は私の幼馴染そっくりの顔だったんだ」
口に出すと再びフラッシュバックしてくるあの瞬間。間合いに入った刹那のこの世とあの世の間をすり抜けた肌がひやっとする感覚と、見上げたフードの影で浮かび上がる真横に引き伸ばされた口角。強い風が吹いて慌ててフードを押さえつけるほんの僅かな隙に、見えてしまったのだ。
この十年間、一度も忘れることのなかった幼馴染の面影を彷彿とさせる端正な横顔が。
「ほんとベタなおとぎ話かよ~って感じだよね」
この淀んだ空気を何とかしようと思い空笑いしてみるが、彼女は依然深刻そうに俯きながら口に手を当てていた。暫くの静寂の後、顔を上げた親友の瞳は潤んでいた。彼女は受け入れがたいというように首を振って唇を噛む。
「蛍、やだよ……ねぇ、死神って何?本当に死んじゃうの?」
私はそれに無言のまま遠くを見つめる。私にも分からなかった。あれが本当に死神なのかは分からない。何なら私は死神じゃない可能性の方が高いと思っている。それを信じたい。けれど、あんなローブを、あんなに冷酷な瞳を、あんなに鋭利な鎌を、目の当たりにして死神じゃなければ彼は一体何者なの。死神以外に当てはまる名前を必死に探した。見つかりはしなかった。
「夏帆には太陽のこと話したっけ?」
「太陽って……確か、蛍の幼馴染の?」
私は夏帆の問いに頷くと、今まで深く触れてこなかった太陽と私の関係について深く話し始める。
実はこの話をするのには結構勇気が必要だった。何せ、常に強気な私の脆かった時代の話だからだ。けれど、夏帆になら聞いてもらいたいと思えた。息を細く吐き、深呼吸をする。記憶の蓋を開けば、お遊戯室のかび臭い匂いが鼻に充満した。
杉山太陽は私の幼馴染であり、唯一無二の男だった。彼と出会ったのは幼稚園のとき、男勝りな性格の私は当時クラスメイトから村八分にされていた。今考えれば仕方がなかったと思う。みんな同じがいい、可愛いものが正義でそれ以外は悪、が根幹である女児が、外で木登りをすることが好きでフリフリのレースよりも動きやすいズボンの方が好きな私のことを受け入れられるはずがなかった。しかし、当時の私は自分への待遇が悲しくて、また怒りに燃えていた。
自らの正義のみで世界が回っていると考えている彼女らが許せなかったのだ。私は彼女たちがキラキラした指輪が好きという感情と同じくらい、泥臭い外遊びが大好きだった。ただそれだけなのに、まるで私とあなたは違う生き物ねと勝手にタグ付けされて冷遇される世界が苦しかった。
そして同時にもう一人、クラスメイトから仲間外れにされている人がいた。それが太陽だった。
「太陽は名前通り、私の太陽だったの」
「……好きだったの?」
夏帆の言葉に私の脳内では太陽との思い出が湧き出す。
『たいよー……どこにもいかないで』
『どこにもいかないよ。ずっと、ずっとぼくがそばにいるからね』
『ほんとう?』
『うん、ずっとそばにいてだいすきっていう。かみさまに喉をとられちゃっても紙にかいてだいすきっていうし、もし書きすぎて紙がなくなっちゃったら……そしたら心のなかでずーっとだいすきするからね』
『……うん』
『だから、ほたるちゃんもう泣かないよ。わらって』
ただの過去の思い出だった。
ありふれた、幼稚園児の稚拙で脆くてすぐに忘れてしまうようなくだらない会話。
しかしそれが、痛いくらいに眩しく、私をいつまでも過去に縛り付ける。
そのときは漠然と私はきっと将来この人と結婚するんだろうなと思っていた。
「私と太陽は色々あって仲良くなったけど……小学校にあがるタイミングで彼は急に消えちゃった」
「消えたってどういうこと?」
「行方不明になったの。当時私が住んでいた場所は信じられないくらい田舎で、田んぼと山しかないようなところだったからご近所一軒一軒に訪ねては『うちにはいない』って門前払いされて、それから太陽のお母さんはみるみる元気がなくなってっちゃって」
あの日から全てが変わってしまったのだ。
『蛍ちゃん、もうやめにしましょう』、太陽のお母さんは最後にこう言ってつむじを見せた。村一番の美人と評判で、ふっくら艶のあった頬も痩せこけ見る影をなくし、目には青いクマが一生取れないシミみたいに浸み込んでいた。その顔が無理やり笑おうと歪むものだからあの時の私は不気味で仕方なかった。
「太陽さんは結局見つかったの?」
「ううん、未だに見つかってない」
「じゃあ彼はもう」
その言葉の続きを私は分かっていた。それでも認めたくない自分がずっと胸の中を占領していた。
彼はきっと死んでいる。
そんなこと、太陽のお母さんも私も頭では分かっていたはずだ。それでも探し続けたのは、それだけ太陽という存在が体を心を占めていたからだ。それは誰かの止める声も、罵声も、届かないくらい遠く遠くに、しかしたしかに、太陽が私たちに刻み続けてきたものがあったからだった。
「夏帆、ごめんね。今日はもう帰ってもらっていいかな」
「でも……」
「ちょっと一人で……考えたくて」
私が寂しげに、しかし有無を言わさぬ圧力でそう言うと、夏帆は頷き病室をそっと後にした。
半透明の体は明らかに生きているそれではなかった。
私はこれからどうなってしまうのだろう。死神に会おうが会わまいが、もうすぐ死ぬという事実に変わりはなかった。
しかし、もしあの死神にもう一度会えたなら話をしなければならない。
あの日、どうしていなくなったのか。
どうして死神になんてなってしまったのか。
どうしてあの朝、自分が誰なのか尋ねていたのか。
貴方は本当に太陽なのか。
死ぬのは怖かった。でも、あの死神が本当に太陽なら殺されてもいいと思ってしまった。
いや、正確には違う。
例え、太陽の皮を被った死神だとしても、私は迷いながらもきっと抱きしめてしまうだろうから。
そう、これは不可抗力なのだ。
『たいよー』
小さい頃の私がいつまで経っても心の奥で君の名前を呼んでいる。うるさい、もう太陽はいないかもしれないんだよ。何度も唱えたって、幼い私は不思議そうに今の私を見つめている。この子は私の本心を見透かしているのだろう。だから消えないのだ、いつまでもずっと私の中で溢れる言葉はたった一つのなのだ。
『どこにもいかないで』
肺が急激にしぼんで息が吸えなくなる。私はセミロングの髪をぐちゃぐちゃに揉みしだきながら、ベットの上で小さく蹲った。
「なんであんな奴、好きになっちゃったんだろう……」