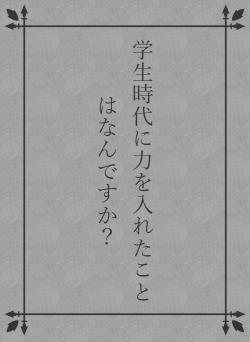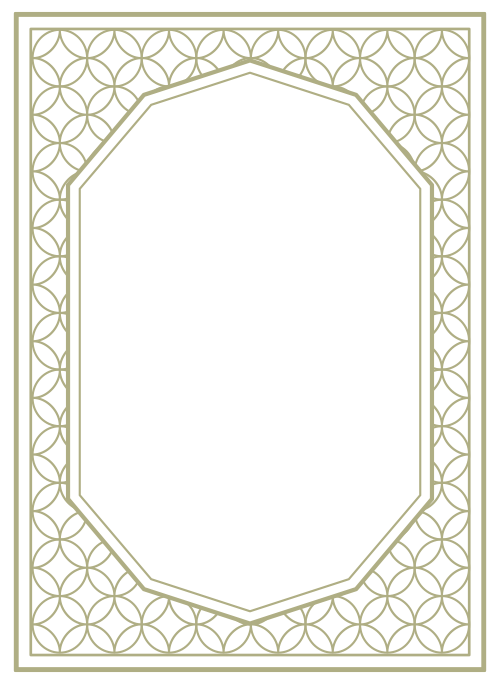その少女に初めて出会ったのも、地蔵の前だった。
山と里は結界で隔たれているが、あくまでもそれは下級の邪気だけの話であり、俺は昔から好きに行き来ができていた。
気まぐれで山を降りたその先で、傷だらけの着物に身を包んだ少女が座っているのを見かけて足を止めた。
あんな地蔵に何か祈っているのだろうか。そんなことを思っていたら、少女の後ろから小石が飛んできた。少し離れたところで同い年ぐらいの子どもたちが数人集まっている。
「生贄が地蔵守ってんじゃねえよ」「そこどけ」「どうせ地蔵に生贄やめたいですってお祈りしてんだろ」
少女は身体中に石をぶつけられながらも、そこを断固として動くことはなかった。
なぜそんなところにいるのか。離れてしまえばいい。
少女が小さな声で言った。
「もう……このお地蔵様に意地悪しないで」
よく見れば、地蔵の一部が欠けていた。おそらくあの子どもたちが地蔵に石を投げているのを目撃し、少女が身体を張って守っているのだろう。健気で、不憫だ。
それに──
「……生贄、ね」
それをじっと見つめる。
これまでにも何人か生贄と呼ばれる少女が村から送られてきた。
しかしその全員を、村へと返してきた。正直、そんなものは必要もないのだが、鬼は人と関わることは禁じられている。何十年前か、とある少女が生贄として供えられたが「あの村には戻りたくない」と言ったために、隣の村へとおろしてやった。
そのせいか「山に入ると出られなくなる」といった言い伝えが村にできているらしい。
そうでなくとも、病が流行ると「鬼神様が怒っている」と意味のわからない解釈とともに、人間を供え物にしようとしてくる。
今度の娘はあの子か。
空中で、指で小さく円を描く。するとたちまち風が吹き、それをひょいっと子どもたちがいる場所へと向けて投げた。
「う、うわっなんだ!?」「竜巻か!?」
慌てて退散する子どもたちに、少女がおそるおそる顔を上げて見送っている。
いなくなったのを確認すると、ホッとしたような顔で投げられた石をまた元の場所に戻し始めた。
それから地蔵の前まで行くと、自分の着物の裾を破り、地蔵の欠けた場所に巻いた。
「……変かな。お地蔵様にはいらないかも。でも、お地蔵を直せる力はないし」
そうして近くにあった彼岸花を手にして「ごめんなさい」と小さく言った。
「これだと枯れちゃうかな……そのまま咲いていたかったよね」
まさか、彼岸花に謝っているのか?
「でも、お地蔵様のお花がないから……ごめんなさい」
鮮やかな赤が古びた花瓶を彩る。
小さな歩幅で少女が帰っていく。見てみたくなった。どんな教育を受けたらあんな子どもに育つのだろうか。
そうして、わかった。
あれは親の教育ではない。あの子自身に備わった心なのだと。
「だから! 言い方が違うって言ってるでしょう!」
帰宅してからの少女は、母から厳しく叱責されていた。理由は「きちんと怒れないから」だ。
「邪魔者! いい? 思いっきり恨むみたいな感じで言うの!」
「じゃ、じゃま……」
「もう! なんでこんなこともできないのよ!」
どんと肩を押され地べたに転がる。少女は「ごめんなさい」と震えた声で言った。しかし母親は少女を見向きもしないで家の中に入り、施錠した。
「ごめんなさい……ごめんなさい」
ぽつり、ぽつり、と少女の頬に涙がこぼれる。
少女が恨まれているのは、その容姿のせいだろう。子どもながらに大人びており、整った顔立ちをしていた。
「おいで」
気付けば地面に降りて少女を呼んでいた。
「……だれ、ですか?」
「隣の村から来たんだ。美味しいご飯を食べよう」
なんて誘えばいいかわからなかった。でも、この言葉なら、どんな人間でも喜ぶと思った。
しかし少女は首を左右に振るだけだった。
「……だめ、私は食べちゃいけないから」
「どうして?」
「ちゃんと……怒れなかったから」
怒られたからではなく、怒れなかった。
「ちょっと、だれと話してるの?」
家の窓から少女と似た顔がこちらを見ていた。
髪も肌も、まるで与えられたものを充分に受けているような身なりだった。しかし、少女と比べると、美しさの差は歴然だった。似てはいるが、しかし何かが似ていない。また虐げられている少女のほうが圧倒的に綺麗だった。
「あっ……その」
よく似た少女は窓から出たあの顔に怯えていた。
「大丈夫」
涙を溢していた少女の前に立ち、こちらを不思議そうに見ている少女に手をかざした。すると、ぱたりと意識を失うようにその場に倒れた。
「えっ……ど、どうしたんですか」
「眠っているだけ。心配しなくてもいい」
「あっ……でも、見つかってしまったので」
「忘れているさ。大丈夫、俺の言うことを信じて」
彼女に手を伸ばす。
「ほら、行こう」
連れ出して、そのあとどうするべきかは考えていなかった。
ただ、あの場に少女を置いておきたくなかったのだ。
「何が食べたい? どこに行きたい?」
「あ……ええと」
もじもじとしていた彼女は、やがて躊躇しながら「お地蔵様のところに」と行った。
どこへでも連れて行こうと思っていた。
それなのに、さっきまでいた場所でいいというのだろうか。
少女を連れて地蔵の前まで歩いてくると、しきりに後ろを気にしている。
「この時間は外出してはいけないことになっているんです。だから、ここにいることがバレてしまったら」
「俺が説明する」
「あの、どうしてそこまでしてくださるんですか……?」
そう聞かれて戸惑った。
いつかこの子が俺の元に生贄としてやってくるからだろうか。
いや、そうではない。
まだこの国にも、心のやさしい人間がいるのだとわかったからだ。
いつか出会ったとき、彼女は俺のことを覚えているだろうか。
いや、忘れていたほうがいい。
「名を教えてくれ」
少女は首を傾げ、それからはっとした。
「千代です」
「……いい名だな」
「祖母がつけてくれたんです」
初めて見せる笑みだった。自分の名を気に入っているというよりも、その祖母を愛していたのだろう。
「あの、お地蔵様に詳しかったりしますか」
「なぜ?」
「……お地蔵さんが男か女か知りたかったのです」
ふっと、笑ってしまいそうだった。
本物を知ったらこの子はどんな顔を見せるのだろうか。時折、山に訪れてはくるが、未だに若作りに励んでいる。
「そうだな……どっちだと思う?」
「考えてみたんですが、わからなくて……ただ、女物の柄が好きでないのならと思って」
彼女は、さっき自分が巻いた着物を見ていた。なるほど、地蔵の趣味を気にしているのか。
「そういう意味では気にしない人だろう。地蔵が知りたいのは人の心だから」
「心……?」
「どんなものを供えられたとしても、そこに心があればいい。真心というやつだろうな」
子どもには少し難しかっただろうか。
少女は少し考えたあと「……ありがとうございます」と深々と頭を下げた。
邪魔者だと言えない少女。人を怒れない少女。
「さっきは、どうしてあんな練習を?」
「あ……ええと、悪役をしないといけなくて」
少女は手を何度か変えた。
「私は生贄として産まれて……最後まで悪い人でいろと姉に言われて」
「どうして君が?」
「生贄になっていいからです」
まるで、そう言われて育ってきたような人間の言葉だった。
自分なんてどこにもない。そうすることが当たり前かのように。
「そんな人はいないよ」
「え……」
「でも、君が来てくれたら楽しいだろうね」
「楽しい、ですか……私が供物で、向こうの人は満足してもらえるんでしょうか」
自分が生贄になるということよりも、供物としての自分に価値があるのか。
そこまで考えてしまうようになったのは、やはりあの親の影響なのか。
「大丈夫、生贄としてじゃなくて、受け入れてくれるさ」
「……それなら、よかったです」
ホッとしたような顔。
「……いつか、迎えに行こう」
「え?」
「そう遠くない未来に」
彼女に手を向ける。記憶を消す。覚えていないほうがいい。忘れたまま生きなさい。
そうして、また見つけた。ずっと待っていた。彼女が現れてくれるのを。
地蔵の前に座るその姿を見たとき、つい抱きしめてしまいたくなった。
いたのか、そうか、ずっとここにいたのか。
そんな瞳を宿して、生きてきてしまったのか。
俺を見るその目は全てに絶望していた。あの頃の瞳では、もう俺を見てくれないだろうか。
会ったことがあると言えば、君は驚いただろう。
『人が神を敬うように、人を敬っていたのが鬼だとしたら……とてもいい人だったと思います』
だが、心はあの頃のままだ。今はそれだけでいい。
もうすぐだ、迎えに行くのは。待っていろ──千代。
腕に巻いた淡い桃色の布が揺れた。
山と里は結界で隔たれているが、あくまでもそれは下級の邪気だけの話であり、俺は昔から好きに行き来ができていた。
気まぐれで山を降りたその先で、傷だらけの着物に身を包んだ少女が座っているのを見かけて足を止めた。
あんな地蔵に何か祈っているのだろうか。そんなことを思っていたら、少女の後ろから小石が飛んできた。少し離れたところで同い年ぐらいの子どもたちが数人集まっている。
「生贄が地蔵守ってんじゃねえよ」「そこどけ」「どうせ地蔵に生贄やめたいですってお祈りしてんだろ」
少女は身体中に石をぶつけられながらも、そこを断固として動くことはなかった。
なぜそんなところにいるのか。離れてしまえばいい。
少女が小さな声で言った。
「もう……このお地蔵様に意地悪しないで」
よく見れば、地蔵の一部が欠けていた。おそらくあの子どもたちが地蔵に石を投げているのを目撃し、少女が身体を張って守っているのだろう。健気で、不憫だ。
それに──
「……生贄、ね」
それをじっと見つめる。
これまでにも何人か生贄と呼ばれる少女が村から送られてきた。
しかしその全員を、村へと返してきた。正直、そんなものは必要もないのだが、鬼は人と関わることは禁じられている。何十年前か、とある少女が生贄として供えられたが「あの村には戻りたくない」と言ったために、隣の村へとおろしてやった。
そのせいか「山に入ると出られなくなる」といった言い伝えが村にできているらしい。
そうでなくとも、病が流行ると「鬼神様が怒っている」と意味のわからない解釈とともに、人間を供え物にしようとしてくる。
今度の娘はあの子か。
空中で、指で小さく円を描く。するとたちまち風が吹き、それをひょいっと子どもたちがいる場所へと向けて投げた。
「う、うわっなんだ!?」「竜巻か!?」
慌てて退散する子どもたちに、少女がおそるおそる顔を上げて見送っている。
いなくなったのを確認すると、ホッとしたような顔で投げられた石をまた元の場所に戻し始めた。
それから地蔵の前まで行くと、自分の着物の裾を破り、地蔵の欠けた場所に巻いた。
「……変かな。お地蔵様にはいらないかも。でも、お地蔵を直せる力はないし」
そうして近くにあった彼岸花を手にして「ごめんなさい」と小さく言った。
「これだと枯れちゃうかな……そのまま咲いていたかったよね」
まさか、彼岸花に謝っているのか?
「でも、お地蔵様のお花がないから……ごめんなさい」
鮮やかな赤が古びた花瓶を彩る。
小さな歩幅で少女が帰っていく。見てみたくなった。どんな教育を受けたらあんな子どもに育つのだろうか。
そうして、わかった。
あれは親の教育ではない。あの子自身に備わった心なのだと。
「だから! 言い方が違うって言ってるでしょう!」
帰宅してからの少女は、母から厳しく叱責されていた。理由は「きちんと怒れないから」だ。
「邪魔者! いい? 思いっきり恨むみたいな感じで言うの!」
「じゃ、じゃま……」
「もう! なんでこんなこともできないのよ!」
どんと肩を押され地べたに転がる。少女は「ごめんなさい」と震えた声で言った。しかし母親は少女を見向きもしないで家の中に入り、施錠した。
「ごめんなさい……ごめんなさい」
ぽつり、ぽつり、と少女の頬に涙がこぼれる。
少女が恨まれているのは、その容姿のせいだろう。子どもながらに大人びており、整った顔立ちをしていた。
「おいで」
気付けば地面に降りて少女を呼んでいた。
「……だれ、ですか?」
「隣の村から来たんだ。美味しいご飯を食べよう」
なんて誘えばいいかわからなかった。でも、この言葉なら、どんな人間でも喜ぶと思った。
しかし少女は首を左右に振るだけだった。
「……だめ、私は食べちゃいけないから」
「どうして?」
「ちゃんと……怒れなかったから」
怒られたからではなく、怒れなかった。
「ちょっと、だれと話してるの?」
家の窓から少女と似た顔がこちらを見ていた。
髪も肌も、まるで与えられたものを充分に受けているような身なりだった。しかし、少女と比べると、美しさの差は歴然だった。似てはいるが、しかし何かが似ていない。また虐げられている少女のほうが圧倒的に綺麗だった。
「あっ……その」
よく似た少女は窓から出たあの顔に怯えていた。
「大丈夫」
涙を溢していた少女の前に立ち、こちらを不思議そうに見ている少女に手をかざした。すると、ぱたりと意識を失うようにその場に倒れた。
「えっ……ど、どうしたんですか」
「眠っているだけ。心配しなくてもいい」
「あっ……でも、見つかってしまったので」
「忘れているさ。大丈夫、俺の言うことを信じて」
彼女に手を伸ばす。
「ほら、行こう」
連れ出して、そのあとどうするべきかは考えていなかった。
ただ、あの場に少女を置いておきたくなかったのだ。
「何が食べたい? どこに行きたい?」
「あ……ええと」
もじもじとしていた彼女は、やがて躊躇しながら「お地蔵様のところに」と行った。
どこへでも連れて行こうと思っていた。
それなのに、さっきまでいた場所でいいというのだろうか。
少女を連れて地蔵の前まで歩いてくると、しきりに後ろを気にしている。
「この時間は外出してはいけないことになっているんです。だから、ここにいることがバレてしまったら」
「俺が説明する」
「あの、どうしてそこまでしてくださるんですか……?」
そう聞かれて戸惑った。
いつかこの子が俺の元に生贄としてやってくるからだろうか。
いや、そうではない。
まだこの国にも、心のやさしい人間がいるのだとわかったからだ。
いつか出会ったとき、彼女は俺のことを覚えているだろうか。
いや、忘れていたほうがいい。
「名を教えてくれ」
少女は首を傾げ、それからはっとした。
「千代です」
「……いい名だな」
「祖母がつけてくれたんです」
初めて見せる笑みだった。自分の名を気に入っているというよりも、その祖母を愛していたのだろう。
「あの、お地蔵様に詳しかったりしますか」
「なぜ?」
「……お地蔵さんが男か女か知りたかったのです」
ふっと、笑ってしまいそうだった。
本物を知ったらこの子はどんな顔を見せるのだろうか。時折、山に訪れてはくるが、未だに若作りに励んでいる。
「そうだな……どっちだと思う?」
「考えてみたんですが、わからなくて……ただ、女物の柄が好きでないのならと思って」
彼女は、さっき自分が巻いた着物を見ていた。なるほど、地蔵の趣味を気にしているのか。
「そういう意味では気にしない人だろう。地蔵が知りたいのは人の心だから」
「心……?」
「どんなものを供えられたとしても、そこに心があればいい。真心というやつだろうな」
子どもには少し難しかっただろうか。
少女は少し考えたあと「……ありがとうございます」と深々と頭を下げた。
邪魔者だと言えない少女。人を怒れない少女。
「さっきは、どうしてあんな練習を?」
「あ……ええと、悪役をしないといけなくて」
少女は手を何度か変えた。
「私は生贄として産まれて……最後まで悪い人でいろと姉に言われて」
「どうして君が?」
「生贄になっていいからです」
まるで、そう言われて育ってきたような人間の言葉だった。
自分なんてどこにもない。そうすることが当たり前かのように。
「そんな人はいないよ」
「え……」
「でも、君が来てくれたら楽しいだろうね」
「楽しい、ですか……私が供物で、向こうの人は満足してもらえるんでしょうか」
自分が生贄になるということよりも、供物としての自分に価値があるのか。
そこまで考えてしまうようになったのは、やはりあの親の影響なのか。
「大丈夫、生贄としてじゃなくて、受け入れてくれるさ」
「……それなら、よかったです」
ホッとしたような顔。
「……いつか、迎えに行こう」
「え?」
「そう遠くない未来に」
彼女に手を向ける。記憶を消す。覚えていないほうがいい。忘れたまま生きなさい。
そうして、また見つけた。ずっと待っていた。彼女が現れてくれるのを。
地蔵の前に座るその姿を見たとき、つい抱きしめてしまいたくなった。
いたのか、そうか、ずっとここにいたのか。
そんな瞳を宿して、生きてきてしまったのか。
俺を見るその目は全てに絶望していた。あの頃の瞳では、もう俺を見てくれないだろうか。
会ったことがあると言えば、君は驚いただろう。
『人が神を敬うように、人を敬っていたのが鬼だとしたら……とてもいい人だったと思います』
だが、心はあの頃のままだ。今はそれだけでいい。
もうすぐだ、迎えに行くのは。待っていろ──千代。
腕に巻いた淡い桃色の布が揺れた。