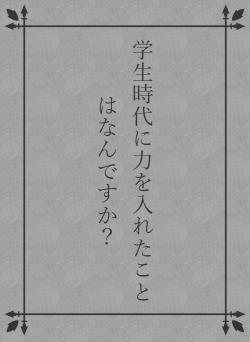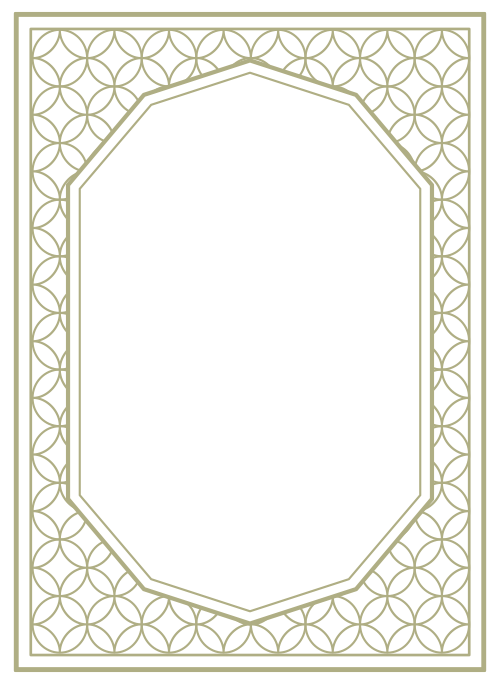***
山と村の境には、古くから強力な結界が張られていると伝えられていた。それは村の者たちが無闇に山へ踏み込まぬように、そして山の頂に住むとされる鬼神様が村へ降りてこないようにするためのものだ。代々、村の長老たちがそれを守り続け、村の平穏を保ってきたと言われている。
「これがその結界か?」
山道の入り口で足を止め、有真様は何気なく周囲に視線を巡らせた。
その瞬間、何かが変わった。空気が僅かにざわめき、風が止まったかと思えば、次には木々が微かに震えた。結界は目に見えるものではない。だが、確かにそこに何かの気配を感じさせる場の力があった。
「結界……というよりは、封印術のようなものか」
有真様は微かに笑みを浮かべ、まるで目に見えるかのように手を伸ばした。その指先が虚空を軽く撫でると、ぱりん、とガラスが割れるような音が響いた。
それは結界が崩れる音だった。
「っ……!」
息を呑む。結界は人間が数百年もの間、守り続けてきたものだ。それを有真様は、まるで蜘蛛の巣を払いのけるかのように、たった一振りの手で壊してしまったのだ。
壊れた瞬間、空気が一変した。辺りは静寂に包まれたかと思えば、次の瞬間、何か重苦しい気配が漂い始めた。その場に立つだけで、自然と背筋が張り詰めるような感覚に襲われる。
「壊さないでも通れたんだけどね」
そんな私の心中を知ってか知らずか、有真様は肩をすくめ、軽い調子で言った。
「ちょっとした腹いせ、ってとこかな」
「腹いせ……?」
恐る恐る問いかけると、有真様は口元に薄い笑みを浮かべたまま、気怠げに首を傾げた。
「結界なんて俺にとっては意味がない。それが腹立たしくてね。ま、壊さなくても通れるけど、一応形だけでも怒りをぶつけておこうかと」
有真様の言葉には、明らかに嘲りが込められていた。
「それほど意味のない術なのですか?」
「俺にとっては、ね。他の者にはそこそこ役立つらしいけど」
そう言うと、有真様は辺りを見回し、少し楽しげな表情を浮かべた。
「結界ってのは邪を寄せ付けないためにあるものだ。この山にも面倒な奴らがそこら中にいる。普通の人間なら、これを壊した瞬間に命を落としているところだろうな」
有真様が軽く足を踏み出すと、その気配すらもまた霧散するように消えていった。結界の崩壊すら彼に影響を与えない。むしろ、この山全体が彼の力を前にしてひれ伏しているようだった。
「千代、お前は心配しなくてもいい。俺の側にいる限り、どんな邪も触れさせない」
有真様の背中越しに響いたその声は、どこまでも自信に満ちていた。それが私を守ると誓う者の言葉であることを、自然と理解できるほどに。
温かな気持ちに包まれていた胸中を、突如として焦げ臭い匂いが引き裂いた。
「……何か燃えている?」
千代は顔を上げた。すると、少し離れた村の一角から黒い煙が立ち昇っているのが見えた。
「火事……!」
その言葉を口にすると同時に、足は自然と駆け出していた。久しぶりに足を踏み入れた村は、わずかな時間で全く様変わりしていた。山を離れてそう長い日数ではないはずなのに、目の前に広がる光景は懐かしさと異様さが入り混じっている。
村の中を進むと、焦げた木材の臭いに混じって、人の叫び声が聞こえてきた。
「あああ、今度は私が……!」
叫んでいるのは一人の少女だった。その声に覚えがある。女学院で同じ教室にいた、内気でいつも目立たないようにしていた少女だ。
「どうしてここに……」
驚きとともに彼女の姿に目を凝らすと、思わず息を呑んだ。彼女は右足を何度も地面に擦りつけており、顔は蒼白、全身が震えていた。その足を見て背筋に冷たいものが走る。
右足は紫色に変色し、その表面からまるで生き物のような目が、じっとこちらを見返しているかのようにぽつりぽつりと現れている。
「だ、誰か、この足を焼いてちょうだい!」
彼女は怯え、泣き叫びながら周囲に助けを求めている。声は張り詰め、喉を壊しそうなほどだった。
「嫌よ! 死にたくない!」
異様な光景とその叫びに、足はその場で止まった。助けたいという思いと、この場をすぐに離れたいという本能が、心の中でせめぎ合う。
「何が起こって……」
呟くように声が漏れる。焦げた匂いが漂い、辺りには村人の姿も見当たらない。
彼女はなおも叫び続けている。涙を流し、何度も地面に足を叩きつけているが、その異様な足は動きを止めるどころか、目のようなものがさらに増えていくように見える。
「嫌だ……! 気持ち悪い! 誰か! 誰か火を!」
叫び声は悲鳴に似た絶叫へと変わっていた。その狂おしい声が耳をつんざく中、別の場所からも悲鳴が聞こえてくる。
「いやあああ!」
そちらに目を向けると、炎に照らされた村の一角で若い夫婦が揉み合っていた。男の方は怒りに任せて何かを叫び、女は怯えた顔で必死に後ずさっている。
「焼いて! 早くこの人を焼いておくれ!」
「ふざけるなあ! 俺がこうなったら、お前も道連れにしてやる!」
男の怒声は低く響き、周囲にいるはずの村人たちは、誰一人として近づこうとはしなかった。その夫婦を見て言葉を失う。彼らは以前、家の近くに住んでいた。活気に満ちた夫婦だったはずだ。
だが今、その男の頬に不気味な目のような模様が現れ、まるで実際に動いているかのように見える。女の足元にも同じ異様な変色が広がっていた。
「あの家が悪いんだ! あの家が!」
男は憎しみを込めた声で叫びながら、煙の上がる家を指差した。その指先を追うと、そこは見慣れた屋根だった。
「……私の家?」
燃え上がる家、煙の向こうに見える崩れた壁、そしてそこに向けられる村人たちの怨嗟の目。
一歩、また一歩と足を進めるにつれ、鼓動はどんどん速くなった。
目の前の光景が現実なのか幻なのか分からなくなる。けれど、煙と炎の臭いは確かに本物だった。家の輪郭が焦げて崩れ、そこにかつての家族の暮らしがあったはずなのに、今はただの廃墟へと変わり果てている。
「どうして……」
喉から、自然に言葉が漏れた。村人たちは家から離れた場所で群れを成し、震えたり罵声を浴びせたりしている。
「この家が災いを招いた! この家の娘のせいで村がこうなったんだ!」
怒りの矛先は私の家に集中していた。その理由は分からない。しかし、村人たちの表情には恐怖と憎しみが混じり合い、理性を失っているのが見て取れる。
ごうごうと燃え盛る炎が黒煙を空へと送り込んでいる。そのすぐ近く、まだ火の手がついていない供物が山のように積み上げられていた。見覚えのある品々──米俵や織物、高価な器など。それらはおそらく、私を鬼神様のもとへ生贄として差し出した際に、村から感謝の意として送られてきたものだろう。しかし、いまやその意味も失われ、供物は炎の渦へと飲み込まれようとしていた。
「当然の報いよ!」
誰かの叫ぶ声が聞こえた。
「鬼神様が生贄に満足しなかったのが悪いわ!」
「私の息子を返してちょうだい! あの変な病のせいで死んでしまったじゃないの!」
「あの気味の悪い病を流行らせたのは、この家のせいだ!」
村人たちが家の周囲に集まり、口々に罵声を浴びせている。その目は狂気と憎悪に満ちており、かつての平和だった村の面影はどこにもない。
話を聞く限り、私がいなくなって間もなく、村では奇妙な病が流行り始めたらしい。人々はそれを「鬼神様の怒り」と呼び、矛先を私の家に向けたのだろう。そして、家を焼き尽くすことで禍を断ち切ろうとしている。
「美代……!? 美代!」
突然、人混みを掻き分けるようにして、一人の女性が現れた。その姿を見て、心臓が跳ね上がる。
「いやよ! 待って、中に美代がいるの! 美代、美代、お願いだから返事をして!」
母は私に気付くことなく、燃え盛る火へと飛び込もうとしている。それを必死で「お前まで死ぬぞ!」と父が止めていた。
この中に美代が……?
私はその火の中に飛び込んだ。
足元が揺れ、周囲の温度が一気に跳ね上がった。炎が四方から押し寄せ、息をするたびに肺が灼けるように痛む。目の前が真っ赤に染まり、視界が歪む中で、ただひたすらに美代を探して走った。
「美代、どこ……?」
熱さに視界が霞み、息も上手くできない。体が重く、足が震え、目の前の火が目を焼き、肌を裂くように感じる。それでも、目の前に一度だけ見えた美代の姿を思い出し、私は必死で進み続けた。
もう息が続かない。喉が焼け、全身が汗だらけで、もう立ち止まることすらできなかった。だが、それでも私は手を伸ばし続けた。
その時、ようやく目の前に倒れている美代を見つけた。
血の気が引いた。目の前に広がる赤と黒の世界の中で、ただ無力に倒れている美代の姿が見えた。炎の中で、まるで無力な人形のように、倒れているだけだった。
「美代!」
声がかすれる。叫びたくても声が出ない。私は体を押し殺しながら、必死に彼女の元へ駆け寄った。美代の体は熱く、彼女の顔には意識を失ったあとの冷たい汗が浮かんでいた。
息も絶え絶えで、私はその肩に手を回した。力を振り絞り、美代を引き寄せる。重たい体が不安定に動き、私は震えながらその体を支えた。
けれど、足元の炎は一瞬も私たちを許さなかった。美代の体を引き寄せるたびに、周囲の炎が私を飲み込んでいく。私は火傷を負いながらも、もう少し、もう少しで外に出られる、と思い込んで必死で力を振り絞った。
意識を保てるのは、あとわずかだ。
美代を助けるため、私は目をつむり、額に浮かぶ汗を振り払いながら、必死でその手を引いた。
「おい、美代が……!」
父が駆け寄り、母も慌てて美代の顔を覗き込む。
「まだ息をしてるわ……!」
その言葉に、私はようやくほっと胸を撫で下ろす。だがその瞬間、母の顔が冷たく歪んでいった。怒りと憎しみが、まるで鬼のように突き刺さるような視線で私を捉えていた。
「どうしてお前がここに……いや、そもそもこれは全てお前の仕業!?」
熱が顔を染め、耳鳴りが響く。その言葉が突き刺さるように響いた。こんなにも怒られている理由が、私にはよくわからなかった。
「生贄として生かしてやったのに、この仕打ちはなんだ!」
母の声は震え、怒りに満ちていた。それでも私が何も言えないでいると、急に近くにあった自転車を手に取った母が、私を目掛けて投げた。
当たる……!
恐怖に体が固まった。自転車が空中で軌道を描き、私に迫ってくる。しかし、その自転車は私には当たらなかった。
有真様が、片手でそれを止めていた。
有真様は冷静に、まるで不意に起こった出来事のように自転車を支えた。あの迫力ある強さで、それを難なく止めた手には、一切の疲れも見えない。
「本当に、ここは醜い者たちばかりだな」
有真様は静かに呟き、私の前にしゃがんだ。彼の眼差しが私を見つめ、その表情からは優しさが感じられる。その視線の中に、私がどれほど深く傷ついていたかがわかっているかのような、ほんの少しの気配を感じた。
「心配で来てみたが、……火傷をさせてしまったな」
有真様は冷静に、私の毛先をすくい上げた。その目には、悲し気な色が浮かんでいる。
「だ、誰よ……!」
母が震える声で叫ぶ。その声音には、言葉にできないほどの恐怖と疑念が込められていた。
「誰? お前は誰に娘を嫁がせたんだ?」
有真様が冷徹に返したその言葉が、私の母には重く響いた。母はその言葉の意味を理解する間もなく、反応した。
「ま、まさか鬼神様……」
父がその言葉を呟くと、目を見開き、しばらく言葉を失った。どうやらその正体に気づいたらしい。
「人間は本当に愚かだな」
有真様の声は無感情で、冷たく響く。彼の目には、私を使い捨てのように扱った村の人々を見下す視線があった。
父はその言葉に驚愕し、すぐに土下座した。頭を地面に擦りつけるその姿勢が、ただの謝罪ではなく、まるで命を懸けた必死の懇願のように見えた。
「鬼神様、どうかお許しを……!」
その姿勢は、まるで命の保障を求めるような恐怖に満ちていた。
「生贄に満足していただけなかったのでしょうか? それでこの病を……」
父の声は震えていた。私に背を向け、焦点を合わせているかのように有真様を見つめる目には、あまりにも多くの疑念と恐怖が入り混じっていた。しかしその質問には、どこか必死さが滲んでいる。
「何かにつけて俺の仕業にしたいみたいだな。人間は昔から、なぜ自分たちに非があると思わないんだ」
有真様は一歩前へ出ると、冷ややかな声で言った。その言葉には冷徹さが含まれていたが、同時にあきれたような響きがあった。
「非だなんて……」
母は言葉を失い、足元がふらつくのを必死にこらえていた。
「どうせ千代を山に置いて逃げ帰った男たちにあれが付着したんだろう」
目のようなもの。それは邪のものであるらしい。
「あれは山には邪が住み着いているからな」
有真様の言葉はさらりと流れたが、その言葉が示す意味には深い含みがあった。邪気が山に満ちている──それがどれほど恐ろしいものかを、母は理解しているのかもしれない。
そのとき、不意に火の粉が舞い散り、私の頬にあたった。
「熱っ……」
思わず声を上げてしまったが、その痛みは一瞬で消えた。
「これでは千代が危ないな」
有真様は、指先をぱちんと鳴らすと、まるで火の勢いが完全に逆転したかのように、瞬時にその火は消え失せた。あんなに激しく燃え盛っていた火が、まるで何事もなかったかのように消えていく様子に、私はただ呆然と立ち尽くすしかなかった。
一瞬で周囲は静寂に包まれ、その後はただ、私たちの周囲に広がる煙が薄れ、空気が清らかさを取り戻すのを感じる。そして、そのまま私の頬をゆっくりと撫でると、痛みは消えた。
「さあ、帰ろうか」
有真様は私を優しく立ち上がらせる。彼の手に支えられて、ようやく身体が安定したその瞬間、微かにだが美代の手が動いた。その動きはとても弱々しく、まるで何かに引き寄せられるかのように震えていた。
「美代……!?」
母はその反応に驚き、すぐに美代の元へ駆け寄った。父も同じように美代の側に身をかがめ、顔を覗き込む。美代の目がゆっくりと開いていく様子は、まるで長い眠りから目覚めたかのようだった。
「おかあさ……」
母は震える声で美代の名前を呼んだ。その声に答えるように、美代は微かに口を動かす。しかし、すぐにその瞳が私に注がれ、驚いて声を上げた。
「どうして千代がここに……!」
美代は目の前にいる私に驚愕し、その顔に一瞬の恐怖を見せた。その後、視線は家の残骸に向けられる。燃え落ち、今ではわずかに柱だけが残る家を見上げると、その瞳に怒りの炎が灯った。
「お前か! お前がやったのか!」
美代の声は震え、激しく高揚していた。まるで私がすべてを背負い込んだように、罪を押しつけるような口調だった。
「ちが、」
必死に言葉を絞り出す。しかし、どんな言葉を紡ごうとも、すでに美代の怒りは私を貶めることにしか興味を持っていないようだった。私は何も言えず、ただ震えながらその場に立っていた。
「生贄にされた腹いせにやったのだろう! それとも私への報復か!?」
美代はその怒りを収めることなく、私を見て怒鳴り続ける。私が生贄として捧げられたこと、それが全ての元凶だと美代は信じて疑っていない。
美代の身体が再び揺れ、もう一度私へと向かって手を伸ばす。しかし、その勢いはもはや完全に乱れていて、肺が焼けてしまったのか、息を吸うのも苦しそうだった。それでも、怒りと憎しみの感情だけは消えることなく、美代は私に迫ろうとする。
「どうして! 私よりも顔がいいだけではなく、家まで奪おうとするの!」
顔、という言葉に耳を疑った。それは、私にとって初めて言われたことで、今までの苦しみの中で、こんなふうに形にされることを考えたこともなかった。私の顔が何かを奪う力を持っているのか、それとも美代にとってはそれが唯一の価値だったのか、考える暇もなく言葉が続いた。
「お前さえいなければ! お前が悪い! お前が産まれてきたから悪いんだ!」
目の前の美代の顔に浮かぶのは、憎悪と無力感の入り混じった表情だ。虐げられることはあった。しかし、これだけの怒りをぶつけられたことはなかった。私の胸に突き刺さる言葉が、深くて冷たく感じられる。
だが、その瞬間、私と美代の間にひときわ冷徹な影が立ちはだかる。
「私の妻をそれ以上侮辱するようなら、私から手を下してもいいんだぞ」
有真様の低い声が、空気を切り裂くように響いた。その言葉には、単なる威圧だけでなく、彼の力の本質が宿っているのを感じ取った。村に災いをもたらすことも、彼にとってはさほど難しいことではないのだろう。
父はひっと息を呑んだ。目を見開き、震えながら有真様に一歩後退する。その顔に浮かんだ恐怖が、どれほどまでに有真様の力を理解しているかを物語っている。
美代は、そんな父の姿を目にしても、全く気に留めない。むしろ、今度は有真様を睨みつけ、その怒りをさらに激しく燃え上がらせた。
「妻? まさかこの千代が?」
美代の目が鋭く有真様を刺し、その目に新たな疑念と嫌悪感が広がる。
「千代、私に見せびらかしにきたの? 綺麗な人、私が生贄でもよかったぐらい」
美代の言葉に、どこか嘲笑めいた響きが含まれる。自嘲と自己嫌悪が交錯した笑み。
「無駄よ。あなたはまたどうせ捨てられる。あなたを必要としてくれる人なんてこの世にはいないのだから」
その言葉が、私の心に深く突き刺さったが──。
「大丈夫だ」
有真様の穏やかな声が耳に届いた。
「行こう」
もし有真様がいなければ、もうすでに崩れ去っていただろう。彼の存在が、私を支えてくれている。それだけで、他には何も必要ないと感じるほどだった。
彼の存在は、私にとって絶対的だ。それが私を支えている。村にも家族にも見捨てられても、有真様だけは違う。私はその安心感を胸に、何も考えずに彼に従おうと頷いた。
行き先がどこであれ、どこへでもついていこうと心から思う。
有真様が先を歩き、私はその背中を追った。後ろからは美代の罵声が響いていたが、振り返ることはしなかった。
屋敷の前まで来ると、屋根の上にあった鳳凰の置物が動いた。
「え……」
それはゆっくりと羽を伸ばして私を見つめる。
「帰っていたらしいな」
有真様が言った。
「帰って……え」
「千代がこの屋敷に戻ったからだろう」
鳳凰は私を見つめていた。その目は、まるでこの屋敷へと歓迎してくれているようにも感じる。
「言っただろう、いつか会えると」
有真様は屋敷の大きな扉を開けた。その瞬間、足が止まってしまった。確かに有真様の言葉を信じてきたはずだ。捨てられることはない、もう迷わないと決意したはずなのに、どうしても心の奥底で不安が広がっていくのが分かる。
そんな私の気持ちを感じ取ったかのように、有真様が振り返った。その瞳は穏やかで、優しさを湛えている。彼が私を見つめるその表情に、私の中の全てが少しずつ溶けていくような気がした。
「おいで」
その一言が、私の心を軽くしてくれる。無意識のうちに、私はその言葉に従っていた。彼の声には何の不安もなく、ただ優しさだけがこもっている。それが、私を包み込むように感じる。
足が自然に動き、私は彼に近づいていく。玄関の敷居をまたぐ瞬間、私はまるで他の世界に足を踏み入れたような気がした。けれど、そこには恐れがあったわけではなく、どこか心地よい安心感が広がっていた。
「おかえり、千代」
その言葉が私の耳に届いたとき、胸がぎゅっと締めつけられるような感覚に襲われた。それは、誰にも言われたことがない言葉だった。家に帰ることがこんなにも嬉しく感じられるなんて、思ってもいなかった。けれど有真様がそう言ってくれることで、私は初めて「帰る場所」があるのだと感じた。
涙が、思わずこぼれそうになるのを感じた。今までずっと抱え込んでいた不安や恐怖が、一気にあふれ出しそうになる。でも、どうしてもそれを許したくなくて、必死にこらえる。けれど、有真様の優しさに触れるたび、涙が溢れそうになる自分を止めることができなかった。
私はその涙を拭いもせず、ただ静かに頷く。心の中で、ようやく少しだけ安心した自分を感じることができた。この屋敷で、私の新しい「家族」として、有真様と共に歩んでいけるのだと。
山と村の境には、古くから強力な結界が張られていると伝えられていた。それは村の者たちが無闇に山へ踏み込まぬように、そして山の頂に住むとされる鬼神様が村へ降りてこないようにするためのものだ。代々、村の長老たちがそれを守り続け、村の平穏を保ってきたと言われている。
「これがその結界か?」
山道の入り口で足を止め、有真様は何気なく周囲に視線を巡らせた。
その瞬間、何かが変わった。空気が僅かにざわめき、風が止まったかと思えば、次には木々が微かに震えた。結界は目に見えるものではない。だが、確かにそこに何かの気配を感じさせる場の力があった。
「結界……というよりは、封印術のようなものか」
有真様は微かに笑みを浮かべ、まるで目に見えるかのように手を伸ばした。その指先が虚空を軽く撫でると、ぱりん、とガラスが割れるような音が響いた。
それは結界が崩れる音だった。
「っ……!」
息を呑む。結界は人間が数百年もの間、守り続けてきたものだ。それを有真様は、まるで蜘蛛の巣を払いのけるかのように、たった一振りの手で壊してしまったのだ。
壊れた瞬間、空気が一変した。辺りは静寂に包まれたかと思えば、次の瞬間、何か重苦しい気配が漂い始めた。その場に立つだけで、自然と背筋が張り詰めるような感覚に襲われる。
「壊さないでも通れたんだけどね」
そんな私の心中を知ってか知らずか、有真様は肩をすくめ、軽い調子で言った。
「ちょっとした腹いせ、ってとこかな」
「腹いせ……?」
恐る恐る問いかけると、有真様は口元に薄い笑みを浮かべたまま、気怠げに首を傾げた。
「結界なんて俺にとっては意味がない。それが腹立たしくてね。ま、壊さなくても通れるけど、一応形だけでも怒りをぶつけておこうかと」
有真様の言葉には、明らかに嘲りが込められていた。
「それほど意味のない術なのですか?」
「俺にとっては、ね。他の者にはそこそこ役立つらしいけど」
そう言うと、有真様は辺りを見回し、少し楽しげな表情を浮かべた。
「結界ってのは邪を寄せ付けないためにあるものだ。この山にも面倒な奴らがそこら中にいる。普通の人間なら、これを壊した瞬間に命を落としているところだろうな」
有真様が軽く足を踏み出すと、その気配すらもまた霧散するように消えていった。結界の崩壊すら彼に影響を与えない。むしろ、この山全体が彼の力を前にしてひれ伏しているようだった。
「千代、お前は心配しなくてもいい。俺の側にいる限り、どんな邪も触れさせない」
有真様の背中越しに響いたその声は、どこまでも自信に満ちていた。それが私を守ると誓う者の言葉であることを、自然と理解できるほどに。
温かな気持ちに包まれていた胸中を、突如として焦げ臭い匂いが引き裂いた。
「……何か燃えている?」
千代は顔を上げた。すると、少し離れた村の一角から黒い煙が立ち昇っているのが見えた。
「火事……!」
その言葉を口にすると同時に、足は自然と駆け出していた。久しぶりに足を踏み入れた村は、わずかな時間で全く様変わりしていた。山を離れてそう長い日数ではないはずなのに、目の前に広がる光景は懐かしさと異様さが入り混じっている。
村の中を進むと、焦げた木材の臭いに混じって、人の叫び声が聞こえてきた。
「あああ、今度は私が……!」
叫んでいるのは一人の少女だった。その声に覚えがある。女学院で同じ教室にいた、内気でいつも目立たないようにしていた少女だ。
「どうしてここに……」
驚きとともに彼女の姿に目を凝らすと、思わず息を呑んだ。彼女は右足を何度も地面に擦りつけており、顔は蒼白、全身が震えていた。その足を見て背筋に冷たいものが走る。
右足は紫色に変色し、その表面からまるで生き物のような目が、じっとこちらを見返しているかのようにぽつりぽつりと現れている。
「だ、誰か、この足を焼いてちょうだい!」
彼女は怯え、泣き叫びながら周囲に助けを求めている。声は張り詰め、喉を壊しそうなほどだった。
「嫌よ! 死にたくない!」
異様な光景とその叫びに、足はその場で止まった。助けたいという思いと、この場をすぐに離れたいという本能が、心の中でせめぎ合う。
「何が起こって……」
呟くように声が漏れる。焦げた匂いが漂い、辺りには村人の姿も見当たらない。
彼女はなおも叫び続けている。涙を流し、何度も地面に足を叩きつけているが、その異様な足は動きを止めるどころか、目のようなものがさらに増えていくように見える。
「嫌だ……! 気持ち悪い! 誰か! 誰か火を!」
叫び声は悲鳴に似た絶叫へと変わっていた。その狂おしい声が耳をつんざく中、別の場所からも悲鳴が聞こえてくる。
「いやあああ!」
そちらに目を向けると、炎に照らされた村の一角で若い夫婦が揉み合っていた。男の方は怒りに任せて何かを叫び、女は怯えた顔で必死に後ずさっている。
「焼いて! 早くこの人を焼いておくれ!」
「ふざけるなあ! 俺がこうなったら、お前も道連れにしてやる!」
男の怒声は低く響き、周囲にいるはずの村人たちは、誰一人として近づこうとはしなかった。その夫婦を見て言葉を失う。彼らは以前、家の近くに住んでいた。活気に満ちた夫婦だったはずだ。
だが今、その男の頬に不気味な目のような模様が現れ、まるで実際に動いているかのように見える。女の足元にも同じ異様な変色が広がっていた。
「あの家が悪いんだ! あの家が!」
男は憎しみを込めた声で叫びながら、煙の上がる家を指差した。その指先を追うと、そこは見慣れた屋根だった。
「……私の家?」
燃え上がる家、煙の向こうに見える崩れた壁、そしてそこに向けられる村人たちの怨嗟の目。
一歩、また一歩と足を進めるにつれ、鼓動はどんどん速くなった。
目の前の光景が現実なのか幻なのか分からなくなる。けれど、煙と炎の臭いは確かに本物だった。家の輪郭が焦げて崩れ、そこにかつての家族の暮らしがあったはずなのに、今はただの廃墟へと変わり果てている。
「どうして……」
喉から、自然に言葉が漏れた。村人たちは家から離れた場所で群れを成し、震えたり罵声を浴びせたりしている。
「この家が災いを招いた! この家の娘のせいで村がこうなったんだ!」
怒りの矛先は私の家に集中していた。その理由は分からない。しかし、村人たちの表情には恐怖と憎しみが混じり合い、理性を失っているのが見て取れる。
ごうごうと燃え盛る炎が黒煙を空へと送り込んでいる。そのすぐ近く、まだ火の手がついていない供物が山のように積み上げられていた。見覚えのある品々──米俵や織物、高価な器など。それらはおそらく、私を鬼神様のもとへ生贄として差し出した際に、村から感謝の意として送られてきたものだろう。しかし、いまやその意味も失われ、供物は炎の渦へと飲み込まれようとしていた。
「当然の報いよ!」
誰かの叫ぶ声が聞こえた。
「鬼神様が生贄に満足しなかったのが悪いわ!」
「私の息子を返してちょうだい! あの変な病のせいで死んでしまったじゃないの!」
「あの気味の悪い病を流行らせたのは、この家のせいだ!」
村人たちが家の周囲に集まり、口々に罵声を浴びせている。その目は狂気と憎悪に満ちており、かつての平和だった村の面影はどこにもない。
話を聞く限り、私がいなくなって間もなく、村では奇妙な病が流行り始めたらしい。人々はそれを「鬼神様の怒り」と呼び、矛先を私の家に向けたのだろう。そして、家を焼き尽くすことで禍を断ち切ろうとしている。
「美代……!? 美代!」
突然、人混みを掻き分けるようにして、一人の女性が現れた。その姿を見て、心臓が跳ね上がる。
「いやよ! 待って、中に美代がいるの! 美代、美代、お願いだから返事をして!」
母は私に気付くことなく、燃え盛る火へと飛び込もうとしている。それを必死で「お前まで死ぬぞ!」と父が止めていた。
この中に美代が……?
私はその火の中に飛び込んだ。
足元が揺れ、周囲の温度が一気に跳ね上がった。炎が四方から押し寄せ、息をするたびに肺が灼けるように痛む。目の前が真っ赤に染まり、視界が歪む中で、ただひたすらに美代を探して走った。
「美代、どこ……?」
熱さに視界が霞み、息も上手くできない。体が重く、足が震え、目の前の火が目を焼き、肌を裂くように感じる。それでも、目の前に一度だけ見えた美代の姿を思い出し、私は必死で進み続けた。
もう息が続かない。喉が焼け、全身が汗だらけで、もう立ち止まることすらできなかった。だが、それでも私は手を伸ばし続けた。
その時、ようやく目の前に倒れている美代を見つけた。
血の気が引いた。目の前に広がる赤と黒の世界の中で、ただ無力に倒れている美代の姿が見えた。炎の中で、まるで無力な人形のように、倒れているだけだった。
「美代!」
声がかすれる。叫びたくても声が出ない。私は体を押し殺しながら、必死に彼女の元へ駆け寄った。美代の体は熱く、彼女の顔には意識を失ったあとの冷たい汗が浮かんでいた。
息も絶え絶えで、私はその肩に手を回した。力を振り絞り、美代を引き寄せる。重たい体が不安定に動き、私は震えながらその体を支えた。
けれど、足元の炎は一瞬も私たちを許さなかった。美代の体を引き寄せるたびに、周囲の炎が私を飲み込んでいく。私は火傷を負いながらも、もう少し、もう少しで外に出られる、と思い込んで必死で力を振り絞った。
意識を保てるのは、あとわずかだ。
美代を助けるため、私は目をつむり、額に浮かぶ汗を振り払いながら、必死でその手を引いた。
「おい、美代が……!」
父が駆け寄り、母も慌てて美代の顔を覗き込む。
「まだ息をしてるわ……!」
その言葉に、私はようやくほっと胸を撫で下ろす。だがその瞬間、母の顔が冷たく歪んでいった。怒りと憎しみが、まるで鬼のように突き刺さるような視線で私を捉えていた。
「どうしてお前がここに……いや、そもそもこれは全てお前の仕業!?」
熱が顔を染め、耳鳴りが響く。その言葉が突き刺さるように響いた。こんなにも怒られている理由が、私にはよくわからなかった。
「生贄として生かしてやったのに、この仕打ちはなんだ!」
母の声は震え、怒りに満ちていた。それでも私が何も言えないでいると、急に近くにあった自転車を手に取った母が、私を目掛けて投げた。
当たる……!
恐怖に体が固まった。自転車が空中で軌道を描き、私に迫ってくる。しかし、その自転車は私には当たらなかった。
有真様が、片手でそれを止めていた。
有真様は冷静に、まるで不意に起こった出来事のように自転車を支えた。あの迫力ある強さで、それを難なく止めた手には、一切の疲れも見えない。
「本当に、ここは醜い者たちばかりだな」
有真様は静かに呟き、私の前にしゃがんだ。彼の眼差しが私を見つめ、その表情からは優しさが感じられる。その視線の中に、私がどれほど深く傷ついていたかがわかっているかのような、ほんの少しの気配を感じた。
「心配で来てみたが、……火傷をさせてしまったな」
有真様は冷静に、私の毛先をすくい上げた。その目には、悲し気な色が浮かんでいる。
「だ、誰よ……!」
母が震える声で叫ぶ。その声音には、言葉にできないほどの恐怖と疑念が込められていた。
「誰? お前は誰に娘を嫁がせたんだ?」
有真様が冷徹に返したその言葉が、私の母には重く響いた。母はその言葉の意味を理解する間もなく、反応した。
「ま、まさか鬼神様……」
父がその言葉を呟くと、目を見開き、しばらく言葉を失った。どうやらその正体に気づいたらしい。
「人間は本当に愚かだな」
有真様の声は無感情で、冷たく響く。彼の目には、私を使い捨てのように扱った村の人々を見下す視線があった。
父はその言葉に驚愕し、すぐに土下座した。頭を地面に擦りつけるその姿勢が、ただの謝罪ではなく、まるで命を懸けた必死の懇願のように見えた。
「鬼神様、どうかお許しを……!」
その姿勢は、まるで命の保障を求めるような恐怖に満ちていた。
「生贄に満足していただけなかったのでしょうか? それでこの病を……」
父の声は震えていた。私に背を向け、焦点を合わせているかのように有真様を見つめる目には、あまりにも多くの疑念と恐怖が入り混じっていた。しかしその質問には、どこか必死さが滲んでいる。
「何かにつけて俺の仕業にしたいみたいだな。人間は昔から、なぜ自分たちに非があると思わないんだ」
有真様は一歩前へ出ると、冷ややかな声で言った。その言葉には冷徹さが含まれていたが、同時にあきれたような響きがあった。
「非だなんて……」
母は言葉を失い、足元がふらつくのを必死にこらえていた。
「どうせ千代を山に置いて逃げ帰った男たちにあれが付着したんだろう」
目のようなもの。それは邪のものであるらしい。
「あれは山には邪が住み着いているからな」
有真様の言葉はさらりと流れたが、その言葉が示す意味には深い含みがあった。邪気が山に満ちている──それがどれほど恐ろしいものかを、母は理解しているのかもしれない。
そのとき、不意に火の粉が舞い散り、私の頬にあたった。
「熱っ……」
思わず声を上げてしまったが、その痛みは一瞬で消えた。
「これでは千代が危ないな」
有真様は、指先をぱちんと鳴らすと、まるで火の勢いが完全に逆転したかのように、瞬時にその火は消え失せた。あんなに激しく燃え盛っていた火が、まるで何事もなかったかのように消えていく様子に、私はただ呆然と立ち尽くすしかなかった。
一瞬で周囲は静寂に包まれ、その後はただ、私たちの周囲に広がる煙が薄れ、空気が清らかさを取り戻すのを感じる。そして、そのまま私の頬をゆっくりと撫でると、痛みは消えた。
「さあ、帰ろうか」
有真様は私を優しく立ち上がらせる。彼の手に支えられて、ようやく身体が安定したその瞬間、微かにだが美代の手が動いた。その動きはとても弱々しく、まるで何かに引き寄せられるかのように震えていた。
「美代……!?」
母はその反応に驚き、すぐに美代の元へ駆け寄った。父も同じように美代の側に身をかがめ、顔を覗き込む。美代の目がゆっくりと開いていく様子は、まるで長い眠りから目覚めたかのようだった。
「おかあさ……」
母は震える声で美代の名前を呼んだ。その声に答えるように、美代は微かに口を動かす。しかし、すぐにその瞳が私に注がれ、驚いて声を上げた。
「どうして千代がここに……!」
美代は目の前にいる私に驚愕し、その顔に一瞬の恐怖を見せた。その後、視線は家の残骸に向けられる。燃え落ち、今ではわずかに柱だけが残る家を見上げると、その瞳に怒りの炎が灯った。
「お前か! お前がやったのか!」
美代の声は震え、激しく高揚していた。まるで私がすべてを背負い込んだように、罪を押しつけるような口調だった。
「ちが、」
必死に言葉を絞り出す。しかし、どんな言葉を紡ごうとも、すでに美代の怒りは私を貶めることにしか興味を持っていないようだった。私は何も言えず、ただ震えながらその場に立っていた。
「生贄にされた腹いせにやったのだろう! それとも私への報復か!?」
美代はその怒りを収めることなく、私を見て怒鳴り続ける。私が生贄として捧げられたこと、それが全ての元凶だと美代は信じて疑っていない。
美代の身体が再び揺れ、もう一度私へと向かって手を伸ばす。しかし、その勢いはもはや完全に乱れていて、肺が焼けてしまったのか、息を吸うのも苦しそうだった。それでも、怒りと憎しみの感情だけは消えることなく、美代は私に迫ろうとする。
「どうして! 私よりも顔がいいだけではなく、家まで奪おうとするの!」
顔、という言葉に耳を疑った。それは、私にとって初めて言われたことで、今までの苦しみの中で、こんなふうに形にされることを考えたこともなかった。私の顔が何かを奪う力を持っているのか、それとも美代にとってはそれが唯一の価値だったのか、考える暇もなく言葉が続いた。
「お前さえいなければ! お前が悪い! お前が産まれてきたから悪いんだ!」
目の前の美代の顔に浮かぶのは、憎悪と無力感の入り混じった表情だ。虐げられることはあった。しかし、これだけの怒りをぶつけられたことはなかった。私の胸に突き刺さる言葉が、深くて冷たく感じられる。
だが、その瞬間、私と美代の間にひときわ冷徹な影が立ちはだかる。
「私の妻をそれ以上侮辱するようなら、私から手を下してもいいんだぞ」
有真様の低い声が、空気を切り裂くように響いた。その言葉には、単なる威圧だけでなく、彼の力の本質が宿っているのを感じ取った。村に災いをもたらすことも、彼にとってはさほど難しいことではないのだろう。
父はひっと息を呑んだ。目を見開き、震えながら有真様に一歩後退する。その顔に浮かんだ恐怖が、どれほどまでに有真様の力を理解しているかを物語っている。
美代は、そんな父の姿を目にしても、全く気に留めない。むしろ、今度は有真様を睨みつけ、その怒りをさらに激しく燃え上がらせた。
「妻? まさかこの千代が?」
美代の目が鋭く有真様を刺し、その目に新たな疑念と嫌悪感が広がる。
「千代、私に見せびらかしにきたの? 綺麗な人、私が生贄でもよかったぐらい」
美代の言葉に、どこか嘲笑めいた響きが含まれる。自嘲と自己嫌悪が交錯した笑み。
「無駄よ。あなたはまたどうせ捨てられる。あなたを必要としてくれる人なんてこの世にはいないのだから」
その言葉が、私の心に深く突き刺さったが──。
「大丈夫だ」
有真様の穏やかな声が耳に届いた。
「行こう」
もし有真様がいなければ、もうすでに崩れ去っていただろう。彼の存在が、私を支えてくれている。それだけで、他には何も必要ないと感じるほどだった。
彼の存在は、私にとって絶対的だ。それが私を支えている。村にも家族にも見捨てられても、有真様だけは違う。私はその安心感を胸に、何も考えずに彼に従おうと頷いた。
行き先がどこであれ、どこへでもついていこうと心から思う。
有真様が先を歩き、私はその背中を追った。後ろからは美代の罵声が響いていたが、振り返ることはしなかった。
屋敷の前まで来ると、屋根の上にあった鳳凰の置物が動いた。
「え……」
それはゆっくりと羽を伸ばして私を見つめる。
「帰っていたらしいな」
有真様が言った。
「帰って……え」
「千代がこの屋敷に戻ったからだろう」
鳳凰は私を見つめていた。その目は、まるでこの屋敷へと歓迎してくれているようにも感じる。
「言っただろう、いつか会えると」
有真様は屋敷の大きな扉を開けた。その瞬間、足が止まってしまった。確かに有真様の言葉を信じてきたはずだ。捨てられることはない、もう迷わないと決意したはずなのに、どうしても心の奥底で不安が広がっていくのが分かる。
そんな私の気持ちを感じ取ったかのように、有真様が振り返った。その瞳は穏やかで、優しさを湛えている。彼が私を見つめるその表情に、私の中の全てが少しずつ溶けていくような気がした。
「おいで」
その一言が、私の心を軽くしてくれる。無意識のうちに、私はその言葉に従っていた。彼の声には何の不安もなく、ただ優しさだけがこもっている。それが、私を包み込むように感じる。
足が自然に動き、私は彼に近づいていく。玄関の敷居をまたぐ瞬間、私はまるで他の世界に足を踏み入れたような気がした。けれど、そこには恐れがあったわけではなく、どこか心地よい安心感が広がっていた。
「おかえり、千代」
その言葉が私の耳に届いたとき、胸がぎゅっと締めつけられるような感覚に襲われた。それは、誰にも言われたことがない言葉だった。家に帰ることがこんなにも嬉しく感じられるなんて、思ってもいなかった。けれど有真様がそう言ってくれることで、私は初めて「帰る場所」があるのだと感じた。
涙が、思わずこぼれそうになるのを感じた。今までずっと抱え込んでいた不安や恐怖が、一気にあふれ出しそうになる。でも、どうしてもそれを許したくなくて、必死にこらえる。けれど、有真様の優しさに触れるたび、涙が溢れそうになる自分を止めることができなかった。
私はその涙を拭いもせず、ただ静かに頷く。心の中で、ようやく少しだけ安心した自分を感じることができた。この屋敷で、私の新しい「家族」として、有真様と共に歩んでいけるのだと。